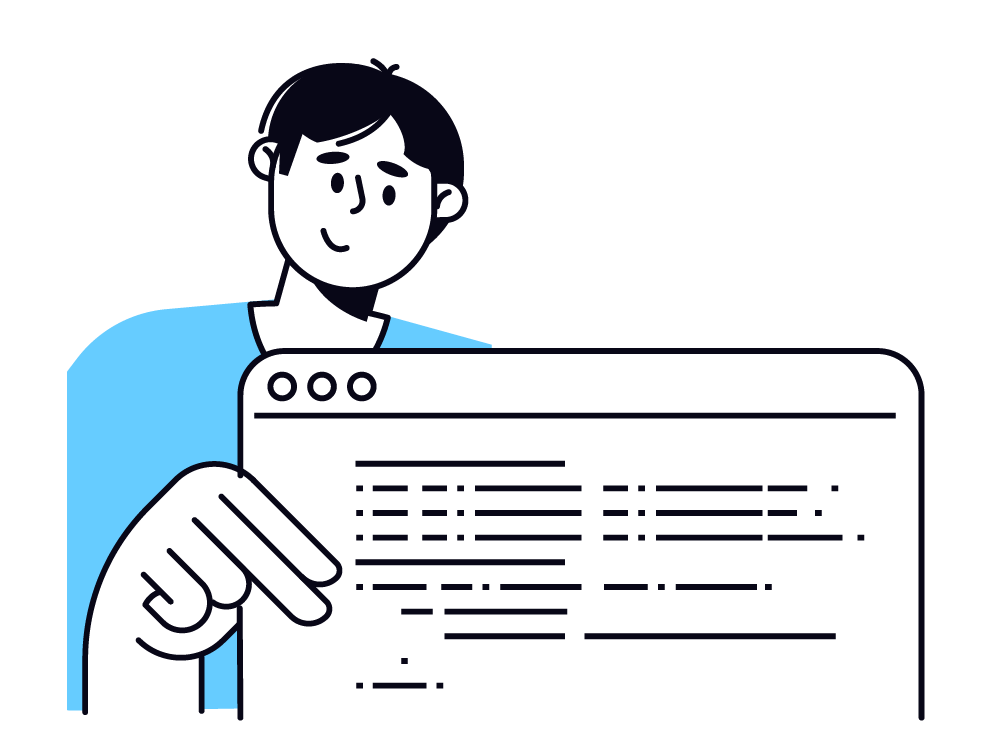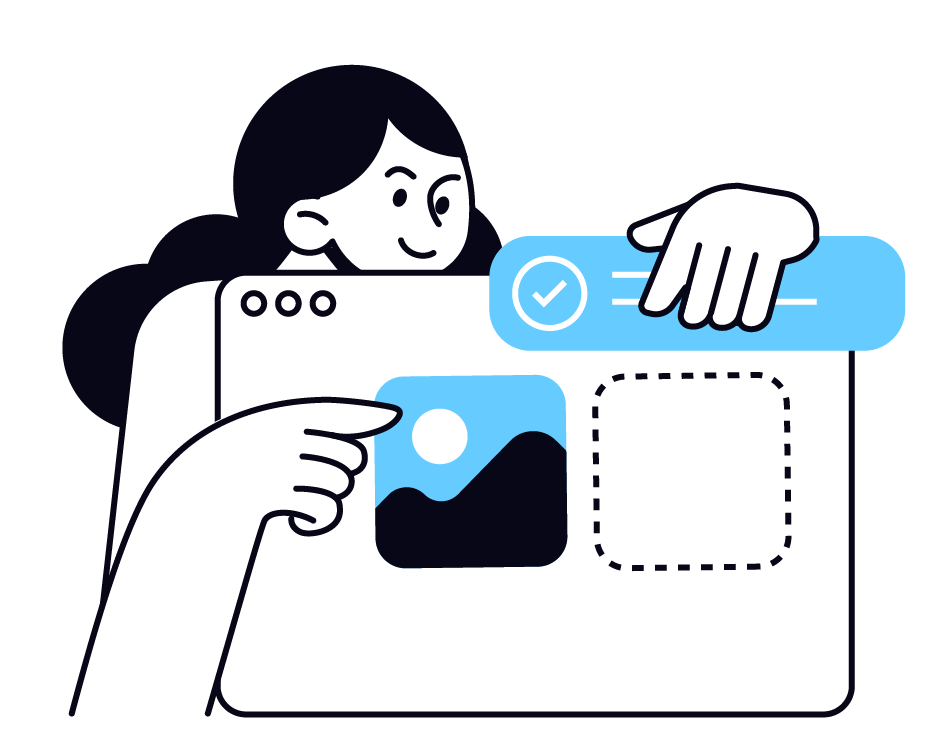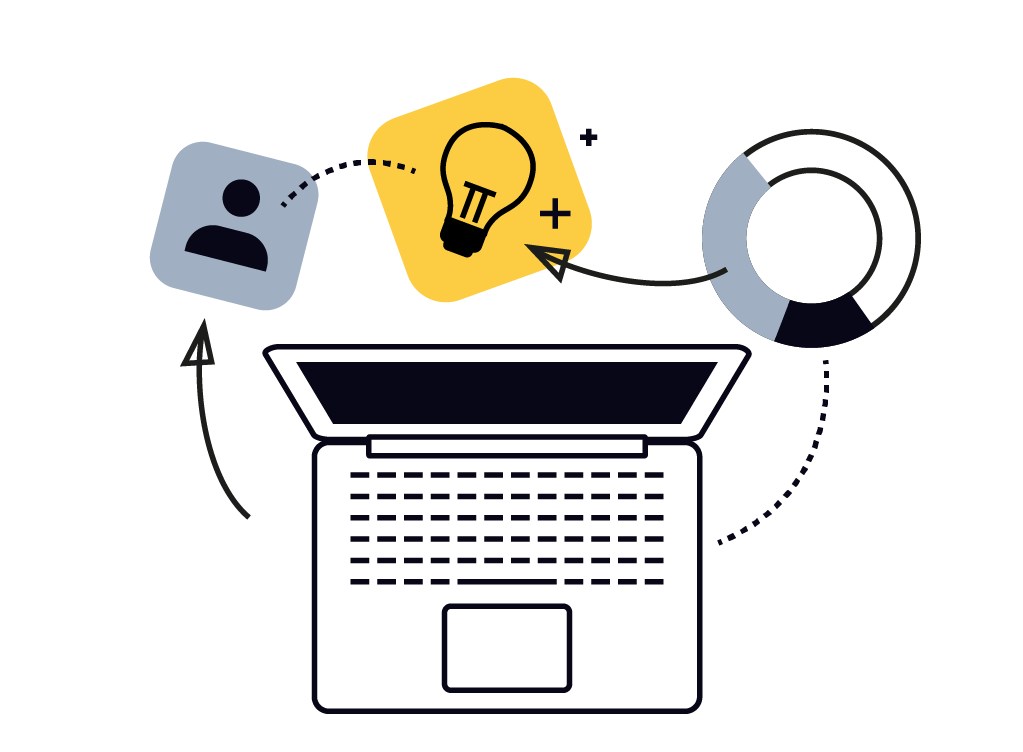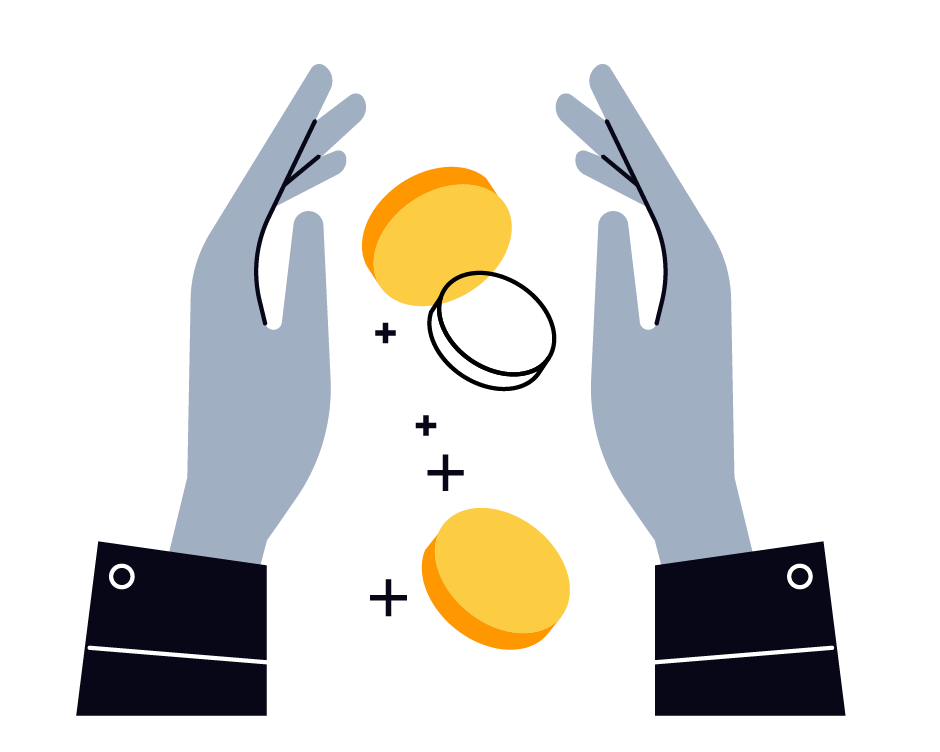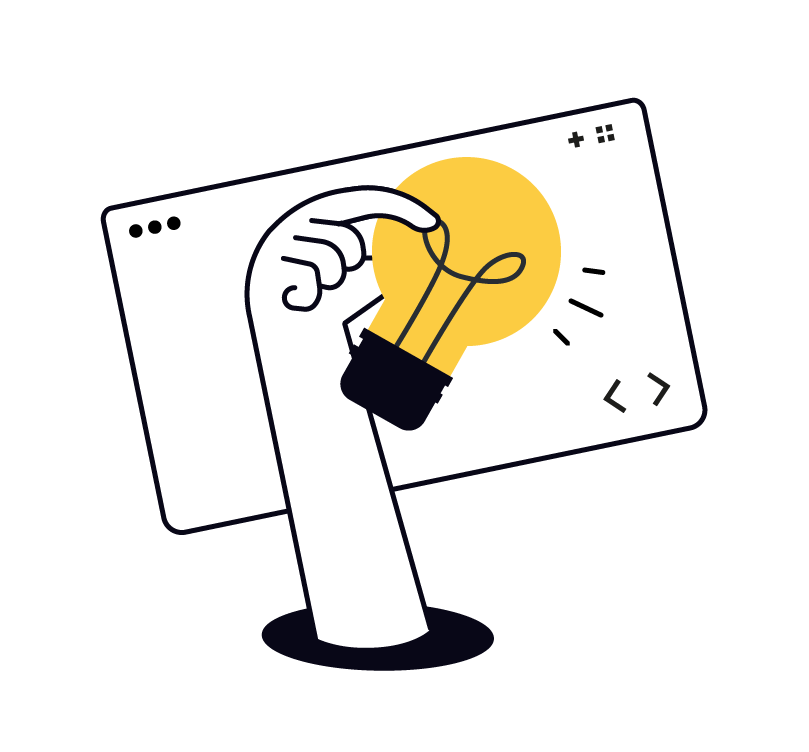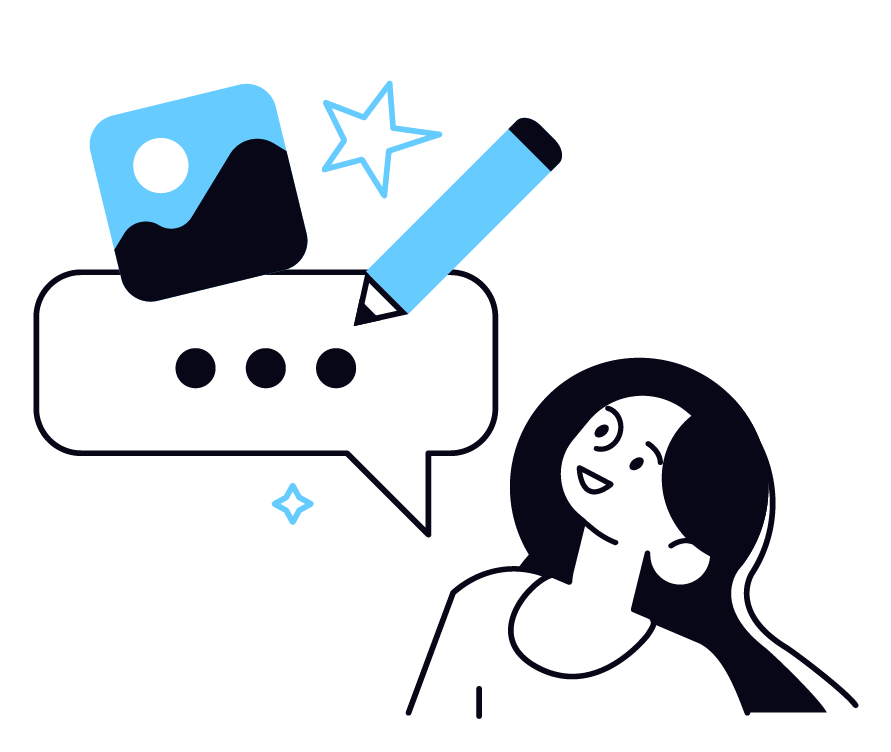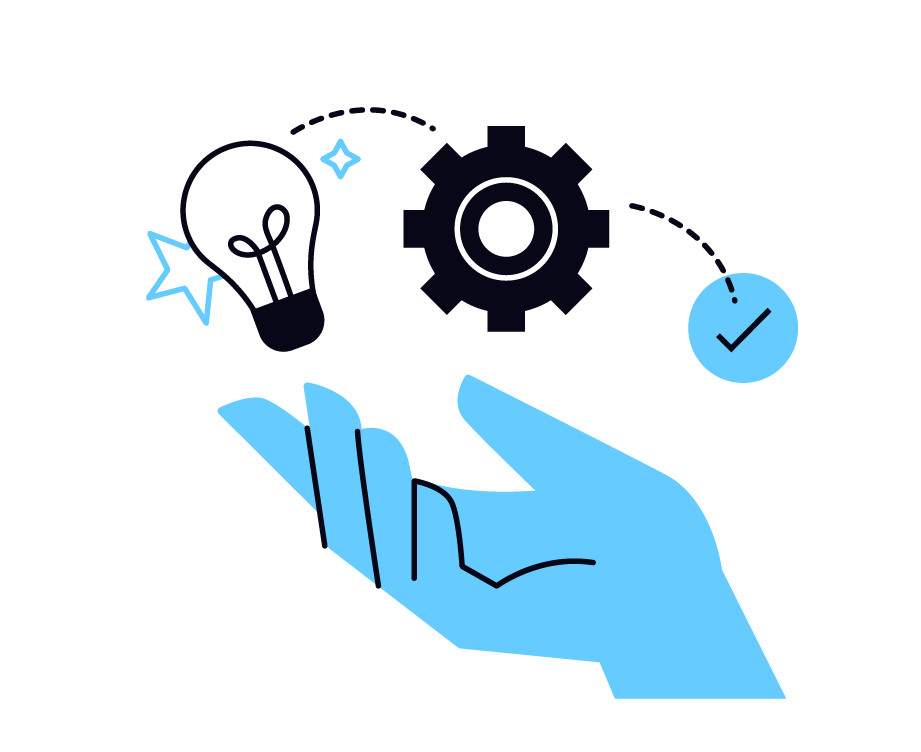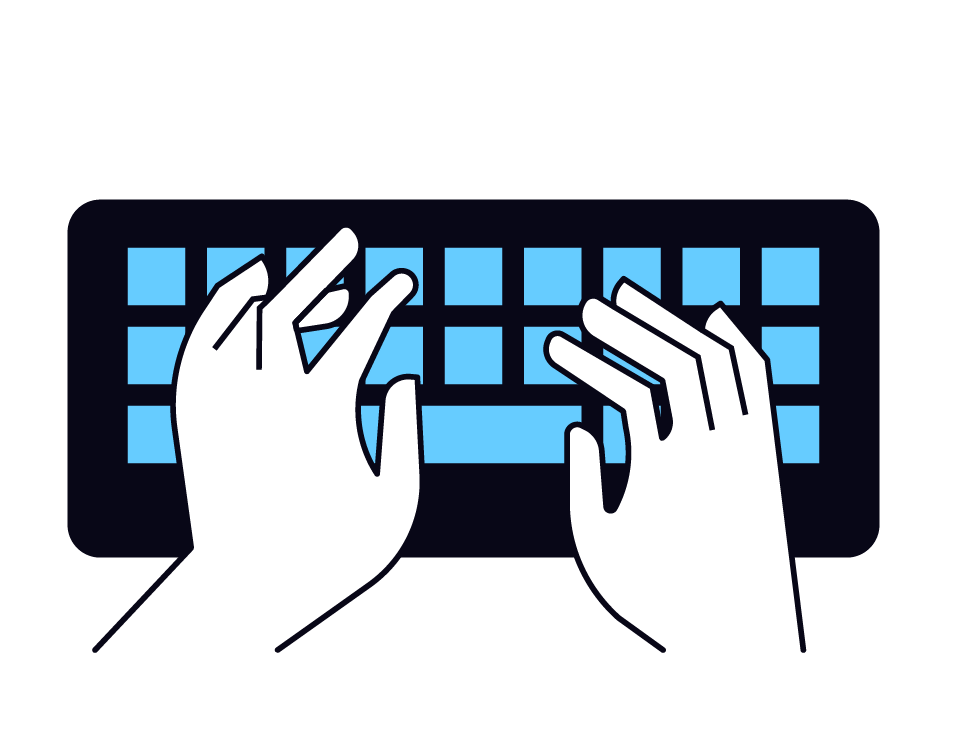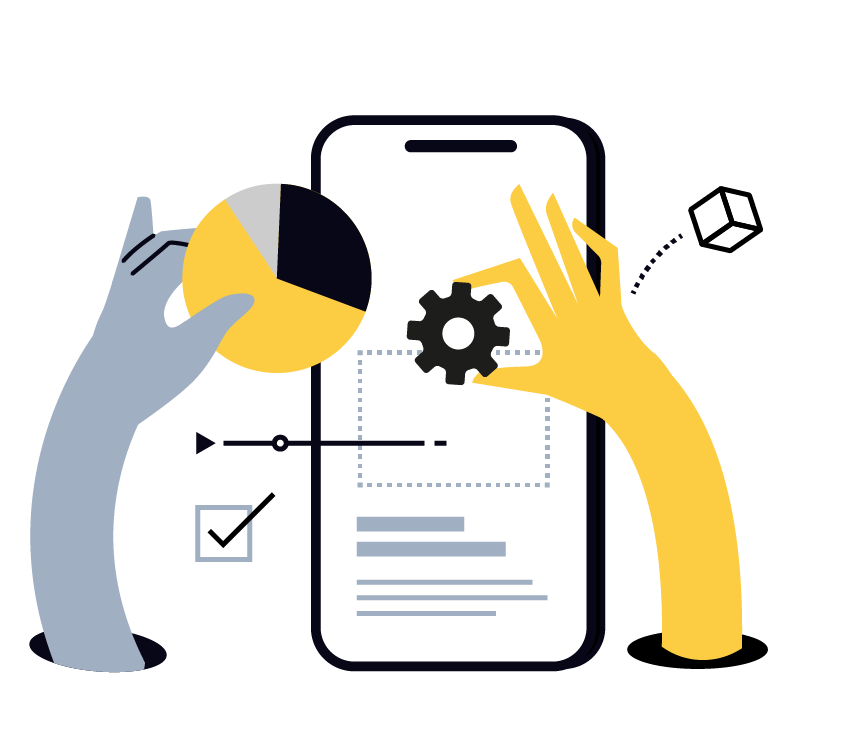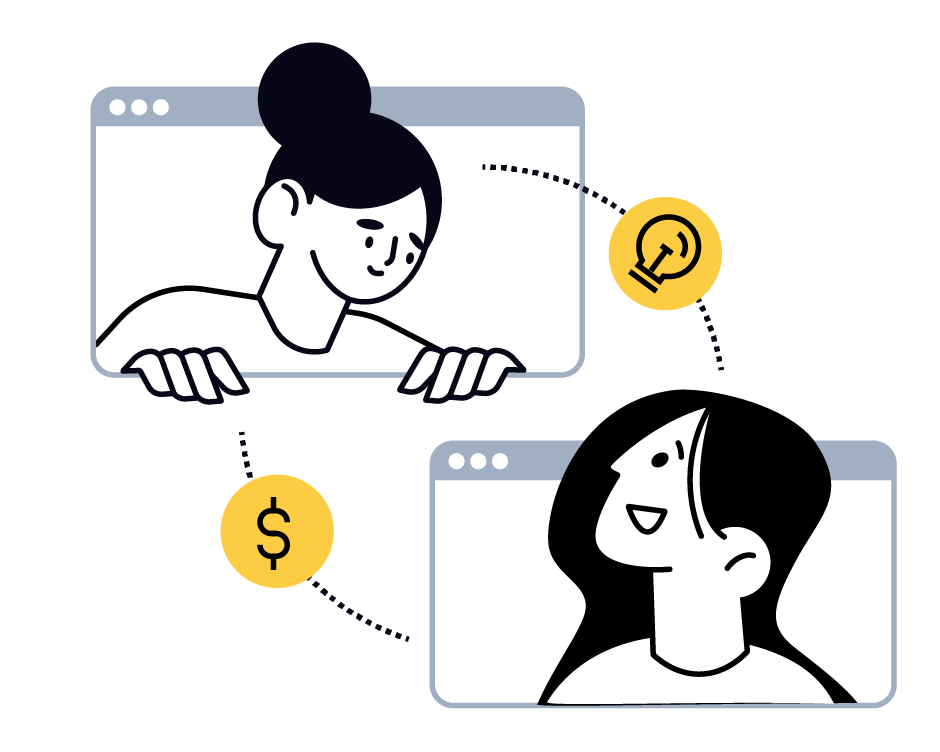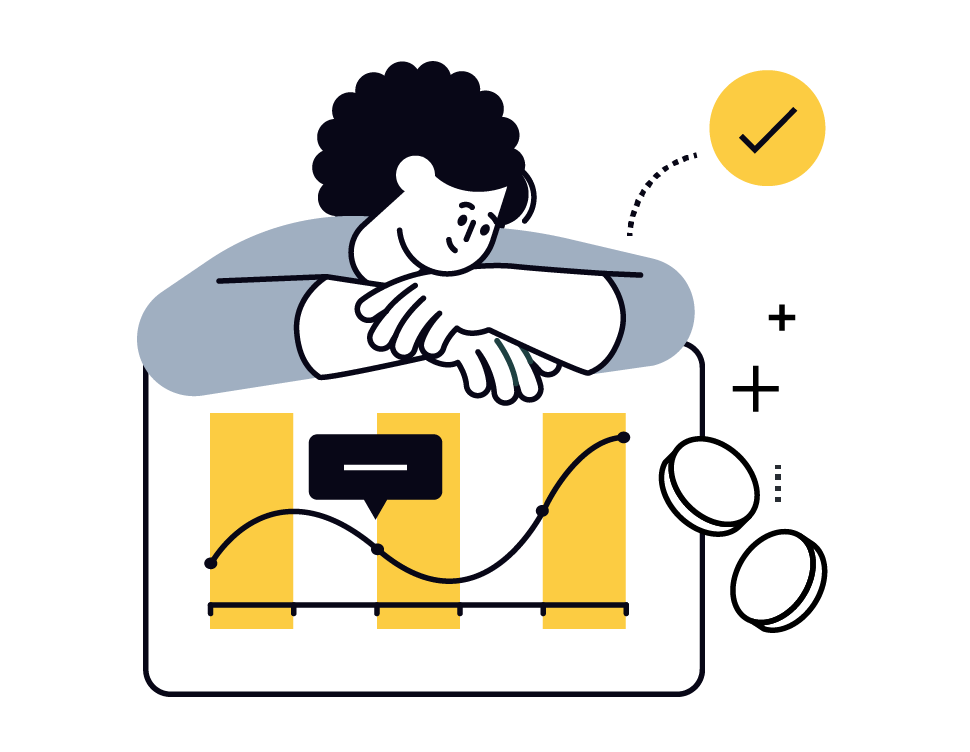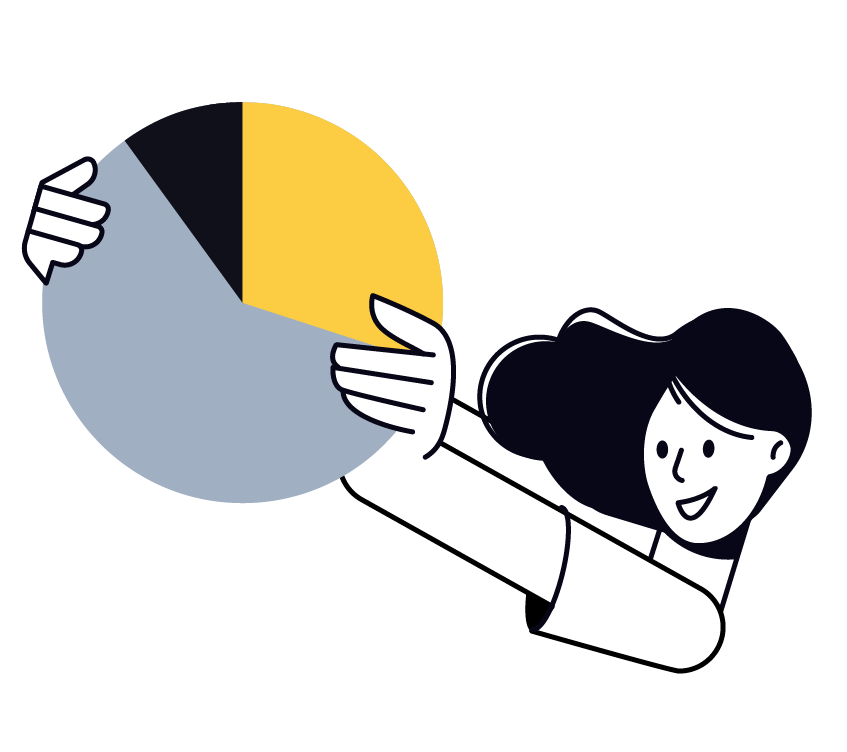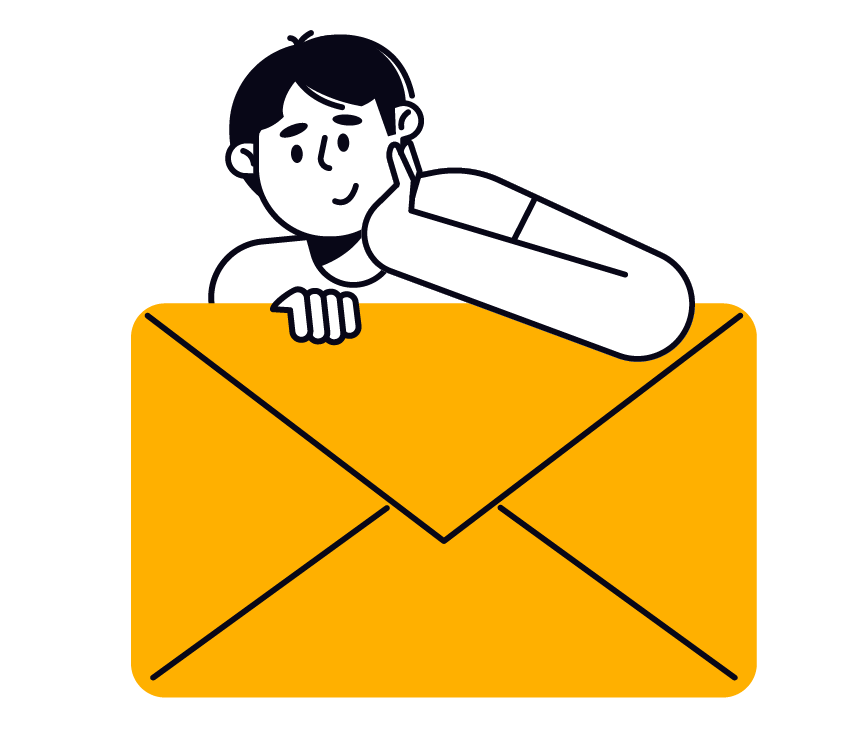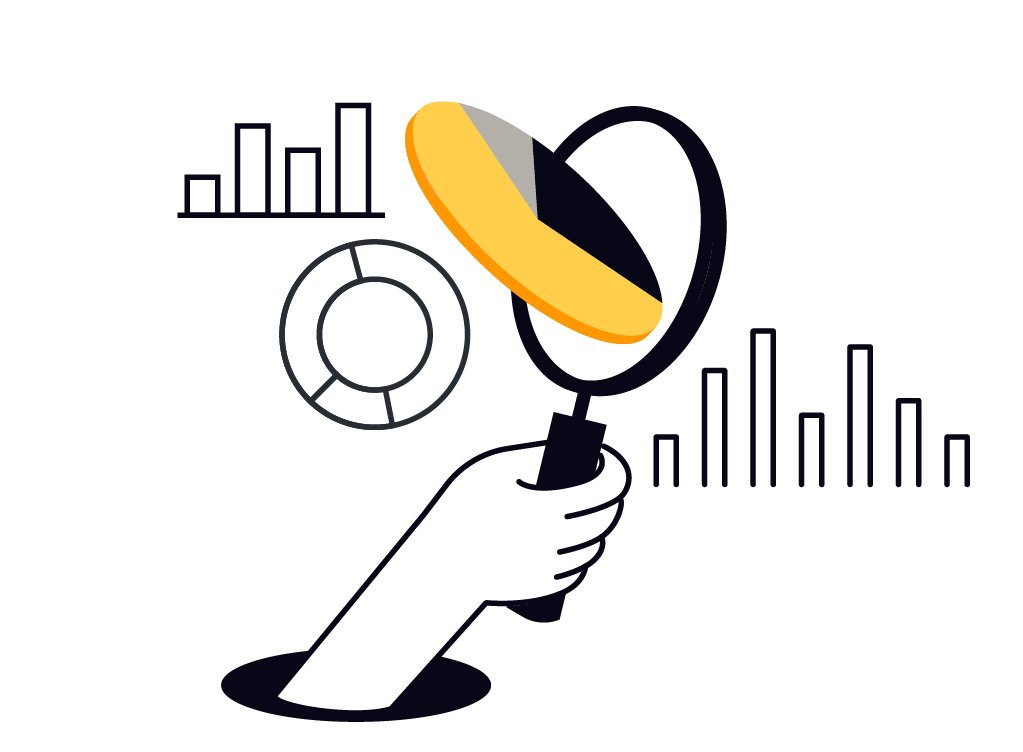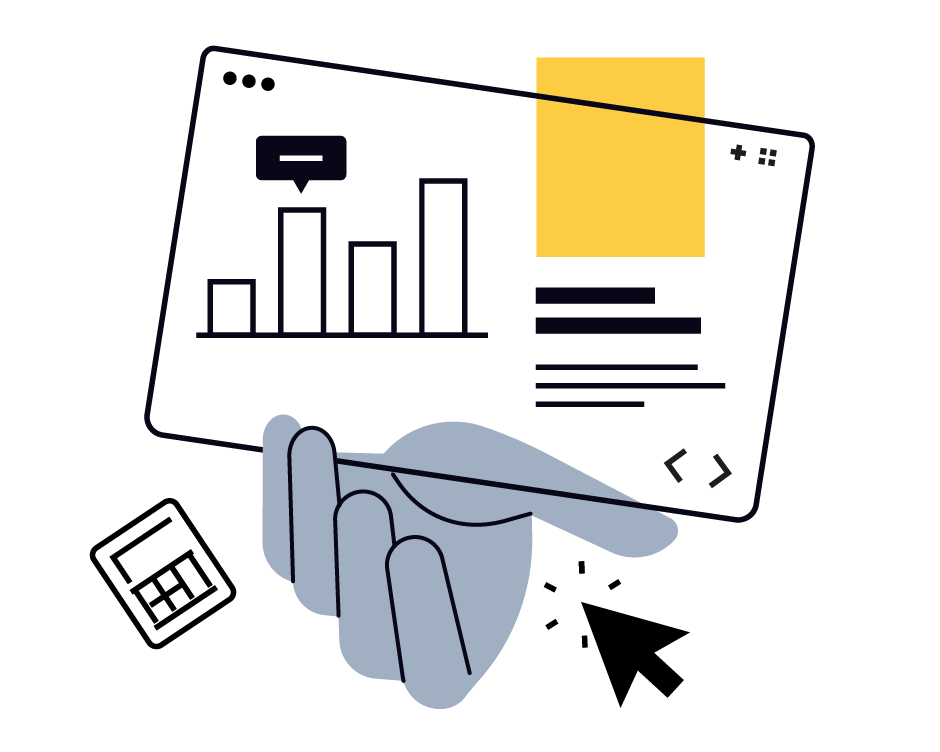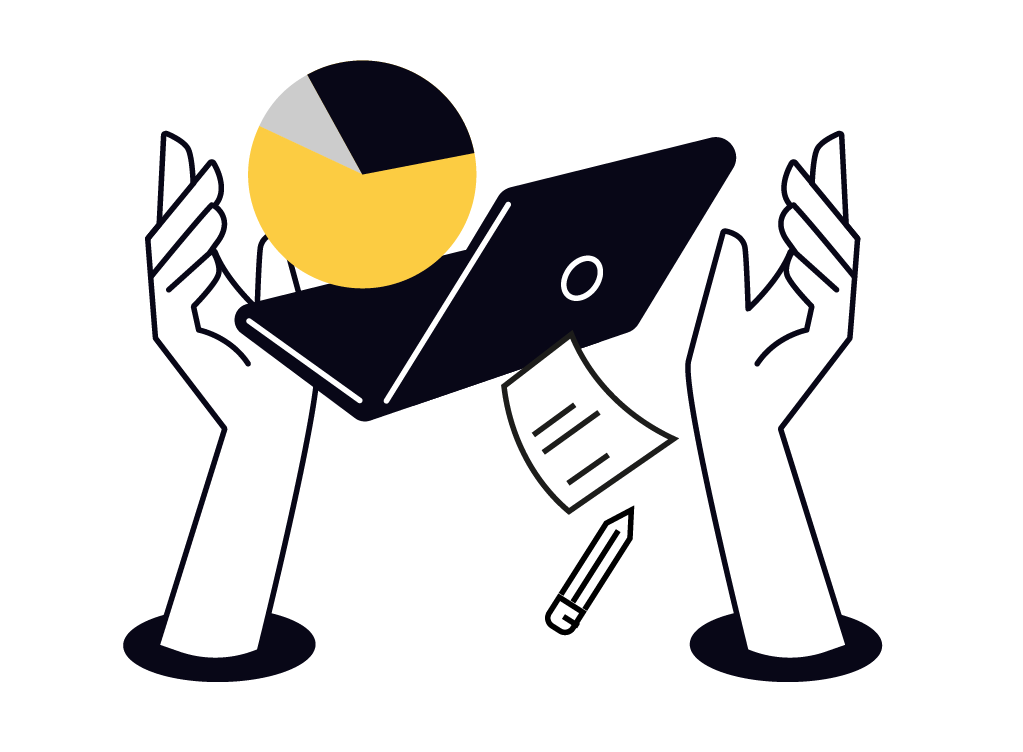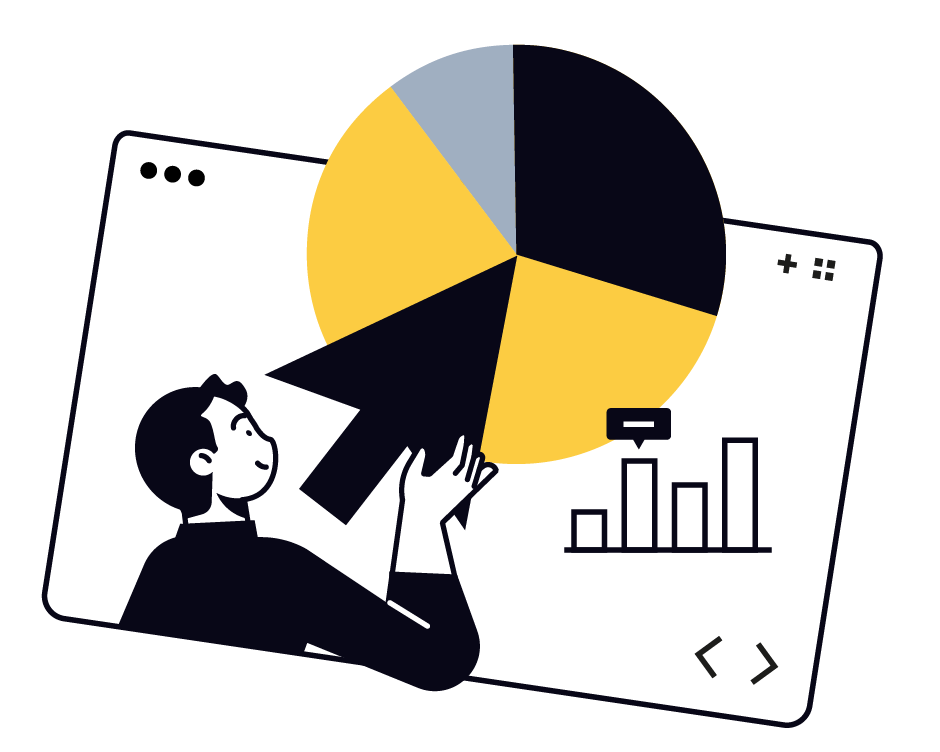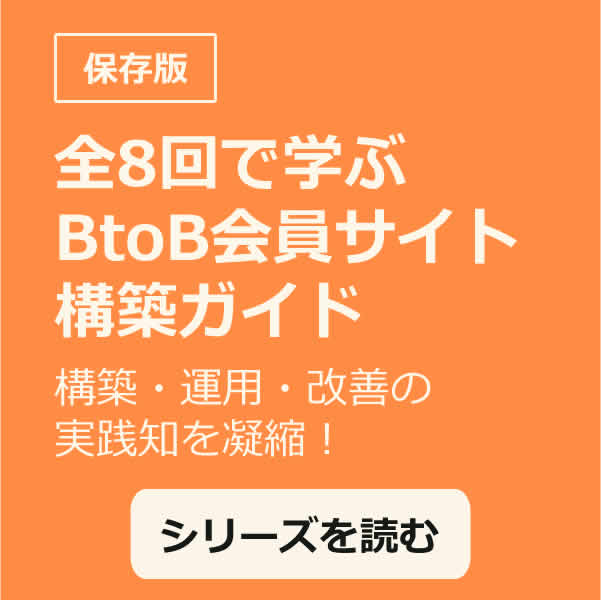この記事について(前提・ディスクレーマー)
本稿の費用・期間・効果はBtoB企業向け中〜大規模サイトの支援案件で観測した中央値ベースの参考値です。 業種・規模・要件・体制・SLA(稼働率)/RTO/RPO、監査・法規要件により大きく変動します。検討時は最新情報と自社条件での再計算をお願いします。
本稿は一般的情報の提供を目的とし、特定製品や方式の優位性を断定するものではありません。
本稿での用語定義
クラウド(SaaS): 提供事業者がインフラ・運用を担当
オンプレミス: 自社でインフラ・運用を担当(商用パッケージ/OSS)
自社開発: 独自に設計・実装したシステム
1. 本記事の使い方
1-1. Q&Aの構成
本記事は、CMS導入に関する疑問を以下の7つのカテゴリーに分類しています:
Q&Aのカテゴリー:
- 導入判断に関する質問(Q1〜Q5):そもそもCMSは必要か?
- 予算・コストに関する質問(Q6〜Q10):いくらかかる?コスト削減できる?
- 技術・スキルに関する質問(Q11〜Q15):知識がなくても大丈夫?
- 運用に関する質問(Q16〜Q20):導入後、ちゃんと使える?
- トラブル・リスクに関する質問(Q21〜Q25):失敗したらどうする?
- 選定・比較に関する質問(Q26〜Q30):どうやって選べばいい?
- 移行に関する質問(Q31〜Q35):既存サイトからの移行は大変?
1-2. 質問の探し方
目次から探す: 気になるカテゴリーから該当する質問を探す
キーワードで探す: ブラウザの検索機能(Ctrl+F/Cmd+F)でキーワード検索
順番に読む: 導入検討の流れに沿って、Q1から順番に読む
2. 導入判断に関する質問
Q1. CMSは本当に必要ですか?HTMLで十分では?
A. 以下の条件に1つでも当てはまる場合、CMS導入を検討する価値があります。
【想定条件】 BtoB/中〜大規模。多拠点・多部門運用、承認あり、月間更新10〜100本、監査・可用性要件あり
CMS導入を検討するサイン(規模別):
中規模サイト:
- ページ数500超
- 編集者20名超
- 承認フロー2段階以上
- 外部委託が恒常化
大規模サイト:
- マルチサイト運用
- HA(高可用性)構成やDR(災害復旧)前提
- 監査ログ(1〜3年保持)必須
- 配信経路(Web/メール/LP)一元化
小規模サイト(副対象):
- 月1回以上更新
- 非エンジニア更新が中心
- 複数人でコンテンツを更新
HTML管理が現実的なケース:
- ページ数が10ページ以下
- 更新頻度が年に数回程度
- 更新作業ができるエンジニアが社内にいる
- 承認フローが不要
判断の目安(試算例):
想定条件: BtoB企業/従業員300〜1,000名/月30ページ更新/承認2段階
【更新コストの比較】
HTML管理:1ページ更新に30分〜1時間(エンジニアが作業)
CMS:1ページ更新に10〜15分(非エンジニアが作業)
月30ページ更新する場合:
HTML:月15〜30時間 × 人件費5,000円 = 月7.5万円〜15万円
CMS:月5〜7.5時間 × 人件費3,000円 = 月1.5万円〜2.3万円
年間で72万円〜152万円の削減効果
※人件費は地域・雇用形態で変動(時給2,000〜4,000円で再計算可能)
まとめ(一般的な見立て):
権限・承認・テンプレート一括反映・監査ログの4要素のうち2つ以上が必須なら、CMS採用の合理性が高い傾向にあります。
Q2. 小規模サイトでもCMSは導入すべきですか?
A. ページ数が少なくても、以下の条件に当てはまる場合は導入を検討する価値があります。
小規模サイトでもCMS導入が有効なケース:
- 非エンジニアが更新作業を行う
- 将来的にページ数を増やす予定がある
- ブログやニュースを定期的に更新する
- 複数拠点・複数ブランドのサイトを統合管理したい
小規模サイトに適したCMS:
- SaaS/クラウド型CMS(月額3,000円〜1万円程度)
- 初期費用が低く、小さく始められる
- 代表的なSaaS例:WordPress.com、Wix、Jimdo等(用途により異なる)
※最新情報の確認: 各サービスの仕様・価格は変動するため、導入検討時は公式サイトで最新情報をご確認ください。
導入しない判断もあり:
- ページ数が5ページ以下
- 年に1〜2回しか更新しない
- 更新作業ができるエンジニアが社内にいる
こうした場合は、HTML管理や無料のホームページ作成サービスで十分な可能性があります。
Q3. 既に業者にサイト更新を委託しています。CMSは必要ですか?
A. 外部委託費が月3万円以上かかっている場合、CMS導入で内製化することでコスト削減できる可能性があります。
外部委託とCMSのコスト比較(試算例):
想定条件: BtoB企業/従業員300〜1,000名/月30ページ更新/承認2段階
※金額は参考値。要件・規模・契約条件により大きく変動します。
【外部委託の場合(5年間の総コスト)】
月額費用:15万円 × 60ヶ月 = 900万円
【CMS導入+内製化の場合(5年間の総コスト)】
初期費用:500万円(CMS導入+トレーニング+カスタマイズ)
月額費用:5万円(CMS利用料+保守)× 60ヶ月 = 300万円
社内工数:月30時間 × 人件費3,000円 × 60ヶ月 = 540万円
合計:1,340万円
→ この例では外部委託の方が割安
ただし、更新頻度や緊急差し込みが増えると内製の方が総コストは逆転しやすくなります。 以下の場合はCMS導入が有効です:
- 外部委託費が月30万円以上
- 更新頻度が高い/緊急差し込みが多い
- 更新のたびに納期待ちでスピードが遅い
- 細かい修正でも費用が発生する
- 将来的に更新頻度を上げたい
判断のポイント:
コストだけでなく、「スピード」「柔軟性」も考慮しましょう。CMSなら、思い立ったときにすぐ更新に対応できる可能性があります。
Q4. WordPressは無料と聞きましたが、本当に無料で使えますか?
A. WordPress本体は無料ですが、実際の運用には以下のコストが発生します。
WordPressを使う場合の実際のコスト:
想定条件: BtoB企業/従業員50〜300名/基本的なコーポレートサイト
※金額は参考値。要件・規模・契約条件により大きく変動します。
【初期費用】
- ドメイン取得:年間1,000円〜3,000円
- サーバー契約:月額500円〜3,000円
- テーマ購入:0円〜3万円(無料テーマもあり)
- プラグイン購入:0円〜5万円(必要に応じて)
- 初期設定・カスタマイズ:10万円〜100万円(自社対応なら不要)
【年間ランニングコスト】
- サーバー費用:年間6,000円〜3.6万円
- ドメイン更新:年間1,000円〜3,000円
- セキュリティプラグイン:年間0円〜2万円
※マネージドWAFやホスティング側のバックアップで代替されるケースもあり
- バックアッププラグイン:年間0円〜1万円
- 保守費用(外部委託の場合):年間12万円〜60万円
【最小構成の例(自社で全て対応)】
初期:ドメイン1,000円 + サーバー初期費用3,000円 = 4,000円
年間:サーバー6,000円 + ドメイン1,000円 = 7,000円
→ 5年間の総コストで3.9万円
【一般的な構成の例(初期設定は外部委託)】
初期:50万円(設定・カスタマイズ)
年間:サーバー1.2万円 + 保守24万円 = 25.2万円
→ 5年間の総コストで176万円
「無料」の範囲:
- WordPress本体のソフトウェアは無料
- ただし、サーバー、ドメイン、保守には費用がかかる
- 完全に無料で使えるのは、WordPress.comの無料プラン(機能制限あり)
WordPress本体は無料ですが、実運用には年間数万円〜数十万円のコストがかかります。
Q5. 今すぐ導入すべきか、もう少し様子を見るべきか迷っています
A. 以下のチェックリストで判断しましょう。3つ以上当てはまる場合、早期導入を検討する価値が高いです。
早期導入を検討する価値が高いサイン:
□ 更新作業に時間がかかりすぎている(1ページ1時間以上)
□ 外部委託費が高額になっている(月10万円以上)
□ 更新のたびに提供事業者を待つ時間が長い(1週間以上)
□ 誤公開やミスが頻繁に発生している(月1回以上)
□ 複数人で更新作業を分担したいが、できていない
□ コンテンツマーケティングを強化したいが、更新が追いつかない
□ Webサイトのリニューアルを検討している
様子を見てもよいケース:
- 現状の運用に特に問題がない
- 予算の確保が難しい(半年〜1年後に再検討)
- 社内体制が整っていない(まずは体制構築から)
「現状維持のコスト」と「CMS導入のコスト」を5年間で比較し、削減効果が50万円以上なら導入を検討する価値があります。
3. 予算・コストに関する質問
Q6. CMS導入にはいくらかかりますか?
A. CMSの種類や規模によって、初期費用は0円〜数千万円、月額費用は0円〜数十万円と大きく異なります。
CMSタイプ別の費用目安:
想定条件: 企業規模別の標準的な構成
※金額は参考値。要件・規模・契約条件により大きく変動します。
| CMSタイプ | 初期費用 | 年額/運用 | 5年間の総コスト(概算) | 向き |
|---|---|---|---|---|
| SaaS/クラウド(小規模) | 0円〜10万円 | 18万円〜60万円 | 90万円〜310万円 | 単一サイト・部門限定 |
| SaaS/クラウド(中規模) | 100万円〜500万円 | 36万円〜120万円 | 280万円〜1,100万円 | 多部門標準化 |
| SaaS/クラウド(エンタープライズ) | 500万円〜3,000万円 | 300万円〜1,200万円 | 2,000万円〜9,000万円 | マルチサイト/高可用/監査 |
| オンプレミス(OSS) | 500万円〜3,000万円 | 120万円〜600万円 | 1,100万円〜6,000万円 | カスタム重視 |
| 商用パッケージ(オンプレミス) | 1,000万円〜6,000万円 | 360万円〜1,500万円 | 2,800万円〜1億3,500万円 | SLA/監査厳格 |
| 自社開発 | 3,000万円〜 | 変動 | 要試算(要件依存) | 極要件のみ |
※高額レンジについて: エンタープライズ以上のケースは、大規模/マルチサイト/高可用性DB・冗長化・監査要件フル搭載時の上限例です。
企業規模別の予算目安:
- 小規模企業(従業員50名以下):初期50万円以下、年額18万円以下
- 中小企業(従業員50〜300名):初期100万円以上500万円以下、年額36万円以上120万円以下
- 中堅企業(従業員300〜1,000名):初期500万円以上2,000万円以下、年額120万円以上360万円以下
- 大企業(従業員1,000名以上):初期1,000万円以上、年額360万円以上
補足:
- オープンソースCMS:ライセンス費用なし、年額費用は保守・サーバー費用のみ
- 商用パッケージCMS:年間ライセンス費用(50万円〜500万円)または買い切りライセンス+保守費用が発生
- 上記は目安です。実際の費用は、要件、カスタマイズの範囲、ページ数、トラフィック量によって大きく変動します。
Q7. 予算が限られています。何から削減すればよいですか?
A. 以下の優先順位で検討しましょう。
コスト削減の優先順位:
1. CMSタイプの見直し(効果:大)
- オンプレミス型 → SaaS/クラウド型に変更(初期費用を大幅削減)
- 商用CMS → オープンソースCMSに変更(ライセンス費削減)
2. カスタマイズ範囲の縮小(効果:大)
- 独自機能の開発を見送り、標準機能で対応
- デザインはテンプレートを活用
- 段階的にカスタマイズ(初回は最小限、後から追加)
3. 初期の移行範囲の縮小(効果:中)
- 全ページ移行ではなく、新規ページのみCMSで管理
- 旧サイトは並行運用し、徐々に移行
4. トレーニングの内製化(効果:小)
- 外部トレーニングではなく、社内で勉強会を実施
- オンラインドキュメントを活用
削減してはいけないコスト:
- セキュリティ対策(SSL証明書、WAF等)
- バックアップ体制
- 最低限の保守・サポート
これらを削減すると、後から大きなトラブルにつながる可能性があります。
Q8. 初期費用とランニングコスト、どちらを重視すべきですか?
A. 利用期間が3年以上なら、ランニングコストを重視する方が総コストを抑えられる傾向があります。
判断の考え方(試算例):
想定条件: BtoB企業/従業員300〜1,000名/基本的なコーポレートサイト
【パターンA:初期費用重視】
初期費用:100万円
月額費用:10万円
5年間の総コスト:100万円 + 10万円 × 60ヶ月 = 700万円
【パターンB:ランニングコスト重視】
初期費用:500万円
月額費用:3万円
5年間の総コスト:500万円 + 3万円 × 60ヶ月 = 680万円
→ 5年間で見るとパターンBが20万円安い
利用期間別の判断基準:
- 1年以内の短期利用:初期費用を重視する傾向
- 3年以上の長期利用:ランニングコストを重視する傾向
- 5年以上の長期利用:初期費用が高くても、月額費用が低い方が総額で安くなる傾向
※変動要因: SLA要件、冗長化の有無、拡張頻度によって上記の傾向は変動します。
注意点: SaaS/クラウド型は柔軟に解約に対応できる場合が多いですが、オンプレミス型は初期投資が無駄になる可能性があります。利用期間の見通しを慎重に検討しましょう。
Q9. ROI(投資対効果)はどう計算すればよいですか?
A. 以下の式で計算します:ROI = (効果 - 投資額)÷ 投資額 × 100
効果の計算方法:
想定条件: BtoB企業/従業員300〜1,000名/月間コンテンツ更新量が中〜多
1. 削減される工数を金額換算
現状:月120時間 × 人件費5,000円 = 月60万円
CMS導入後:月60時間 × 人件費3,000円 = 月18万円
削減効果:月42万円 → 年間504万円
2. 削減される外部委託費
現状:月20万円
CMS導入後:月5万円
削減効果:月15万円 → 年間180万円
3. 増加する売上・問い合わせを金額換算
問い合わせ数が月50件 → 75件に増加(50%向上)
受注率20% → 年間60件の受注増
1件あたり売上100万円 → 年間6,000万円増収
ROIの計算例:
想定条件: BtoB企業/従業員300〜1,000名/中規模サイト
【5年間の効果】
工数削減:504万円 × 5年 = 2,520万円
外部委託費削減:180万円 × 5年 = 900万円
合計効果:3,420万円
【5年間の投資額】
初期費用:1,000万円
ランニングコスト:200万円 × 5年 = 1,000万円
合計投資:2,000万円
【ROI】
(3,420万円 - 2,000万円)÷ 2,000万円 × 100 = 71%
補足: 売上向上効果は不確実性が高いため、コスト削減効果のみで計算し、売上向上は「追加効果」と位置づけることを推奨します。
Q10. 予算承認を得るにはどうすればよいですか?
A. 以下の3点を明確に示した資料を作成しましょう。
予算承認に必要な要素:
想定条件: BtoB企業/従業員300〜1,000名/現状で外部委託または非効率な運用
1. 現状の課題を定量的に示す
【現状の課題】
- 更新作業に月120時間かかっている(年間1,440時間)
- 外部委託費が年間600万円かかっている
- 更新遅延が月10回発生している
- 誤公開が年5回発生している
2. CMS導入で得られる効果を具体的に示す
【導入効果】
- 更新作業が月60時間に削減(年間720時間削減)
- 外部委託費が年間300万円に削減
- 更新遅延がゼロに
- 承認フローで誤公開を防止
3. ROIを5年間で試算
【投資対効果】
効果:年間900万円 × 5年 = 4,500万円
投資:初期1,000万円 + ランニング200万円 × 5年 = 2,000万円
ROI:125%
回収期間:2.2年
承認率を上げるコツ:
- 経営層向けには1ページのサマリーを作成
- グラフや図を活用し、視覚的に理解しやすく
- 競合他社の導入事例を示す
- リスクと対策も明記(「失敗しないための準備」を示す)
4. 技術・スキルに関する質問
Q11. 社内に技術者がいません。CMSを運用できますか?
A. SaaS/クラウド型CMSなら、技術者がいなくても運用に対応できる可能性が高いです。
技術者不要で運用できる可能性が高いCMS:
- SaaS/クラウド型CMS
- 代表的なSaaS例:WordPress.com、Wix、Jimdo、Shopify、HubSpot CMS等(用途により異なる)
技術者不要で運用できる理由:
- サーバー管理が不要(提供事業者が管理)
- セキュリティパッチの適用が標準設定では自動化されることが多い
- バックアップも標準設定では自動化されることが多い
- トラブル時は提供事業者サポートに連絡
必要なスキル:
- Word、Excelの基本操作ができる
- インターネットブラウザを使える
- 画像の基本的な編集ができる(リサイズ、トリミング等)
技術者がいた方がよいケース:
- オンプレミス型CMS(サーバー管理が必要)
- ヘッドレスCMS(フロントエンド開発が必要)
- 大規模カスタマイズ
- 既存システムとの連携
Q12. HTMLやプログラミングの知識は必要ですか?
A. 方式と運用範囲によります。
SaaS/クラウド型:
標準機能内で運用するなら原則不要です。
オンプレミス/商用パッケージ:
運用はノーコード中心でも、サーバー/セキュリティのIT担当が必要です。
自社開発/ヘッドレス:
フロント実装やAPI連携に開発スキルが必須です。
知識不要でできる主な範囲(共通):
- ページ作成/編集/公開
- 画像・動画アップロード
- カテゴリ・タグの設定
- メタ情報(SEO)の設定
- 公開予約
- ユーザー権限の設定
知識があると便利:
- HTMLの基礎知識 → 細かいレイアウト調整
- CSSの基礎知識 → デザインのカスタマイズ
- JavaScriptの基礎知識 → 軽微な動的挙動の追加
知識が必要なケース:
- テンプレートの大幅なカスタマイズ
- 独自機能の開発
- 既存システムとのAPI連携
- ヘッドレスCMSのフロントエンド開発
- オンプレミス環境の設計/運用(冗長化・監視・バックアップ等)
まとめ: SaaS/クラウド型=原則ノーコードで運用可能、オンプレミス/商用=IT運用スキルが別途必要、自社開発/ヘッドレス=開発スキルが前提。
Q13. デザインセンスがありません。見栄えのよいサイトは作れますか?
A. 方式と体制によってアプローチが変わります。
SaaS/クラウド型CMS:
既存テンプレートやテーマを起点に、ブランドカラー・フォント・コンポーネントを調整するだけで短期間で"それらしく"整えるケースが多いです。
オンプレミス/自社開発:
要件に応じて制作会社や社内デザイナーがデザインシステム(色・余白・タイポ・コンポーネント)を設計し、それをCMSのテンプレート/ブロックに落とし込みます。見た目の自由度は高い一方、設計と実装の工数が増える傾向があります。
いずれの方式でも:
既存のUIパーツ(ブロック/モジュール)をカタログ化し、禁止事項を含むガイドラインを整備すると、非デザイナーでも破綻しにくくなります。
テンプレートが豊富なCMS(代表例):
- WordPress:多数のテーマ(有料・無料)
- 主要なSaaSプラットフォーム各社
独自デザインが必要な場合:
制作会社に依頼することもできます。費用は50万円〜300万円程度が目安です。
Q14. トレーニングはどのくらい必要ですか?
A. 規模・方式・ロール構成によってばらつきがあります。
小規模SaaSなら基本1〜2時間×1〜2回で運用開始できることもありますが、中〜大規模(例:承認/権限/多拠点)では1.5〜2時間×3〜5セッションをロール別に実施するケースが一般的です。
ロール別の典型カリキュラム例:
【投稿者(ライター)】
- 基本操作(1.5時間):ページ作成・編集・画像挿入
- 画像・リンク・校正(1.5時間):画像最適化、内部リンク、プレビュー
【編集者】
- レビュー/承認/公開予約(2時間):承認ワークフロー、差戻し操作
- テンプレート反映と差戻し運用(2時間):テンプレート適用、運用ルール
【管理者】
- 権限・監査ログ・バックアップ/復旧(2時間)
- 運用ルール策定(2時間)
定着支援:
運用手順書・NG例集・チェックリストを配布すると定着が早まります。
トレーニング方法:
- 提供事業者のトレーニング:有料(5万円〜20万円)
- オンラインドキュメント:無料、自分のペースで学習
- 動画チュートリアル:無料、視覚的に理解しやすい
- 社内勉強会:先に習得した人が他のメンバーに教える
Q15. スマホ対応は簡単にできますか?
A. 既存のレスポンシブ対応テンプレートを使う場合は、追加実装なしでスマホ表示を整えられるケースが多いです。
一方、新規デザインをゼロから起こす場合は、ブレークポイント設計・画像最適化・タップ領域などのフロント実装工数が必要です。ヘッドレスや自社開発ではこの実装責務が自社/制作会社側に乗る点に留意してください。
選定時の確認ポイント:
- 既存テンプレでどこまで行けるか
- 新規デザイン時の実装責務は誰か
スマホ対応の確認方法:
- スマホで実際にサイトを表示して確認
- ブラウザの開発者ツールでシミュレーション
- Google Mobile-Friendly Testでチェック
注意点:
- 古いテンプレート・テーマはスマホ対応していない場合もあり
- 選定時に「レスポンシブデザイン対応」を要確認
- カスタマイズする場合は、スマホ表示も確認
5. 運用に関する質問
Q16. 導入後、本当に使われるか不安です
A. 以下の3点を押さえれば、社内に定着させられます。
CMS定着の3つのポイント:
1. 業務要件への適合性を検証
「操作しやすい」といった主観ではなく、以下の測定可能な指標で適合性を検証しましょう(一般的な運用で無理なく到達しやすい目安):
- 記事1本あたりの操作ステップ数(目標:10ステップ以内)
- 承認リードタイム(目標:申請から24時間以内)
- 差戻し率(目標:10%以下)
- 教育完了までの時間(目標:1日以内)
デモ/PoCで実際の業務フローを再現し、上記指標を計測しましょう。
2. 運用ルールを明文化
- 役割RACI(誰が責任者、承認者、作業者、情報共有対象か)
- 締切(申請・承認・公開の各期限)
- 品質基準(文字数、画像サイズ、メタ情報等)
- 差戻し基準(どのような場合に差し戻すか)
3. 定着支援体制
- 初月は週次、その後は月次レビュー
- FAQ整備
- トレーニングの再受講枠
失敗パターンと対策:
| 失敗パターン | 原因 | 対策 |
|---|---|---|
| 誰も使わない | 使い方がわからない | トレーニング実施、マニュアル整備 |
| 一部の人しか使わない | 権限がない、操作負荷が高い | 権限設定の見直し、操作ステップの簡素化 |
| 初めだけ使って放置 | 運用ルールがない | 更新頻度の目標設定、定期レビュー |
Q17. 更新作業は本当に楽になりますか?
A. 適切なCMSを選べば、更新作業は大幅に効率化されます。
効率化される作業の例:
想定条件: 従来HTML管理、CMS導入後の比較
【ページ作成】
HTML管理:30分〜1時間(コーディング、FTPアップロード)
CMS:5〜10分(エディタで入力、ボタンクリックで公開)
→ 50〜80%の時間削減
【画像の差し替え】
HTML管理:10分(ファイル名確認、FTPアップロード、キャッシュクリア)
CMS:2分(管理画面でアップロード、自動反映)
→ 80%の時間削減
【複数ページの一括修正】
HTML管理:1時間(全ページを手作業で修正)
CMS:5分(テンプレートを1回修正、全ページに自動反映)
→ 90%以上の時間削減
効率化されない作業:
- コンテンツの企画・執筆
- 画像の撮影・編集
- SEOキーワードの選定
これらはCMSを導入しても、引き続き人手が必要です。
実際の導入事例:
「更新作業が月120時間から月60時間に削減され、その時間をコンテンツ企画に充てられるようになった」(中堅企業・BtoB製造業)
Q18. 複数人で更新する場合、混乱しませんか?
A. CMSの権限管理機能と承認ワークフローを活用すれば、混乱を防げます。
権限管理の設定例:
【管理者】
- 概ねの操作が可能
- ユーザー管理、システム設定
- 人数:1〜2名
【編集者】
- コンテンツの作成・編集・公開
- 他のユーザーの記事も編集可能
- 人数:2〜10名
【ライター(投稿者)】
- コンテンツの作成・編集のみ
- 公開は編集者の承認が必要
- 人数:各部署から1名ずつ
承認ワークフローの例:
1. ライターが記事を作成し、「承認申請」
↓
2. 編集者が内容を確認し、「承認」または「差し戻し」
↓
3. 承認されると自動的に公開(または公開予約)
混乱を防ぐ仕組み:
- 編集中の記事が一覧で確認できる(ダッシュボード)
- 誰が・いつ・何を編集したかの履歴が残る
- 同時編集時は警告が表示される
- バージョン管理で過去の版に戻せる
Q19. セキュリティは大丈夫ですか?
A. SaaS/クラウド型CMSなら、提供事業者がセキュリティ対策を実施するため、社内での対応は最小限で済みます。
SaaS/クラウド型CMSのセキュリティ対策:
- SSL証明書の自動適用(https化)
- 定期的なセキュリティパッチの適用
- DDoS攻撃対策
- WAF(Web Application Firewall)
- 定期的なバックアップ
社内で実施すべきセキュリティ対策:
【必須】
□ 強固なパスワードの設定(12文字以上、英数記号混在)
□ パスワードの定期変更(3〜6ヶ月ごと)
□ 不要なユーザーアカウントの削除
□ 二段階認証の有効化(可能な場合)
【推奨】
□ IPアドレス制限(管理画面へのアクセス制限)
□ 定期的なログイン履歴の確認
□ セキュリティ監査の実施(年1回)
選定時のセキュリティ確認項目:
□ SLA(Service Level Agreement)の有無と内容
□ サポート窓口の対応時間
□ 復旧目標時間(RTO:Recovery Time Objective)
□ 復旧時点目標(RPO:Recovery Point Objective)
□ 二段階認証の対応
□ 監査ログの保持期間
□ バックアップ保持期間
オンプレミス型の場合:
自社でセキュリティ対策を実施する必要があります。IT部門のリソースとスキルが必須です。
セキュリティインシデントが発生した場合:
- SaaS/クラウド型:提供事業者に連絡し、対応を依頼
- オンプレミス型:自社で原因調査・対応
Q20. 更新頻度が低くても意味がありますか?
A. 更新頻度が低くても、以下のメリットがあります。
更新頻度が低い場合のCMSのメリット:
1. 緊急時の対応がスピーディ
- 災害時のお知らせ
- 製品リコール情報
- 営業時間の変更
2. 複数人で管理しやすい
- 担当者の退職・異動時の引き継ぎが楽
- 誰でも更新できる体制
3. 将来の拡張に備えられる
- 将来的にブログやニュースを追加したくなった際、すぐに開始できる
- コンテンツマーケティングを始めるハードルが下がる
4. 保守コストの削減
- HTML管理よりも、長期的には保守しやすい
- 将来のリニューアル時の移行が楽
年に数回しか更新しない場合はHTML管理でもよいですが、月に1回以上更新する、または緊急時の更新が必要な場合はCMS導入を検討する価値があります。
6. トラブル・リスクに関する質問
Q21. 導入に失敗したらどうなりますか?
A. 失敗のパターンは主に3つ。それぞれ対策があります。
失敗パターン1:要件を満たさないCMSを選んでしまった
- 症状: 必要な機能がない、操作負荷が高い
- 影響: 再選定が必要、時間とコストの損失
- 対策: デモ・トライアルで事前確認、要件定義を徹底
失敗パターン2:予算オーバー
- 症状: カスタマイズ費用が想定の2〜3倍に
- 影響: 機能を削減、または追加予算の確保が必要
- 対策: 事前に詳細見積もりを取得、予備費を確保(初期費用の20%)
失敗パターン3:社内に定着しない
- 症状: 誰も使わず、旧来の方法に戻る
- 影響: 導入費用が無駄に
- 対策: 運用ルールの明確化、トレーニングの徹底、業務適合性の検証
小規模(5〜10ページ)でPoC(概念実証)を実施し、問題があれば早期に軌道修正。段階的に導入範囲を拡大しましょう。
Q22. サーバーがダウンしたらどうなりますか?
A. 方式ごとに復旧責任とSLAの扱いが異なります。
SaaS/クラウド型:
- 監視・復旧は提供事業者
- SLA/稼働率・RTO/RPOを契約で確認
- ダウンタイムは年間数時間程度が一般的(稼働率99.9%以上が目安)
※稼働率について: 99.9%は一般的な目安ですが、SLA明示がないサービスもあるため、契約前の確認を推奨します。
オンプレミス(商用/OSS):
- 監視・復旧は自社/保守パートナー
- 冗長構成・監視体制が必須
- IT担当者の24時間対応体制が理想
自社開発:
- 運用/復旧の全責務が自社側
- 体制・手順・演習が鍵
いずれの方式でも:
CDN・キャッシュ・静的フェイルオーバーで影響を緩和できます。
Q23. データが消えたらどうなりますか?
A. バックアップ設計と復旧手順の訓練がカギです。
SaaS/クラウド型:
日次/週次バックアップが用意されることが多いが、**保持期間・復元粒度(ページ単位/全量)**を要確認。復旧も管理画面から実行できる場合が多いです。
オンプレミス/自社開発:
自社でスナップショット+オフサイト保管。年数回の復旧ドリルを推奨します。
バックアップの確認事項:
□ バックアップ頻度(日次?週次?)
□ 保存期間(30日?90日?)
□ 復旧手順の確認(実際に復旧テストを実施)
□ バックアップの保存場所(同じサーバー内はNG)
□ 復元粒度(ページ単位?全量のみ?)
誤削除対策:
ゴミ箱/バージョン復元の有無・保持期間も選定項目に含めましょう。
Q24. 提供事業者がサービスを終了したらどうなりますか?
A. リスクは方式別に異なります。
SaaS/クラウド型:
サービス終了時はデータエクスポート→他CMSへ移行。通知猶予/エクスポート形式/APIを事前確認しましょう。
オンプレミス(商用):
開発元のEoL(End of Life)/サポート打ち切りの可能性。長期サポート契約・後継版の互換を確認しましょう。
自社開発:
キーパーソン退職/技術的負債がリスク。ソース管理/ドキュメント化/バス係数(重要な知識を持つ人数)の確保が必須です。
リスクを減らす選定基準:
- 導入実績が豊富(世界で数万社以上)
- 運営会社が安定している(上場企業、長年の実績)
- ユーザーコミュニティが活発
- データのエクスポート機能がある
サービス終了時の対応:
- 事前通知を確認(通常は6ヶ月〜1年前に通知)
- データをエクスポート(記事、画像、メタ情報等)
- 新しいCMSを選定
- データを移行
- ドメインを切り替え
Q25. セキュリティ事故が発生したらどうなりますか?
A. SaaS/クラウド型なら提供事業者が対応しますが、オンプレミス型は自社で対応が必要です。
セキュリティ事故の例:
- 不正アクセス
- Webサイトの改ざん
- 個人情報の漏洩
- DDoS攻撃
SaaS/クラウド型CMSの場合:
- 提供事業者が24時間監視
- 異常検知時は自動でブロック
- インシデント対応も提供事業者が実施
- 再発防止策も実施
オンプレミス型の場合:
- 自社で監視・対応が必要
- インシデント対応の専門知識が必要
- 対応が遅れると被害が拡大
セキュリティ事故が発生した場合の対応:
- 被害状況の確認
- 提供事業者またはセキュリティ専門家に連絡
- 一時的にサイトを停止(被害拡大を防ぐ)
- 原因調査
- 復旧作業
- 再発防止策の実施
- 必要に応じて、顧客・関係者に報告
事前対策:
セキュリティポリシーの策定、インシデント対応マニュアルの整備、定期的なセキュリティ監査を推奨します。
7. 選定・比較に関する質問
Q26. CMSの選定に何ヶ月かかりますか?
A. 目安は2〜3ヶ月です(企業規模や要件の複雑さで増減)。
選定フェーズのスケジュール(例):
【Week 1-2:要件定義】
- 社内ヒアリング
- 現状分析
- 要件リストの作成
【Week 3-4:候補の絞り込み】
- CMS製品のリサーチ
- 3〜5製品に絞り込み
- RFP(提案依頼書)の作成
【Week 5-6:提案受領・評価】
- 提供事業者から提案書を受領
- 評価シートで比較
- 2〜3製品に絞り込み
【Week 7-8:デモ・トライアル】
- デモンストレーション実施
- トライアル利用(可能な場合)
- 実際の操作感を確認
【Week 9-10:最終選定】
- 社内合意形成
- 最終的に1製品に決定
- 契約交渉
【Week 11-12:契約締結】
- 契約書の確認(法務部門と連携)
- 契約締結
短縮できるケース:
- 小規模サイト → 1ヶ月程度
- 要件がシンプル → 1.5ヶ月程度
- SaaS/クラウド型のみ検討 → 1.5ヶ月程度
長期化するケース:
- 大規模サイト → 4〜6ヶ月
- 複雑なカスタマイズ → 4〜6ヶ月
- ステークホルダーが多数 → 3〜6ヶ月
Q27. デモやトライアルは実施すべきですか?
A. 原則として実施を推奨します。カタログだけでは業務適合性は判断できません。
デモ・トライアルで確認すべきポイント:
【操作負荷の測定】
□ ページ作成にかかる操作ステップ数(目標:10ステップ以内)
□ ページ作成にかかる時間(目標:10分以内)
□ 画像アップロードの手順(目標:3ステップ以内)
□ 公開までのステップ数(目標:3ステップ以内)
【機能】
□ 必須機能が実際に動作するか
□ 承認ワークフローの使い勝手(承認リードタイムの目標:24時間以内)
□ 検索機能の精度
□ レスポンス速度
【デザイン】
□ テンプレートのクオリティ
□ カスタマイズの自由度
□ スマホ表示の確認
【サポート】
□ ドキュメントの充実度
□ サポート対応の質(デモ中に質問してみる)
デモ・トライアルの実施方法:
1. 提供事業者主導のデモ(1〜2時間)
- 提供事業者が画面を共有して説明
- 質問をその場で解決
- 複数の提供事業者を比較しやすい
2. トライアル利用(1〜2週間)
- 実際に社内メンバーが操作
- 実際の業務に近い形で評価
- より正確な判断ができる
重要: 実際に更新作業を行う担当者全員にデモ・トライアルに参加してもらいましょう。
Q28. 複数のCMSを比較する際のポイントは?
A. 評価シートを作成し、定量的に比較しましょう。
評価シートの作成方法:
1. 評価項目を洗い出す
【機能(40点)】
- 必須機能が揃っているか(20点)
- 重要機能が揃っているか(15点)
- あれば便利な機能(5点)
【業務適合性(20点)】
- 操作ステップ数(10点):目標10ステップ以内
- 教育時間(5点):目標1日以内
- ドキュメントの充実度(5点)
【コスト(20点)】
- 初期費用(10点)
- ランニングコスト(10点)
【サポート(10点)】
- サポート体制(5点)
- レスポンスタイム(5点)
【拡張性(10点)】
- 将来の機能追加(5点)
- マルチサイト対応(5点)
2. 各製品を採点
| 評価項目 | 配点 | CMS A | CMS B | CMS C |
|---|---|---|---|---|
| 必須機能 | 20点 | 20点 | 18点 | 16点 |
| 重要機能 | 15点 | 12点 | 15点 | 10点 |
| あれば便利な機能 | 5点 | 3点 | 4点 | 5点 |
| 操作ステップ数 | 10点 | 9点 | 7点 | 8点 |
| 教育時間 | 5点 | 5点 | 4点 | 5点 |
| ドキュメント | 5点 | 4点 | 5点 | 3点 |
| 初期費用 | 10点 | 8点 | 6点 | 9点 |
| ランニングコスト | 10点 | 7点 | 8点 | 9点 |
| サポート体制 | 5点 | 5点 | 4点 | 3点 |
| レスポンスタイム | 5点 | 4点 | 5点 | 3点 |
| 将来の機能追加 | 5点 | 4点 | 5点 | 3点 |
| マルチサイト対応 | 5点 | 3点 | 5点 | 2点 |
| 合計 | 100点 | 84点 | 86点 | 76点 |
3. 総合評価
点数だけでなく、「絶対に譲れない要件」も考慮し、社内で合意形成しましょう。
Q29. 海外製と国産、どちらを選ぶべきですか?
A. 以下の判断基準で選びましょう。
海外製CMSのメリット:
- グローバルシェアが高く、導入実績が豊富
- 機能が充実している
- プラグイン・テーマが豊富
- コミュニティが活発
- 代表例:WordPress、Drupal、Joomla、Contentful、Strapi
海外製CMSのデメリット:
- 日本語ドキュメントが少ない場合も
- 日本語サポートがない、または限定的
- 日本特有の機能(例:全角対応、和暦表示等)に対応していない場合も
国産CMSの特徴(一般論):
日本語ドキュメント・サポートが手厚く、承認フローや稟議運用など国内商習慣に適した機能を備えるものが多い。
※個別製品名について: 本稿では国内CMS各社の個別名の記載を省略しています。
判断基準:
【海外製を選ぶ価値が高いケース】
- グローバル展開を予定している
- 英語のドキュメントで問題ない
- 最新技術・機能を重視
【国産を選ぶ価値が高いケース】
- 日本語サポートが必須
- 社内に英語に対応できる人材がいない
- 日本特有の商習慣に対応したい
Q30. オープンソースと商用、どちらを選ぶべきですか?
A. 社内のIT人材とサポートの必要性で判断しましょう。
オープンソースCMSが適しているケース:
- 初期費用を抑えたい
- 社内にITエンジニアがいる(サーバー管理、カスタマイズ対応)
- 自由なカスタマイズが必要
- 長期的に見てコストを抑えたい
商用CMSが適しているケース:
- 手厚いサポートが必要
- 社内にITエンジニアがいない
- セキュリティ対応を提供事業者に任せたい
- SLA(稼働率保証)が必要
コスト比較の例:
想定条件: BtoB企業/従業員300〜1,000名/中規模サイト
※金額は参考値。要件・規模・契約条件により大きく変動します。
【オープンソースCMS(5年間の総コスト)】
初期:500万円(構築・カスタマイズ)
年間:200万円(サーバー・保守)
合計:1,500万円
※ライセンス費用なし
【商用CMS(5年間の総コスト)】
初期:2,000万円(ライセンス・構築)
年間:600万円(年間ライセンス+保守契約)
合計:5,000万円
※年間ライセンスの場合、毎年更新費用が発生
商用CMSのライセンス形態:
- 買い切り型:初期に一括購入、保守契約は別途
- 年間ライセンス型:毎年更新、保守契約込みの場合も
補足: オープンソースCMSでも、有償サポートを提供している企業もあります(例:WordPressの保守サービス等)。
8. 移行に関する質問
Q31. 既存サイトからの移行は大変ですか?
A. 難易度は情報構造と既存データの品質次第です。一般に以下の三択です。
移行パターン別の現実:
1. 自動移行:
旧CMSの構造と近く、API/エクスポートが整備されている場合に可能。ただし、このパターンが通用するケースは限定的です。
2. 半自動移行:
本文は自動、画像/添付/タグ/内部リンク修正は手作業。多くのプロジェクトがこのパターンになります。
3. 手動再登録:
構造が大きく異なる、または旧データが不良な場合。品質を優先する場合、あえてこの方式を選ぶこともあります。
計画時の重要ポイント:
どのページを"移行せずに新規書き起こすか"まで含めて設計し、品質と工期のトレードオフを可視化しましょう。
移行の難易度(参考):
想定条件: 企業規模別の標準的なサイト構成
【簡単(1〜2週間)】
- ページ数:50ページ以下
- コンテンツ:テキストと画像のみ
- 動的機能なし
【中程度(1〜2ヶ月)】
- ページ数:50〜300ページ
- コンテンツ:テキスト、画像、PDF等
- 簡単な動的機能(お問い合わせフォーム等)
【困難(3〜6ヶ月)】
- ページ数:300ページ以上
- コンテンツ:複雑な構造、データベース連携
- 高度な動的機能(会員機能、EC機能等)
移行範囲を絞る(全ページではなく、重要ページのみ)、段階的に移行(一部のページから開始)、移行ツールを活用(ただし完全自動化は期待しない)などの方法で負荷を軽減できます。
Q32. SEOへの影響はありますか?
A. 適切に設計すれば影響を最小化に努められますが、URL構造やテンプレ制約によっては1対1の301が困難な場合があります。
CMS移行でSEOに影響する要素:
- URLの変更
- サイト構造の変更
- コンテンツの変更
- 表示速度の変化
SEOへの影響を最小化する対策:
1. 301リダイレクトの設定(最重要)
旧URL:https://example.com/old-page.html
新URL:https://example.com/new-page/
301リダイレクトを設定することで:
- 旧URLへのアクセスを新URLに転送
- 検索エンジンの評価を引き継ぐ
- 外部リンクの価値を保持
URL構造が合わない場合の代替手段:
- 近縁コンテンツへの集約リダイレクト
- 恒久削除(410)の明示
- ハブページ新設→関連群を集約
2. サイトマップの再送信
- 新しいサイトマップをGoogle Search Consoleに送信
- インデックスの更新を促進
3. 内部リンクの修正
- 主要な内部リンクを新URLに更新
- リンク切れがないか確認
4. メタ情報の引き継ぎ
- title、descriptionを旧サイトから引き継ぐ
- 必要に応じて最適化
移行後のSEOチェックリスト:
□ 301リダイレクトが正しく設定されているか確認する
□ リンク切れがないか確認する(Screaming Frog等のツール活用)
□ サイトマップを送信する
□ Google Search Consoleでクロールエラーを確認する
□ ページ表示速度を確認する(PageSpeed Insights)
□ 移行後2〜4週間、検索順位を毎日モニタリングする
大規模サイトのリダイレクト運用Tips:
ページ数が多い場合、正規表現やパスマッピングで一括適用し、例外のみ個別設定する方が現実的です。
Q33. 移行期間中、サイトは停止しますか?
A. ダウンタイムを最小限に抑えられるよう計画しましょう。
段階移行(並行運用→切替)を選べばほぼ無停止も狙えますが、一括移行では数時間規模の停止が発生することがあります。深夜帯の切替・事前リハーサル・ロールバック手順の用意が肝要です。
移行の方式:
方式1:段階的移行(推奨)
1. 新CMSを別ドメインで構築・テスト
2. 一部のページから新CMSに移行
3. 問題がなければ、全ページを順次移行
4. 最後にドメインを切り替え
ダウンタイム:ほぼゼロ(ドメイン切り替え時のみ数分〜数時間)
方式2:一括移行
1. 新CMSを構築・テスト(旧サイトと並行)
2. 移行日を決定し、サイトを一時停止
3. データを一括移行
4. 動作確認
5. 新サイトを公開
ダウンタイム:数時間〜1日程度
移行作業は深夜・早朝に実施(アクセスが少ない時間帯)、事前に十分なテストを実施、移行手順書を作成しリハーサルを実施、トラブル時のロールバック手順を準備することでダウンタイムを最小化できます。
ユーザーへの告知:
移行予定日の1〜2週間前に告知、移行中は「メンテナンス中」ページを表示、問い合わせ先を明記。
Q34. 旧サイトのデータは保存しておくべきですか?
A. 保存を推奨します。最低でも1年間は保管することをお勧めします。
旧サイトのデータを保存する理由:
1. トラブル時のロールバック
- 移行後に重大な問題が発覚した場合、旧サイトに戻せる
- データ移行漏れが見つかった場合、旧データから復旧できる
2. 法的・コンプライアンス上の理由
- 過去の公開情報の記録として保持
- 問い合わせ対応で過去の情報が必要になる場合
3. コンテンツの参照
- 移行時に削除したページを後から復活させたい場合
- 過去のコンテンツを参考にする場合
保存方法:
【推奨】
- サーバー全体のバックアップ(データベース + ファイル)
- 外部ストレージに保存(Amazon S3、Google Cloud Storage等)
- 複数箇所に保存(バックアップのバックアップ)
【最低限】
- 静的HTML化してダウンロード(wget、HTTrack等のツール活用)
- ローカルPCまたは外部HDDに保存
保存期間:
最低1年間、推奨3年間。法的要件がある場合はそれに従ってください。
Q35. 移行後、旧URLへのアクセスはどうなりますか?
A. 301リダイレクトを設定すれば、旧URLへのアクセスも新URLに自動転送されます。
301リダイレクトとは:
- 「このページは恒久的に移転しました」という意味
- ブラウザと検索エンジンに新しいURLを伝える
- SEO評価を引き継ぐ
リダイレクト設定の例:
【.htaccessファイル(Apacheサーバーの場合)】
Redirect 301 /old-page.html https://example.com/new-page/
【Nginxの場合】
rewrite ^/old-page.html$ https://example.com/new-page/ permanent;
【CMSの機能で設定】
多くのCMSはリダイレクト設定機能を標準装備
管理画面から簡単に設定可能な場合が多い
リダイレクト設定のポイント:
原則として概ねの旧URLに対して設定(ページ単位で設定)、トップページだけではなく下層ページも忘れずに、外部サイトからのリンクも考慮。
リダイレクトしない場合のリスク:
404エラー(ページが見つかりません)、外部リンクからのアクセスが失われる、SEO評価がリセットされる、ユーザー体験の悪化。
301リダイレクトは原則として設定を推奨します。
9. 移行方針マトリクス
移行の優先順位を決める際の参考にしてください。
| 優先度 | 品質 | コスト | 期間 | 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 高品質重視 | 高 | 高 | 長 | 手動再登録中心 |
| バランス型 | 中 | 中 | 中 | 半自動+選択的手動 |
| スピード重視 | 低〜中 | 低 | 短 | 自動移行+事後修正 |
10. まとめ:迷ったときの判断基準
本記事では、CMS導入でよくある35の質問に回答しました。最後に、判断に迷ったときの基準をまとめます。
CMS導入の判断基準:
【導入を検討する価値が高いケース】
- ページ数が500以上(大規模)または20以上(中小規模)
- 月に10ページ以上更新する(大規模)または5ページ以上(中小規模)
- 複数人(10名以上)で更新作業を行う
- 外部委託費が月10万円以上
- 非エンジニアが更新作業を行う
- 将来的にページ数・更新頻度を増やす予定
- 監査ログや承認フローが必須
【導入を見送ってもよいケース】
- ページ数が10ページ以下
- 年に数回しか更新しない
- 予算が確保できない
- 社内体制が整っていない
CMSタイプの選び方:
【SaaS/クラウド型】
- 初期費用を抑えたい
- IT人材がいない
- 即座に開始したい
【オンプレミス型】
- 独自カスタマイズが多い
- IT人材がいる
- 長期利用(5年以上)
【自社開発】
- 独自要件が極めて多い
- 大規模な開発チームがある
- 10年以上の長期利用
迷ったら:
- 小規模から始める:いきなり全社展開ではなく、一部のページから
- トライアルを活用:無料トライアルで実際に試す
- 専門家に相談:Webコンサルタント、システムインテグレーター等
CMS導入は企業のWebサイト運営を大きく変える重要な意思決定です。本記事のQ&Aを参考に、自社に最適な選択をしてください。
11. 選定チェックリスト
方式共通チェック項目
□ 操作ステップ数(目標:10ステップ以内)
□ 承認リードタイム(目標:24時間以内)
□ 教育完了時間(目標:1日以内)
□ データエクスポート機能の有無
□ バックアップ保持期間(推奨:90日以上)
□ 監査ログ保持期間(法規要件に応じて)
SaaS/クラウド型追加チェック
□ SLA稼働率(目標:99.9%以上)
□ RTO/RPO
□ サービス終了時のデータ移行サポート
オンプレミス型追加チェック
□ 社内運用体制(24時間監視の可否)
□ 冗長構成の設計
□ 災害復旧計画(DR)
□ 長期サポート契約の有無
記事情報
最終更新日:2025年11月7日
主対象読者: 中堅〜大企業(従業員300〜10,000名規模)で部門横断の更新体制や監査・可用性要件を持つ組織
副対象読者: 中小企業で将来的にマルチサイト/会員・MA連携を視野に入れている組織
※本記事の情報は公開時点のものです。CMS製品の機能や価格は変更される可能性がありますので、導入検討時は必ず最新情報をご確認ください。本稿の費用・期間・効果はBtoB企業向け中〜大規模サイトの支援案件で観測した中央値ベースの参考値です。業種・規模・要件・体制・SLA(稼働率)/RTO/RPO、監査・法規要件により大きく変動しますので、自社の状況に合わせて再計算してください。
本稿は一般的情報の提供を目的とし、特定製品や方式の優位性を断定するものではありません。