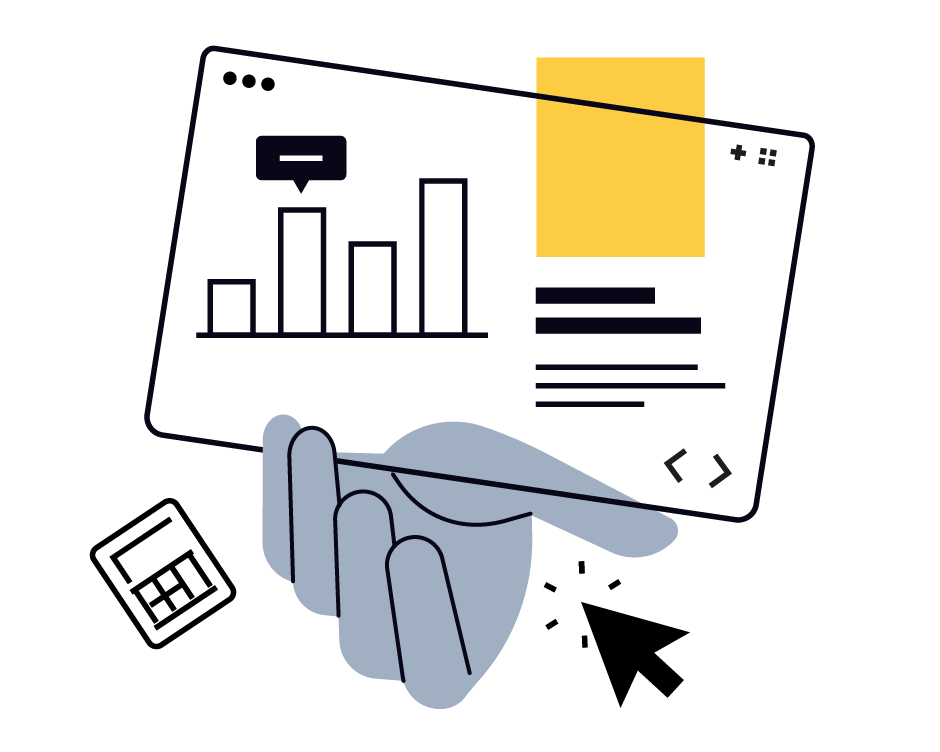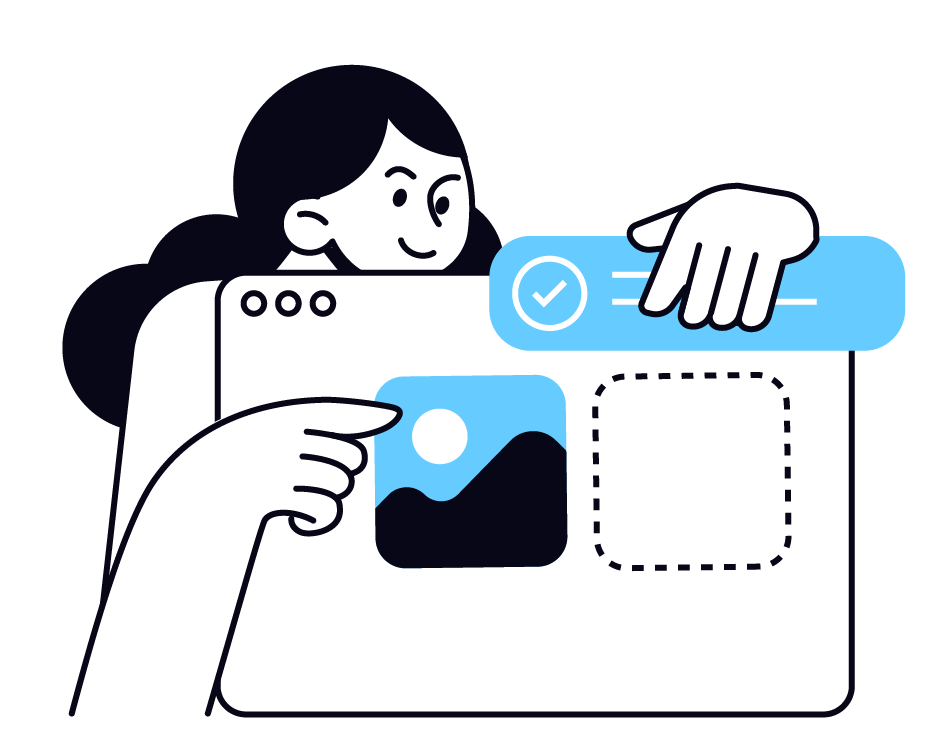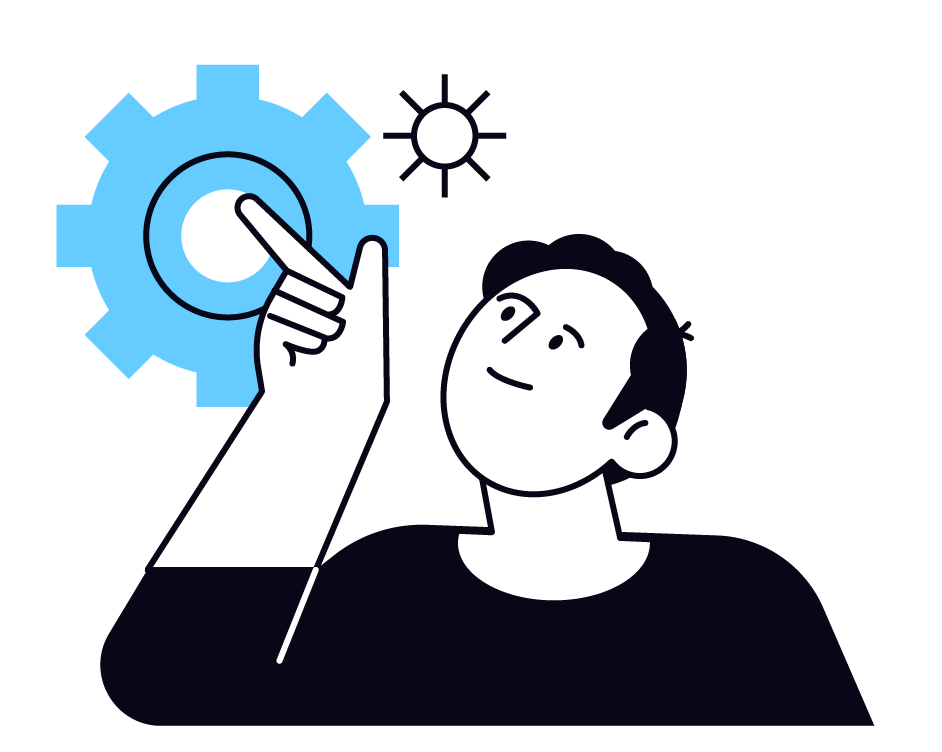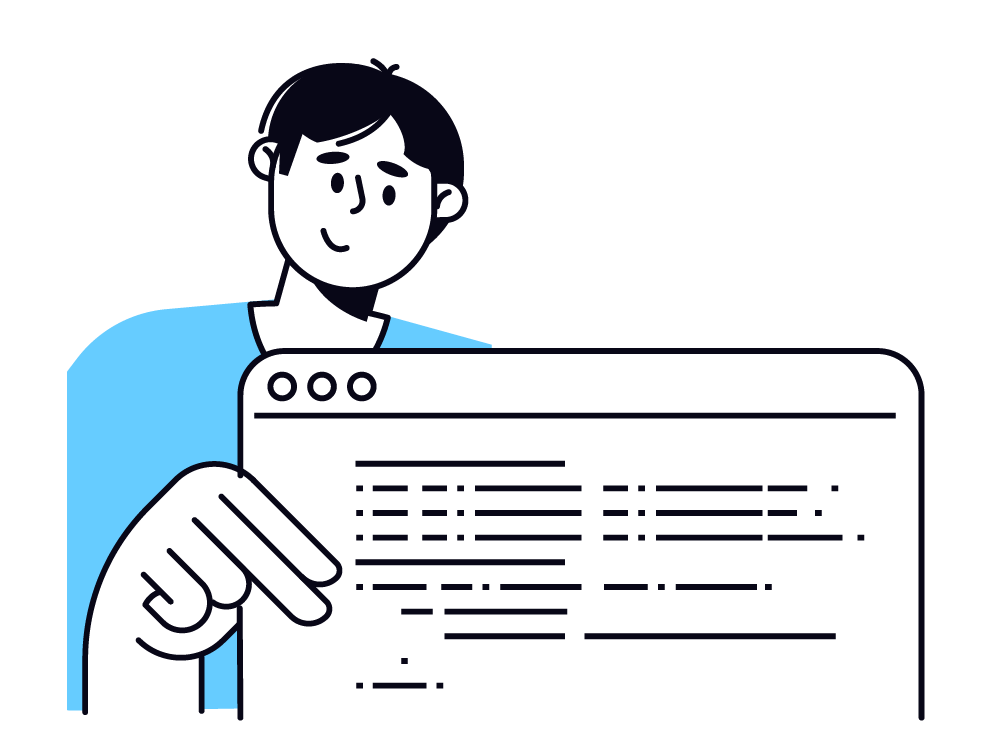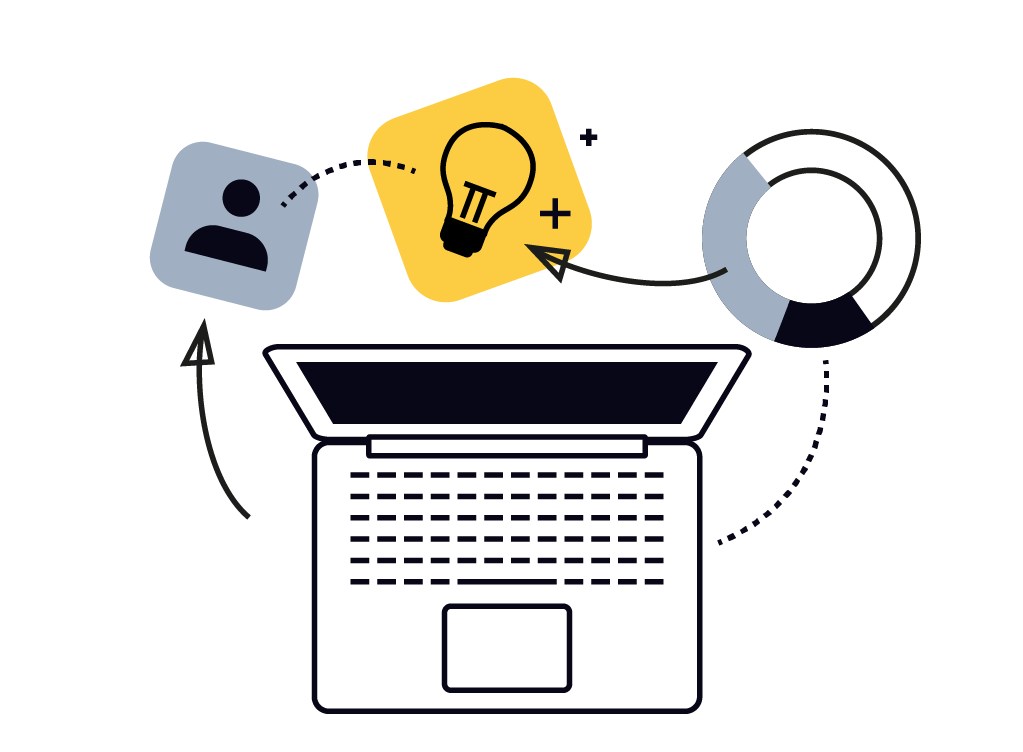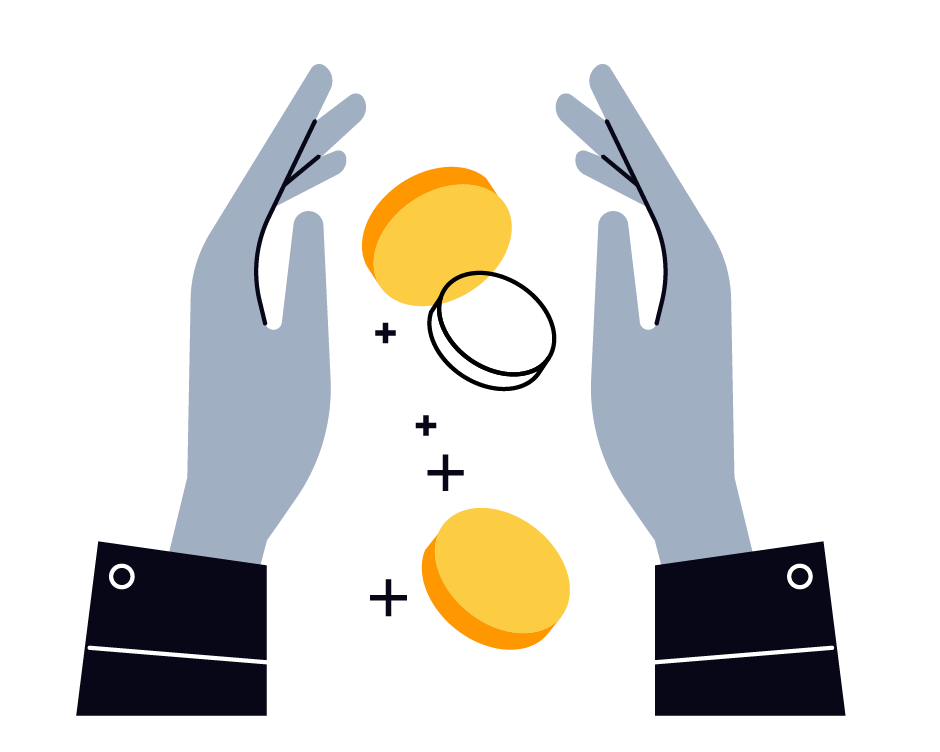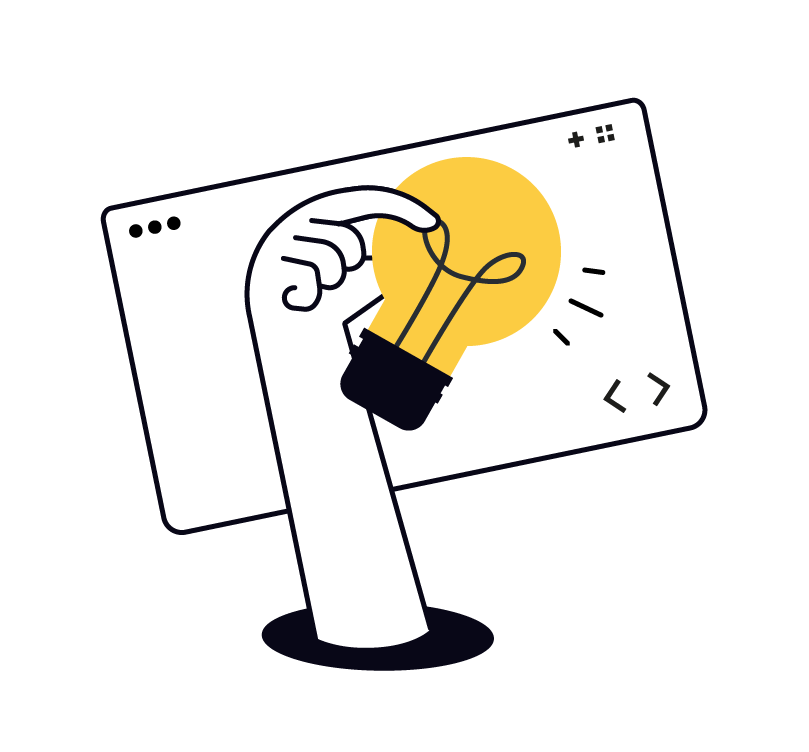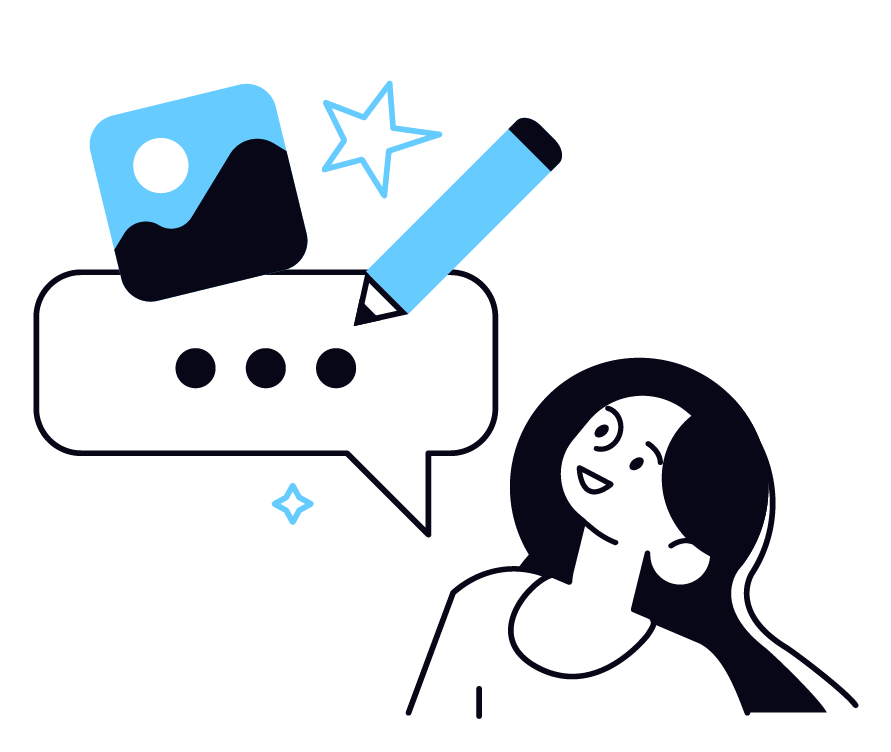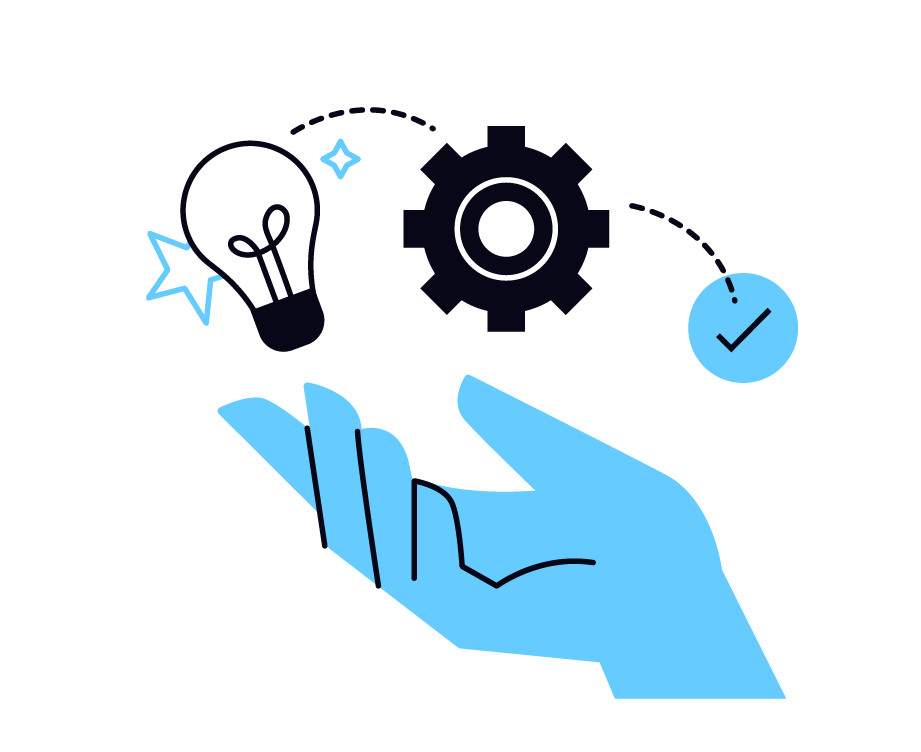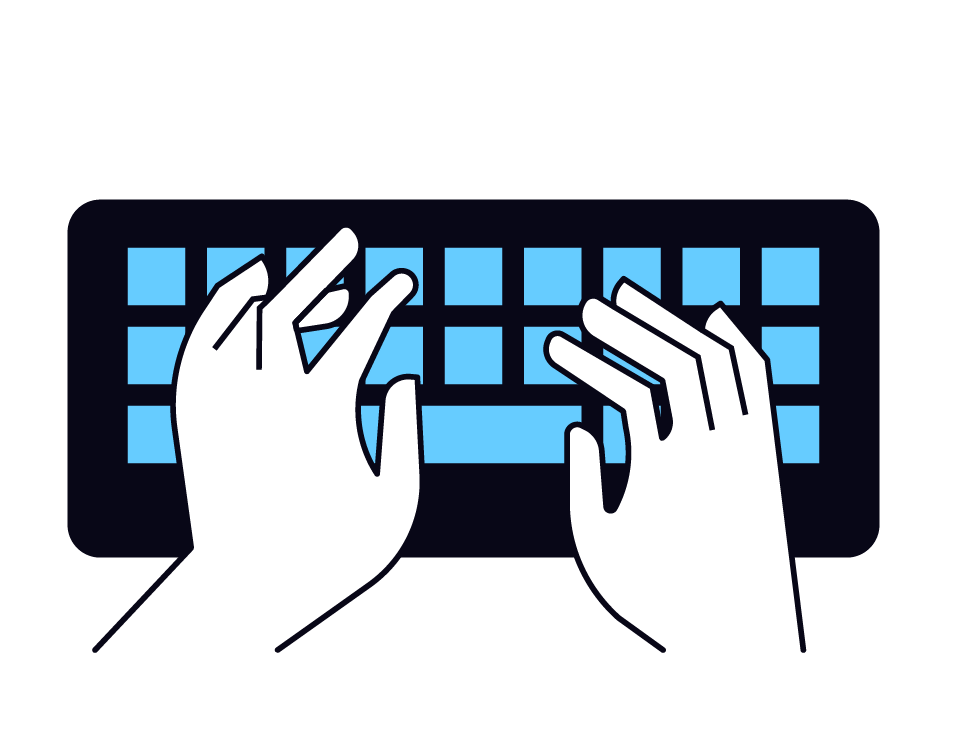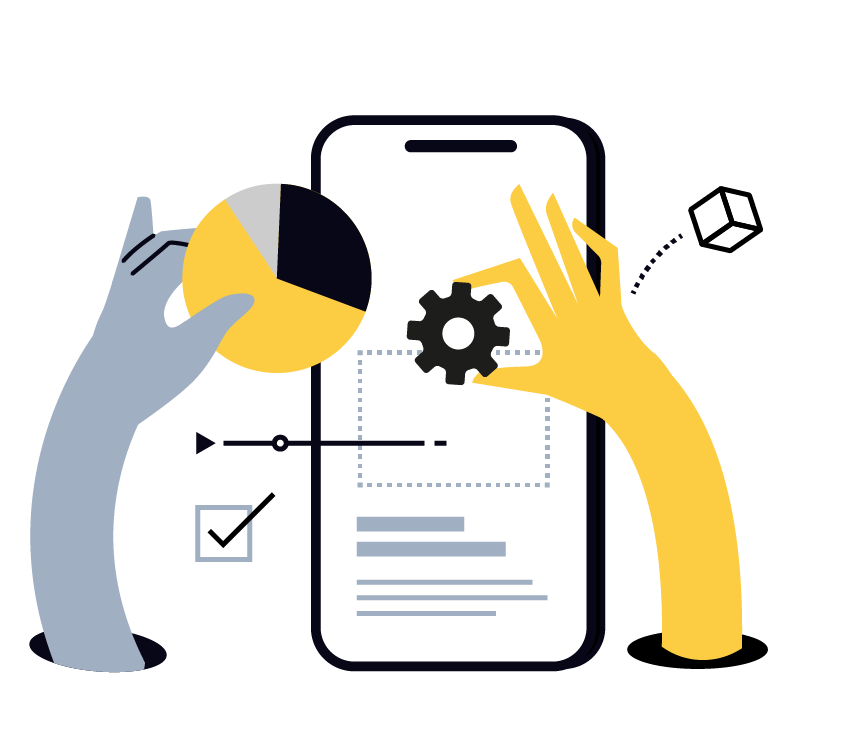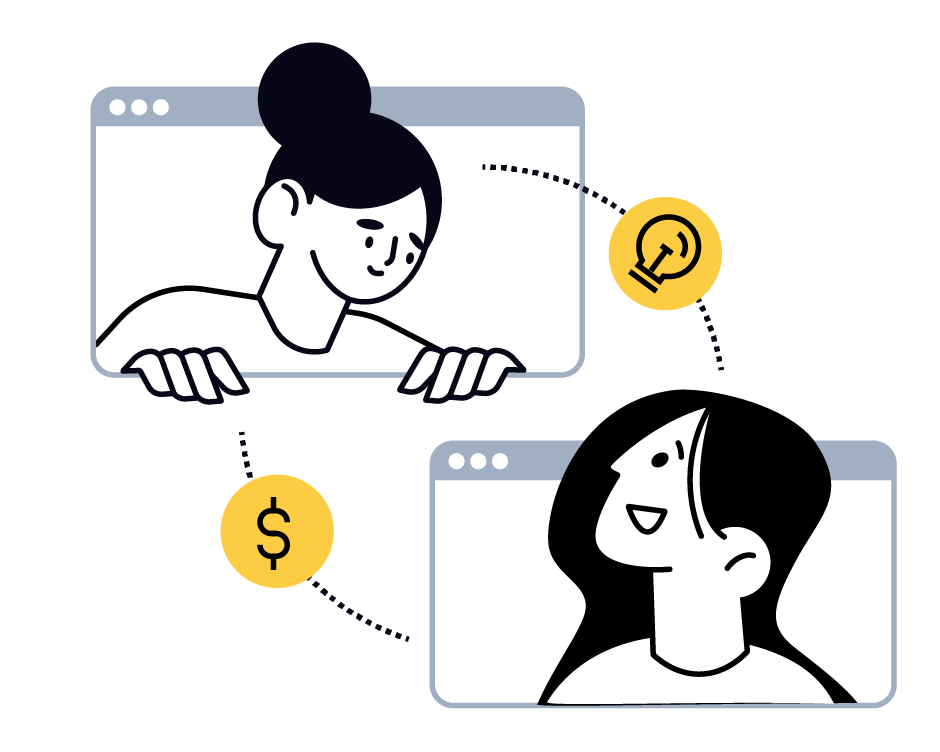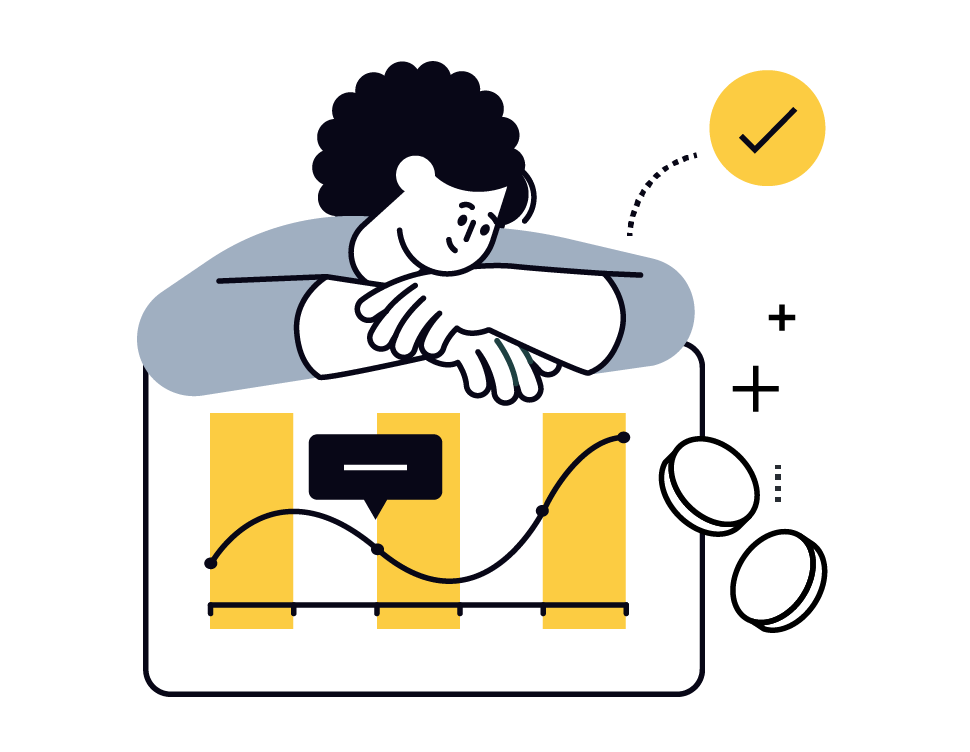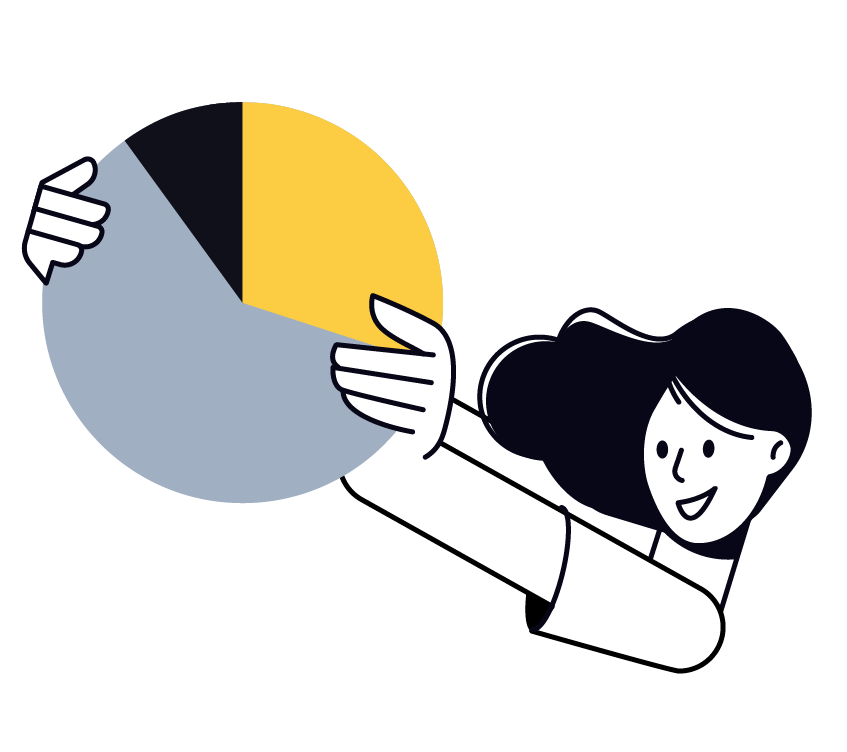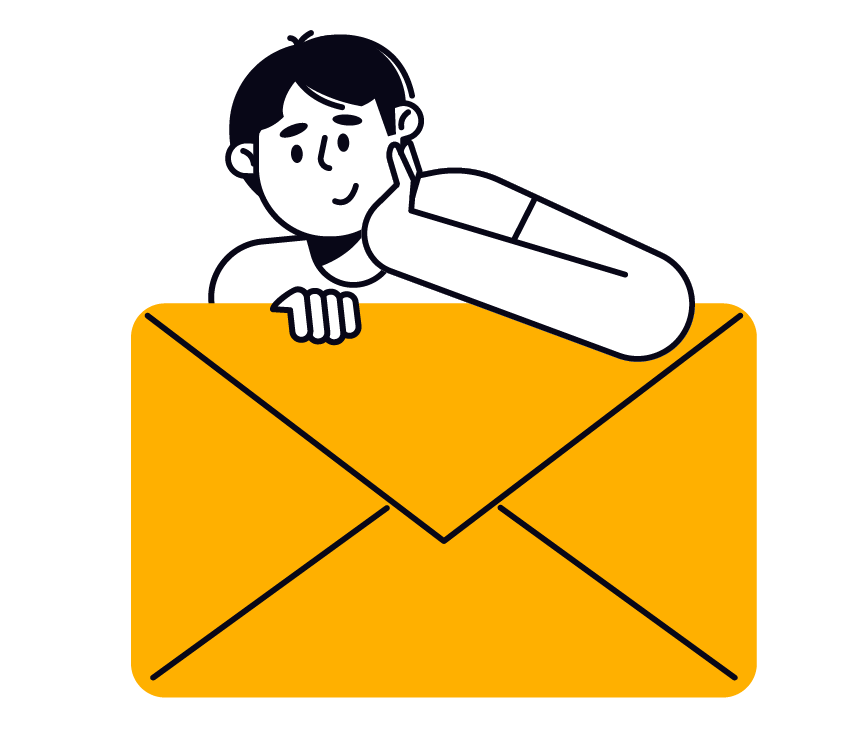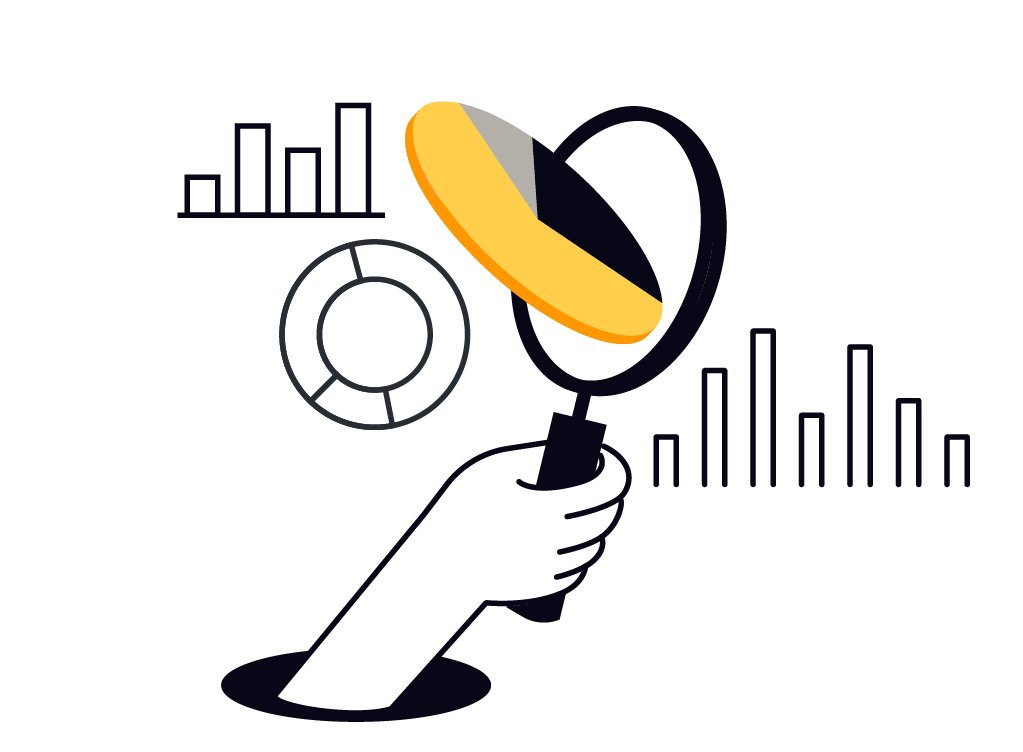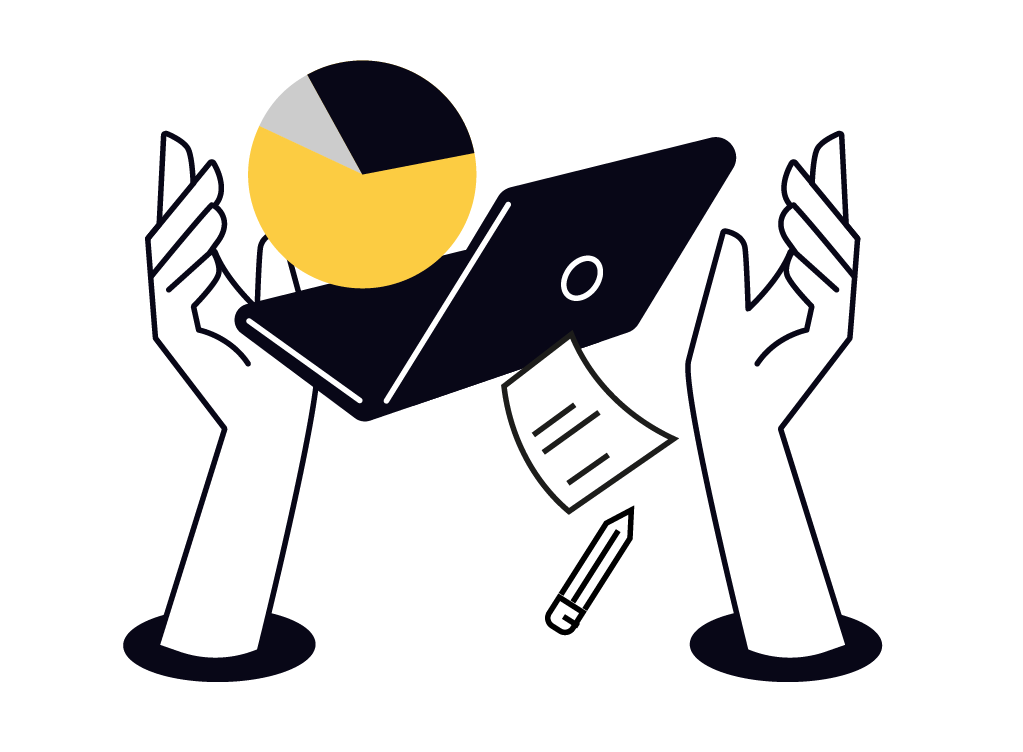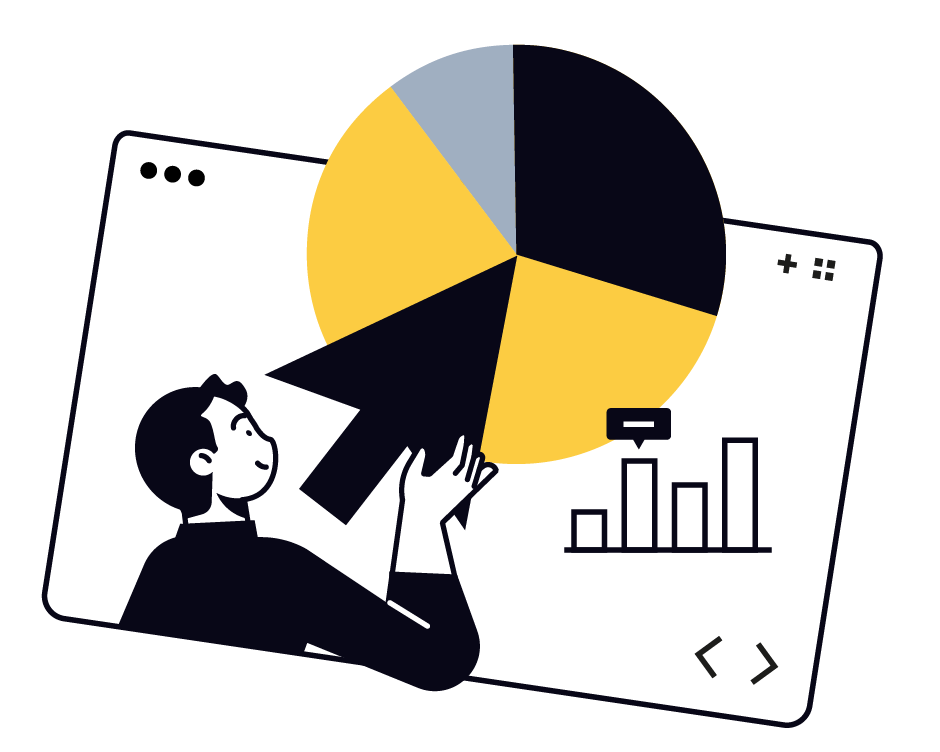1. なぜKPIとダッシュボードが必要なのか?
Webサイトやマーケティング施策の効果を測るうえで、KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)とダッシュボードは不可欠な存在です。KPIがなければ、そもそも「何をもって成功とするか」が定まりません。そして、KPIが定まっていても、データが整理されていなければ、関係者と成果を共有し判断することができません。
特にBtoB企業においては、Web経由の問い合わせや資料請求といったCV(コンバージョン)までのプロセスが長期化するため、途中の段階(中間指標)をしっかりモニタリングしないと、改善のタイミングを逃してしまうこともあります。
たとえば、ある製造業の企業では、定期的にセミナーを開催していたものの、参加申し込みが伸び悩んでいました。データを分析したところ、LPの滞在時間は長いものの申込完了率が低いというKPIから、フォーム入力の負荷が原因であることが判明。フォームの項目を減らしただけでCVが2倍になったという事例もあります。
1-1. KPI設計の基本的な考え方
KPIを設計する際には、以下のようなフレームで段階的に設定するのが有効です。
- 目的(Goal):なぜその施策を行うのか?例)リードを増やしたい
- 成果指標(KGI):最終的に得たい成果。例)資料請求100件/月
- 主要KPI:KGIを構成する中核指標。例)フォーム到達率、完了率、再訪率
- 補助KPI:背景を読み解くサブ指標。例)滞在時間、直帰率、CTR
目的が「とにかくUU(ユニークユーザー)を増やす」になってしまうと、KPIがサイトの集客数だけになり、CVにつながらない施策に走りがちです。逆に、商談や契約といったオフラインに近い成果だけをKPIにすると、Web担当者が施策を回しづらくなるリスクもあります。
1-2. KPIが不明確だと起こる問題
例1:施策の効果が正しく判断できない
SNSで多くのいいねやシェアが付いた投稿があっても、それがリードに直結しなければ本来の目的とはズレが生じます。KPIが設定されていないと「反応がよかった=成功」と誤認されるケースも。
例2:現場と上層部で評価の目線が揃わない
マーケティング部門はフォーム到達率をKPIとして重視していても、営業部門は受注数しか見ていないという状況では、評価指標が分断され改善施策が定まりません。
例3:ダッシュボードがKPIと結びついていない
ダッシュボードに大量の数字やグラフが並んでいるものの、何が重要で何が判断材料なのかがわからず、データが「報告のための報告」になってしまうことがあります。
例4:チームの方向性がバラバラになる
KPIが明確でなければ、チーム内で「どこを目指すのか」「何に注力すべきか」が統一されません。その結果、メンバーがバラバラな指標をもとに動いてしまい、全体として非効率な運用になります。たとえば一方では流入数を増やす施策を行い、もう一方ではCVR改善に注力しているために連携がとれず、どちらの成果も中途半端になるという事態も起こり得ます。
例5:改善サイクルが機能しない
PDCAを回すうえで「どの指標を改善するのか」が曖昧だと、施策の目的と評価が一致せず、改善活動が形骸化してしまいます。A/Bテストを行っても、何をもって良しとするのか判断できず、次の一手が出せないということも。
2. “伝わる”ダッシュボード設計のポイント
2-1. 見せる相手を明確にする
ダッシュボードは、見る人によって設計が変わるべきです。たとえば、Web担当者向けにはPVやCVRといった現場の改善に直結する指標を中心にし、経営層向けには月次での成果やトレンドを俯瞰できる構成が適しています。
よくある課題例:
全社共有のGoogleスプレッドシートに大量の指標が並んでいるが、誰も見ておらず「報告義務を果たすだけ」の存在に。経営層から「で、これ結局どうなってるの?」と言われるケースも散見されます。
対策:
- 相手ごとにKPIの粒度や見せ方を変える
- 「何を見て、どう判断してほしいか」を意識して設計する
- ステークホルダーごとにレイヤーを分けたビューを用意し、同じデータを役割に応じて解釈できるようにする
2-2. ダッシュボードに最低限必要な要素
-
目的にひもづいたKPIの可視化
表面上の数値だけでなく、「なぜこの数値を追っているのか」が理解できるよう、指標の背景や定義も含めて設計します。指標に“注釈”をつけておくことも、KPIの意味を関係者と共有するうえで有効です。 -
推移と比較
単一の数値では判断できないため、前月比・前年比・目標比などを表示し、変化や異常を発見しやすくします。グラフやトレンドラインの活用により、「どこが変化したか」「何が影響しているか」が見えるようになります。 -
行動に結びつく示唆
「良かった/悪かった」だけでなく、「なぜそうなったのか」「次に何をすべきか」が見える設計が重要です。たとえば、CVRが急落したときに「流入元の変化」「フォーム離脱率の増加」などを視覚的に示せれば、改善の議論が進みやすくなります。 -
UI/UXの工夫
ダッシュボードが見づらければ、活用されません。色分けやグラフ形式、視認性の高いフォントなど、伝わる“見せ方”を意識しましょう。情報の優先順位をつけてレイアウトする、重要な数値にはアイコンや背景色で強調するなどの工夫も有効です。
まとめ
KPIとダッシュボードは、単なるレポートではなく「施策の意思決定を支えるツール」です。誰のために、どんな行動を促すために設計するのか?──この視点が欠けると、データは“管理のための情報”になってしまいます。
逆に、目的に沿って整理されたKPIと、見やすく共有しやすいダッシュボードがあれば、マーケティング施策の改善スピードと精度は格段に向上します。CMSの有無を問わず、どんな企業にとっても、この「見える化」は競争力の源泉になりうるのです。