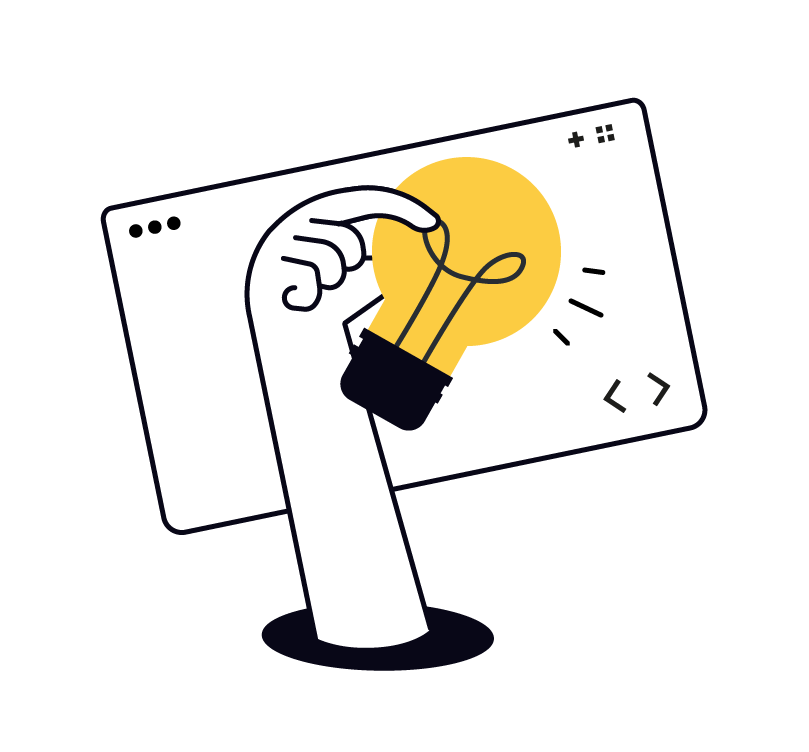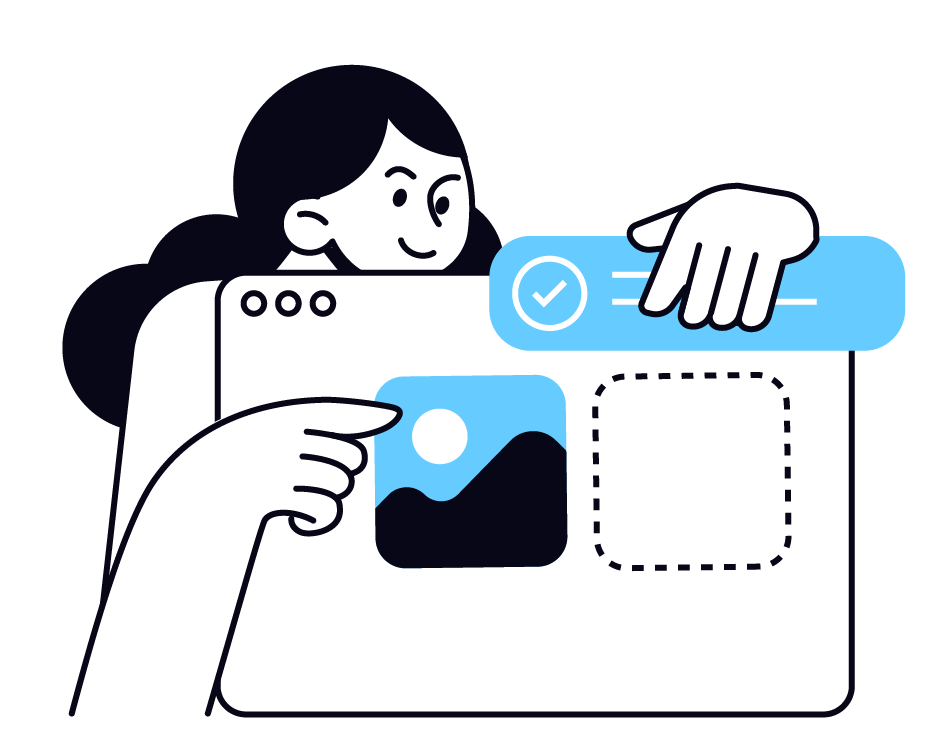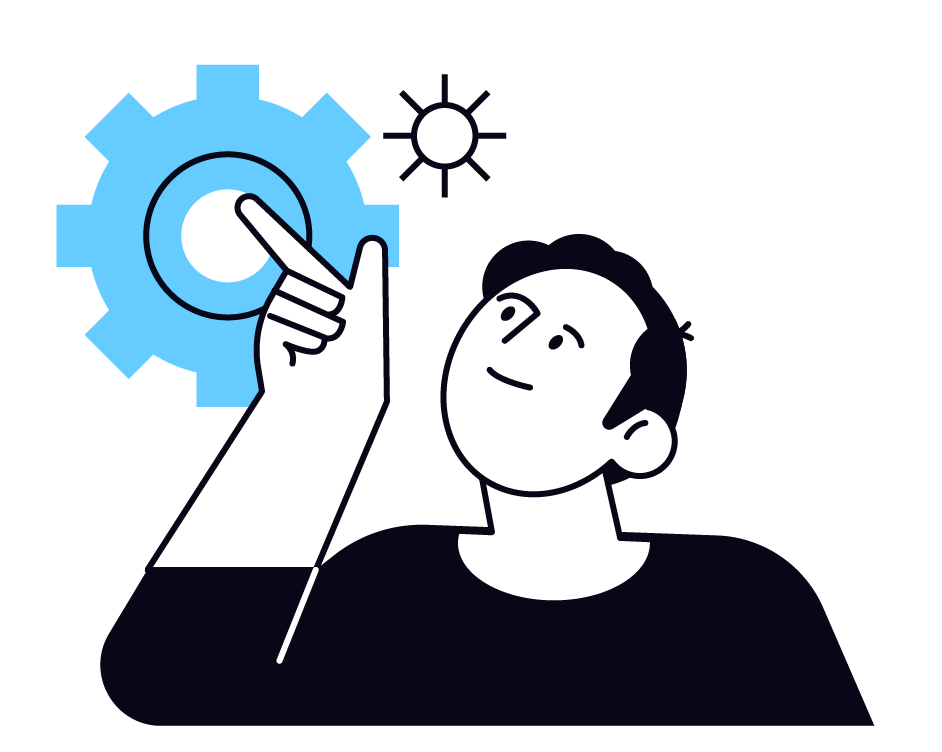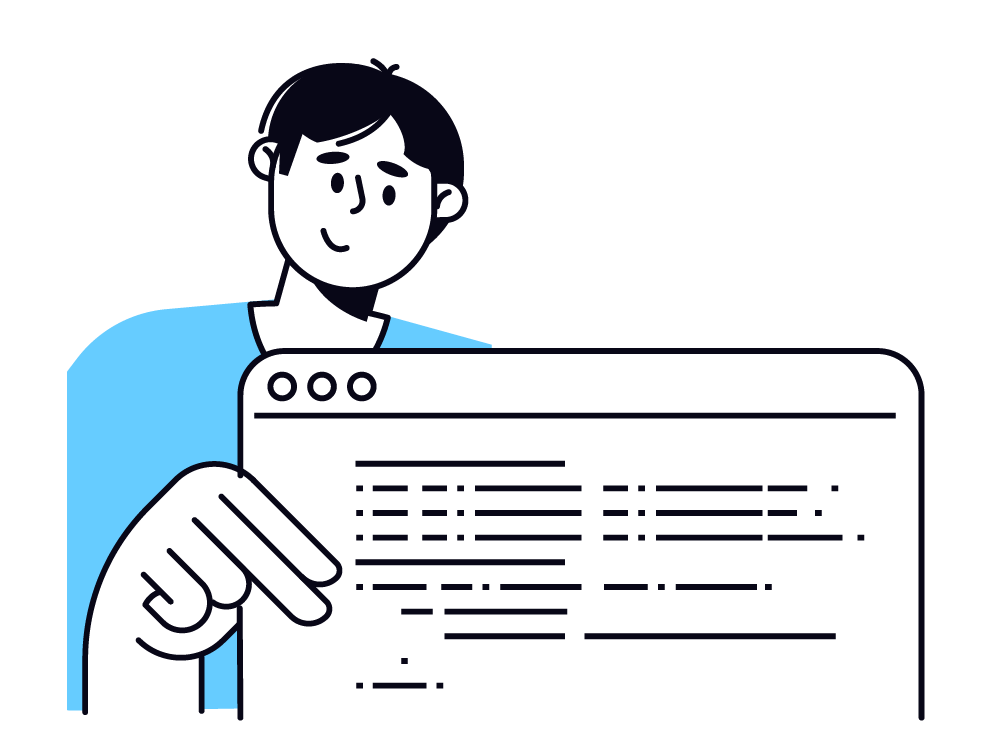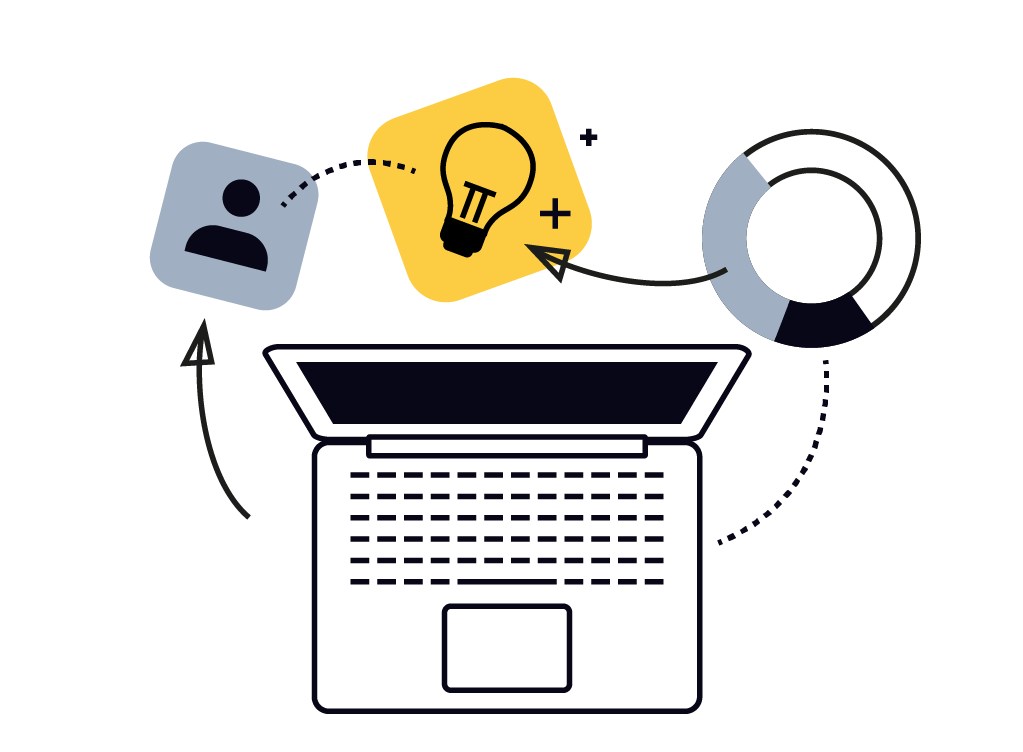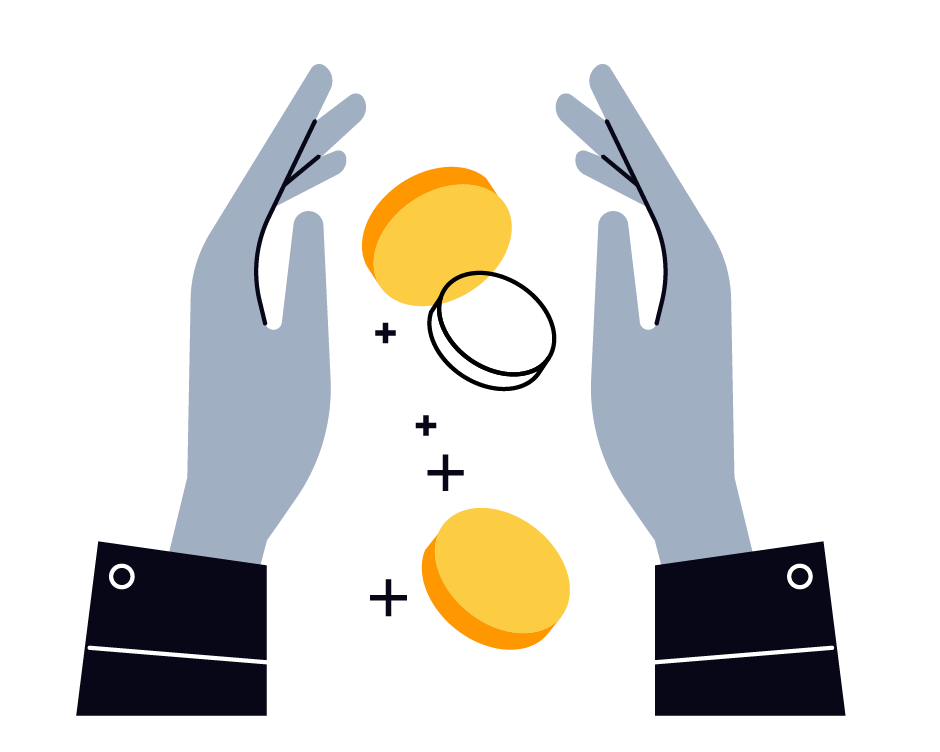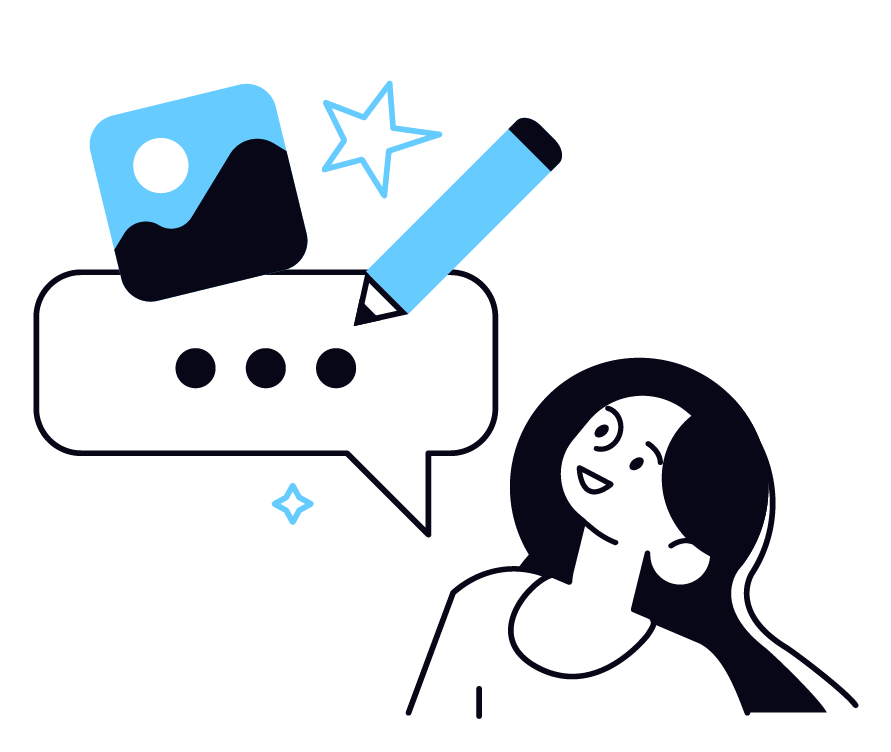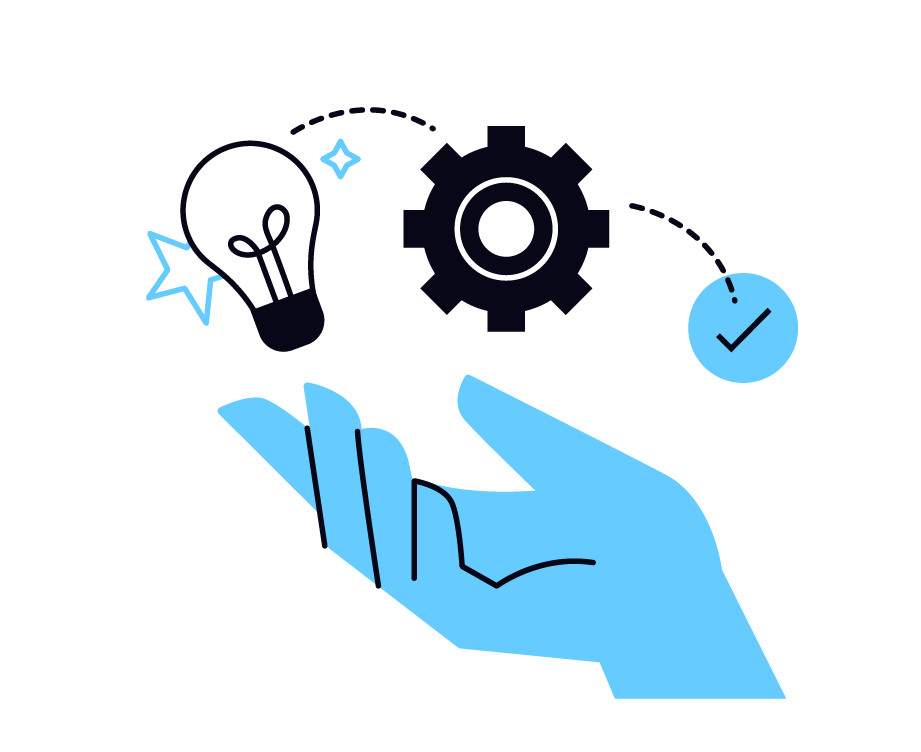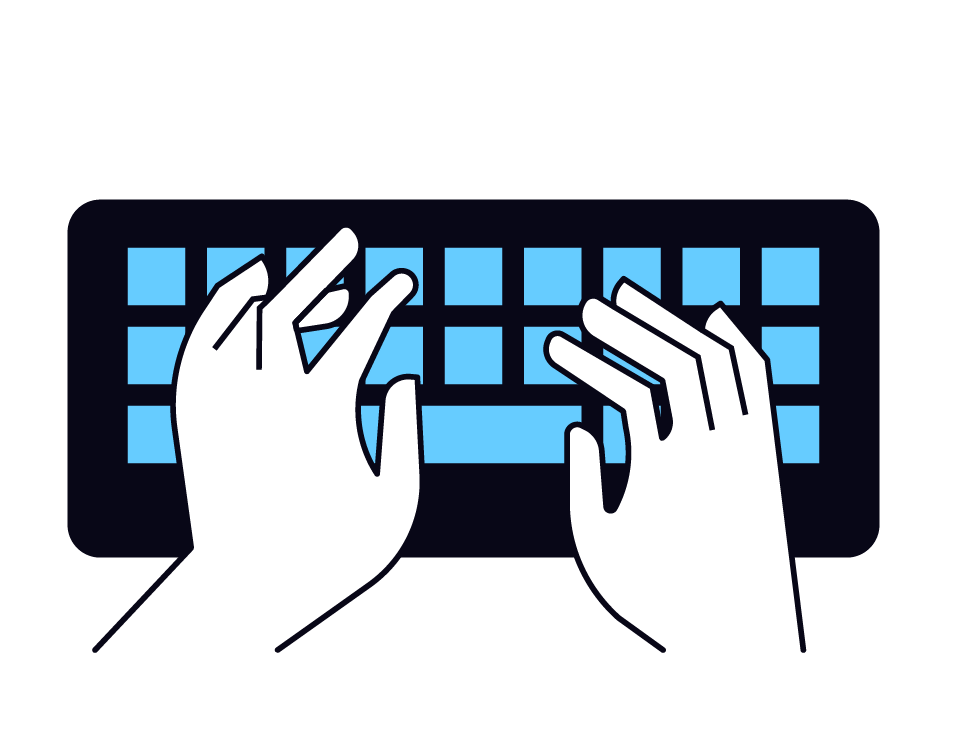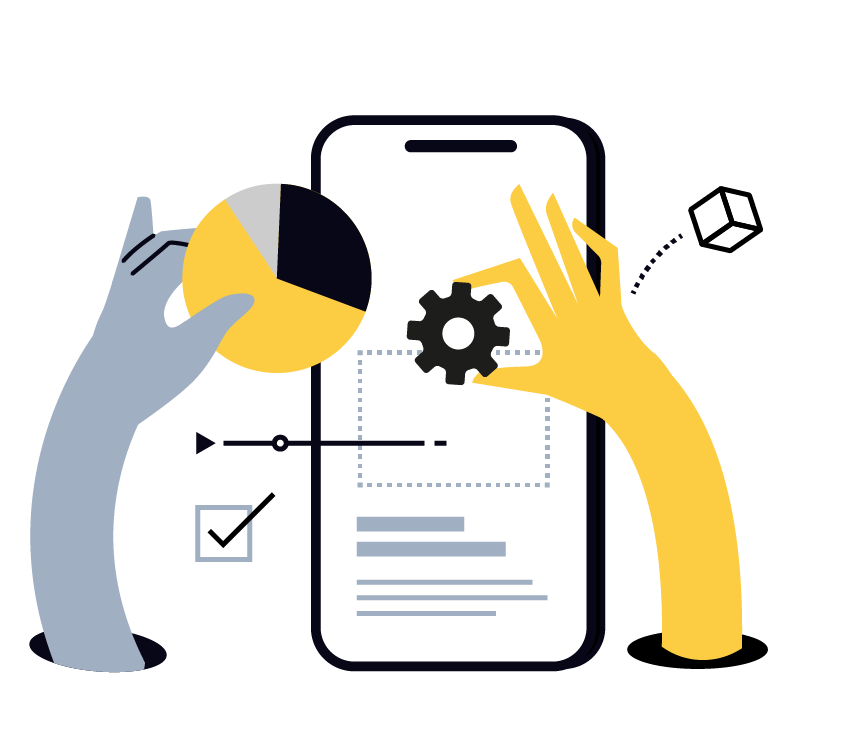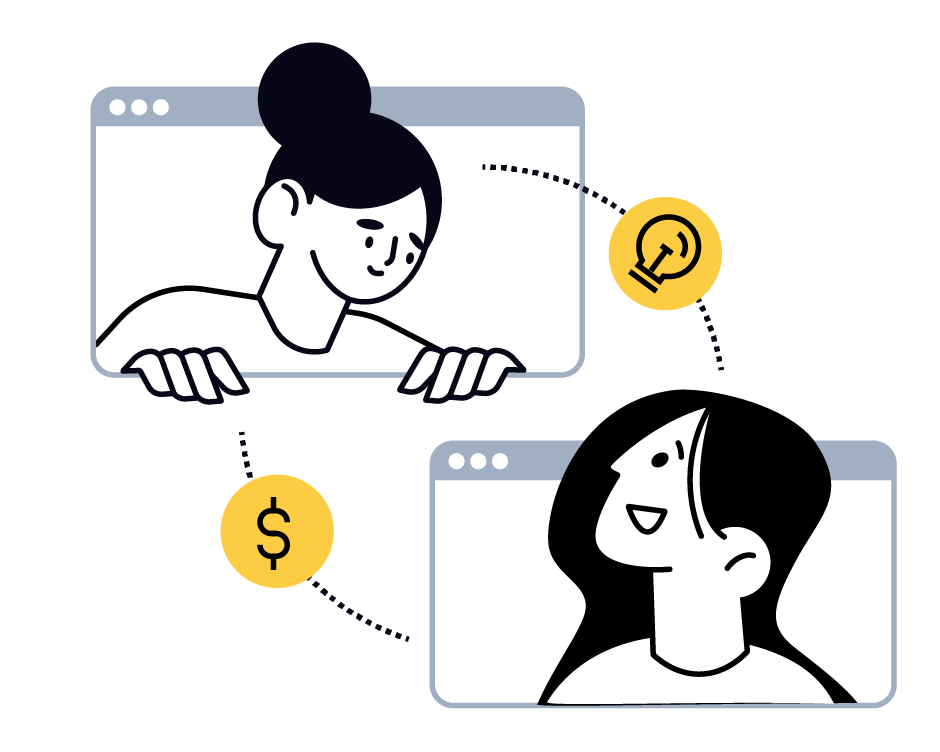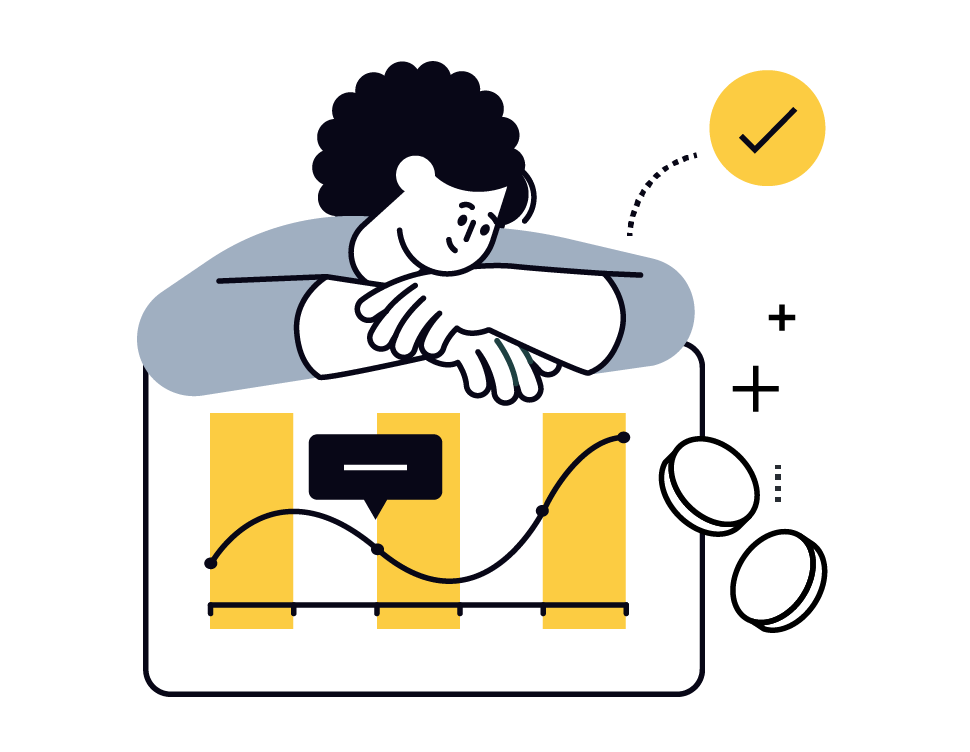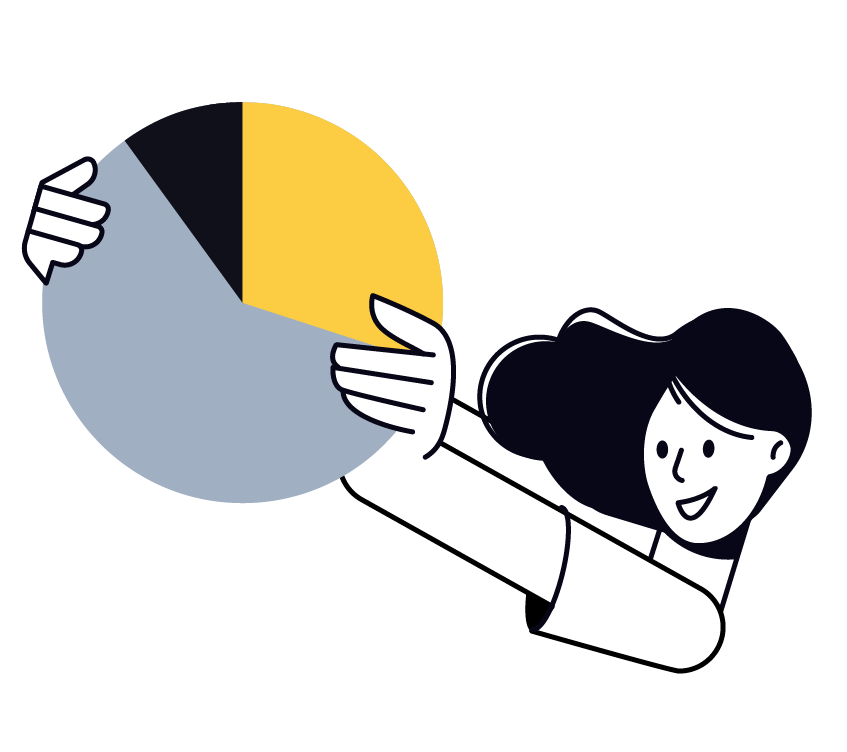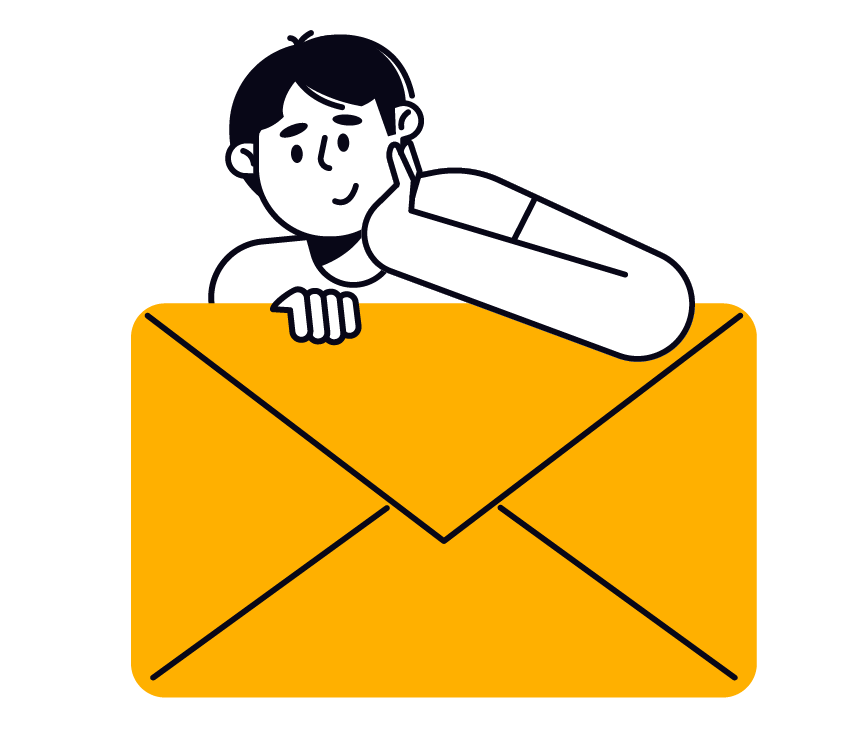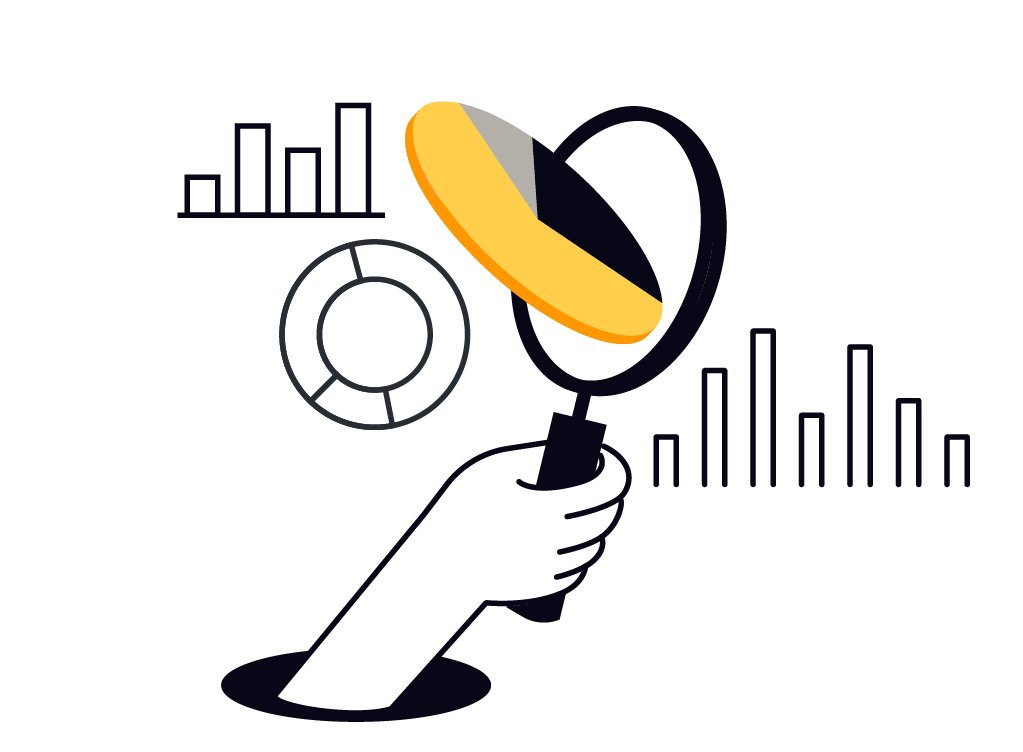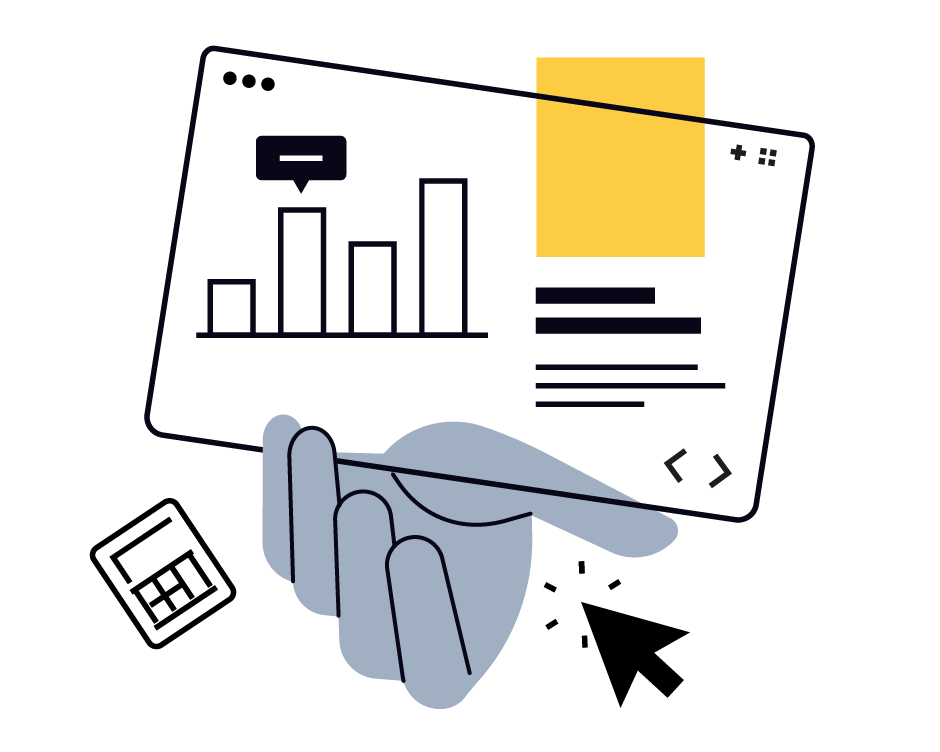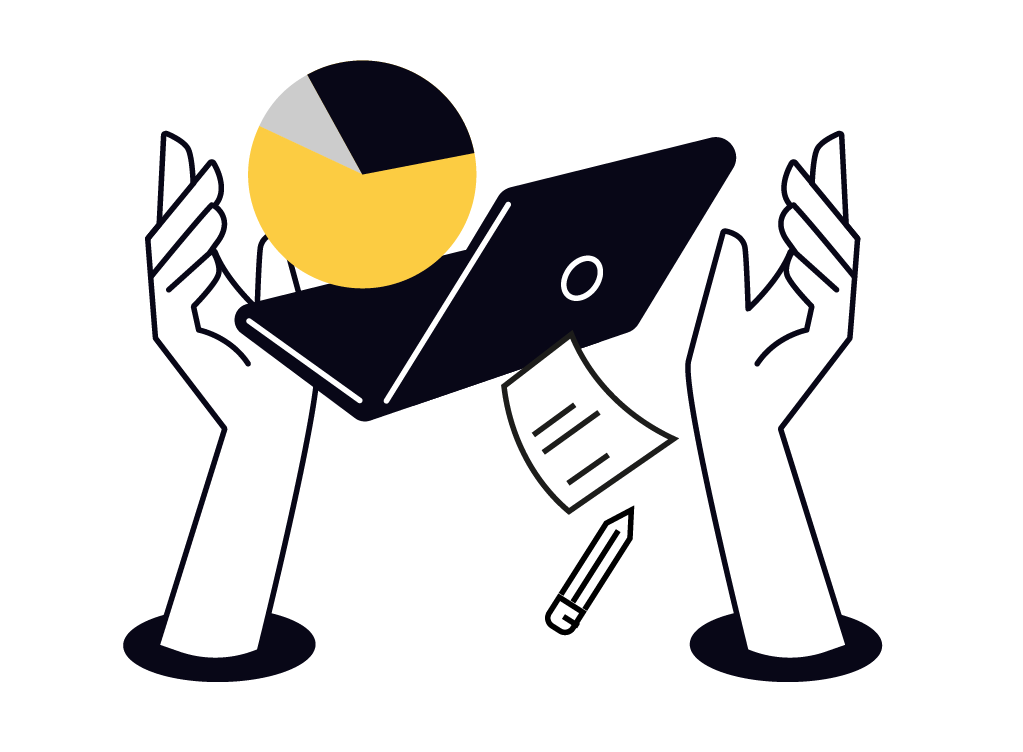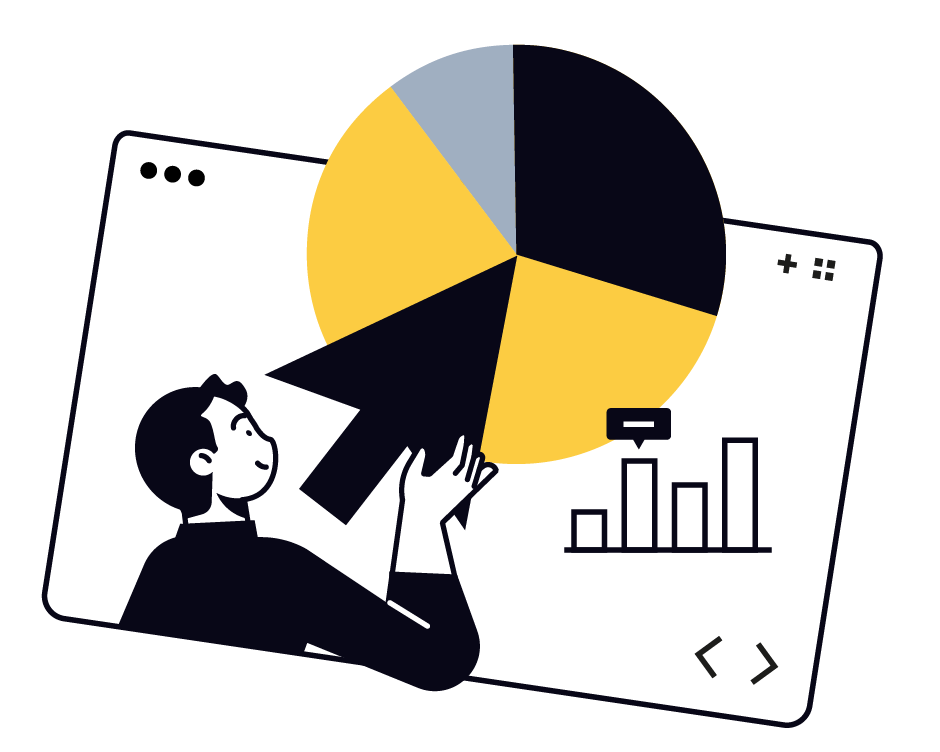1. CMSとMAを連携する意味
CMSは「顧客が触れるコンテンツを蓄積・配信する場」、MAは「見込み顧客の行動を管理・育成する仕組み」です。両者を連携させることで、ユーザーがWebサイト上で何を閲覧し、どのように関心を深めていくのかを可視化し、最適なタイミングで最適なコンテンツを届けられるようになります。
1-1. CMSに蓄積される行動データ
- 記事の閲覧履歴(ジャンル別)
- ダウンロードした資料の種類
- 動画の視聴有無・視聴時間
- 会員登録やフォーム入力の有無
- 再訪頻度や滞在時間
これらのデータをMAに送ることで、単なる「アクセスログ」が「リード育成に活かせる情報」へと変わります。
1-2. MAが担う役割
MAは、上記の行動データをもとに「スコアリング」や「シナリオ配信」を行います。
例えば、ある技術記事を複数回読んでいる人には「比較資料のダウンロード案内」を送り、さらに反応した人には「セミナー招待メール」を送る、といった段階的な施策が可能になります。
さらにMAは以下のような機能を担います:
- スコアリング:ページ閲覧回数や資料DLなどに点数を付与し、見込み度を数値化。営業に「今アプローチすべき相手」を提示できる。
- シナリオ配信:あらかじめ設計したルートに沿って、ユーザーの行動ごとに次のコンテンツを自動配信。検討段階に合わせた情報提供が可能。
- セグメンテーション:業種・役職・企業規模などの属性を掛け合わせ、配信対象を絞り込む。BtoB特有の「複数決裁者」への段階的アプローチにも対応できる。
- アラート通知:重要な行動(例:料金ページを閲覧、問い合わせ直前の動き)があった際に営業へ通知。即時のフォローアップにつなげられる。
これにより「誰に」「どの情報を」「どの順番で届けるか」という設計が自動化され、属人的な対応に依存せず、組織全体で均質な顧客体験を提供できます。
2. シナリオ設計でできること
2-1. 典型的なBtoBシナリオ例
- ステップ1:技術記事を閲覧 → 基礎情報や関連資料を自動送付
- ステップ2:一定期間内に複数回訪問 → セミナーやウェビナーへ招待
- ステップ3:セミナー参加者限定で比較表や導入事例を提供
- ステップ4:スコア閾値を超えたリードを営業部門に引き渡し
長期にわたる検討プロセスが前提となるBtoBでは、このように段階的にナーチャリングする設計が特に有効です。
2-2. パーソナライズの手法
- 行動ベース:閲覧ジャンル、滞在時間、再訪タイミングに応じて出し分け
- 属性ベース:業種・役職・企業規模ごとにコンテンツを最適化
- 時間ベース:休眠ユーザーへのリマインド、週末/平日の送信タイミング調整
「誰に」「どの段階で」「何を届けるか」を設計できるのが、CMSとMA連携の最大の強みです。
3. 成果を測るKPIの例
シナリオを回すだけでは不十分。以下のような指標を追うことで、施策の精度が高まります。
- コンテンツ閲覧後のフォーム送信率
- ダウンロードから商談化までのリード転換率
- スコア閾値を超えたリードの成約率
- パーソナライズ配信メールの開封率・クリック率
KPIを設けることで「どのシナリオが成果につながっているか」を判断でき、PDCAが回しやすくなります。
4. 運用フェーズ別の工夫
- 導入初期:シンプルなシナリオ(例:資料DL→お礼メール)で検証
- 定着期:セグメントを細分化し、役職や興味別の出し分けを拡充
- 拡大期:CRMやSFAと統合し、営業・サポートまで含めた全体最適化
「いきなり高度な設計を目指さない」ことが成功のポイントです。
5. 部門ごとのメリット
- マーケティング部門:リードの温度感を数値化でき、成果を社内に説明しやすい
- 営業部門:商談前に「相手がどの資料を見たか」を把握し、提案の精度を高められる
- カスタマーサポート:FAQ・マニュアルの閲覧履歴をもとに、アフターフォローやクロスセルに活かせる
部門横断で活用することで、「点の施策」から「全社的な顧客体験設計」へと進化します。
6. まとめ:CMS×MA連携で描く未来像
CMSとMAを連携することで、単なる「Webサイト運営」から「顧客体験を設計する戦略基盤」へと進化できます。BtoB特有の長期的な検討プロセスや複数決裁者の存在に対応するには、属人的な営業活動に頼らず、データドリブンで一貫性ある情報提供が不可欠です。
- 顧客にとって:必要な情報が必要なタイミングで届き、検討がスムーズに進む
- 企業にとって:営業効率が高まり、リードから商談・成約までの転換率が向上する
最終的には「顧客に選ばれる理由」をデータと仕組みで作り出すことが、CMS×MA連携の最大の価値です。