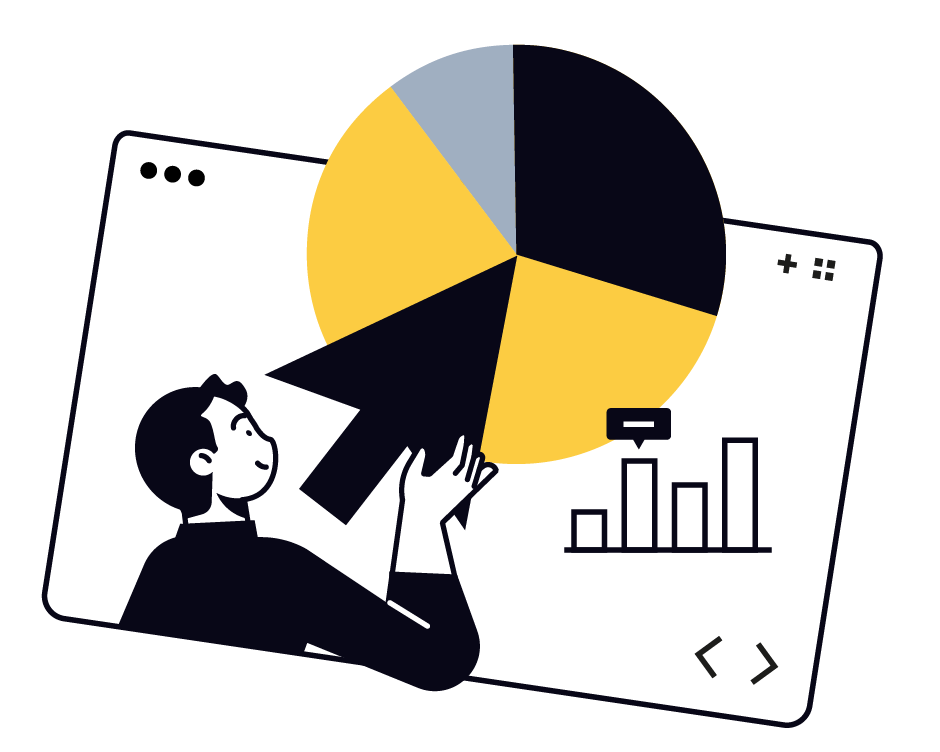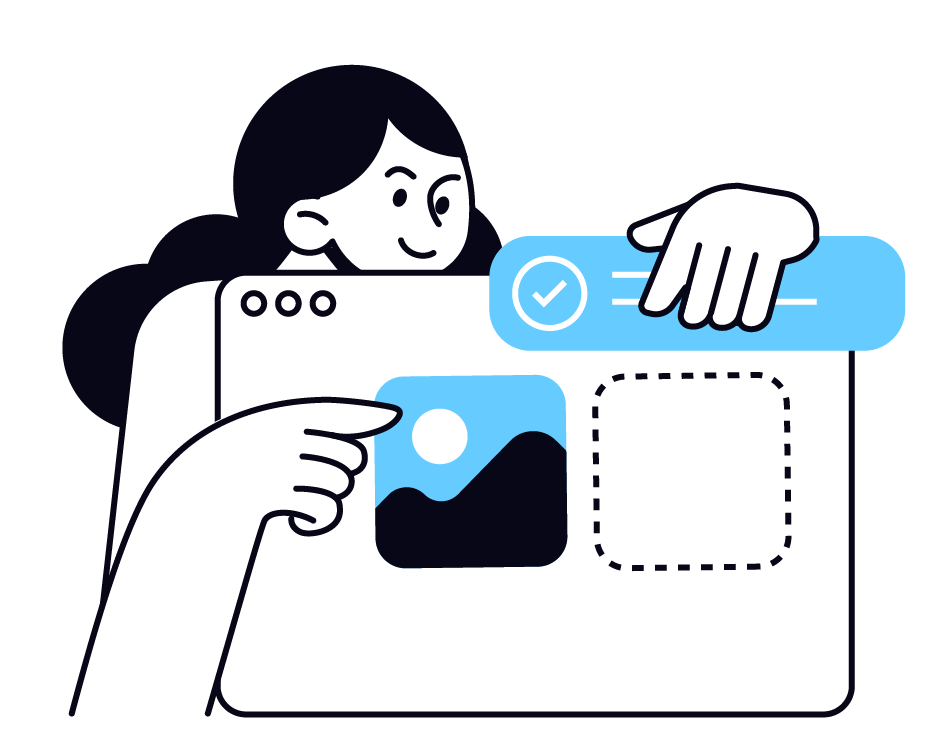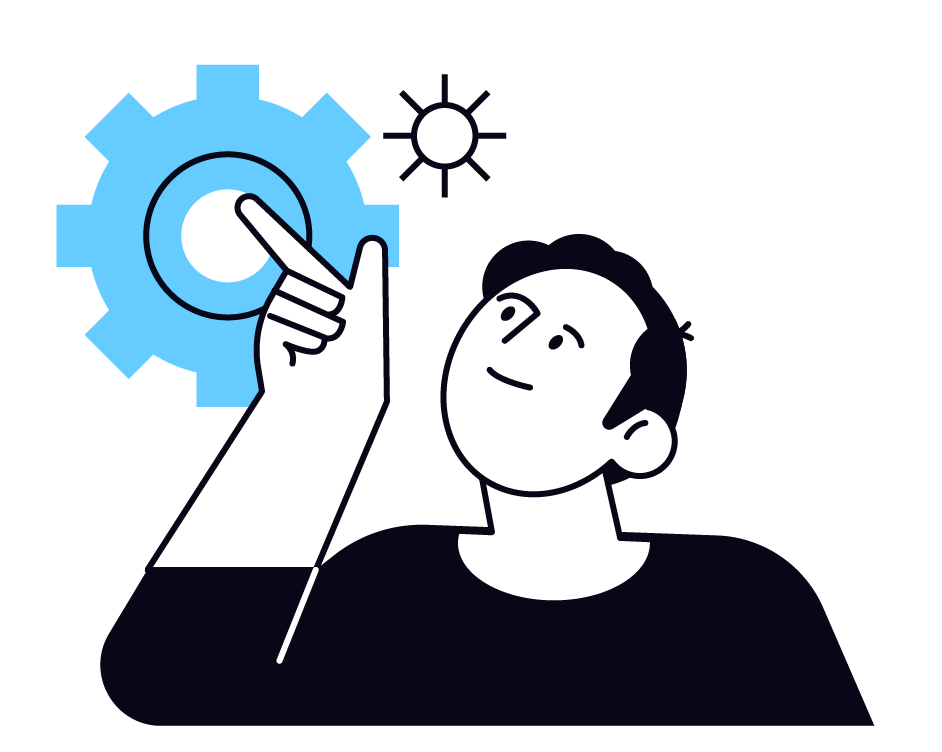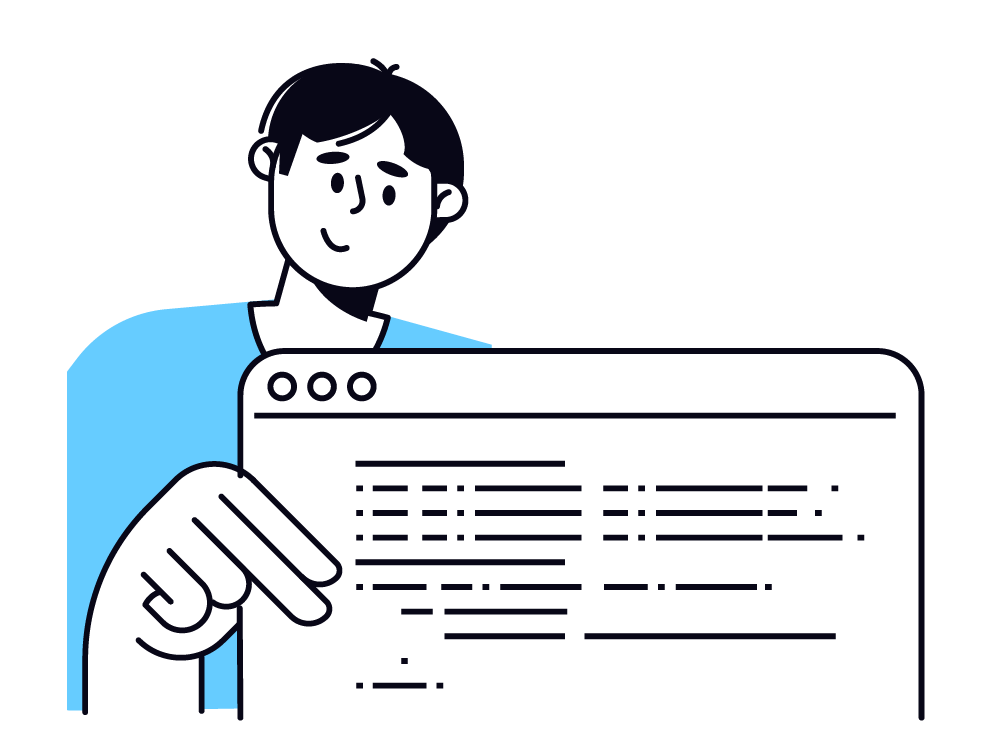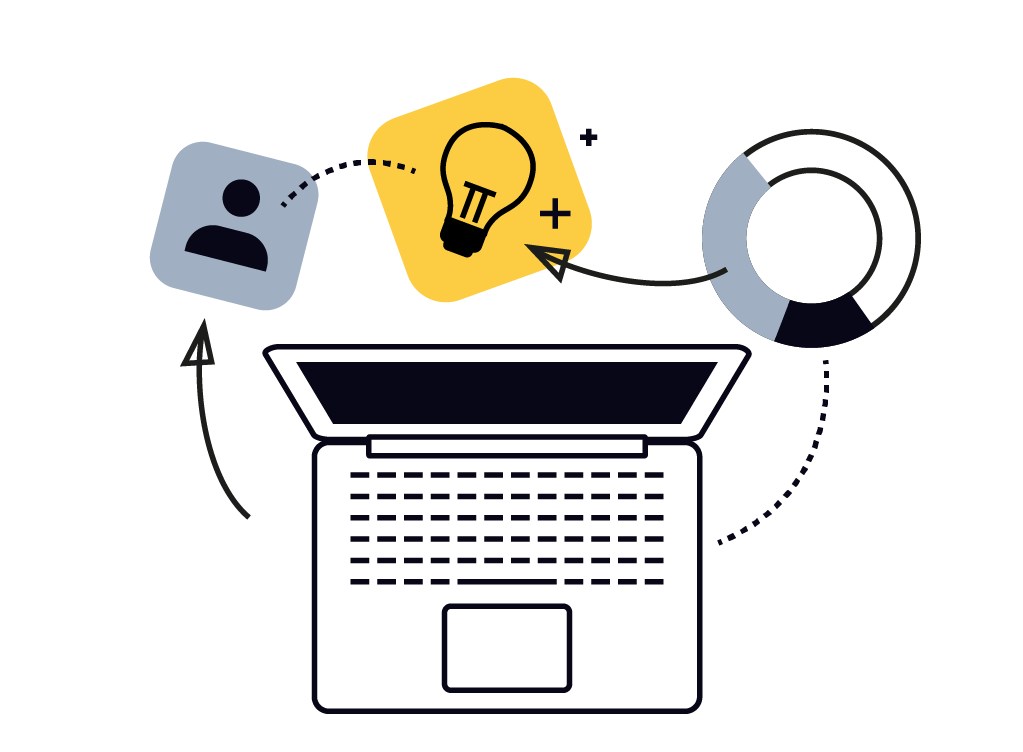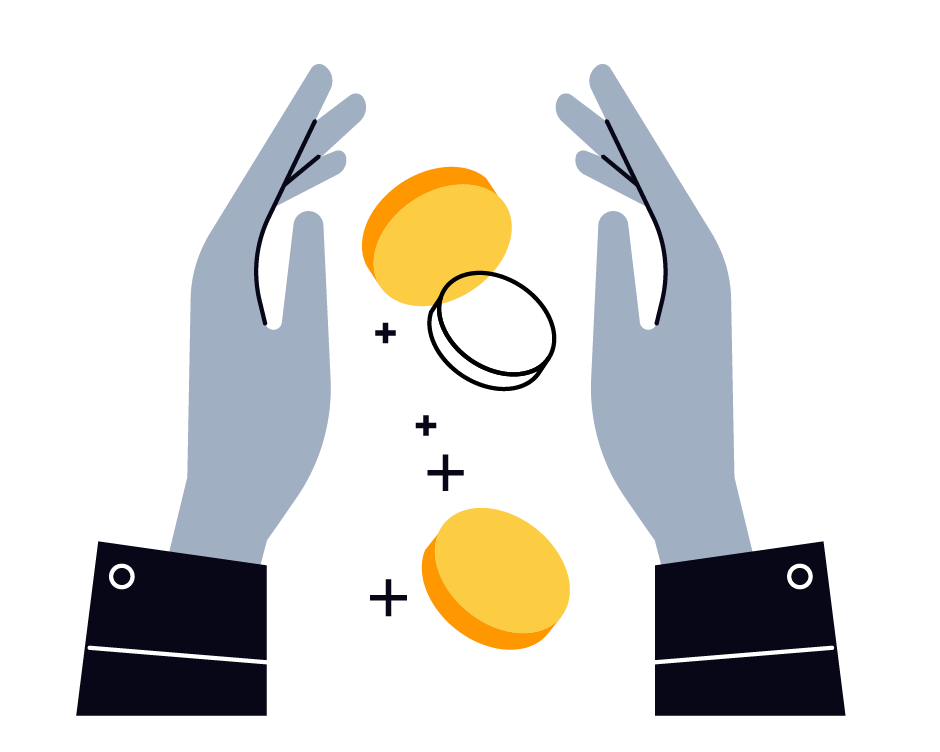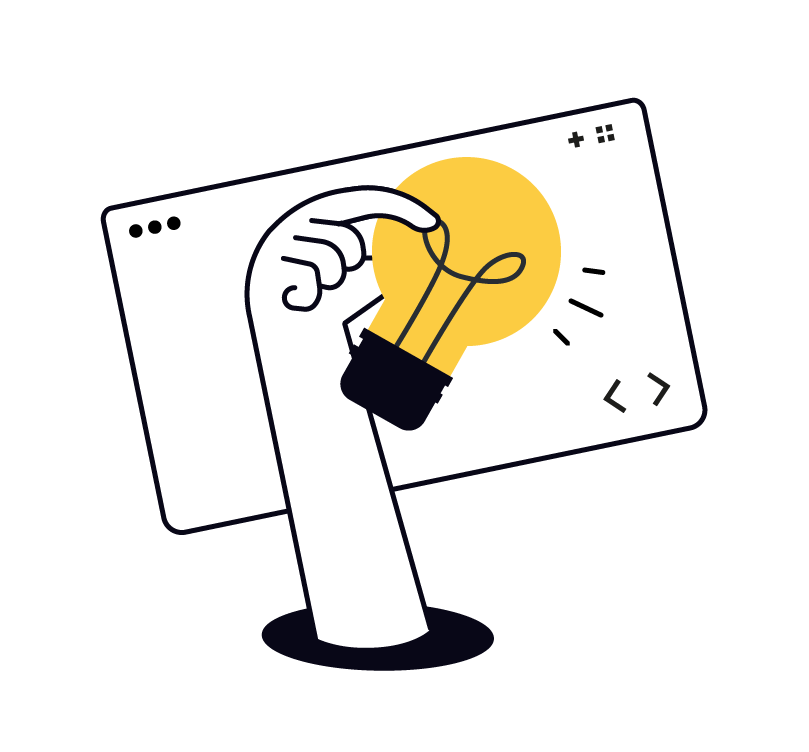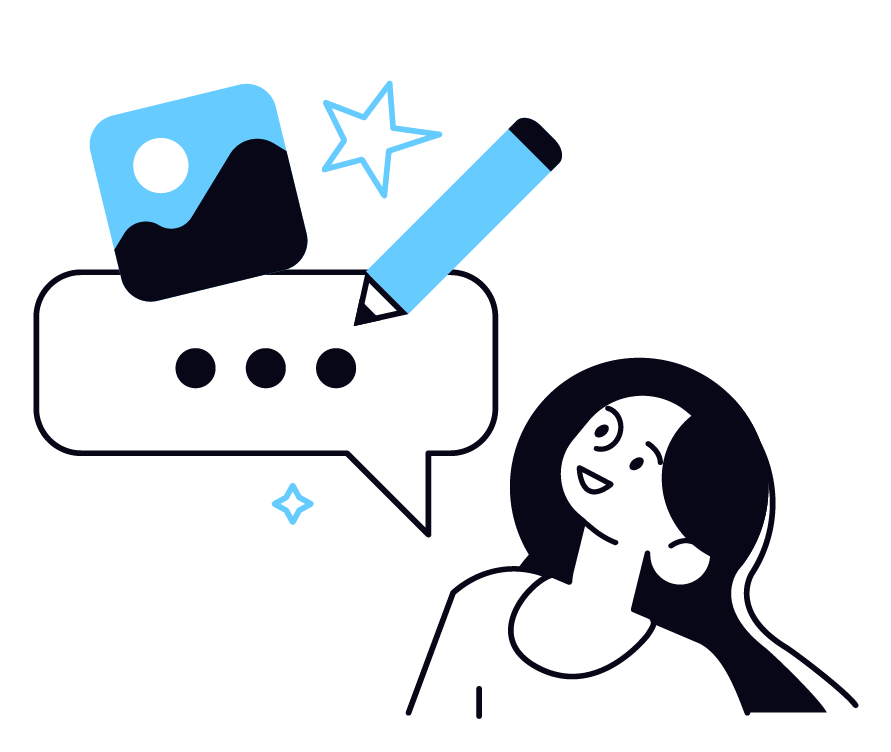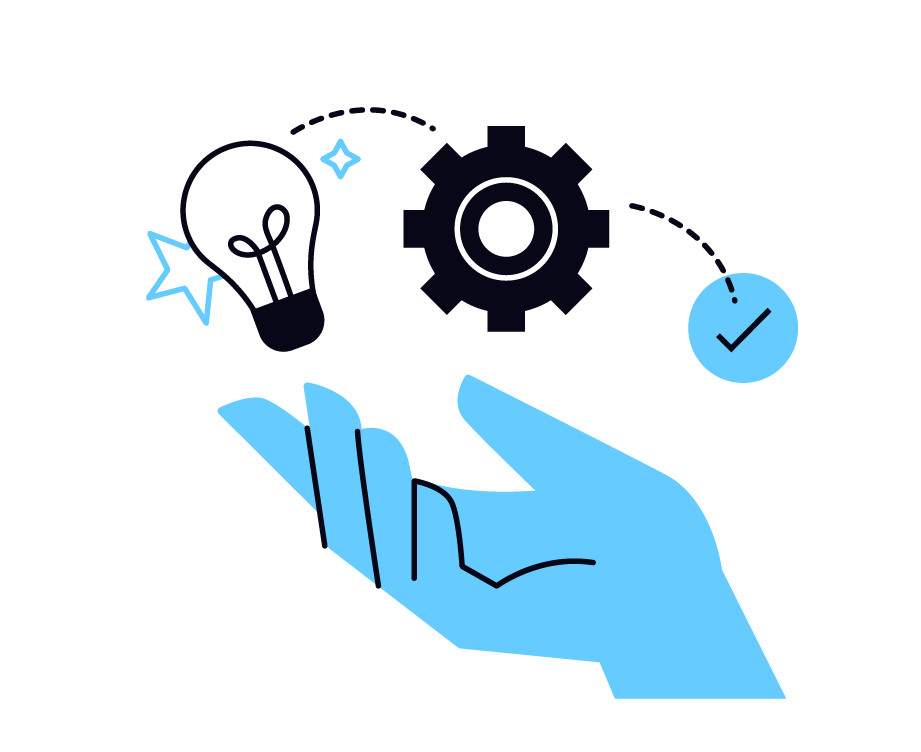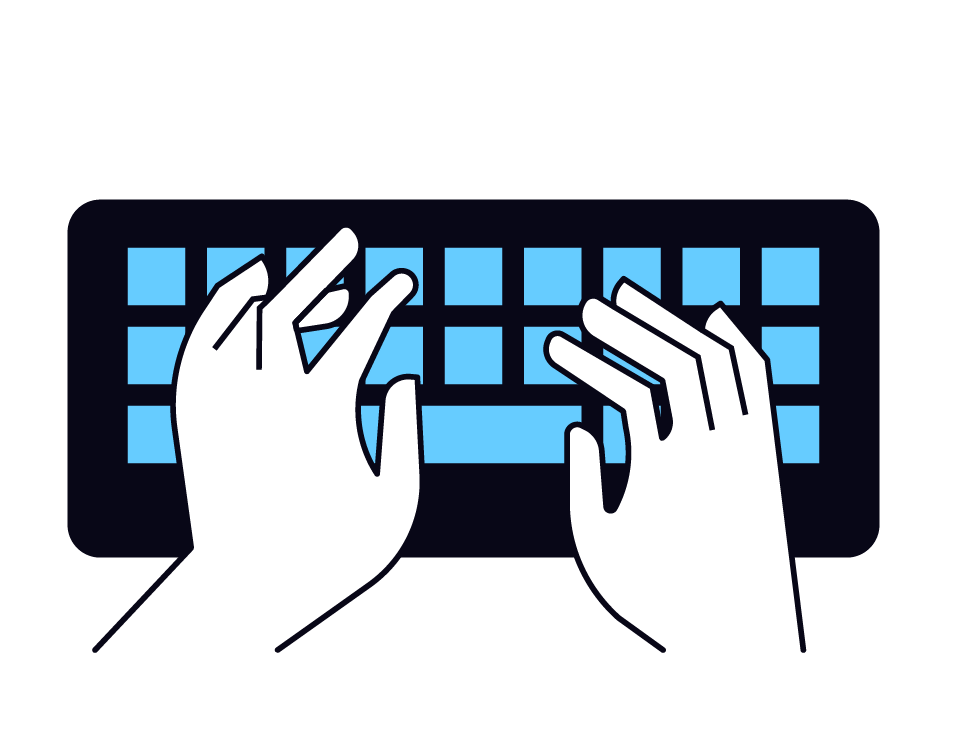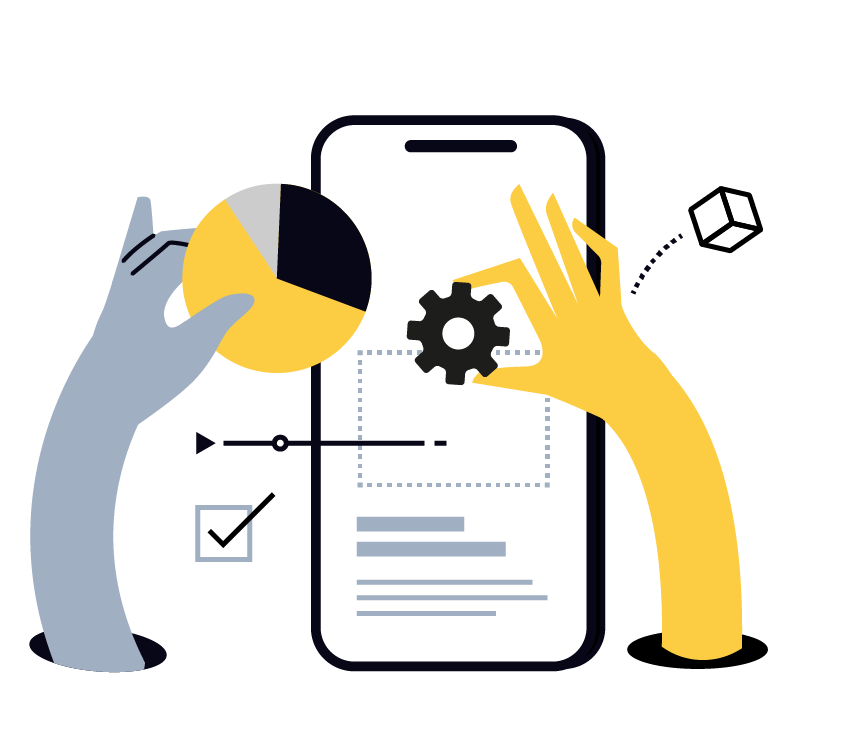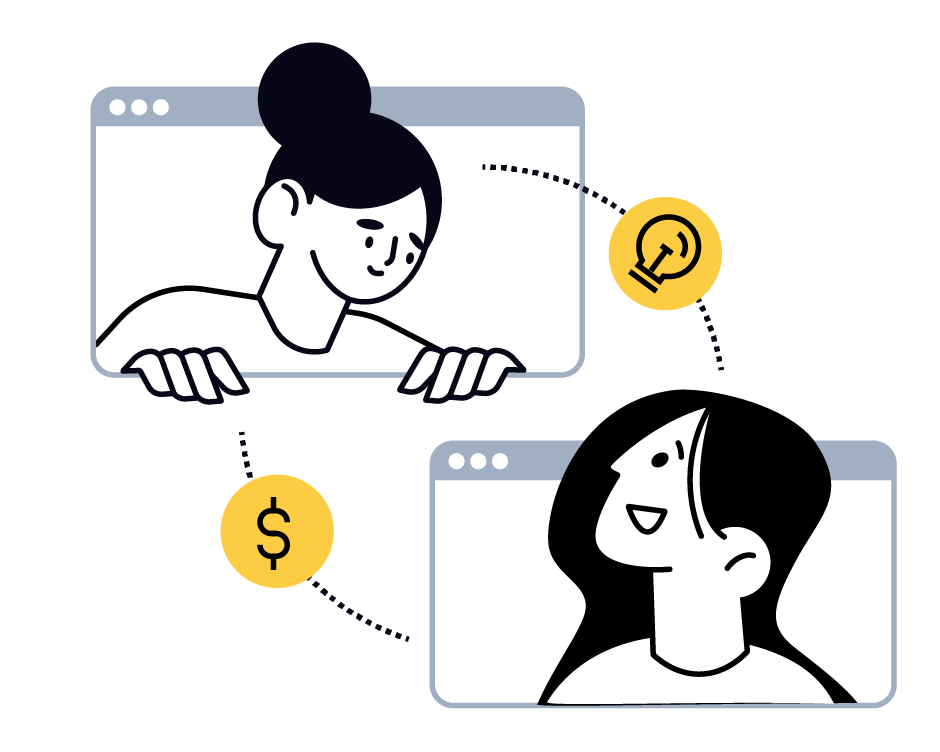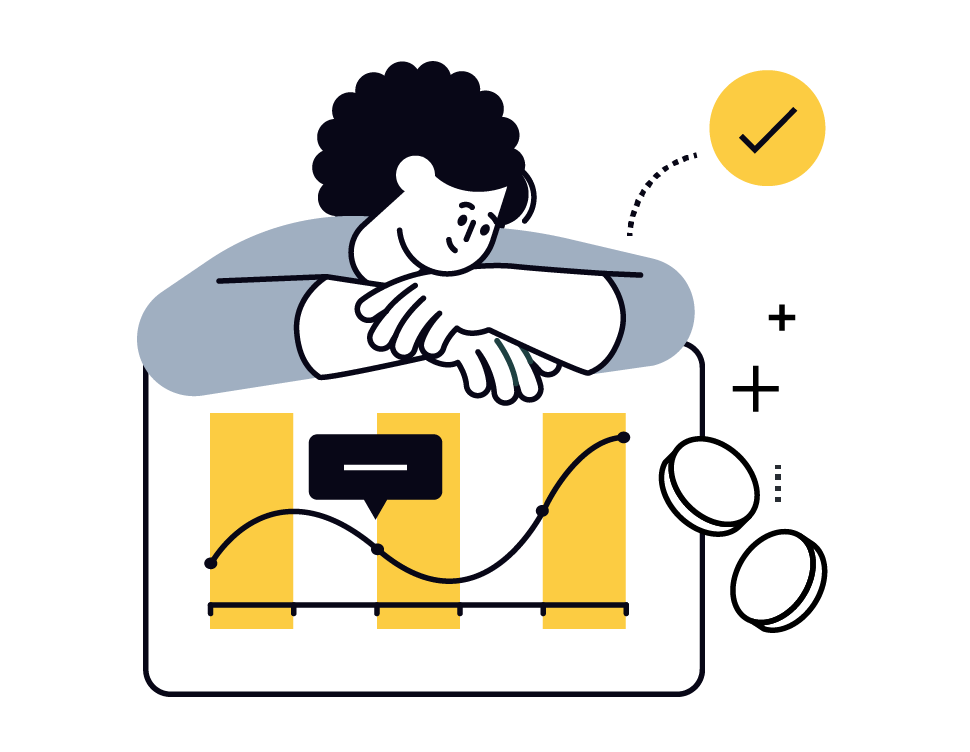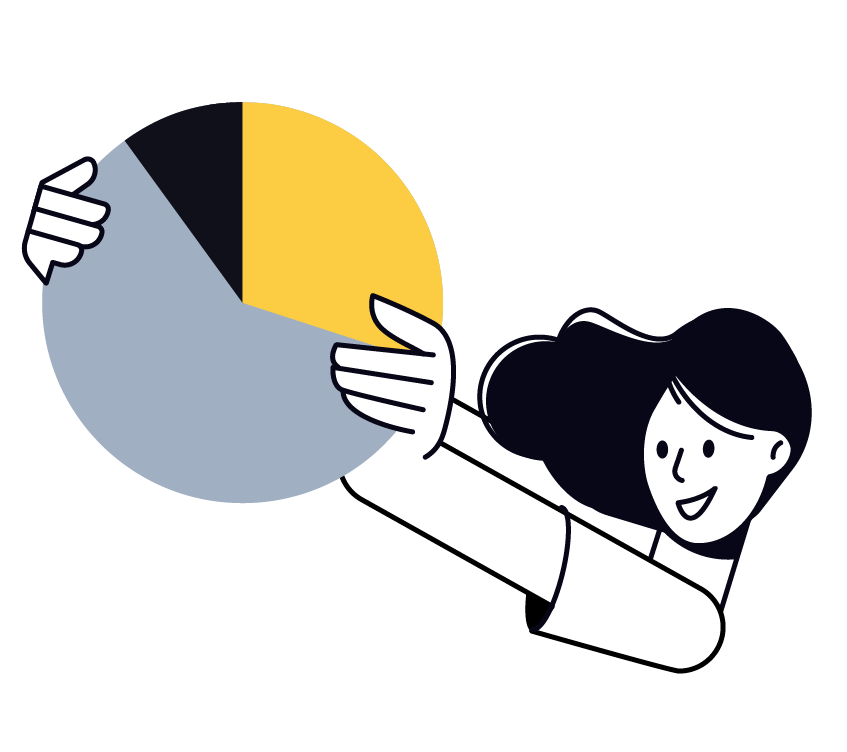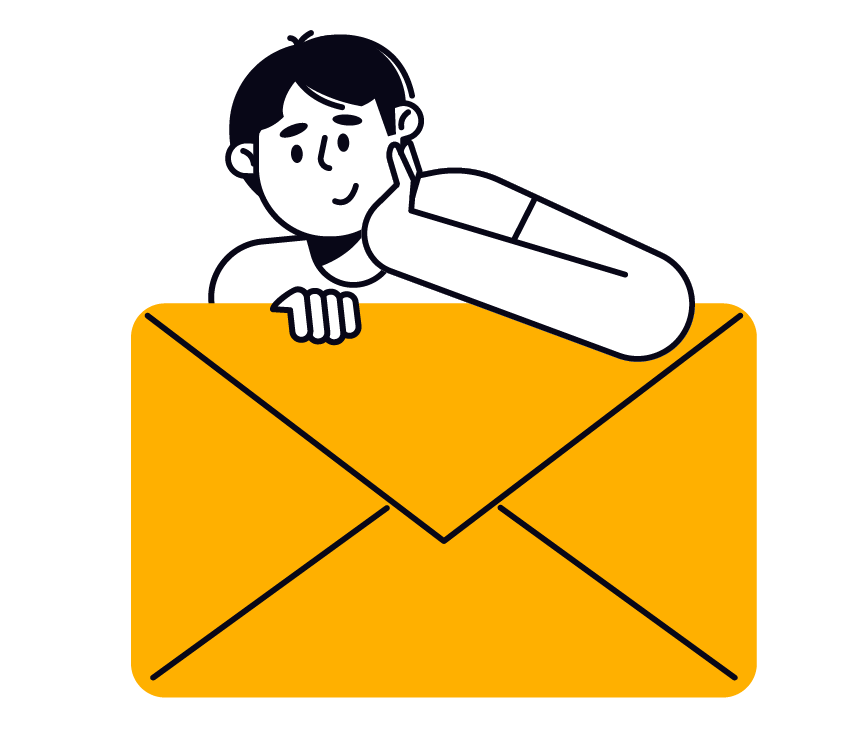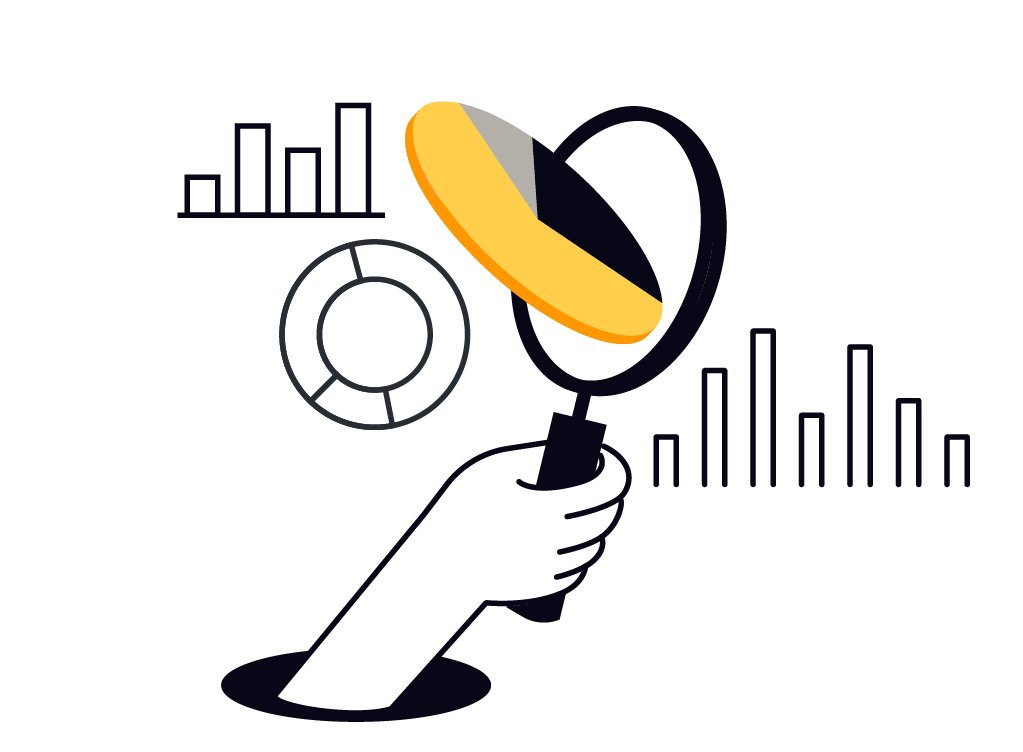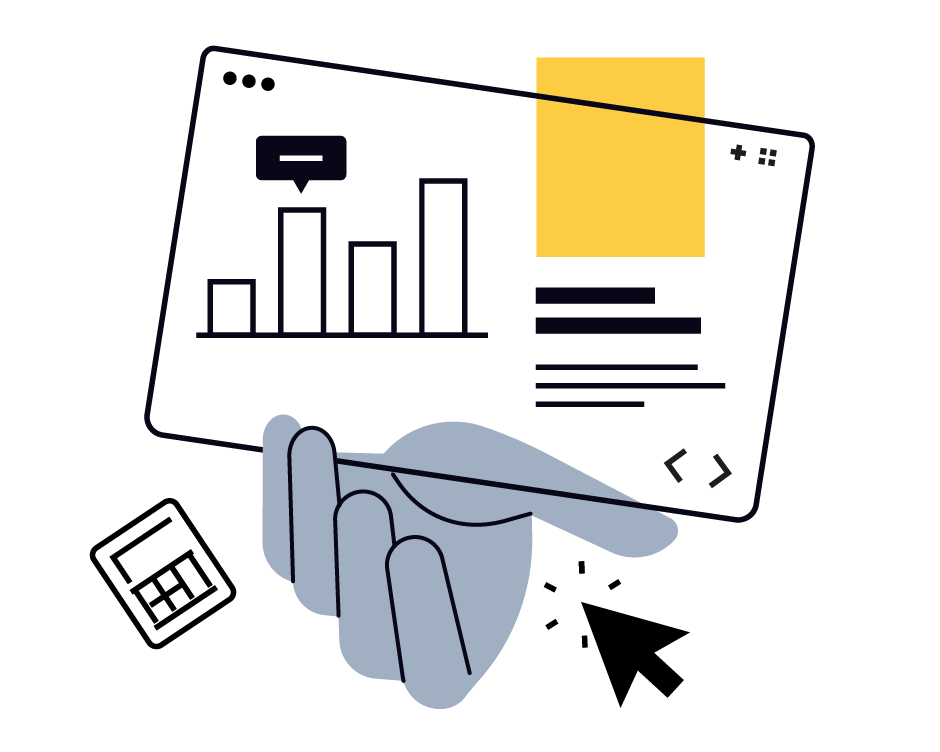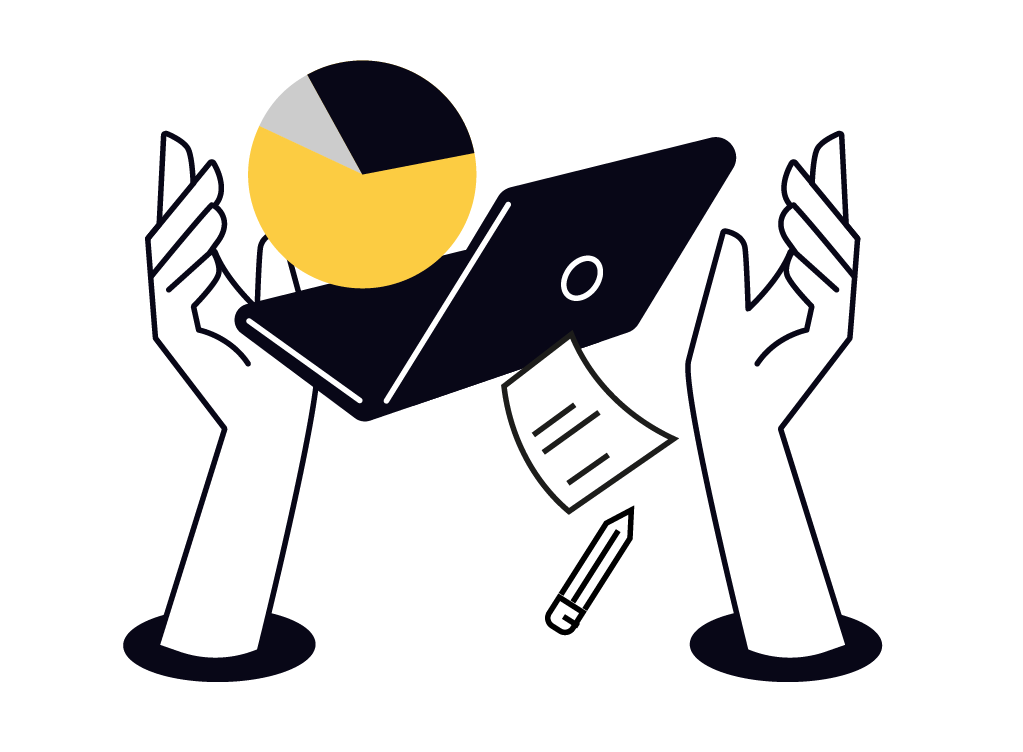1. なぜペルソナとセグメント設計が重要なのか?
BtoBマーケティングにおいて、「誰に向けて施策を行うのか」という視点は成果を大きく左右します。特に会員制Webサイトやメルマガ運用を行う際には、ユーザー像が不明確なままコンテンツや配信を進めても、反応が得られず、リソースが無駄になりがちです。
この課題を解決する手がかりが「行動ログ」×「会員属性」のかけ合わせによるペルソナ設計です。実在するユーザー群の行動データをもとに仮説ペルソナを描き、その特徴を軸にセグメントを設計することで、「誰に、どのような価値を届けるか」を明確にできます。
実際、製薬系の会員サイトでは、同じ医師であっても「製品を検索して閲覧する人」と「動画で学ぶ人」で関心領域や行動導線が大きく異なっていました。それぞれに異なるシナリオを設計したことで、平均滞在時間が1.5倍になり、リード率も向上した事例があります。
1-1. 従来のペルソナ設計の限界と新しいアプローチ
ペルソナ設計といえば、マーケティング担当者が想像で「○○業界で働く40代の男性」といった架空の人物像を描くケースが一般的でした。しかしこの方法では、実際の行動との乖離が生じるリスクがあります。
ログデータを活用したアプローチでは、以下のような現実に即した視点が得られます:
- 商品詳細ページを月3回以上閲覧しているユーザーは、1回だけ見たユーザーの2.3倍CVしやすい
- 資料ダウンロード前にFAQを確認しているユーザーは、フォームの入力完了率が高い
こうした行動の傾向から、リアルなニーズを持つセグメントを特定でき、それぞれに合ったアプローチが可能になります。
1-2. 会員属性との連携で「人となり」が見えてくる
行動ログだけでは“動き”は見えても“背景”はつかみにくいもの。ここで会員属性(登録情報、職種、職位、地域、会員種別など)を掛け合わせることで、以下のような解像度の高い仮説が立てられます:
- 「新人MR(営業)でかつ定期的にFAQを見ている」→製品知識の補完が必要な層
- 「都市部勤務の開業医で資料DLが多い」→患者説明用ツールを探している可能性
このように、会員情報と行動を掛け合わせることで「ペルソナの裏付け」が可能となり、セグメントに対する施策の説得力も高まります。
2. セグメント設計と施策のかけ合わせ方
2-1. セグメントの粒度をどう決めるか?
セグメントの切り口は、細かすぎても運用が複雑になり、粗すぎてもパーソナライズの恩恵が薄れてしまいます。以下の観点で「使えるセグメント」を定義しましょう:
- 目的起点で切る:例)資料DL→商談につなげたい→DL後に再訪していない人
- 行動起点で切る:例)動画コンテンツを3本以上視聴→ナーチャリング段階
- 属性起点で切る:例)○○業界の中小企業経営者→自社導入を検討中
セグメントは、マーケ施策で「誰に何を届けるか」を最適化するための“戦術単位”です。
2-2. ペルソナ × セグメント × 施策 の実践例
以下に、典型的な仮説ペルソナとセグメントの掛け合わせに基づく施策例を紹介します。
| 仮説ペルソナ | 行動ログセグメント | 施策例 |
|---|---|---|
| 製品導入を検討する若手医師 | 製品詳細ページを複数回閲覧 | 比較表付き資料のレコメンド配信 |
| ベテランの病院経営者 | 動画を一度も視聴していない | メールで「○○先生向け最新動画」の案内 |
| 忙しい都市部のクリニック医師 | 滞在時間が短く離脱多発 | ランディングページを簡潔に再設計 |
たとえば、あるBtoB医療系サイトでは、「30代の若手開業医で、定期的に薬剤の比較表を閲覧する」セグメントがCVに直結していることが判明。これに対して、次のような施策が実施されました:
- 比較表をバージョンアップし、PDF化したうえでダウンロードを促進
- ページ下部に「先輩医師の活用事例」動画を設置し、興味を広げる導線を設計
- 次回ログイン時に「あなたがよく見る薬剤比較に新情報があります」という通知を表示
結果として、対象セグメントの平均滞在時間が1.8倍に、比較表DL率も約1.6倍に伸長しました。
また、「病院経営層で過去に動画視聴がない層」に対しては、導入事例を解説した動画コンテンツを「経営者視点からの視聴メリット」としてリライトし、あえて“読ませる”コンテンツメールとして配信したところ、動画再生数が倍増。従来の「動画をクリックさせる」設計から、「読む+見る」へ設計を変えたことが奏功しました。
こうした設計があれば、単に「クリック率が悪いからバナーを変える」といった表面的な対応ではなく、「このセグメントにはこういう届け方が必要だ」と根本的な戦略が立てられます。
まとめ
ユーザー行動と属性をもとにした仮説ペルソナとセグメント設計は、マーケティング施策を「的確な相手に、的確な手法で届ける」ための基盤となります。
データ分析というと難しく感じられるかもしれませんが、最初は「この人たちは何を見て、何をしてくれたのか?」というシンプルな問いから始めればOKです。
CMSやMA(マーケティングオートメーション)を活用する環境にあっても、こうした“人間の行動に基づいた設計”ができているかどうかが、成果の分かれ目になります。
手元のログと会員データを見ながら、まずは1つ、仮説ペルソナとセグメントを設計してみましょう。施策の解像度と成果が、きっと変わってくるはずです。