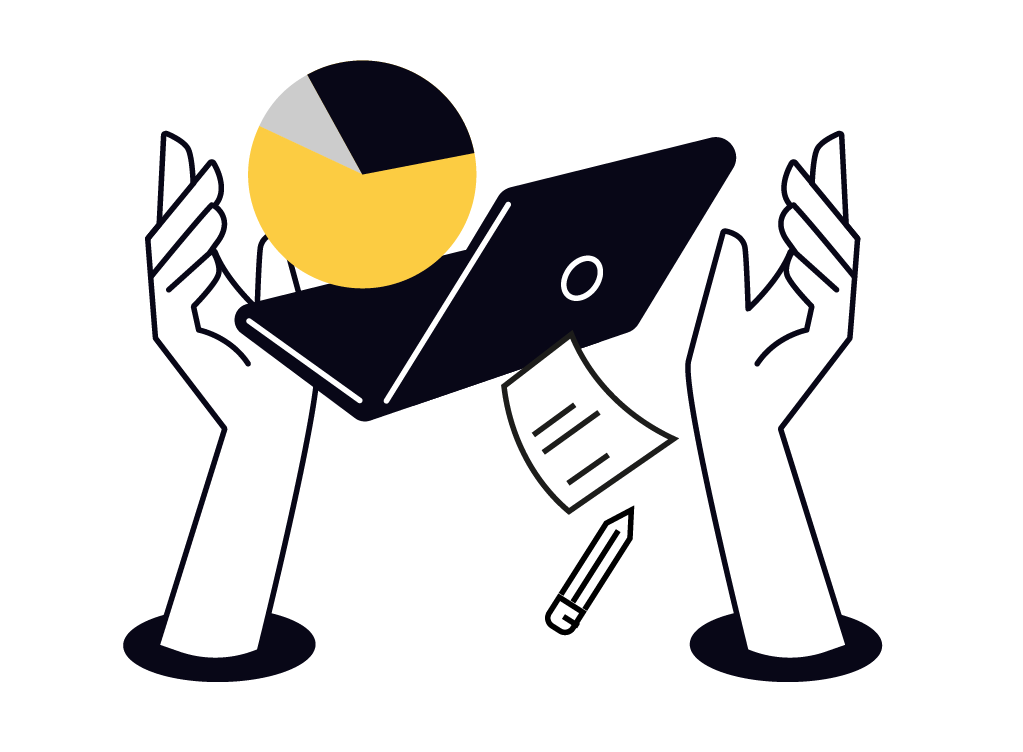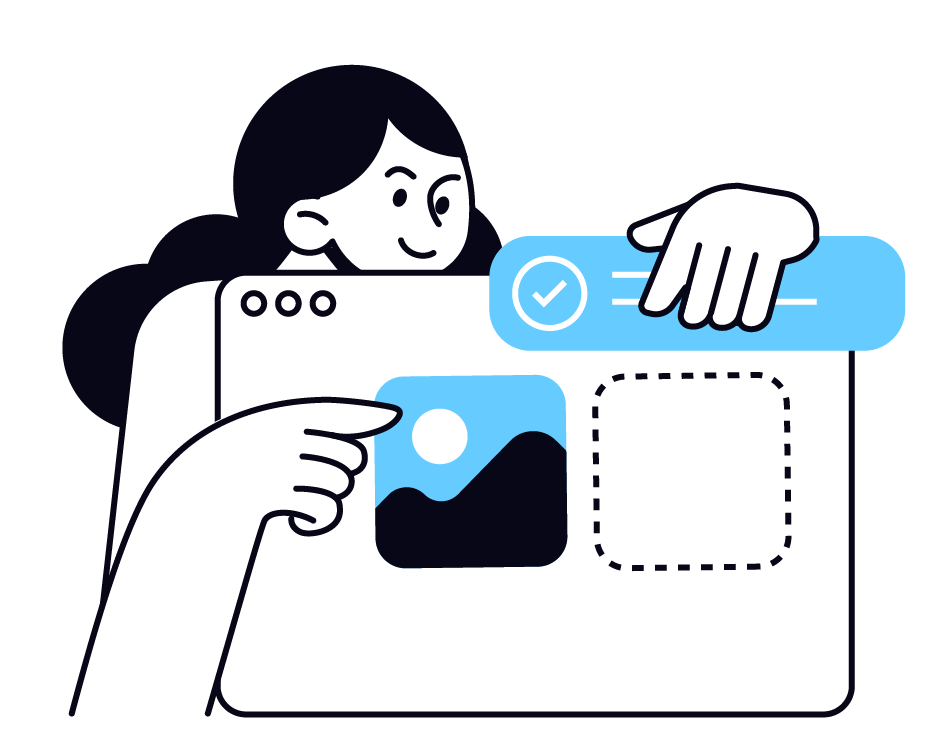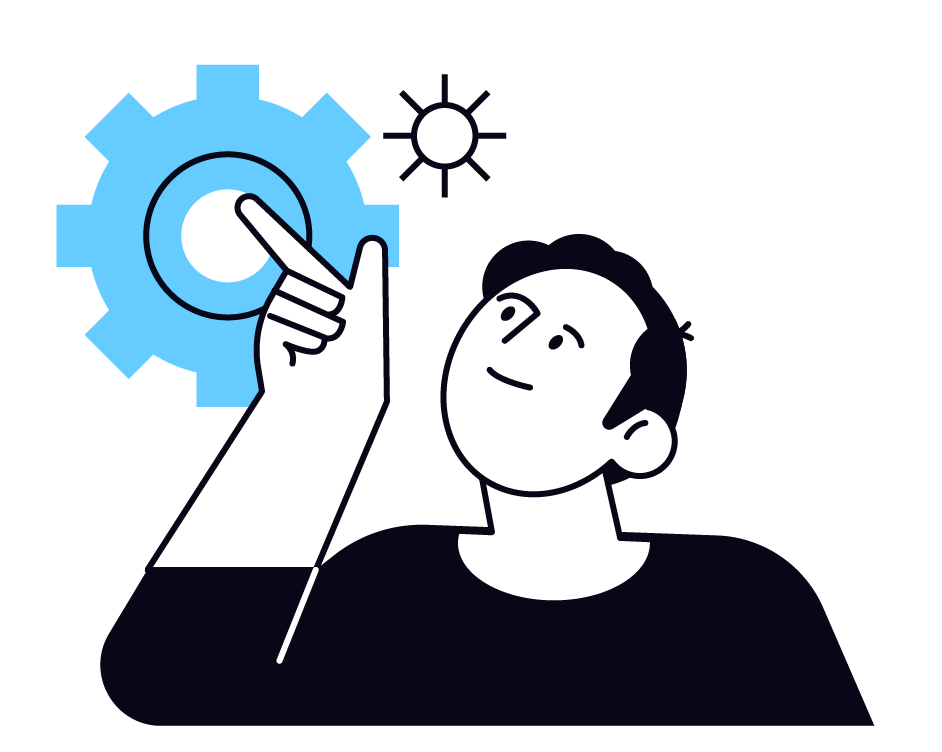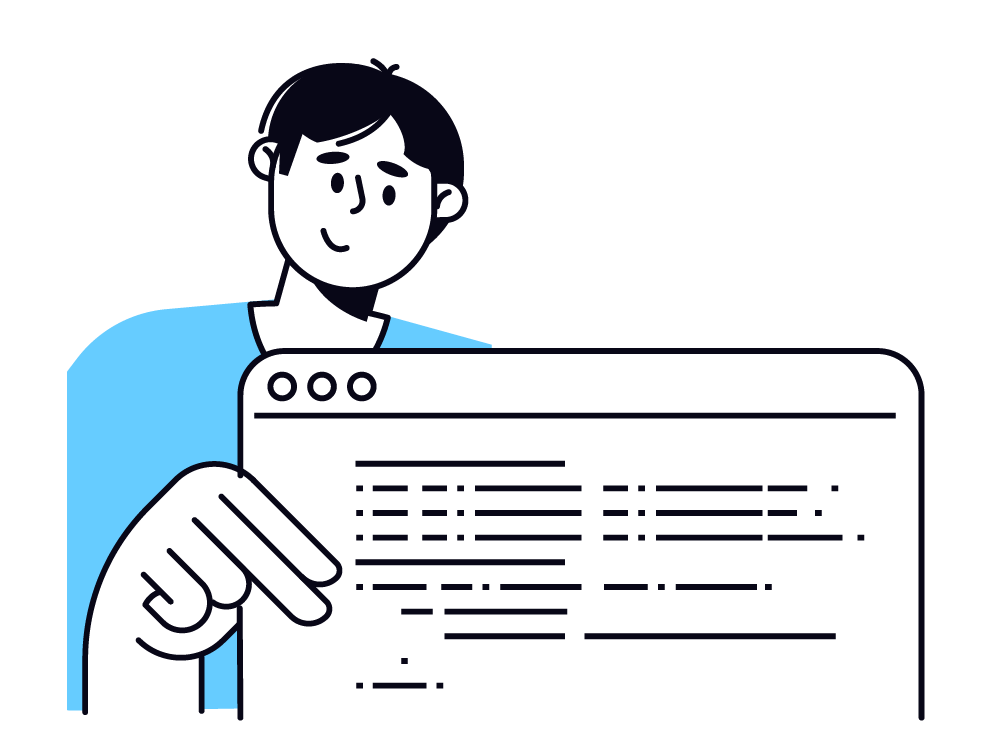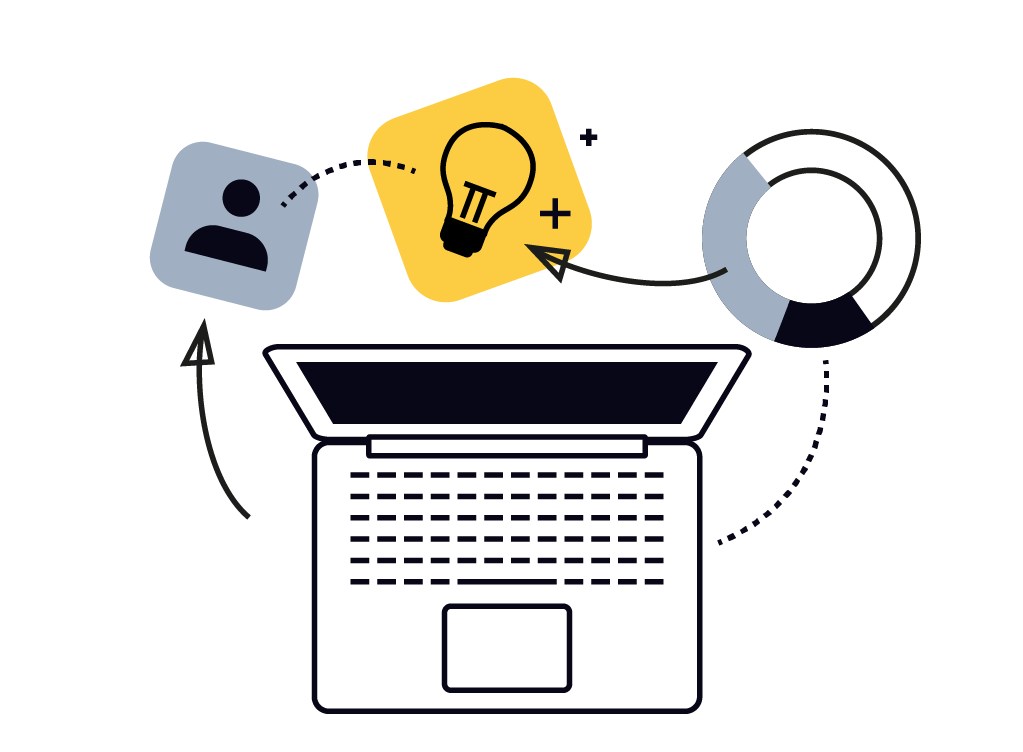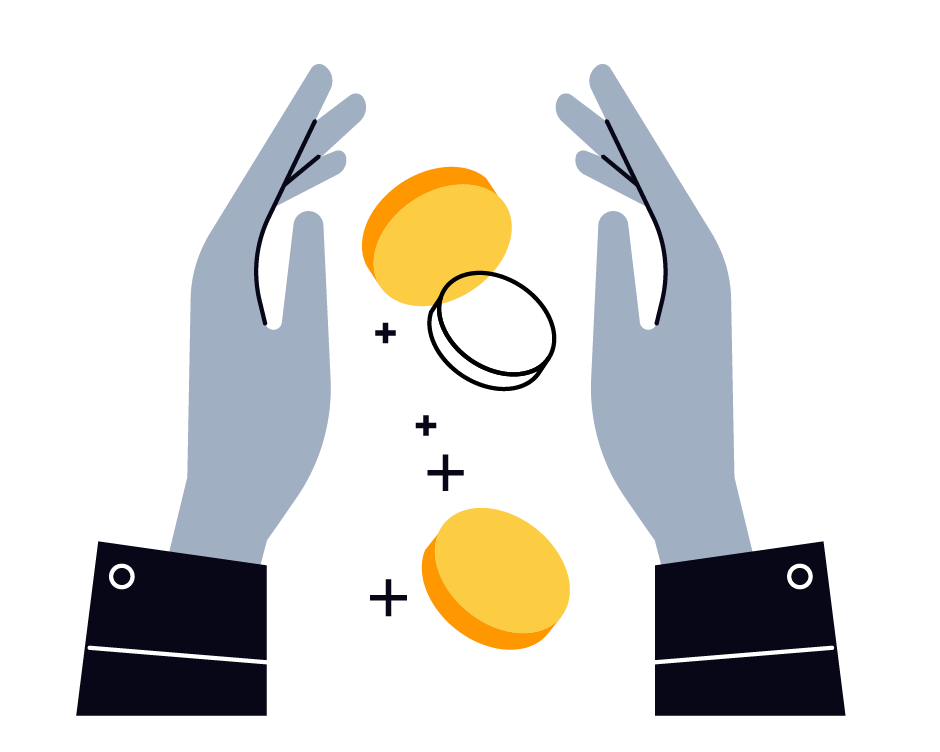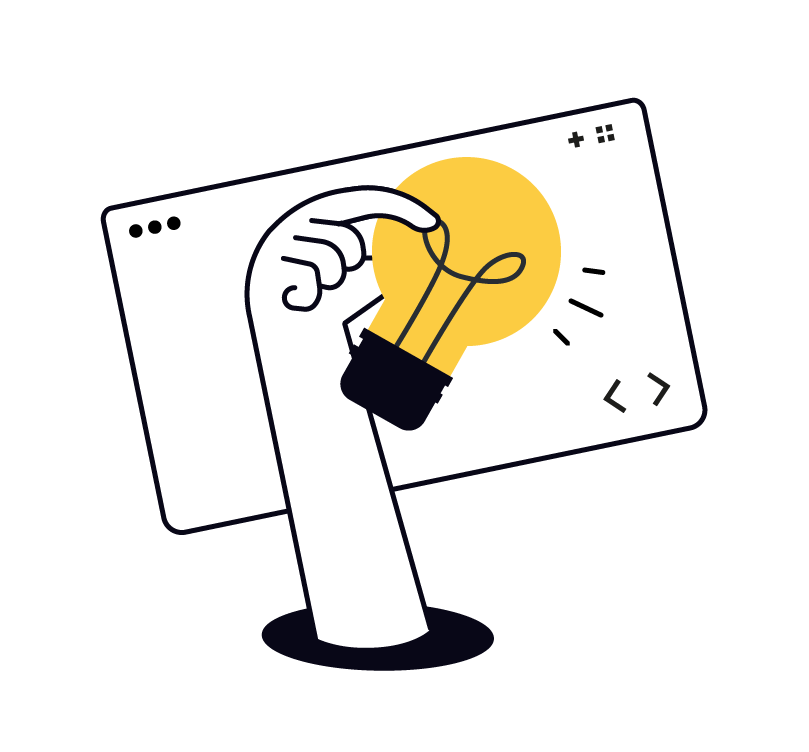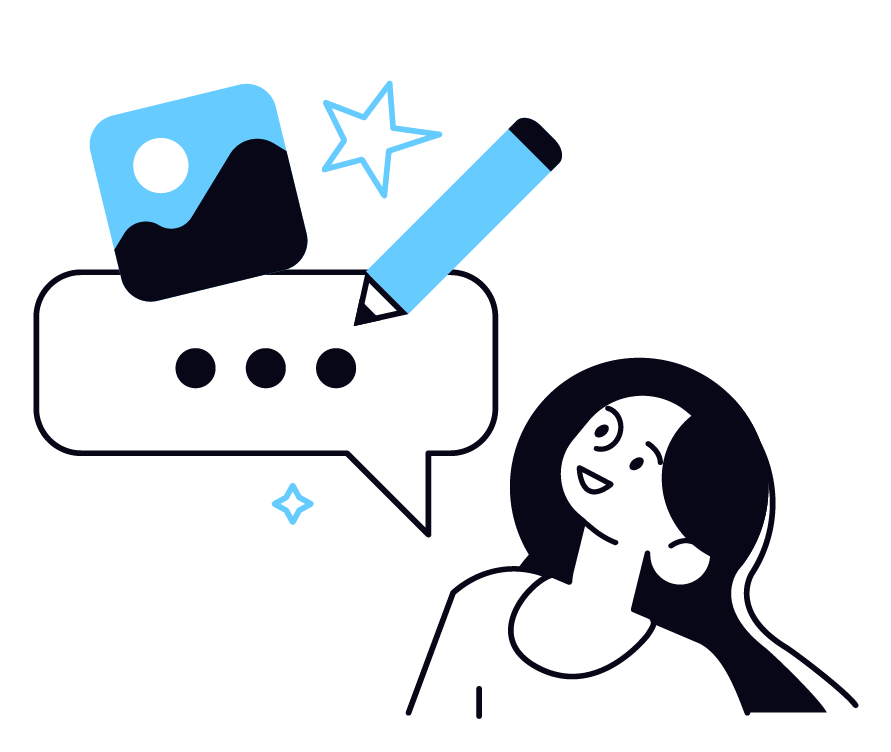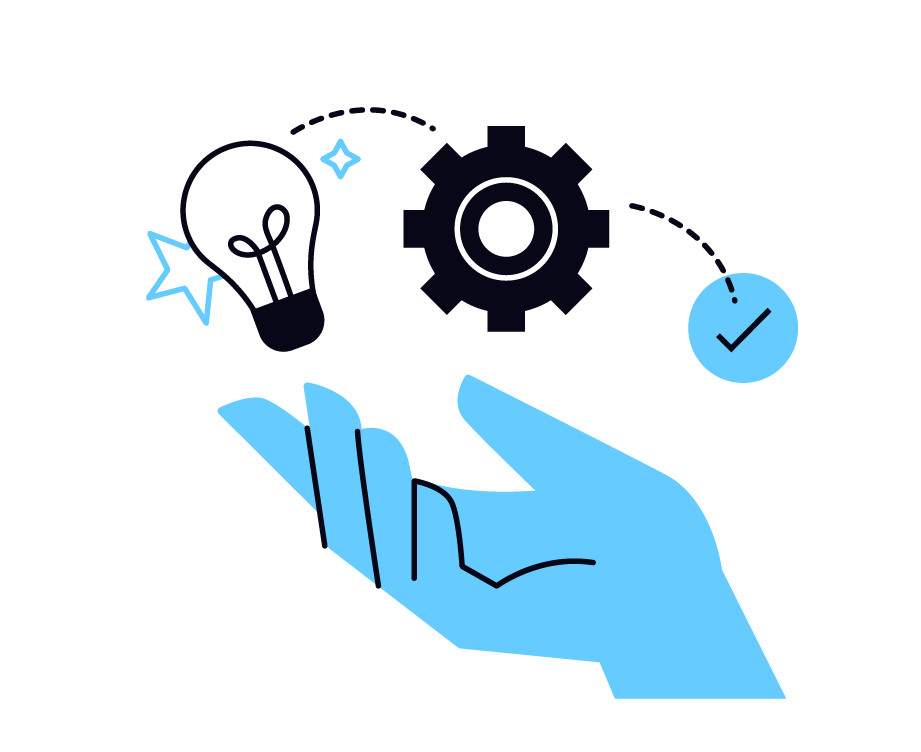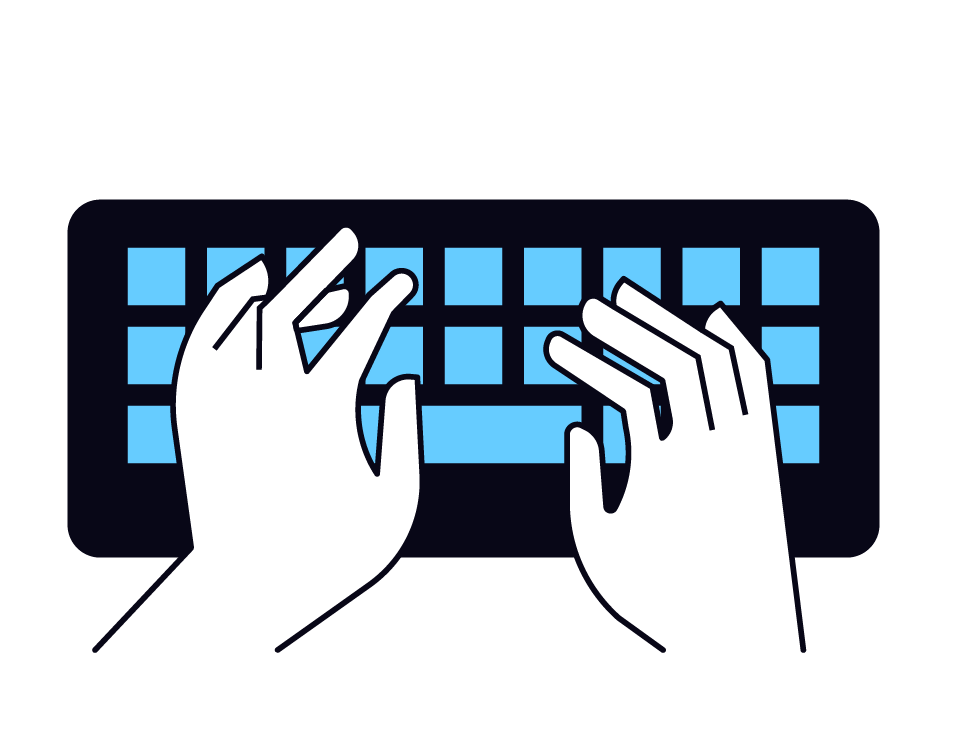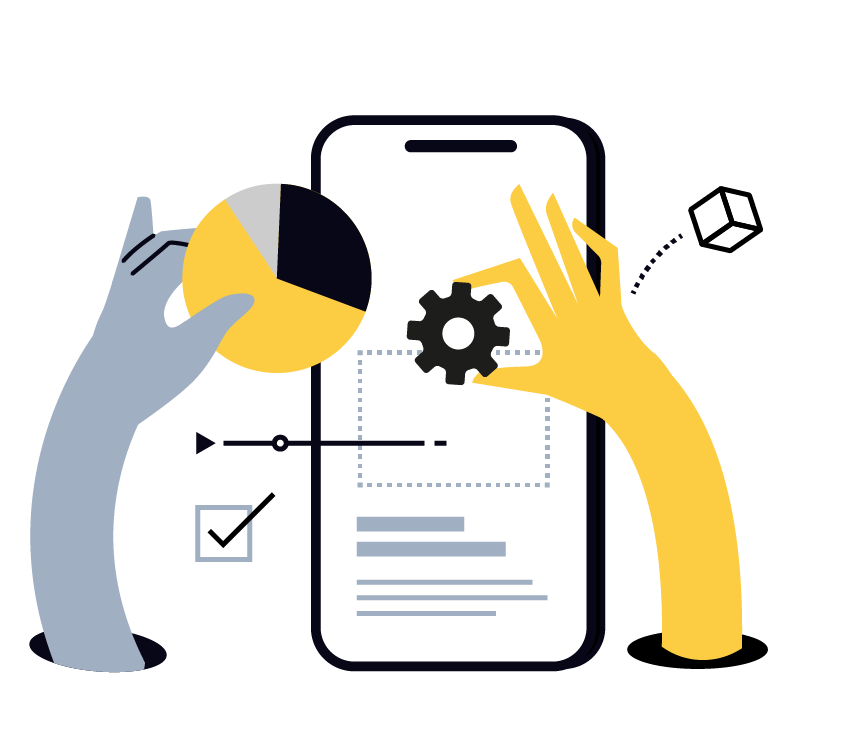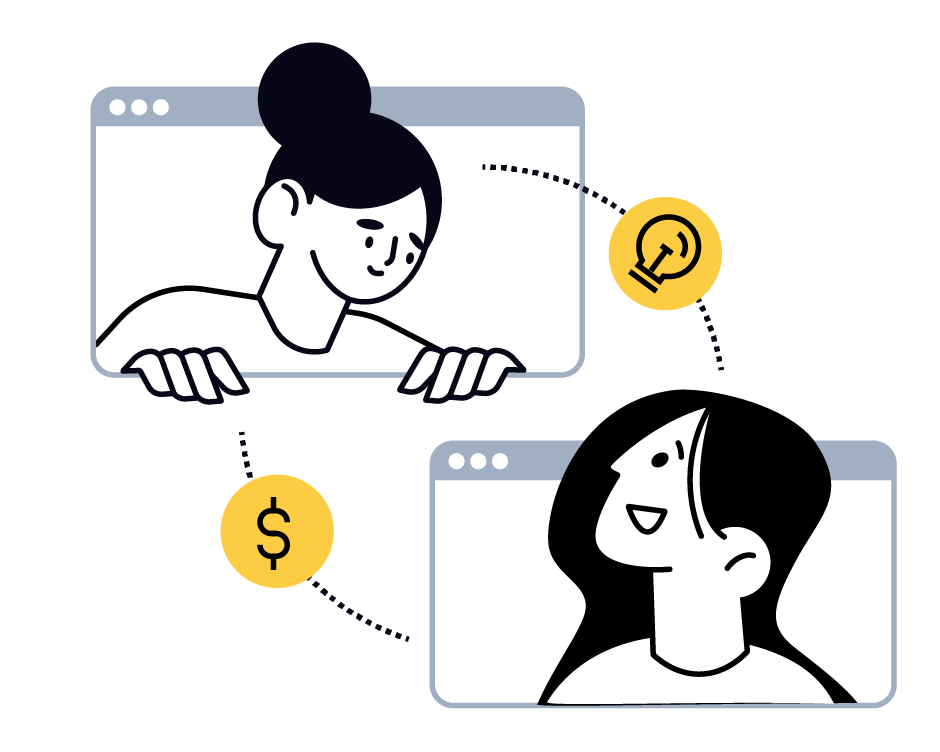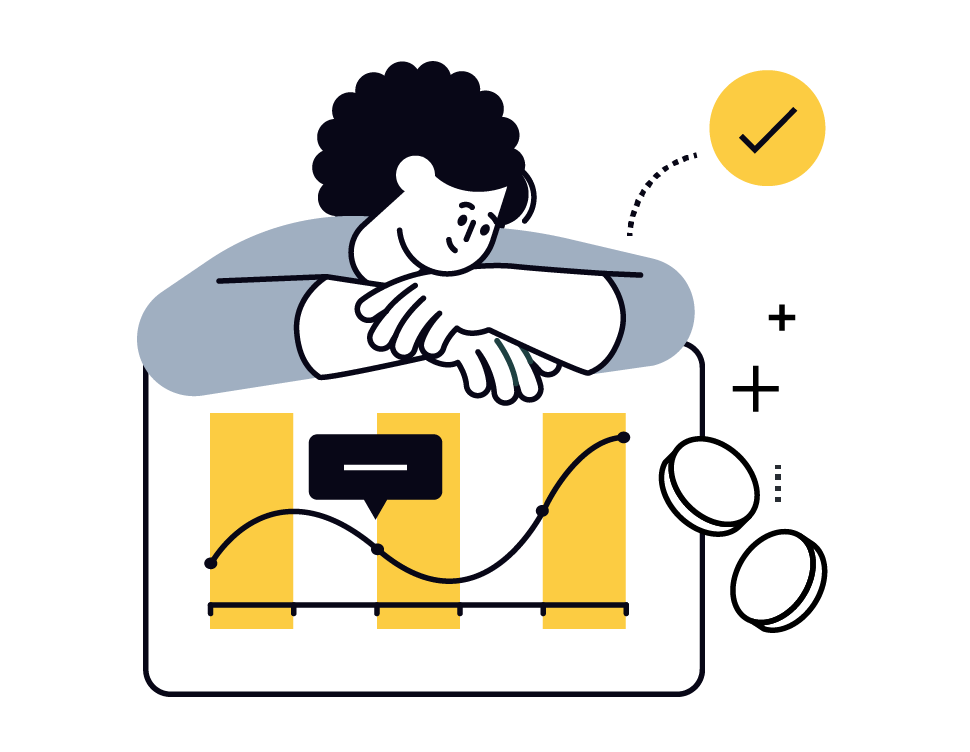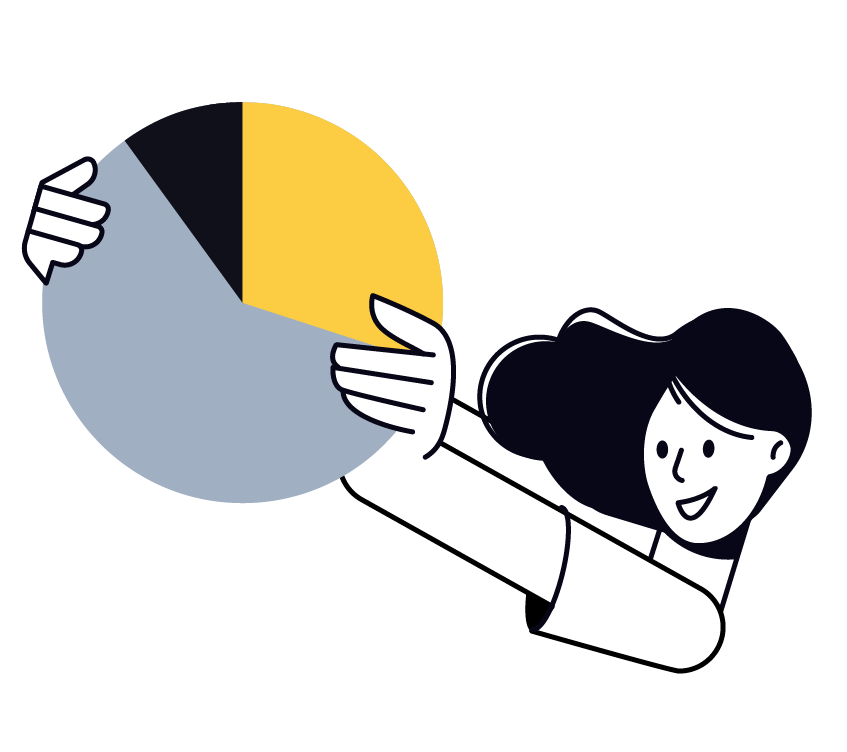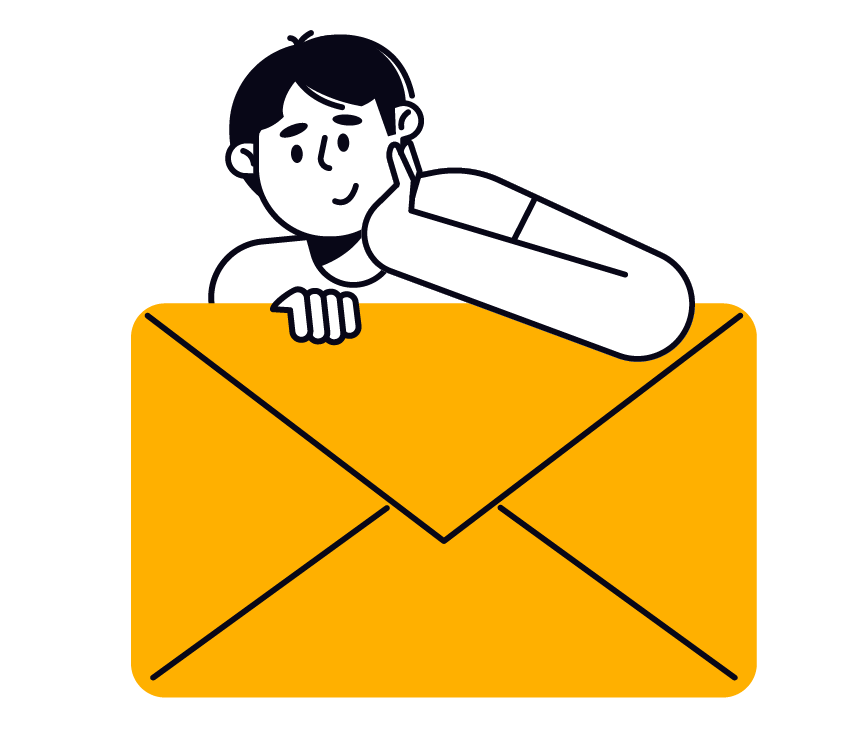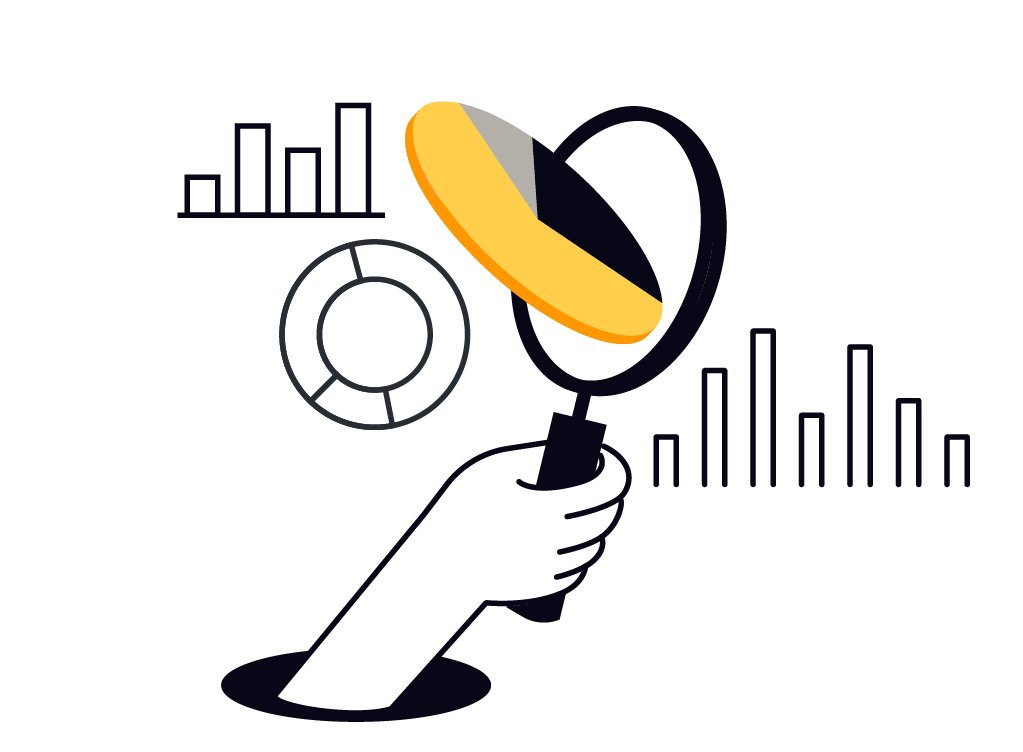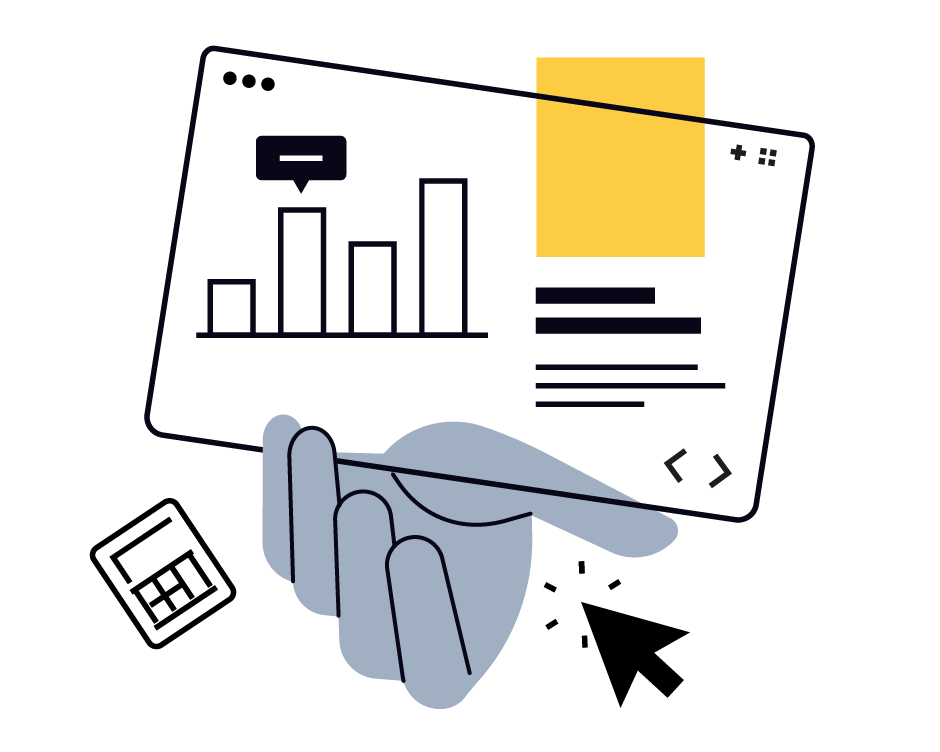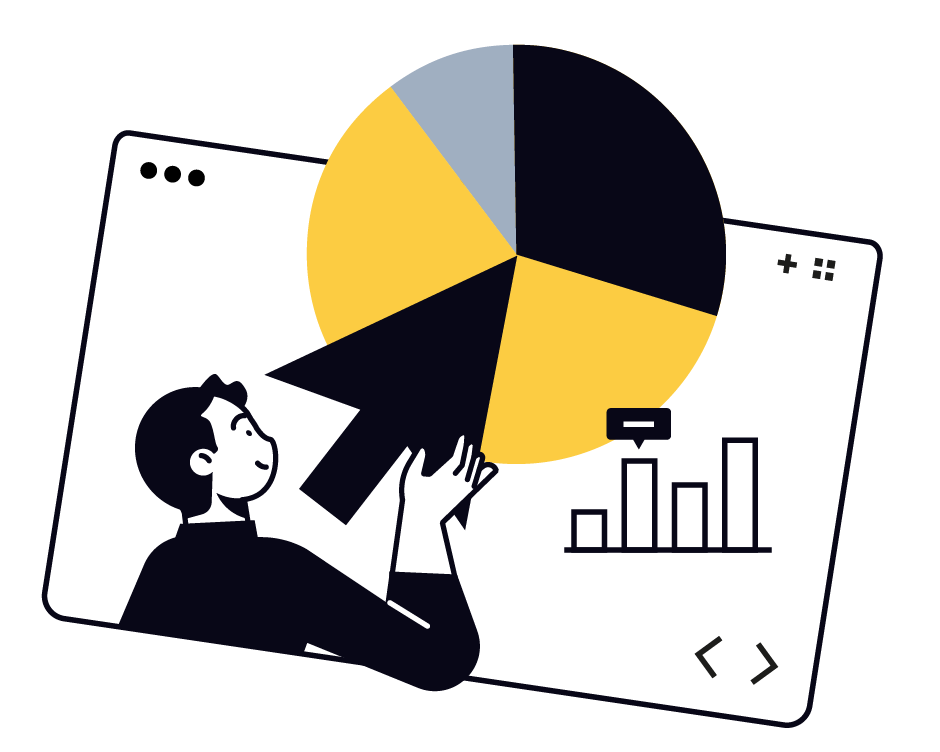1. CRM・SFA・MAの役割を整理する
1-1. CRM(顧客関係管理)の役割
CRMは顧客の属性情報や過去のやり取りを一元管理するための仕組みです。顧客情報を「資産」として蓄積し、部門を越えた顧客対応の質向上に役立ちます。具体的には以下のようなデータが管理されます:
- 基本属性:会社名、部署、役職、担当者名、連絡先
- 購買履歴:購入した製品やサービスの内容、時期、金額
- コミュニケーション履歴:問い合わせ履歴、サポート対応記録、メールや電話の内容
- 契約情報:契約開始日・終了日、更新履歴、契約金額
これらを統合することで「この顧客にはどのような対応をすべきか」が部門を超えて共有され、営業・サポート・マーケティングのすべてに役立ちます。
1-2. SFA(営業支援システム)の役割
SFAは営業担当者の行動や案件の進捗を管理するためのツールです。営業現場の動きを可視化することで、マネジメントの精度向上や営業活動の効率化を支えます。主に以下のようなデータが扱われます:
- 案件情報:案件名、受注予定日、金額、ステータス
- 営業活動ログ:訪問日、商談の議題、進行状況、次回アクション
- 見積・提案履歴:見積金額、提案資料、コンペ状況
- 受注確度のスコア:過去のデータや営業担当者の入力を基に確度を数値化
これらのデータにより「どの案件が優先度高いか」「営業チーム全体のパイプラインはどうなっているか」が一目で分かり、成果予測やリソース配分が最適化されます。
1-3. MA(マーケティングオートメーション)の役割
MAは見込み顧客の行動データを蓄積し、自動的に適切な情報を配信する仕組みです。リードナーチャリングやスコアリングを通じて「温度感の高いリード」を営業に引き渡すことで、マーケと営業の連携を強化します。具体的なデータ例は以下の通りです:
- Web行動データ:サイト訪問履歴、閲覧ページ、滞在時間、フォーム入力内容
- メールデータ:開封履歴、クリック率、配信停止の有無
- イベント参加データ:セミナー申込、来場記録、アンケート回答
- スコアリング情報:一定の条件(例:資料DL+Webセミナー参加)に基づいたリードの優先度数値
これらを活用することで「いま最もアプローチすべきリード」が明確になり、営業活動の効率化につながります。
2. 連携設計のポイント
2-1. データフローの設計
CRM・SFA・MAはそれぞれ得意分野が異なるため、データの流れを明確にすることが重要です。たとえば「MAで行動データを収集→スコアリング→CRMに反映→SFAで営業活動に活用」といったシナリオを設計します。
さらに実践的には:
- 入力元の明確化:WebフォームはMA、営業日報はSFA、顧客情報更新はCRMと役割を分担する。
- データの粒度:MAでは行動単位の細かいログを扱い、CRMでは顧客単位に集約する、といった整理が必要。
- 同期頻度:MA→CRMはリアルタイム、CRM→SFAは1日1回など、目的に応じて最適化する。
こうした流れを設計することで、データが滞留せず、営業活動に直結する情報循環が実現します。
2-2. 部門をまたぐ活用
マーケ部門はMAのリード情報を活用し、営業部門はSFAを通じて案件化を進め、カスタマーサポート部門はCRMで対応履歴を管理します。それぞれのデータが循環することで「顧客を中心にした一元管理」が実現します。
部門ごとに活用できる観点は次の通りです:
- マーケティング部門:リードスコアの高い顧客を可視化し、重点的に施策を展開。
- 営業部門:CRMの過去履歴とMAの最新行動データを組み合わせ、商談の切り口を検討。
- カスタマーサポート部門:契約・サポート履歴を把握しつつ、MAでのWeb行動を参照して問い合わせ背景を理解。
- 経営企画部門:各システムのデータを統合し、顧客生涯価値(LTV)や案件化率をダッシュボードで可視化。
このように「誰が、どのデータをどう使うか」を明確にすることで、部門横断でのシナジーが最大化されます。
3. 導入前に確認すべきチェックリスト
- 目的が明確か? 単なるツール導入ではなく「顧客データ活用で何を実現するか」を定義する。
- 既存システムとの整合性は? CMSや基幹システムとデータ連携できるか確認。
- 運用体制は整っているか? 営業・マーケ・IT部門それぞれが役割を持って運用できるかを事前に設計。
- データの入力ルールは明確か? CRMやSFAに正しい情報が入力されないとMAも機能不全に陥る。
- 評価指標は定義されているか? MAならMQL(Marketing Qualified Lead)、SFAなら案件化率など指標を設ける。
4. 成功パターンと失敗パターンの比較
| 観点 | 成功パターン | 失敗パターン |
|---|---|---|
| 目的設定 | 「商談化率を高めるためにデータを一元管理する」と明確 | 「とりあえず導入すれば成果が出る」と曖昧 |
| データ運用 | 入力ルールを徹底し、営業・マーケ双方が活用 | 営業が入力せず、データが空洞化 |
| 連携設計 | MA→CRM→SFAと流れを定義 | 各システムがバラバラに稼働 |
| 改善サイクル | KPIを定期的に見直し運用改善 | 導入後は放置し、使われなくなる |
5. 運用フェーズ別の工夫
- 導入初期:スモールスタートで限定的な顧客セグメントに適用し、効果を検証。
- 定着期:入力ルールの徹底や定例会議でのレビューにより、データの質を安定化。
- 拡大期:MAでのシナリオ数を増やし、CRM・SFAとのデータ連携を高度化。
6. 導入後に定期的に見直すチェックリスト
- KPIの妥当性:設定した指標が現状の営業・マーケ戦略に合致しているかを再確認する。
- 入力ルールの遵守度:運用が進む中でデータ入力が形骸化していないかを点検する。
- シナリオの鮮度:MAで設計したシナリオが古くなっていないか、顧客行動に即しているかを評価する。
- システム負荷やコスト:データ量やライセンス料が想定を超えていないかを定期的にチェックする。
- 部門間の連携状況:マーケ・営業・サポートの連携が継続的に機能しているかを振り返る。
7. まとめ
CRM・SFA・MAはそれぞれ役割が異なりながらも、連携することで「顧客を中心にした営業・マーケのデータ活用」が可能になります。導入前・導入後のチェックリストや成功/失敗パターンを参照しながら、システムを単なるツールとしてではなく、組織全体の「顧客理解の基盤」として活用することが、BtoBマーケティングの成果に直結します。