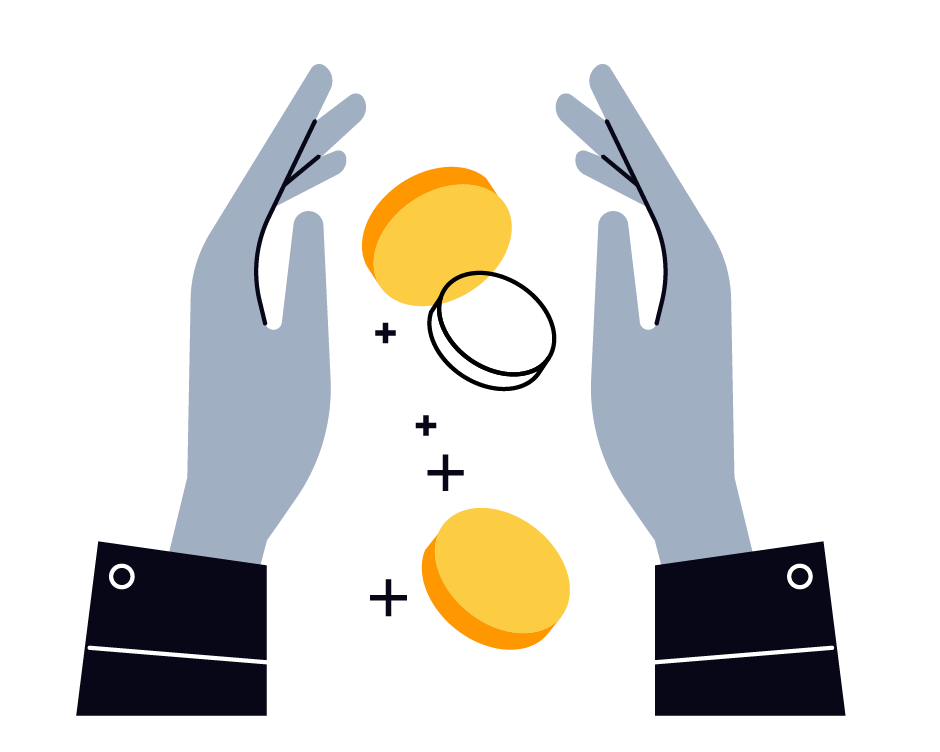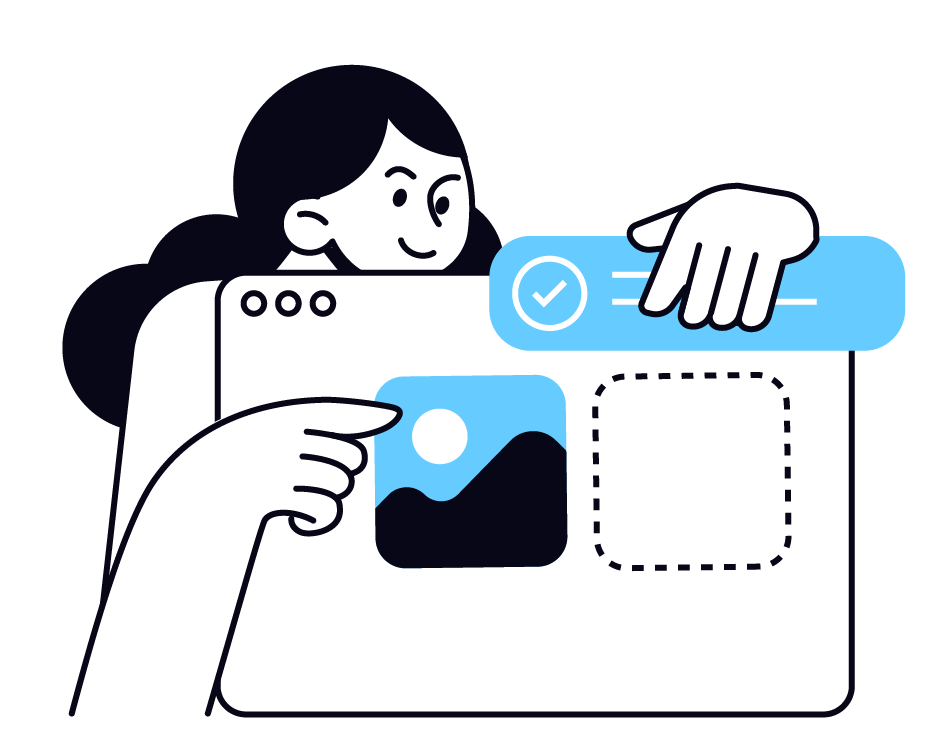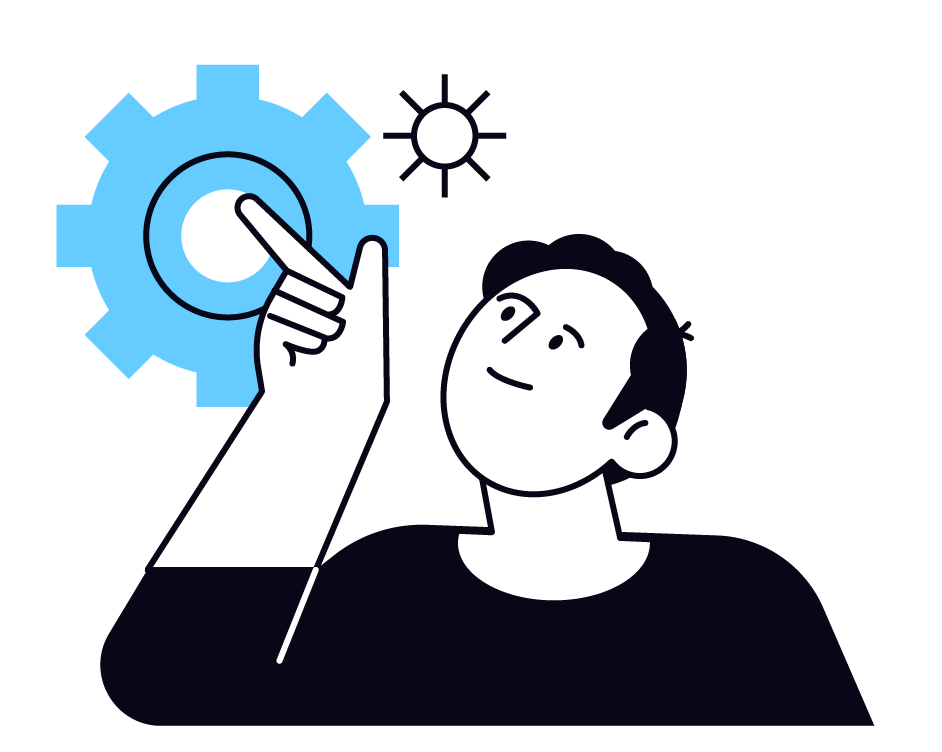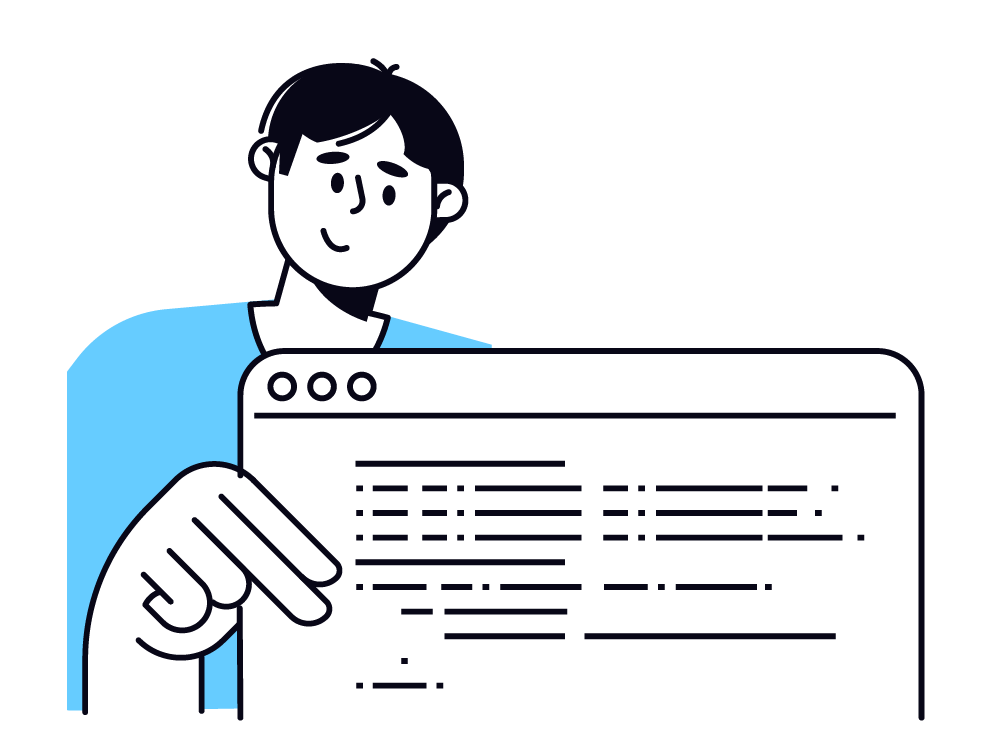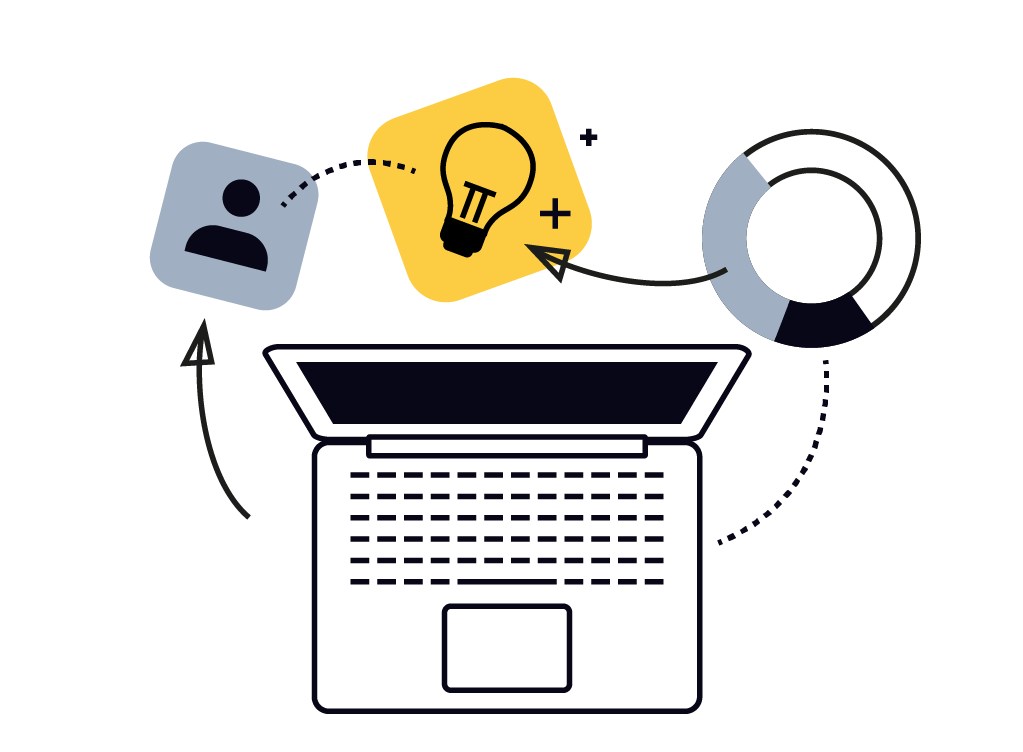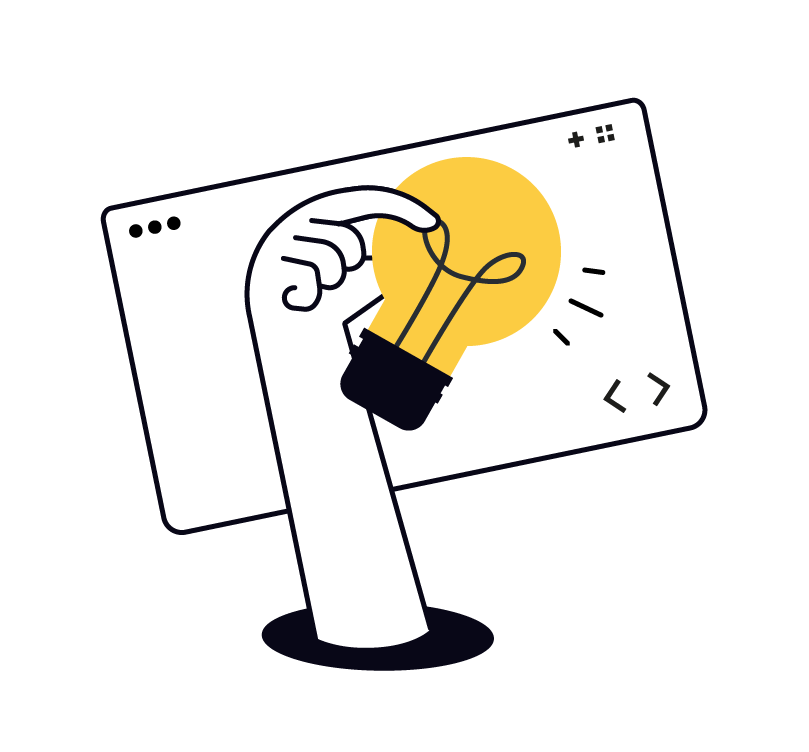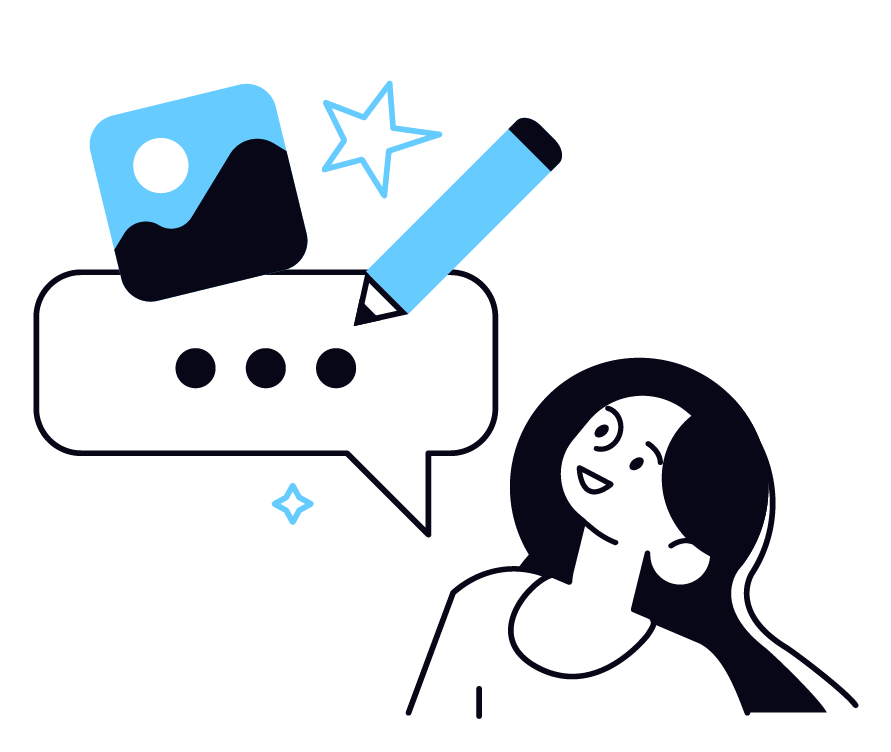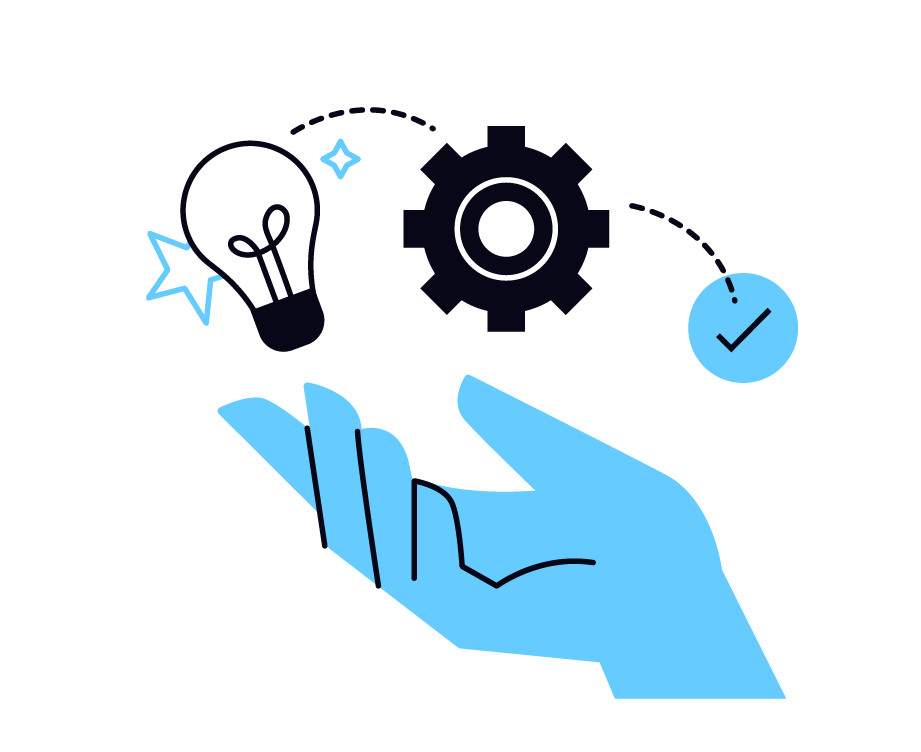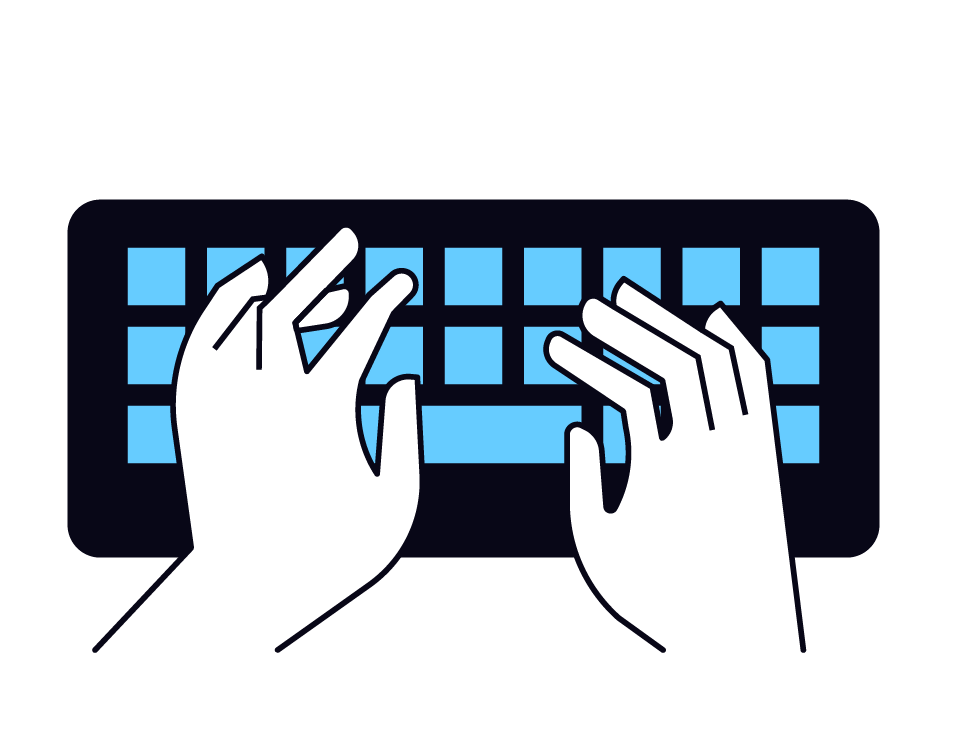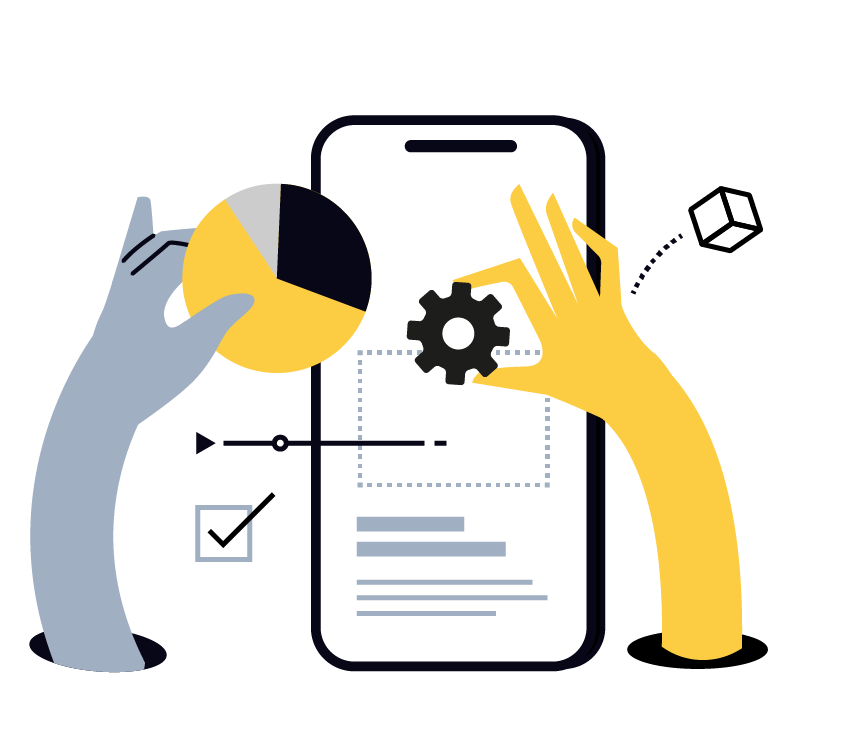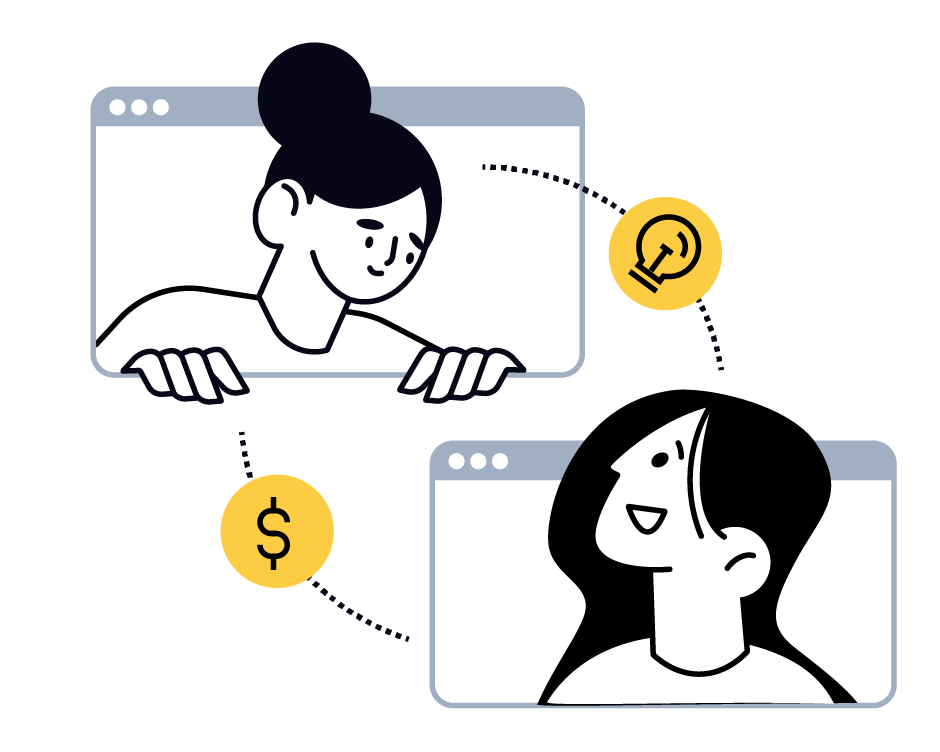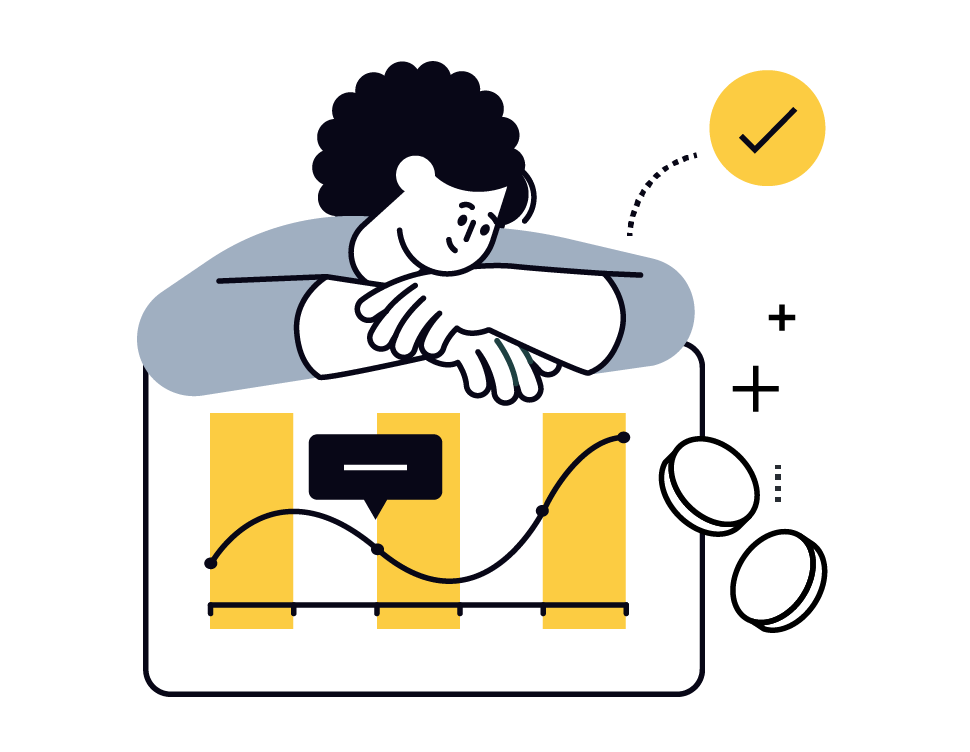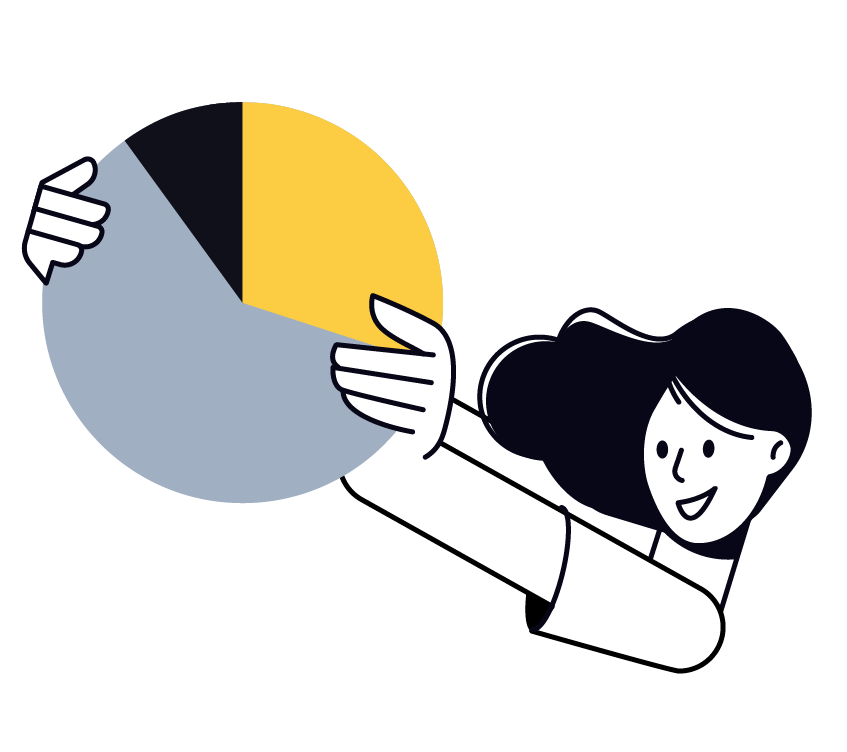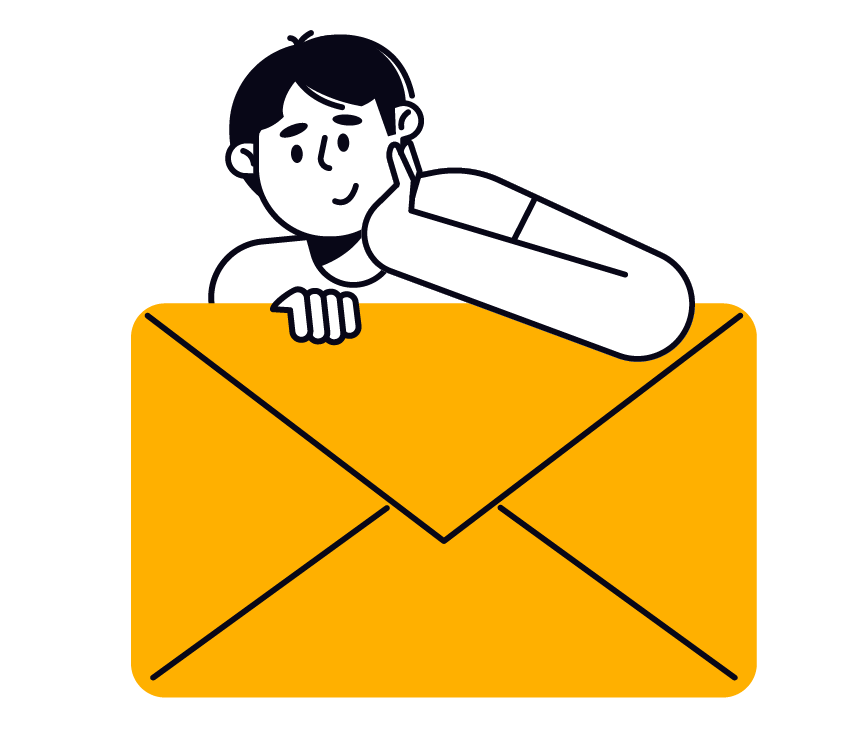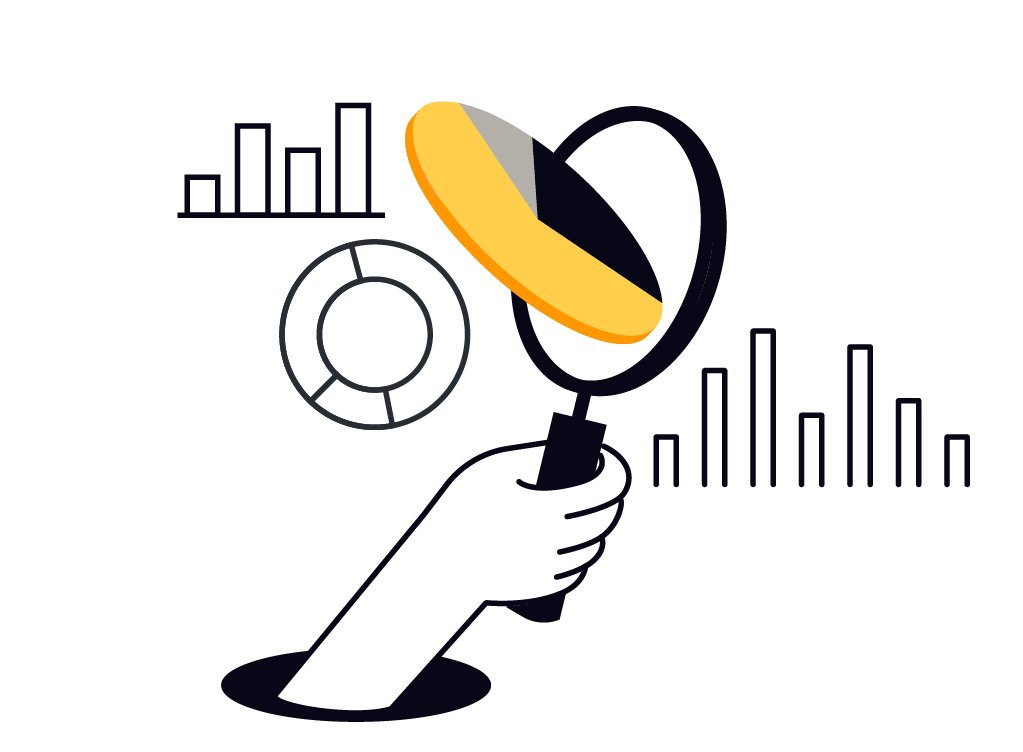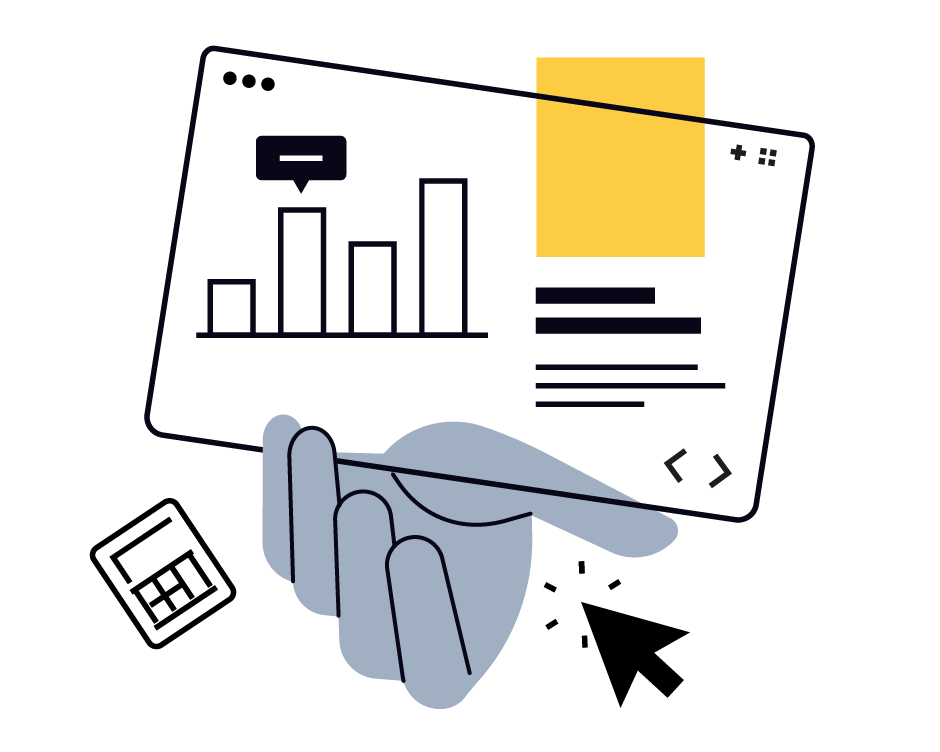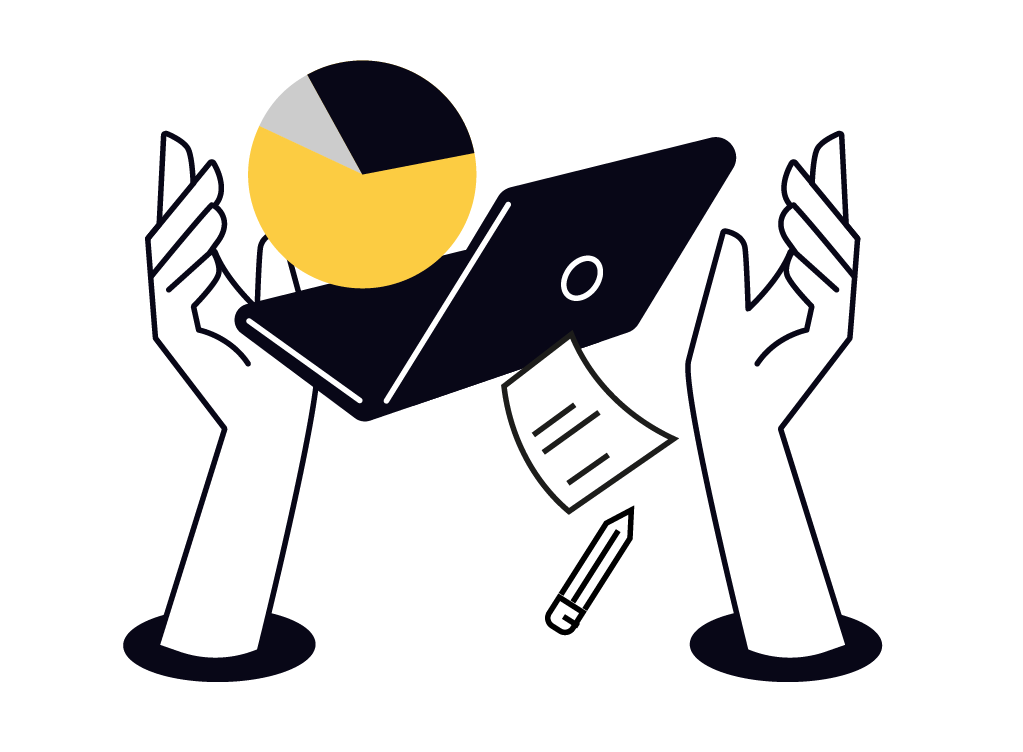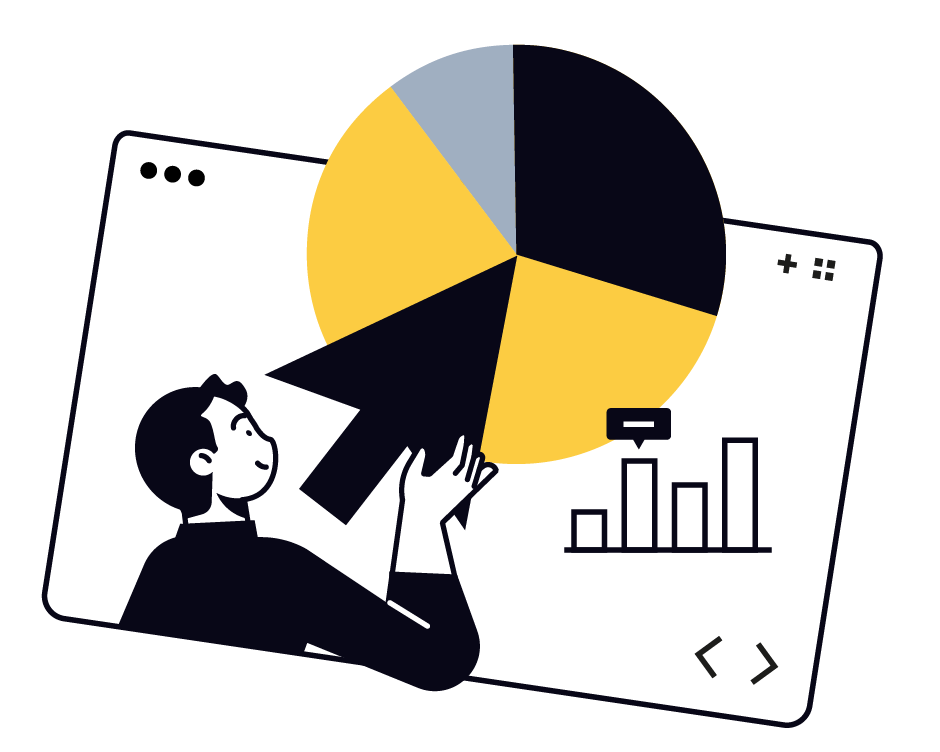1. はじめに:リードは「獲得した後」が重要
BtoBマーケティングにおいて、フォームを通じてリード(見込み顧客)を獲得することは、施策のスタート地点にすぎません。重要なのは、その後の活用プロセスです。
多くの企業が「リード数」や「CV数」をKPIとして重視しますが、リードの獲得だけでは売上にはつながりません。むしろ、獲得したリードをいかに育成(ナーチャリング)し、商談化・受注へとつなげられるかが、マーケティングROIを大きく左右します。
- 獲得したリードをどう分類し、
- どのようなタイミングで接点を作り、
- 適切なアクションに誘導するか
これらを戦略的に設計することが、BtoB企業にとって欠かせないマーケティング戦術です。本記事では、フォームから得た情報を活かし、成果に結びつけるための設計・実践ポイントをSEO視点も交えて詳しく解説します。
2. フォーム情報を活かすための設計思想
2-1. 入力項目を「属性」と「意図」に分類する
フォームには、ユーザーからさまざまな情報が入力されますが、それらは大きく以下の2つに分類できます。
- 属性情報:会社名、業種、所在地、部署、役職、従業員規模など、比較的変更のないプロフィール系の情報。
- 意図情報:資料請求や問い合わせ内容、関心のある製品・サービス、導入検討時期、課題感など、顧客の関心・目的に関わる情報。
この分類を明確に意識することで、「どんな属性の人が、どんなニーズを持っているのか」が読み取れるようになります。単なる名簿ではなく、“営業アプローチすべきリスト”へと変貌させる第一歩です。
2-2. リードスコアリングの前提づくり
リードスコアリングとは、獲得したリードの質や確度を数値化する仕組みです。例えば、営業部門が「温度の高いリード」に優先的にアプローチできるよう、スコアを可視化しておくことで、機会損失を防げます。
スコア設計の前提となるのが、フォームで取得する情報です。
例:
- 導入時期が「3か月以内」 → スコア:高
- 部署が「情報システム部」 → スコア:中
- 興味製品が「競合比較」目的 → スコア:低
こうした前提条件を定めるためにも、フォーム設計は“取得すべき情報”から逆算して設計する必要があります。
3. 活用フェーズ別のシナリオ設計
リード情報は、以下のようなフェーズごとに活用のポイントが異なります。ここでは各フェーズでのシナリオ例を紹介します。
3-1. 獲得直後のアクション
自動返信メールとコンテンツ提供
フォーム送信後に即時で送るサンクスメールは、ただの定型文ではなく、“次の行動を誘導する”内容にすることが重要です。
- 関連資料(PDF、ホワイトペーパー)のリンク
- 動画・ウェビナーアーカイブの案内
- サイト内の関連コンテンツ誘導
メール開封・リンククリック・資料DLなどのログをトラッキングすれば、興味の深度も把握できます。
担当者アサインの自動化
たとえば「業種」「地域」「関心サービス」によって営業担当を自動アサインする仕組みを構築すれば、スピーディなフォローが可能になります。SFAやCRMとの連携が重要なポイントです。
3-2. ナーチャリング施策
ステップメールで関係性を育てる
フォームから獲得したリードに対して、一定の期間をかけて興味を深めてもらう「ステップメール」は、特にBtoBでは有効です。
例:
- Week1:導入事例(同業種・同規模)
- Week2:製品の特長解説コンテンツ
- Week3:課題別ソリューション提案
- Week4:相談会・セミナー案内
Web行動データとの統合
フォーム送信後にユーザーがどのページを閲覧したか、どんな資料をダウンロードしたかを行動ログで追跡すれば、関心領域の深堀りが可能です。
「製品Aに興味があると言ったが、製品Bの比較ページを多く見ている」など、行動と入力情報のギャップから次の打ち手が見えてくることもあります。
3-3. 商談化支援
インサイドセールスの活用
スコアリングにより「確度の高いリード」を抽出したら、インサイドセールスによる架電やオンライン商談の打診を行います。あらかじめフォーム情報を把握した上でアプローチすれば、会話の質も高まります。
営業資料のパーソナライズ
ユーザーが入力した課題や興味関心に合わせて、ホワイトペーパーや導入事例を「相手の立場」に寄せて提案できれば、商談化率は大きく向上します。
4. 実践のポイント
4-1. フォーム項目をシナリオから逆算する
フォーム設計でよくある失敗は、「営業が欲しい情報」を全部詰め込むこと。ユーザーにとっては面倒でしかなく、離脱を招く原因になります。
重要なのは、「どの項目が、どのシナリオの分岐に活用されるか」を設計段階で明確にしておくことです。
具体例:
- 「導入時期」→ スコア付与、即時接触の判断基準に
- 「興味関心のある製品」→ ステップメールの内容出し分け
- 「職種・役職」→ 意思決定者か現場担当者かでシナリオ分岐
4-2. データが活きるMA・CRM連携
フォームから得たデータを“活用できる状態”に保つには、MA(マーケティングオートメーション)やCRMへのスムーズな連携が必要不可欠です。
- MAで:スコアリング、自動配信、セグメント管理
- CRMで:営業アサイン、商談状況管理、次回アクションの記録
手動でエクセル管理していては、せっかくのリード情報も埋もれてしまいます。ツール連携の体制整備は、デジタルマーケティングの土台です。
5. まとめ:リードの活用は「取得設計」から始まっている
リード活用の成功は、フォーム送信後ではなく、**「どんな情報を、どのように取得するか」**というフォーム設計時点から始まっています。
- 入力情報をもとに分類・評価し
- 適切な接点(メール・営業・Webコンテンツ)を提供し
- 商談・受注へとつなげていく
この一連のプロセスをシームレスに構築することで、フォーム入力情報は単なる“問い合わせ”ではなく、ビジネスの成果に直結する“マーケティング資産”へと変わります。
リード獲得に力を入れるすべての企業にとって、「入力情報をどう活かすか」は、CV率以上に大切な視点です。今一度、自社のフォーム設計とその後の活用プロセスを見直してみてはいかがでしょうか?