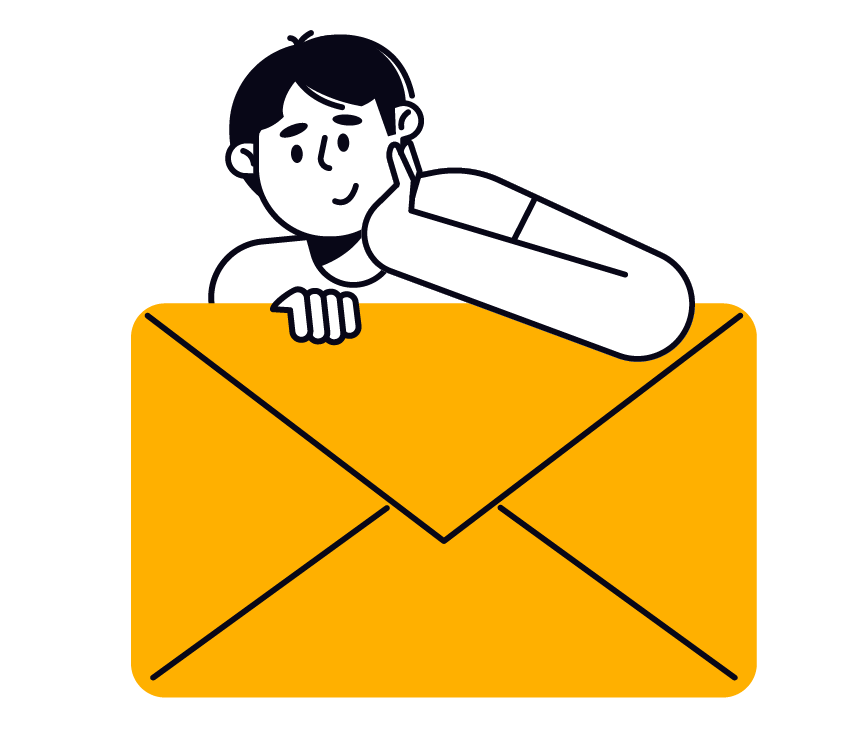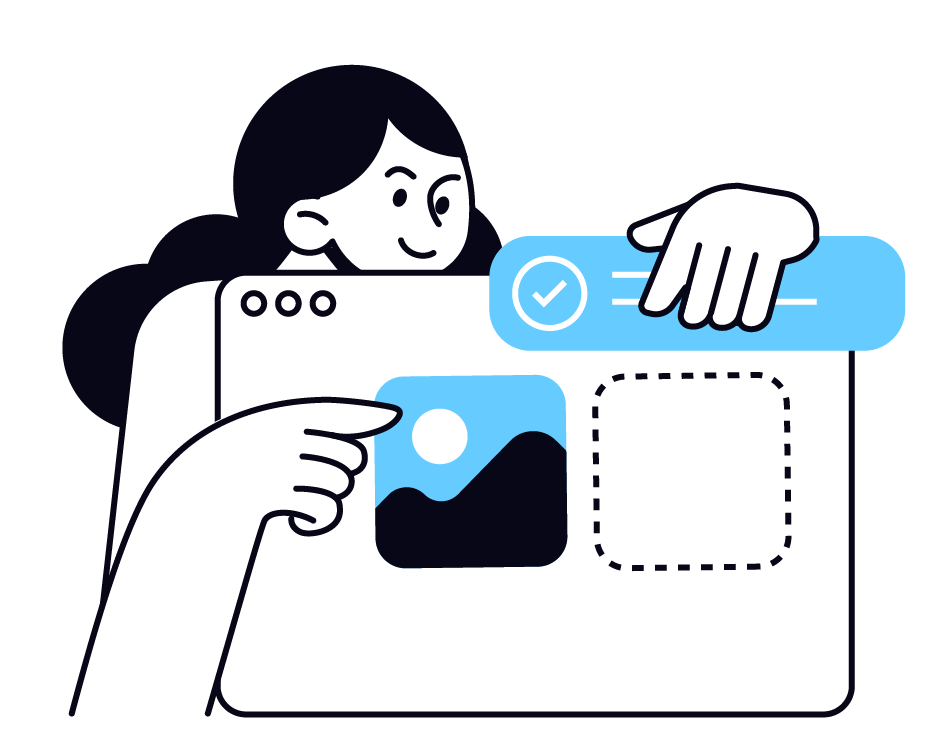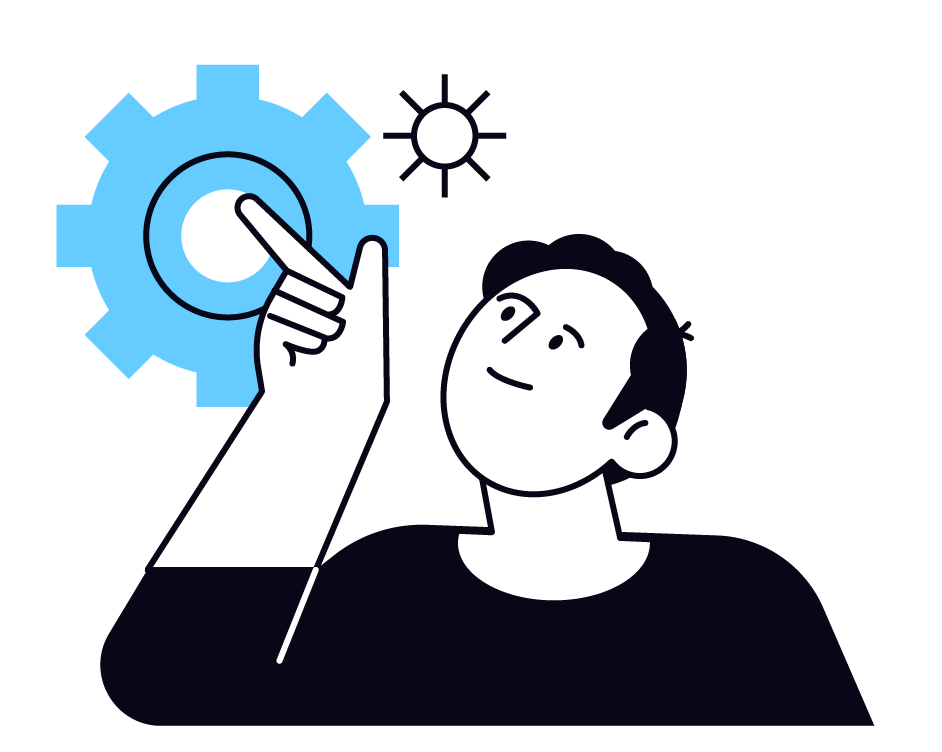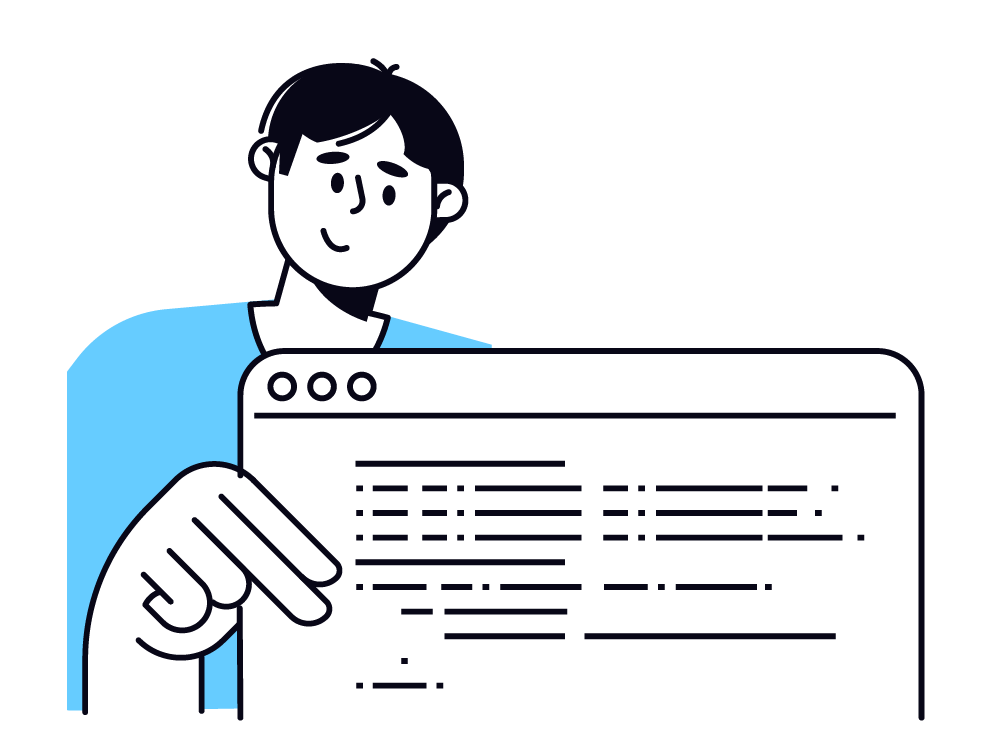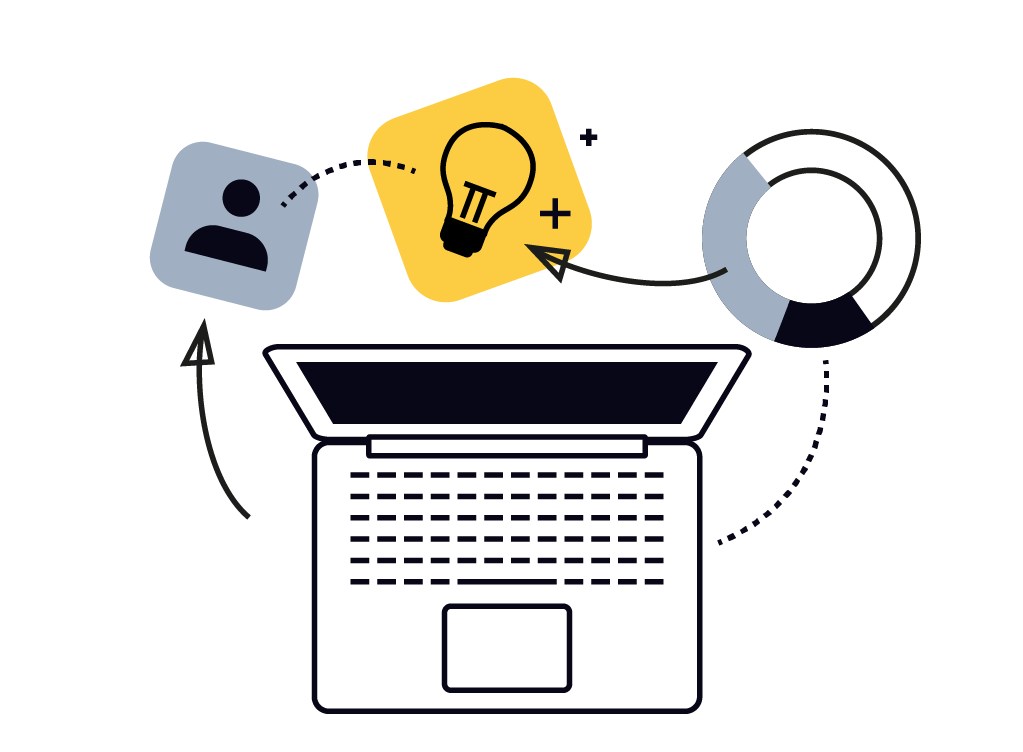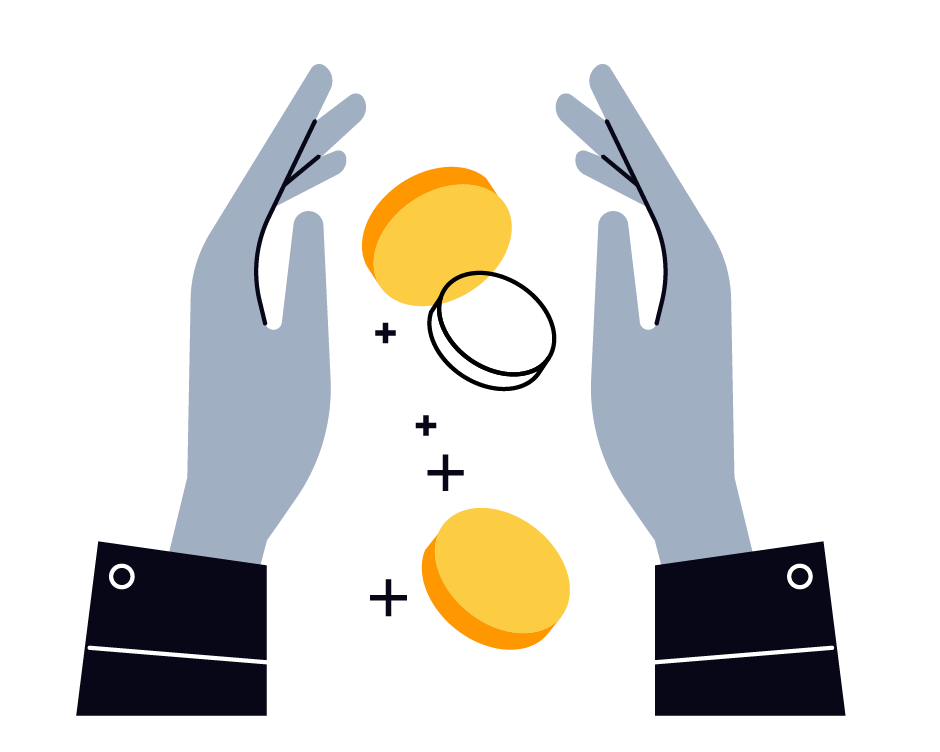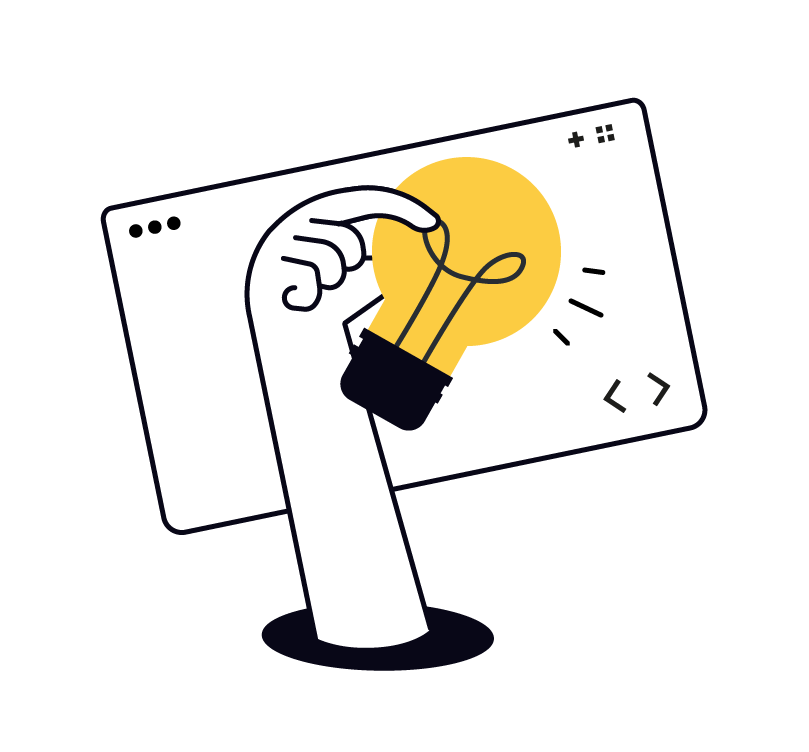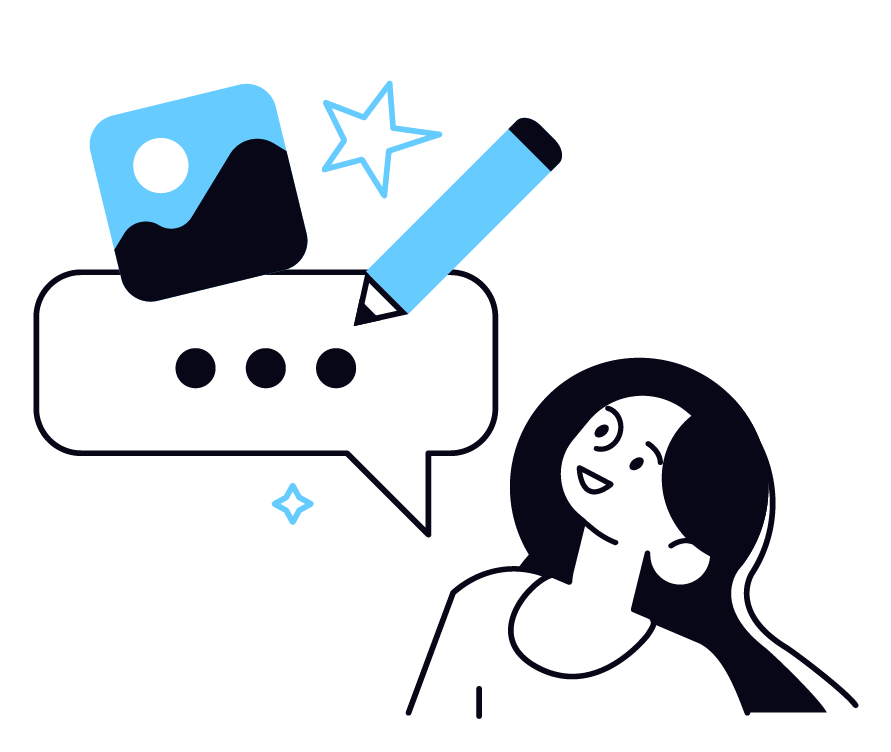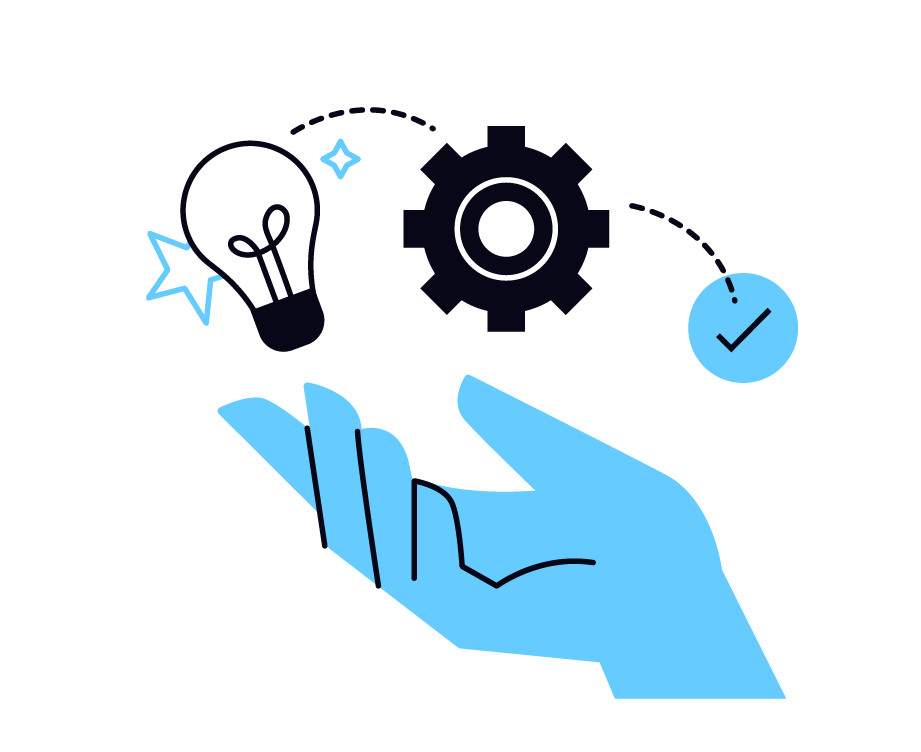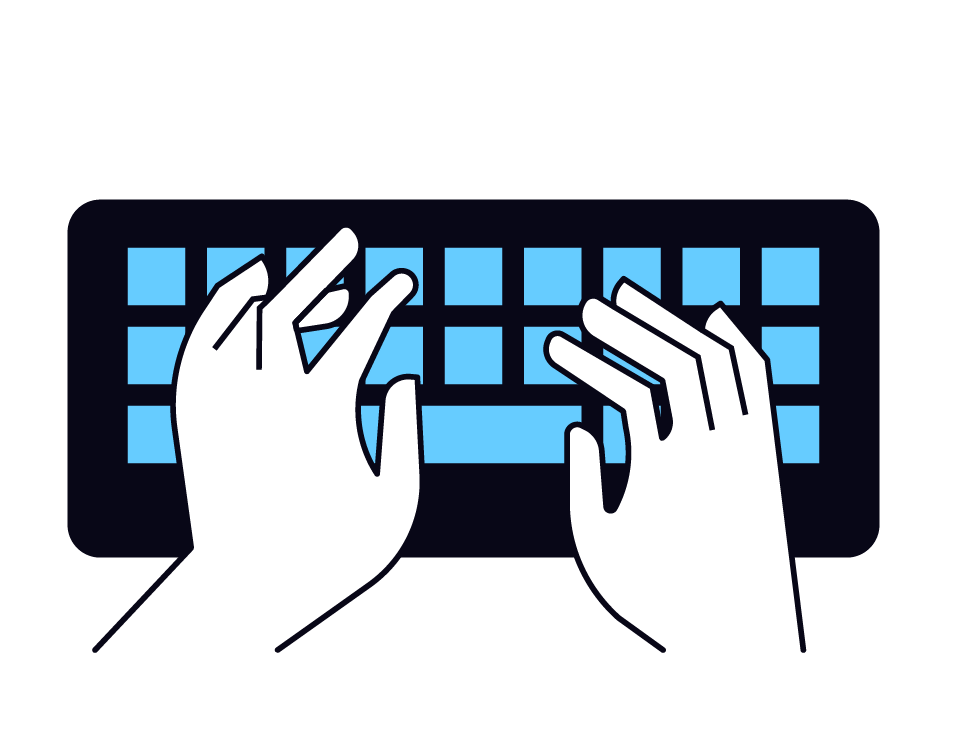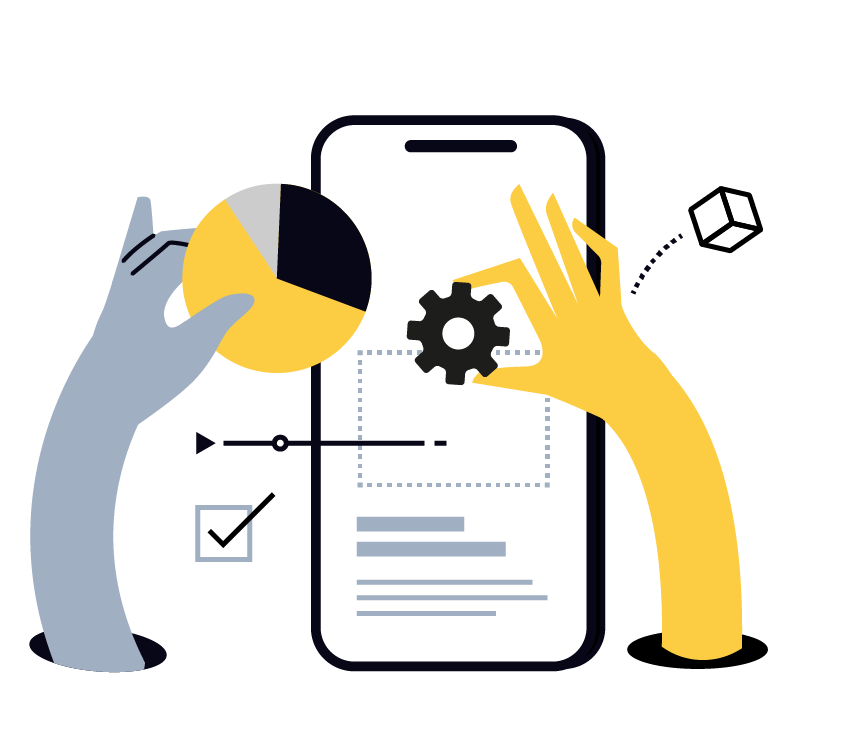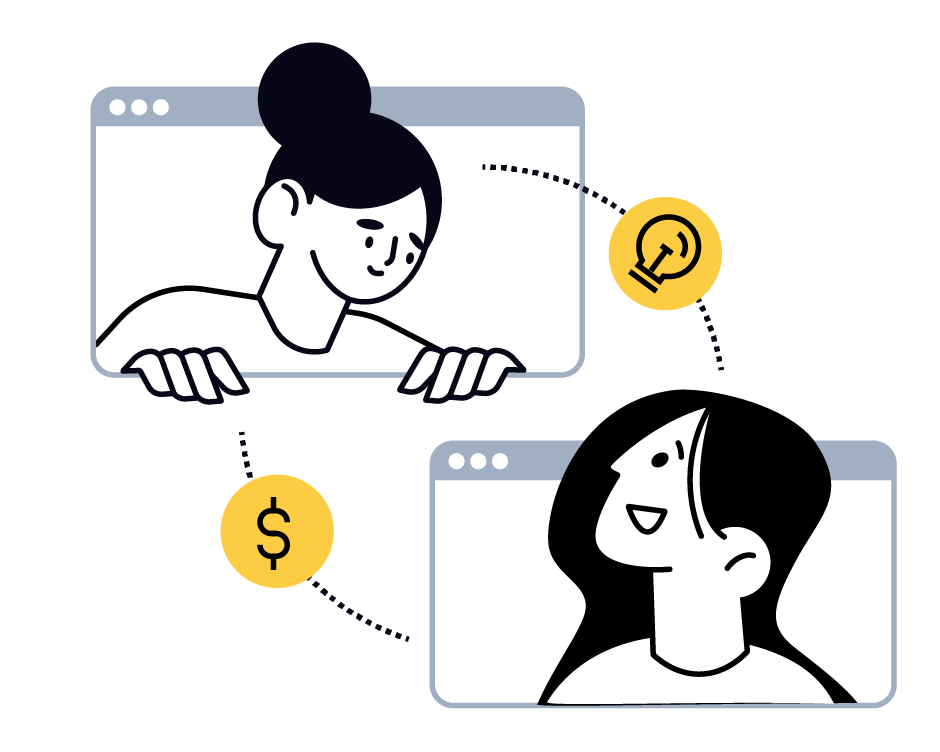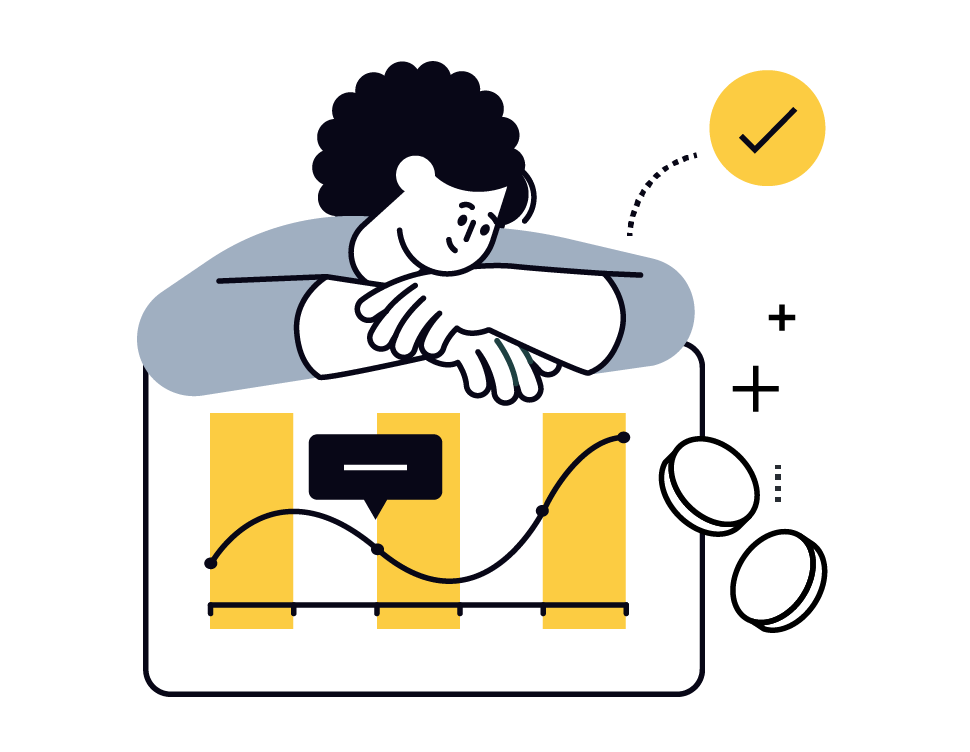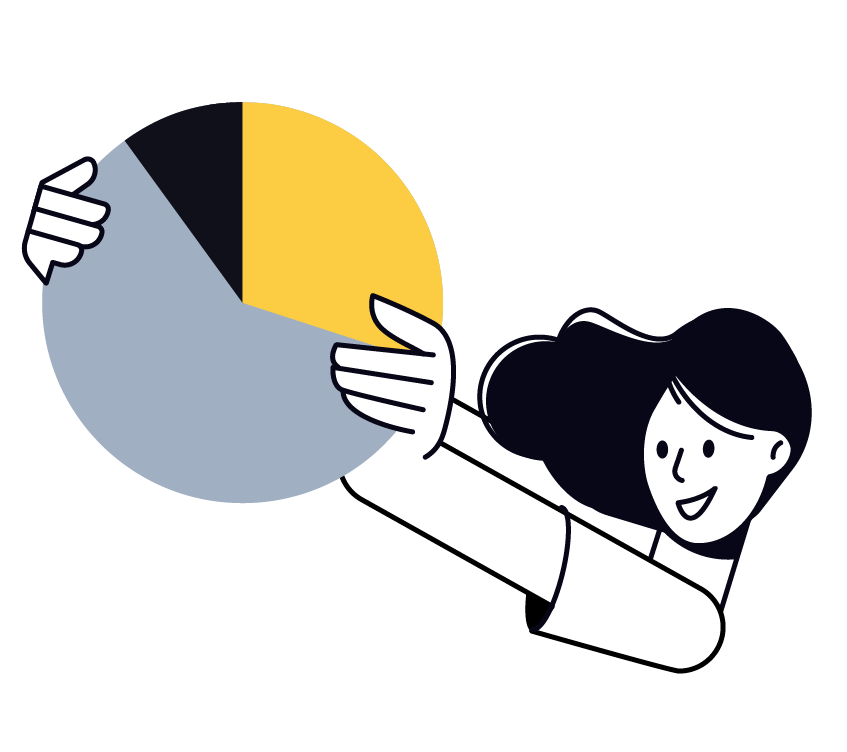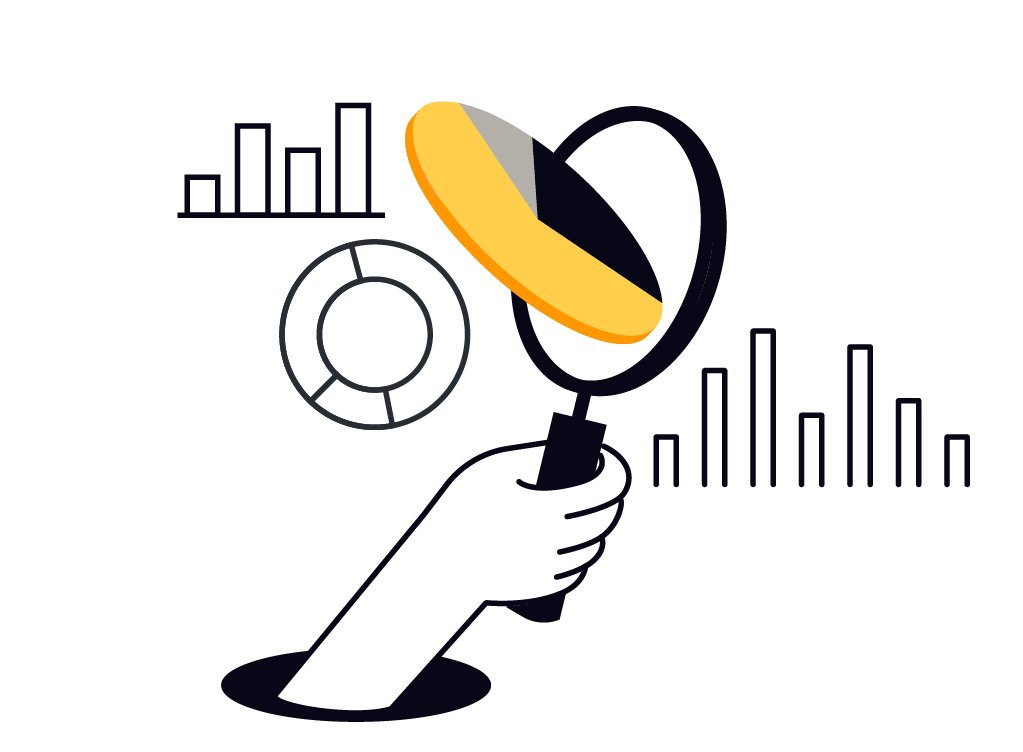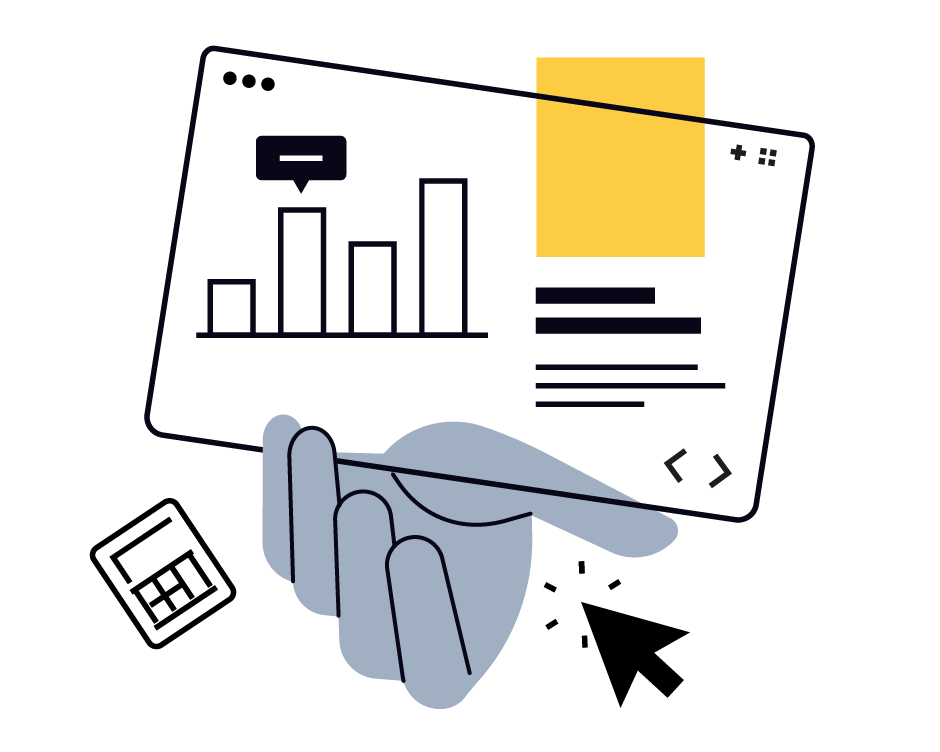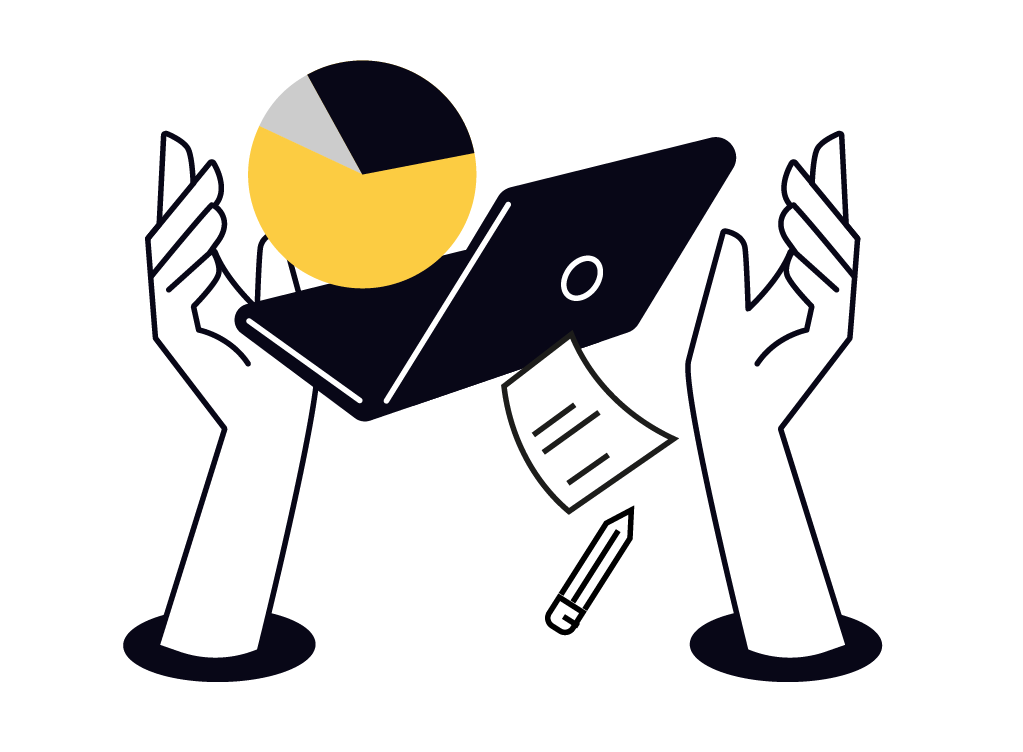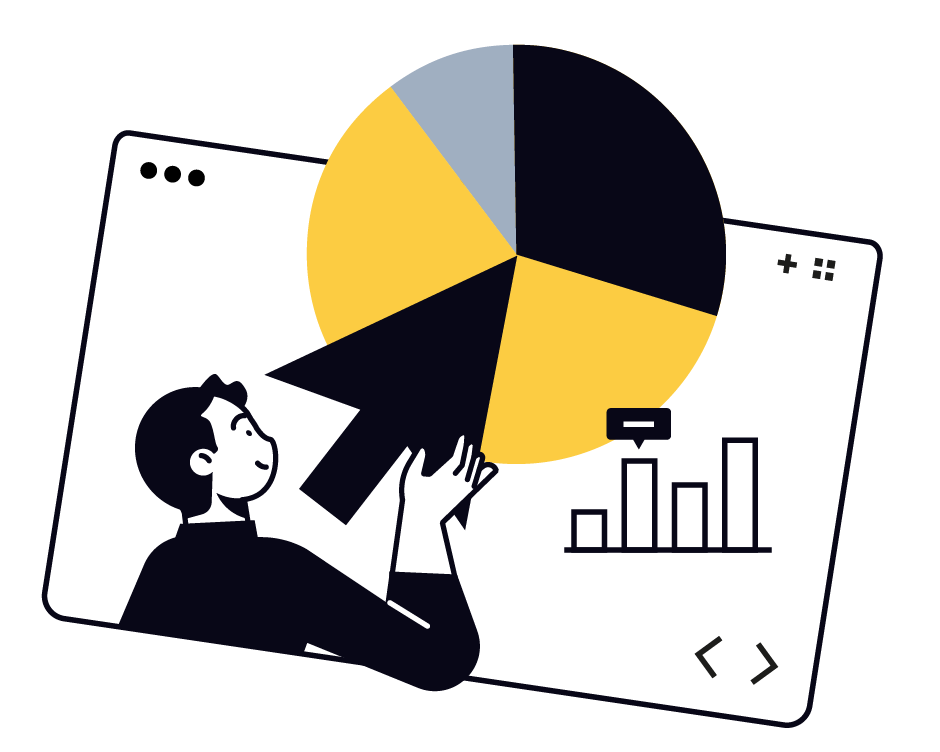BtoBマーケティングにおいて、メール配信は今なお極めて重要なチャネルの一つです。リードナーチャリング、顧客との継続的な関係構築、情報提供、イベント告知など、活用シーンは多岐にわたります。しかし、成果を出すには「何となく配信する」ではなく、戦略的な設計と運用が欠かせません。
本記事では、「BtoB メール配信 基本」「ステップメール 設計」「メールマーケティング 成功法」などのSEOキーワードを意識しつつ、メール配信をBtoBマーケティング施策として最大限活用するための考え方と設計ポイントを、実務に直結する形で詳しく解説します。
1. なぜBtoBマーケティングにおいてメール配信が重要なのか?
1-1. 長期的なリードナーチャリングに適している
BtoB商材は検討期間が長く、関与者が多いという特徴があります。したがって、一度の接点では受注に至らず、継続的な情報提供を通じて関係性を構築していく「ナーチャリング型」のアプローチが必要です。メールは、相手のペースで情報を受け取れる非同期コミュニケーションであり、関係維持のタッチポイントとして最適です。
1-2. データ取得と分析がしやすいチャネル
Webアクセスと異なり、メールは開封・クリックなどの個別行動がログとして取得可能です。これにより、「誰が、どのコンテンツに興味を持ったか」を精度高く把握でき、行動データに基づいたセグメント分けやステップ配信にも活用できます。
また、WebサイトやCMSコンテンツとの連携により、メールからの遷移先コンテンツやCV地点を可視化することで、マーケティングファネル全体を一貫して最適化することも可能です。
2. メール施策におけるありがちな誤解と落とし穴
2-1. 「配信すれば誰かは見る」は通用しない
BtoBのメール開封率は20〜30%前後が平均とされており、実際には7〜8割が未読のままスルーされています。件名、送信者名、配信タイミングの3点を最適化しない限り、内容以前に“開かれないメール”となってしまいます。
- 【NG例】「〇〇社のご案内」 → どの職種にも刺さらず、埋もれる
- 【改善例】「【営業支援】見込み顧客管理に役立つ無料テンプレート」
2-2. 一斉配信=効率的、は危険な思い込み
属性もニーズも異なる相手に同一文面を送っても反応は取れません。業種・職種・関心テーマごとにセグメント分けした配信は、同じ配信数でも2倍以上の反応率差を生むことがあります。
-
ターゲット別の配信設計
- 製造業の営業マネージャー向け
- IT系のマーケ責任者向け
- 医療系の経営層向け
といった粒度でメールを分けることで、「自分のための情報だ」と感じてもらう導線が作れます。
3. 成果につながる配信設計の基本ステップ
BtoBにおけるメール配信の成功には、以下の4ステップが戦略的に設計されている必要があります。
- 配信対象の設計(リストとセグメント)
- メール内容の設計(コンテンツと構成)
- 配信タイミングと頻度の設計
- 効果測定と改善(PDCA)
以下、それぞれのステップについて掘り下げて解説します。
3-1. 配信リストとターゲティングの考え方
配信リストは“営業資産”である
BtoBのメールマーケティングにおいて、配信リストは単なるアドレス集ではなく、育成中の見込み顧客(リード)群です。リストの質は、メールの成果を左右する大きな要因であり、常にCRMやMAツールと連携して最新状態を維持する必要があります。
セグメント設計の考え方
| セグメント軸 | 具体例 |
|---|---|
| 業種 | 製造業/医療/IT/教育 など |
| 職種・役職 | 営業/マーケティング/経営者/現場責任者 |
| 行動履歴 | 資料DL履歴/Web閲覧履歴/イベント参加経験 |
| 顧客ステージ | 初回接点/MQL/SQL/受注済み顧客 |
セグメントを掛け合わせて「適切な相手に、適切な内容を、適切なタイミングで」届けることが成果の出発点です。
3-2. メールコンテンツと配信タイミングの設計
メールの基本構成
- 件名:開封率に直結。数字+メリット訴求が王道。
- 冒頭文:読み手との関係性や目的を明確に。共感・課題提起が効果的。
- 本文構成:1メッセージ1メール。複数トピックは避け、CTAを明確にする。
- CTA(行動喚起):資料DL、セミナー申込、コンテンツ閲覧など。スマホでの押しやすさも考慮。
配信タイミングの考え方
- 曜日・時間帯:火~木の午前10時前後、午後2〜3時が高反応帯。
- トリガー型配信:フォーム送信、資料DL直後など、行動に連動した自動配信。
- 頻度設計:月2〜4回がベース。多すぎると開封率・到達率が悪化する。
メール配信は、ただの情報通知ではなく「戦略的なコミュニケーション施策」です。しっかりとターゲットと目的を定め、ユーザーにとって意味のあるタイミングと内容で届けることが重要です。
この記事で紹介した基本設計をもとに、今後のコンテンツでは「反応率を高める件名と構成」「ログ分析による改善」「シナリオ設計による自動化」など、より高度な施策へと段階的に深堀りしていきます。