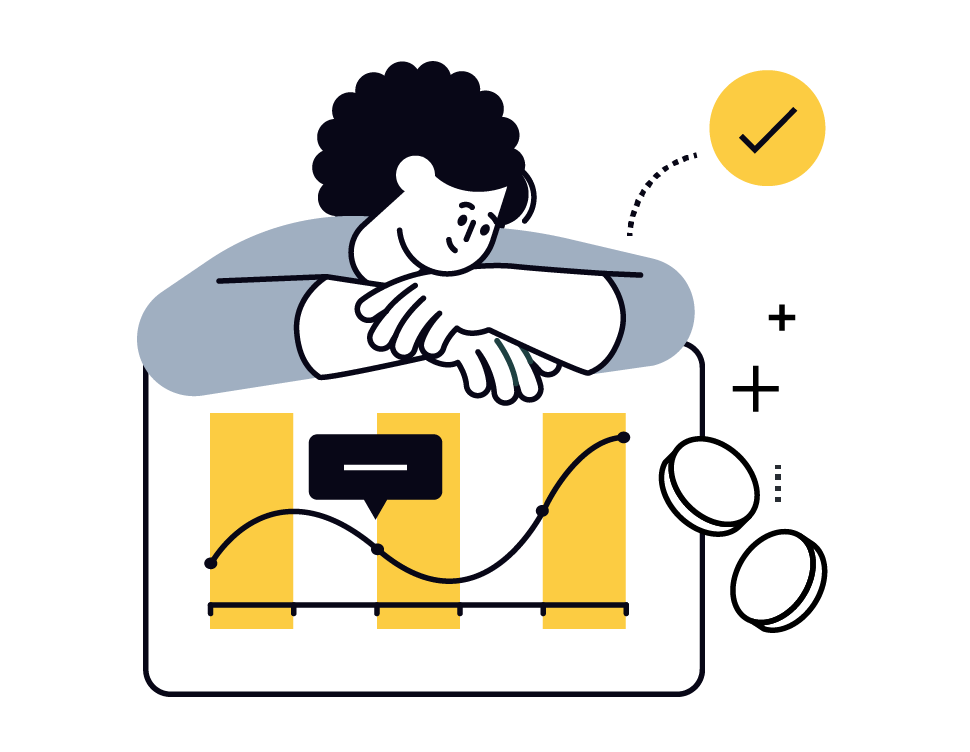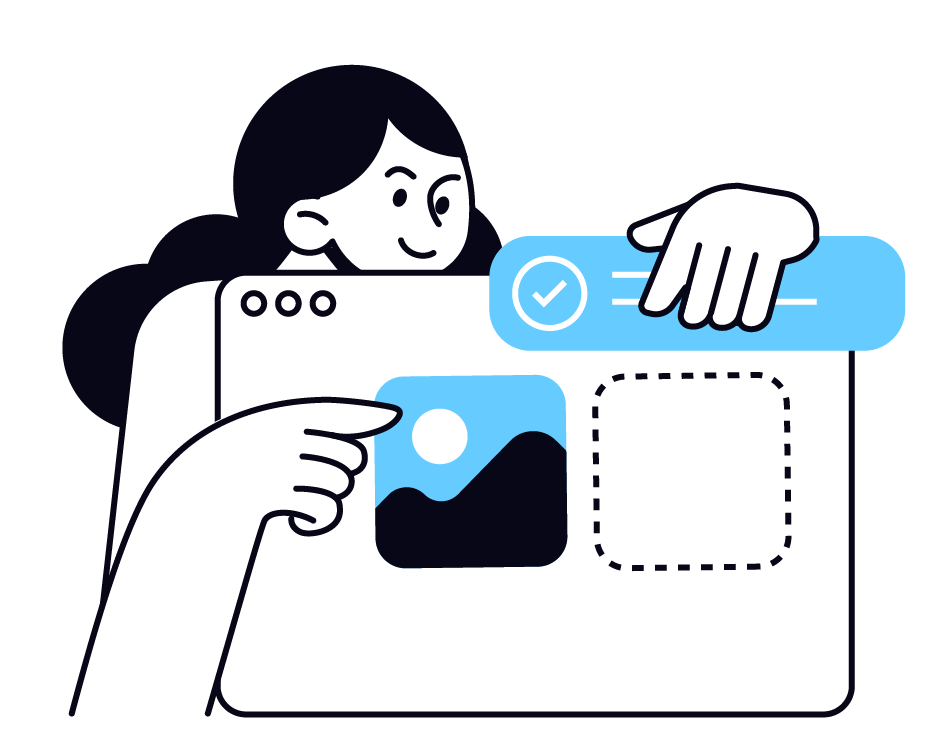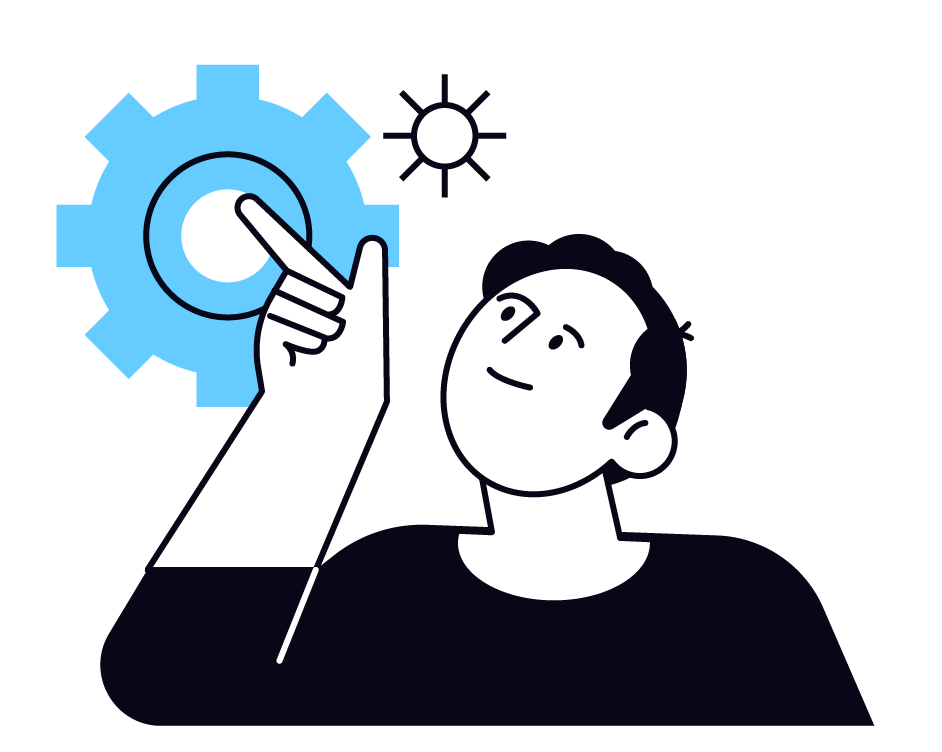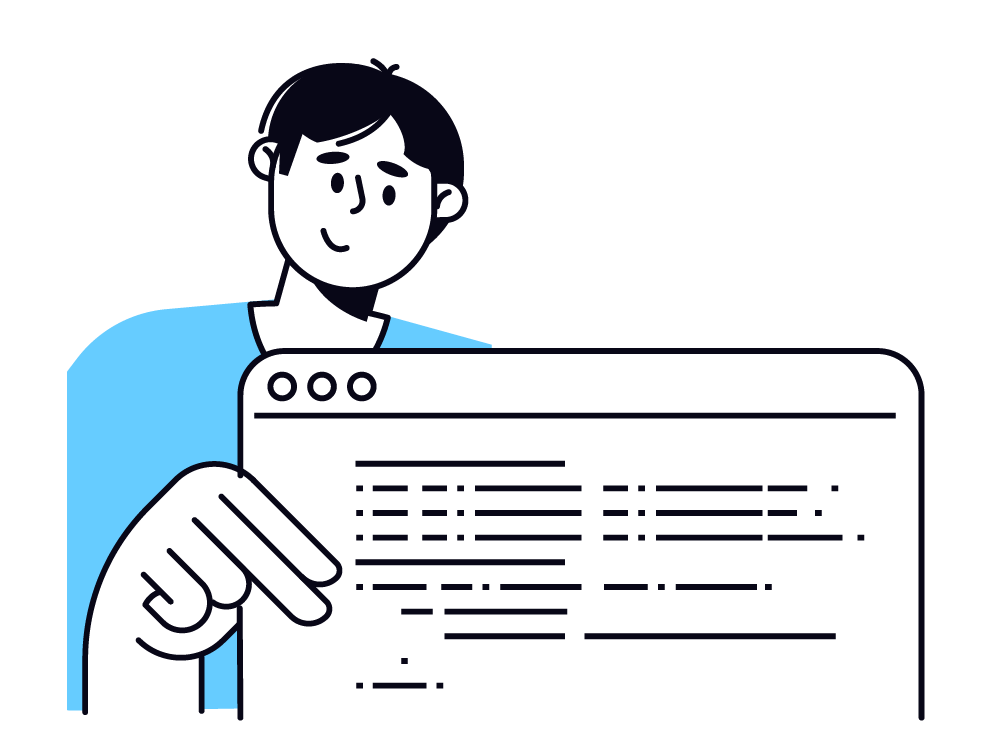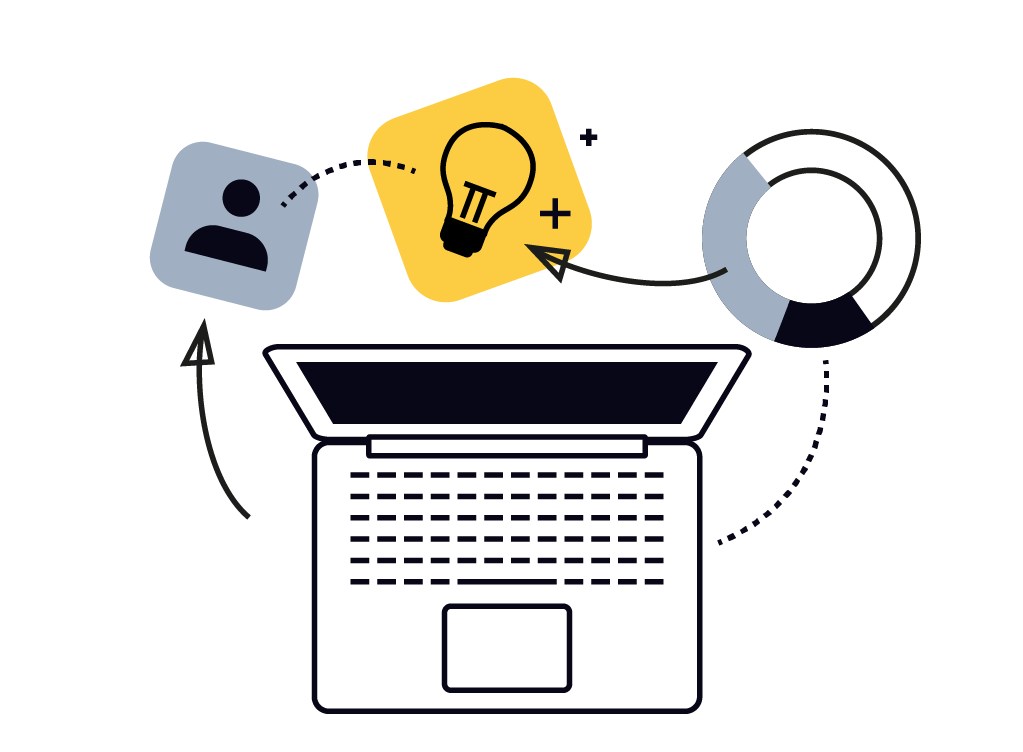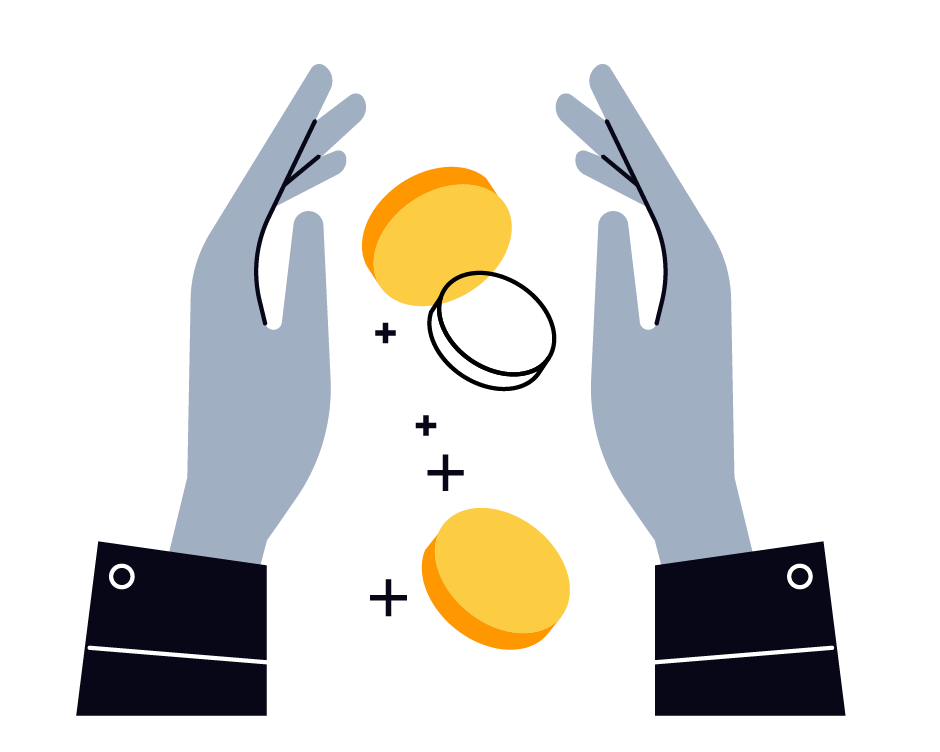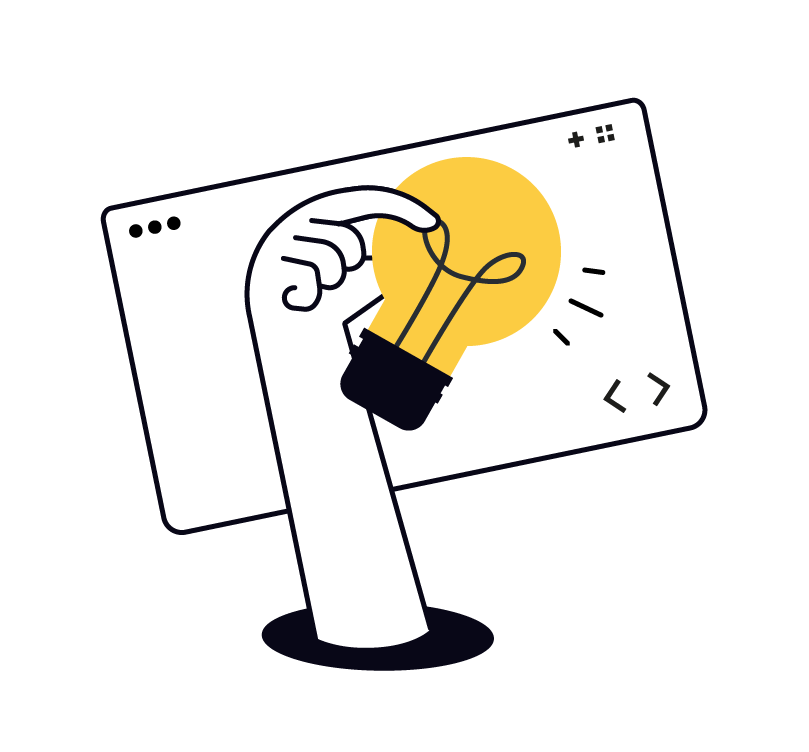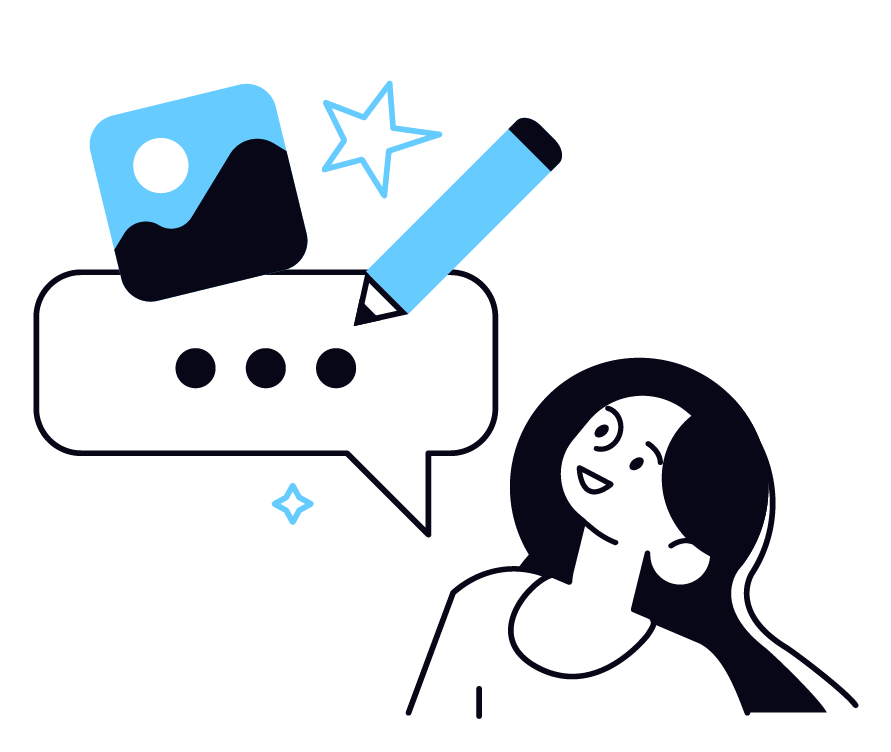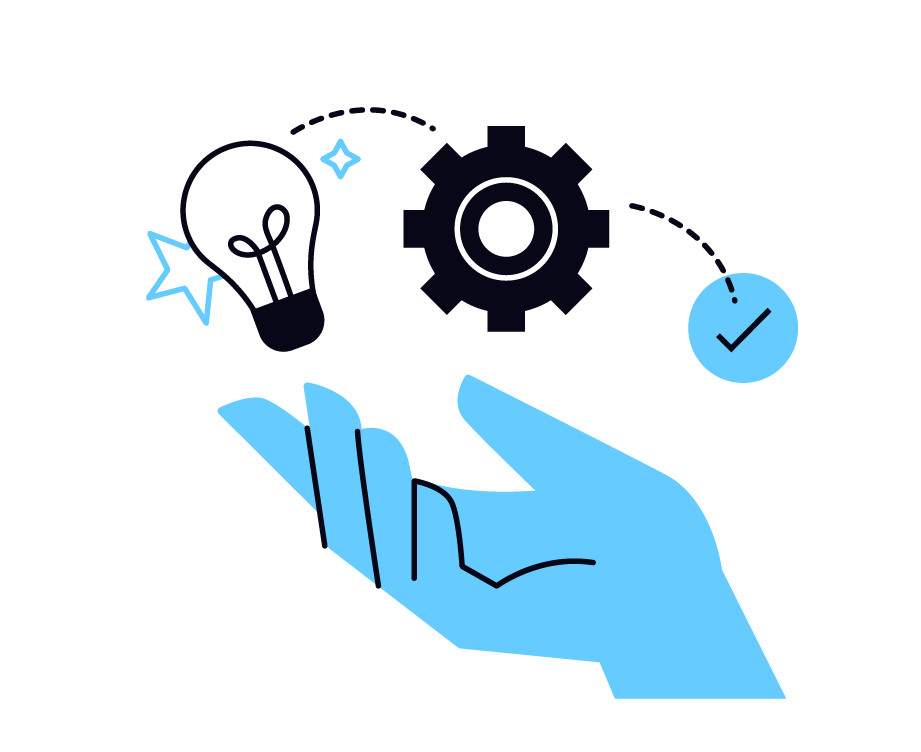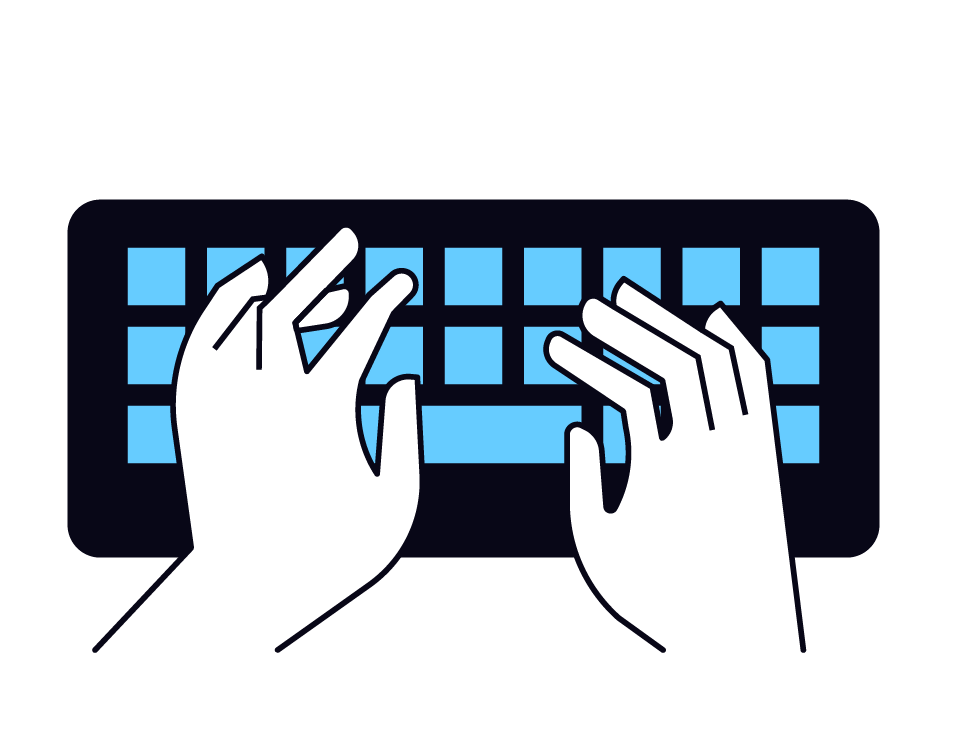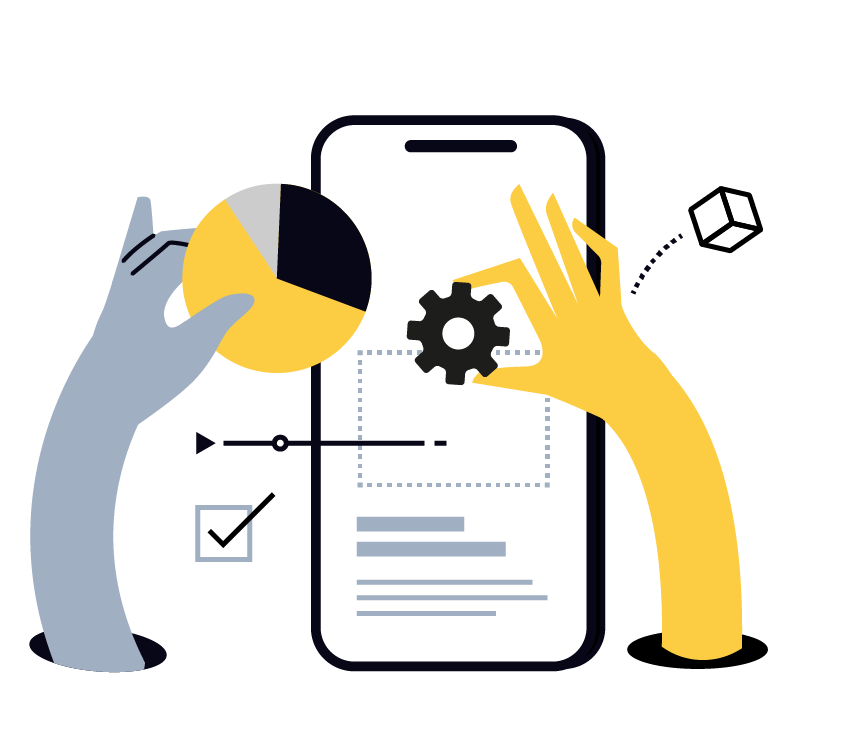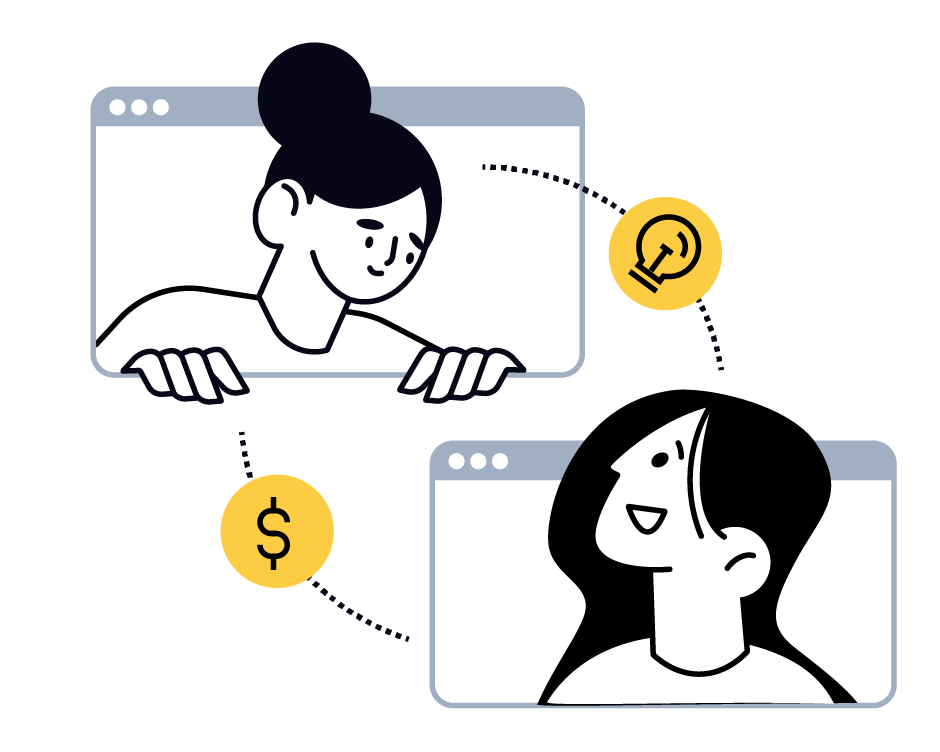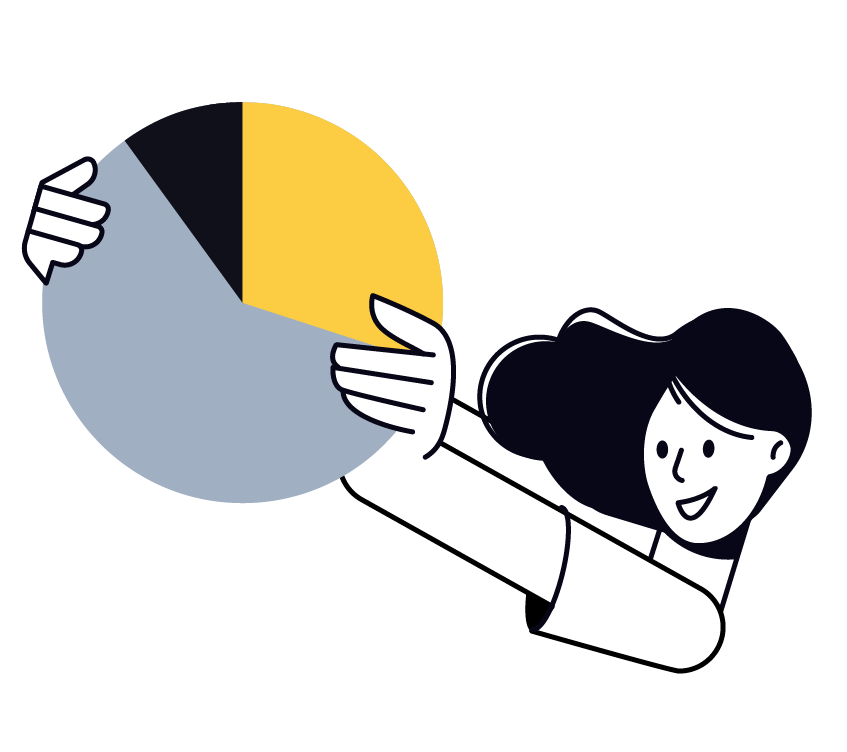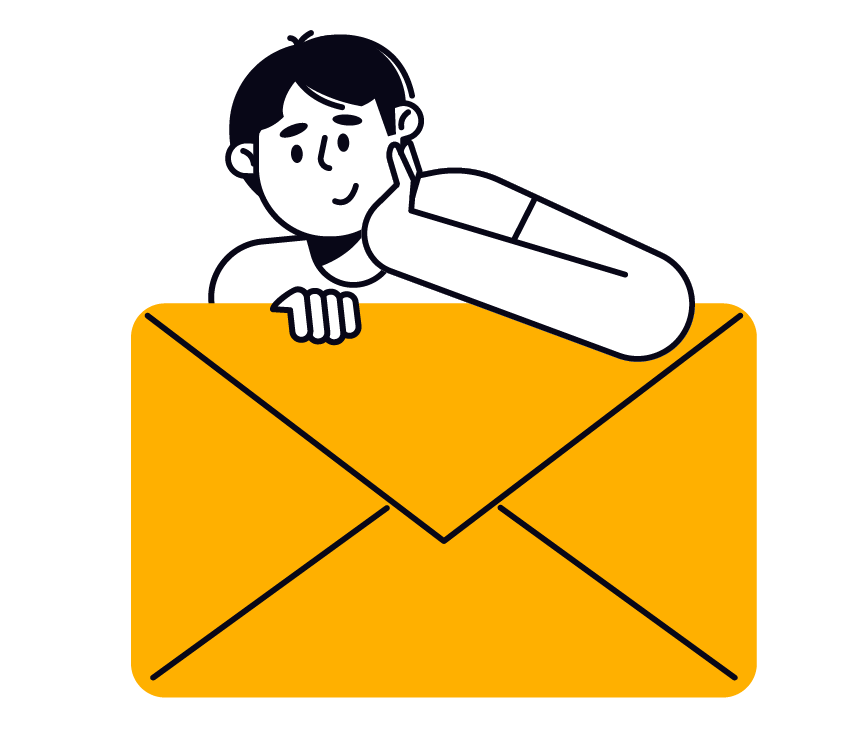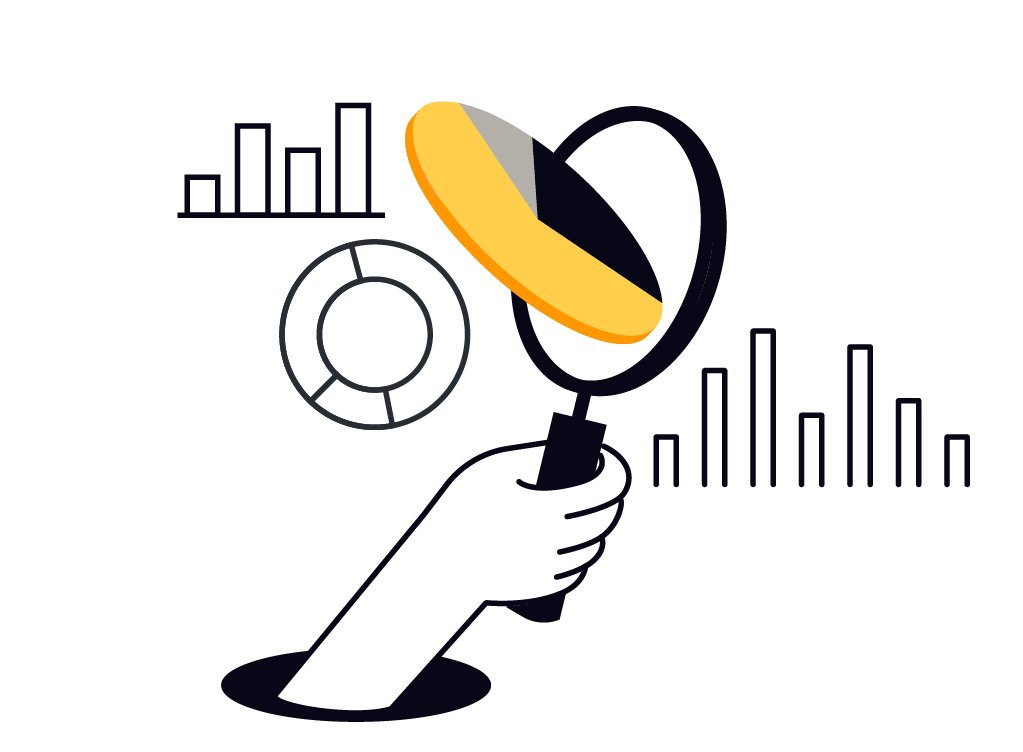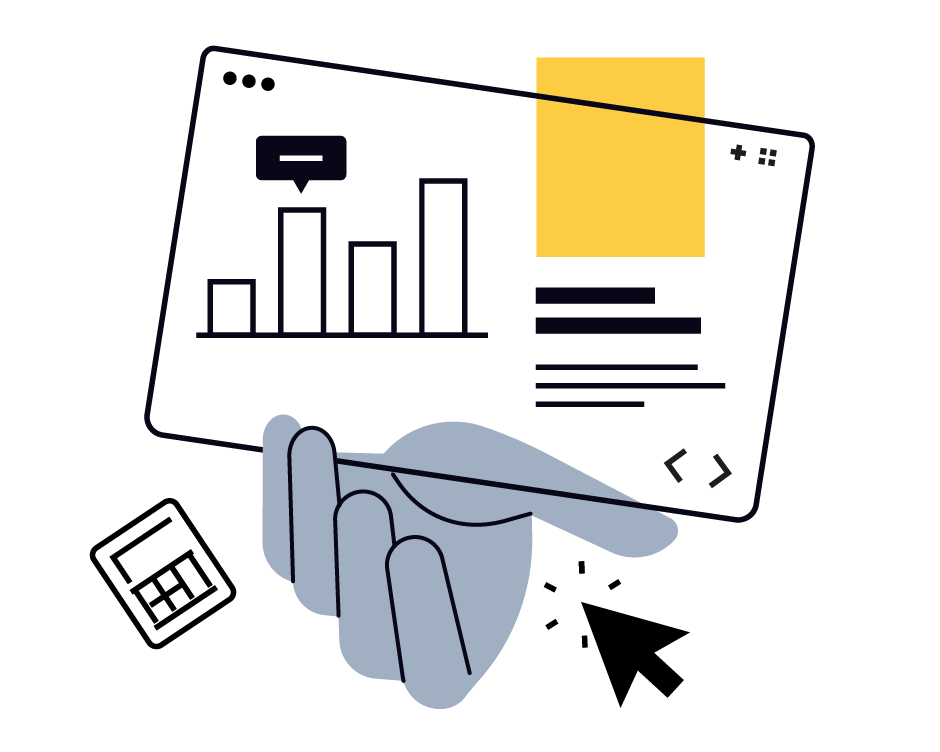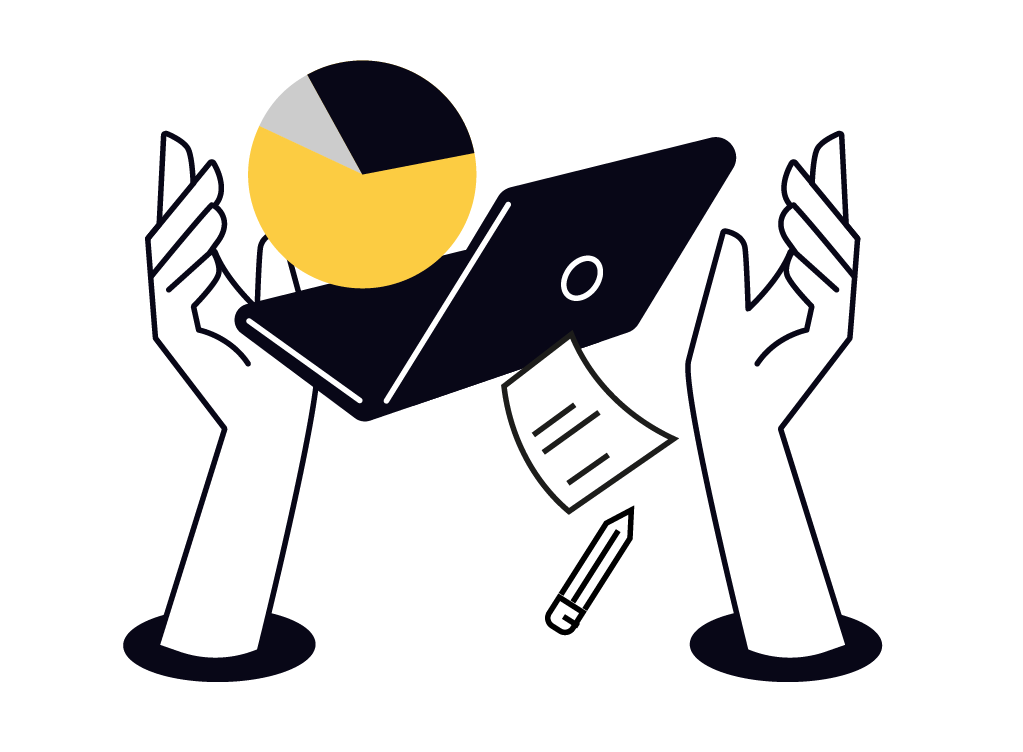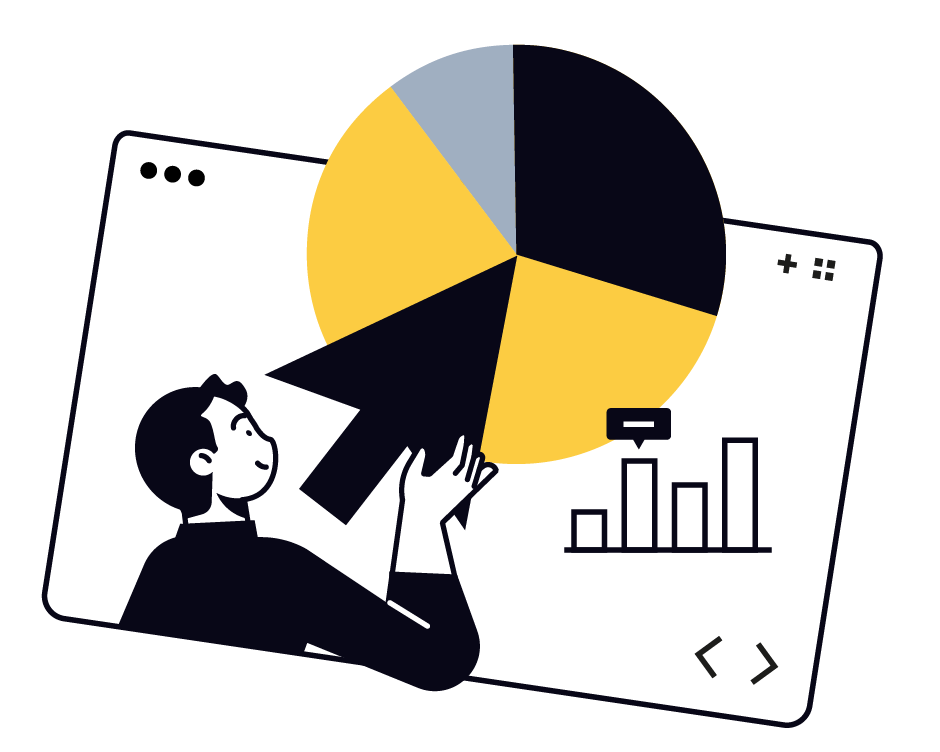1. なぜ今、A/Bテストが重要なのか?
BtoBマーケティングや会員制Webサイトの運用において、「成果を改善したいけど、何から変えればいいかわからない」という悩みはつきものです。そんなときに強力な武器となるのが、A/Bテストです。
感覚や思いつきでの変更ではなく、ユーザーの実際の反応を元に改善の是非を判断できるため、A/Bテストは“科学的な仮説検証”の手段として非常に有効です。
たとえば、あるBtoBの製品サイトで「資料請求ボタンの文言を“無料ダウンロード”から“今すぐ資料を見る”に変更した結果、CVRが1.6倍になった」という事例もあります。こうした改善は、社内の意見や思いつきでは見つけられなかった可能性が高く、テストによる裏付けが重要です。
特に、CMSを活用して複数のランディングページやバナーを管理している場合、テンプレートやコンポーネント単位での変更が可能なため、A/Bテストと非常に相性がよい運用形態です。
1-1. A/Bテストとは?その基本的な仕組み
A/Bテストとは、ある要素(例:ボタンの色や文言、レイアウト、コンテンツの順序など)に対して「Aパターン」と「Bパターン」を用意し、ユーザーをランダムに振り分けて、どちらの反応が良かったかを比較する手法です。
CMSやMAツール、GA4などの分析ツールと連携することで、少ない手間で正確な測定が可能になります。
A/Bテストの基本フロー:
- 仮説の設定(例:「CTAボタンを目立たせた方がクリック率が上がるのでは?」)
- 変数の決定(例:ボタンの色や配置)
- 目標指標の設定(例:クリック率、CVRなど)
- ユーザーへの振り分け(ランダム)
- 結果の比較と有意差の判断
1-2. A/Bテストと他の改善手法との違い
「とりあえず直してみる」や「過去の成功事例を模倣する」ことと、A/Bテストによる検証の違いは、“結果の確からしさ”にあります。
A/Bテストでは、実際のユーザー行動に基づいて改善の効果を数値で確認できるため、社内の意見に左右されず、客観的な改善判断が可能になります。
また、リソースをかけるべき改善ポイントの優先順位づけにも役立ちます。たとえば、バナーを変えるよりもCTA文言の改善の方が効果が高かった、というケースは少なくありません。
特にBtoBの場合、サイト訪問者の数が少ないため、1回1回の訪問の価値が高く、誤った判断による失注リスクも大きくなります。だからこそ、正確に検証し、最適解を導くためのフレームとしてA/Bテストの活用が求められます。
2. 成功するA/Bテスト設計のポイント
2-1. テスト設計で押さえるべき基本視点
効果的なA/Bテストを行うには、以下のような設計ポイントが重要です。
- 1テスト=1変数の原則:同時に複数の要素を変えてしまうと、どの要素が効果を生んだのかがわからなくなります。
- 十分なサンプル数を確保する:母数が少なすぎると、統計的に有意な差を判断できません。CV数ではなく表示回数ベースでの目安も確認しましょう。
- 事前にゴール(KPI)を明確化する:何をもって「成功」とするかを明確に決めておくことが、判断の迷いをなくします。
- ツールと連携して自動化を活用:CMSのA/Bテスト機能や、GA4、MAなどのツール連携によって、測定や比較がスムーズになります。
CMSでの具体例:
CMSを活用すれば、以下のようなケースでテスト設計がしやすくなります:
- 共通パーツ(バナー、CTA、フォーム)の差し替え → どのパーツが成果に寄与したかが明確に
- ページごとにレイアウトを切り替える → テンプレート機能でバリエーション作成も簡単
- テストパターンを一元管理し、複数ページに展開 → 更新や切り替えも容易
2-2. よくある失敗パターンとその回避法
A/Bテストは強力な手段ですが、誤った使い方をすると成果につながらないどころか、逆効果になることもあります。
❌ テスト期間が短すぎる
「3日だけ回したが、Aの方がCVが多かったので採用」といった判断は早計です。偶然の可能性を排除するために、一定期間(最低でも1〜2週間)回す必要があります。
❌ 仮説なしで思いつきテスト
「色を変えてみた」「画像を入れてみた」といった改善も、ユーザーの行動背景に基づいた仮説がなければ、本質的な改善にはつながりません。先にログやヒートマップで課題を洗い出すべきです。
❌ CV以外の指標を見てしまう
CTRだけを見て判断すると、「たくさんクリックされたが、離脱率も高い」などの失敗があります。ゴールに紐づく指標(たとえば「お問い合わせ完了率」)を判断軸にしましょう。
❌ 片方だけ動的要素がある
「Aは通常バナー、Bは動画付きバナー」といったケースで、表示スピードや読み込み環境の差異が影響する可能性があります。テスト条件はなるべく平等に保ちましょう。
❌ BtoB特有の母数の少なさに気づかず実施
BtoCと違い、BtoBのサイトでは1日の訪問者数が限られるため、十分なサンプル数の確保に時間がかかることがあります。焦って途中でテストを止めないよう、実施前に期間や閾値を設定しておきましょう。
3. まとめ:テスト文化が成果を生む
A/Bテストは一発逆転の魔法ではありません。しかし、施策ごとに「仮説 → 検証 → 改善」のPDCAを回す文化を根づかせることで、少しずつ、しかし着実に成果を積み上げていける仕組みです。
特にBtoBや会員制サイトのように、ターゲットが明確で改善の余地が多い領域では、小さな最適化が大きなリターンを生みます。
まずは、ひとつのコンテンツやCTAボタンからでもかまいません。仮説を立て、シンプルなテストを実行してみる。そこで得た“事実”を次の改善につなげる──その一歩が、データドリブンな運用の出発点になります。
「思いつきの変更」から、「根拠のある改善」へ。A/Bテストの文化を、マーケティングチームに根づかせていきましょう。