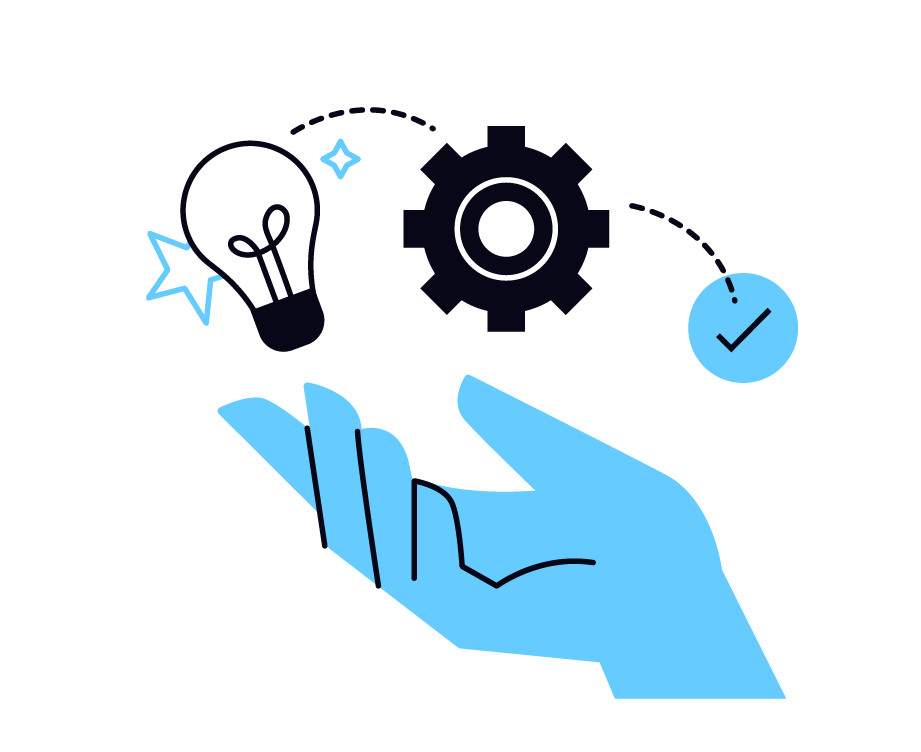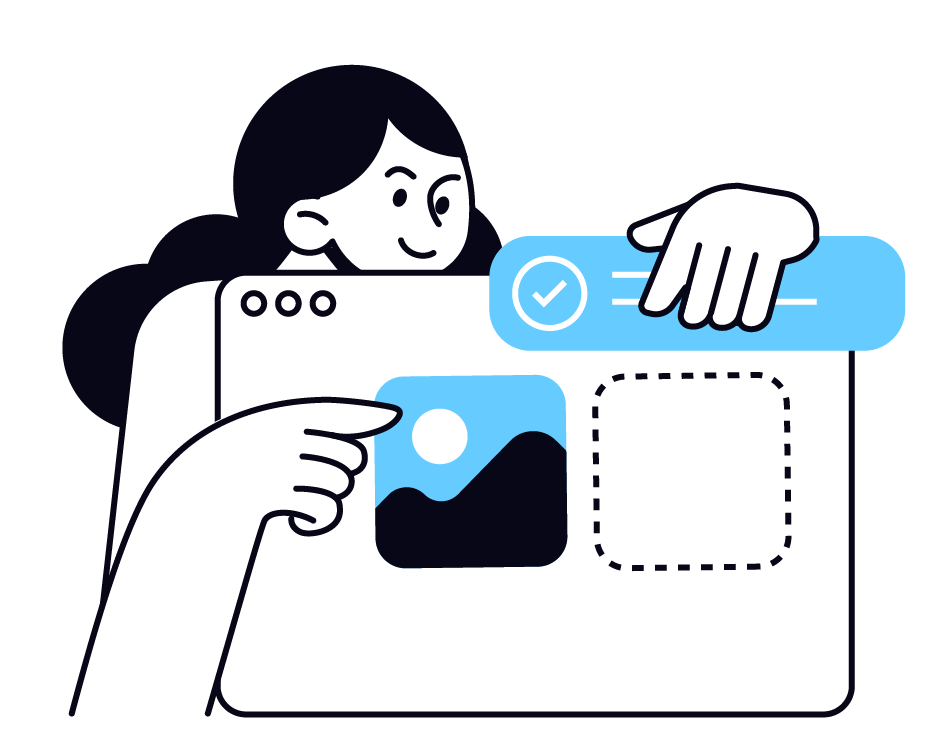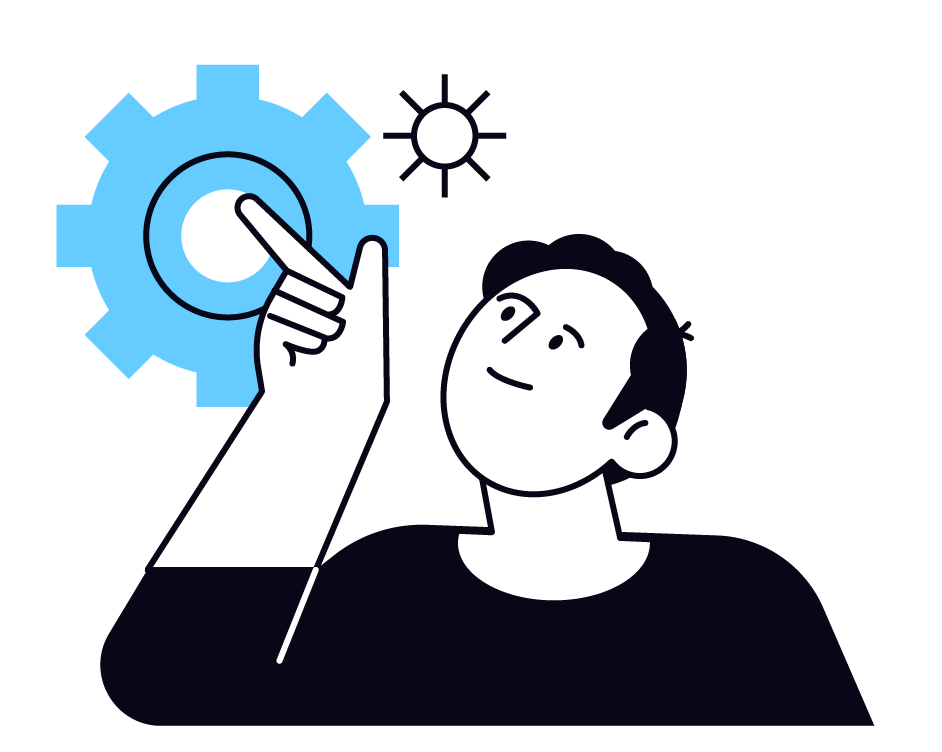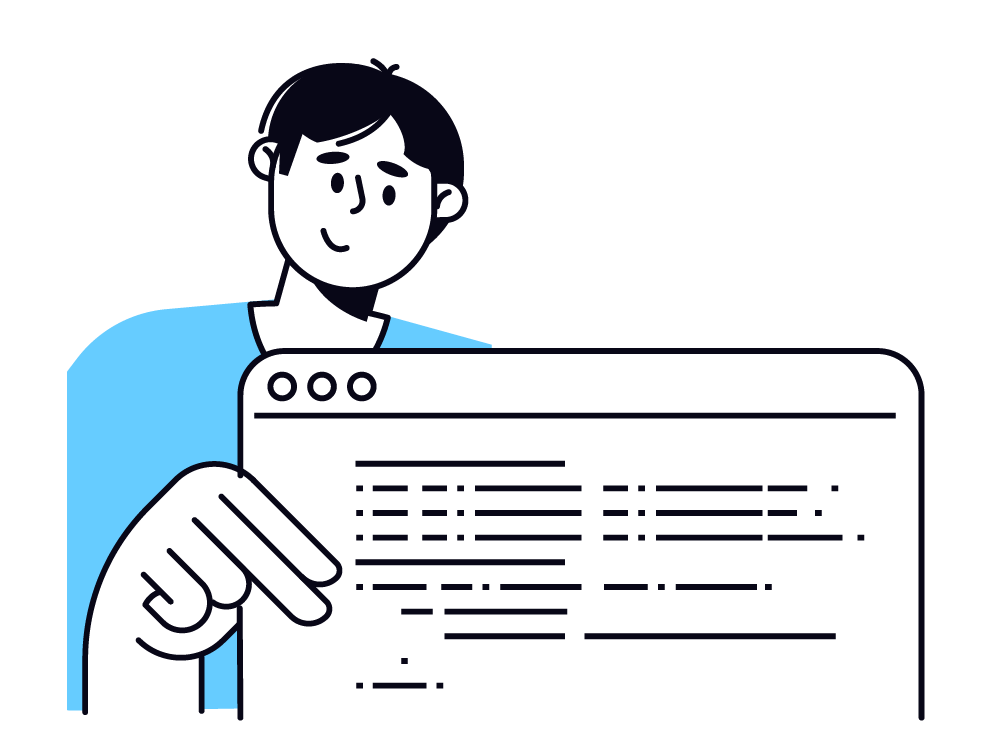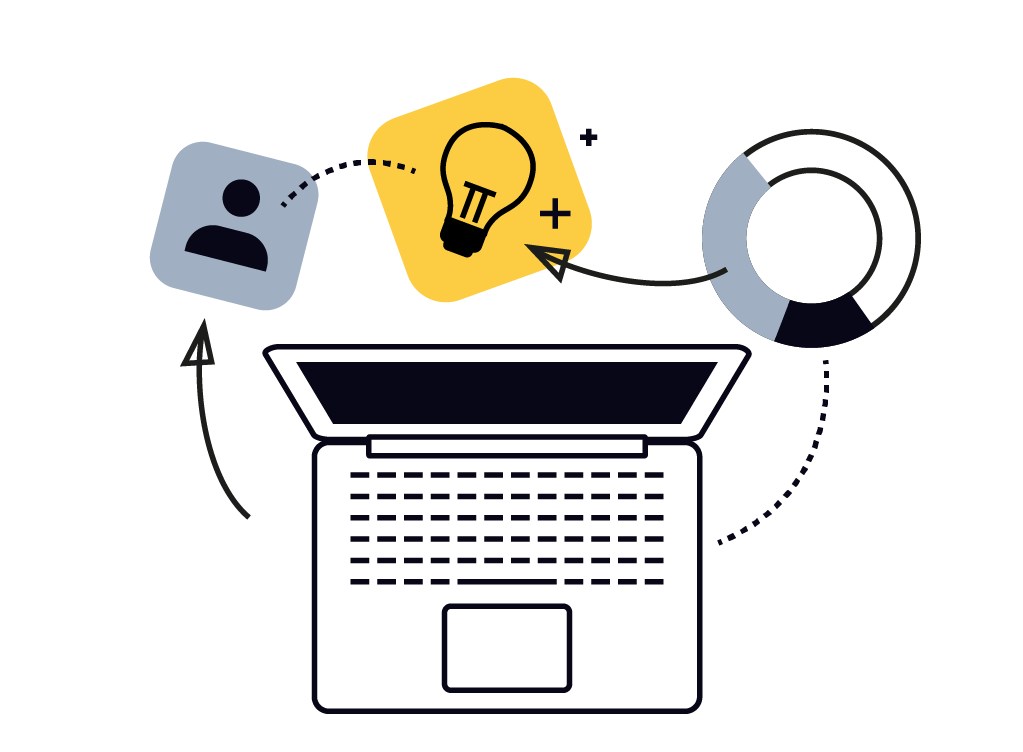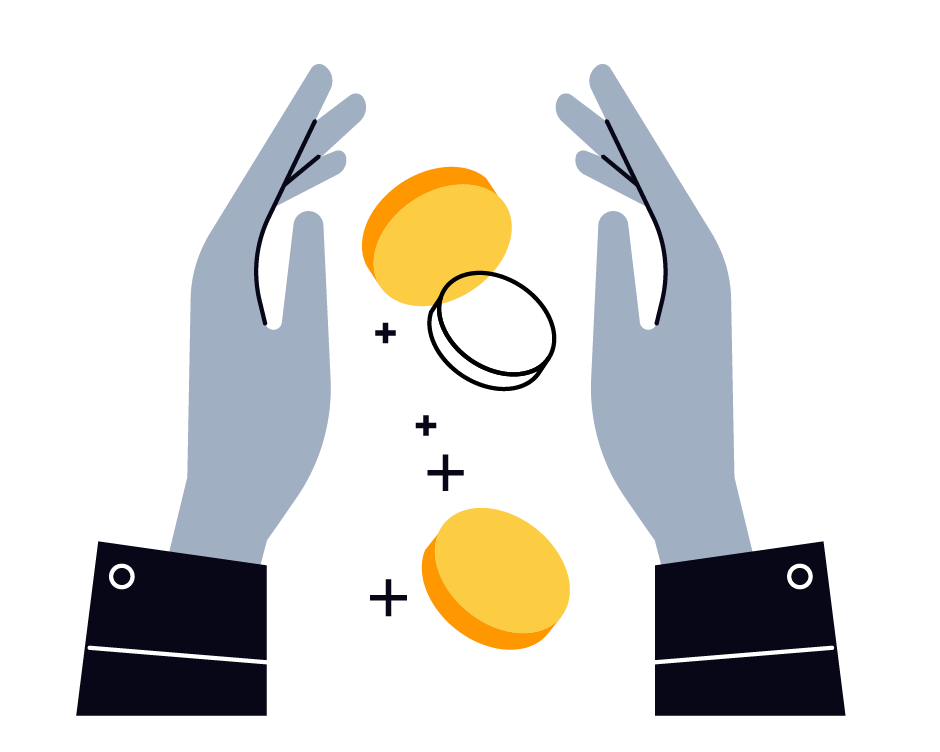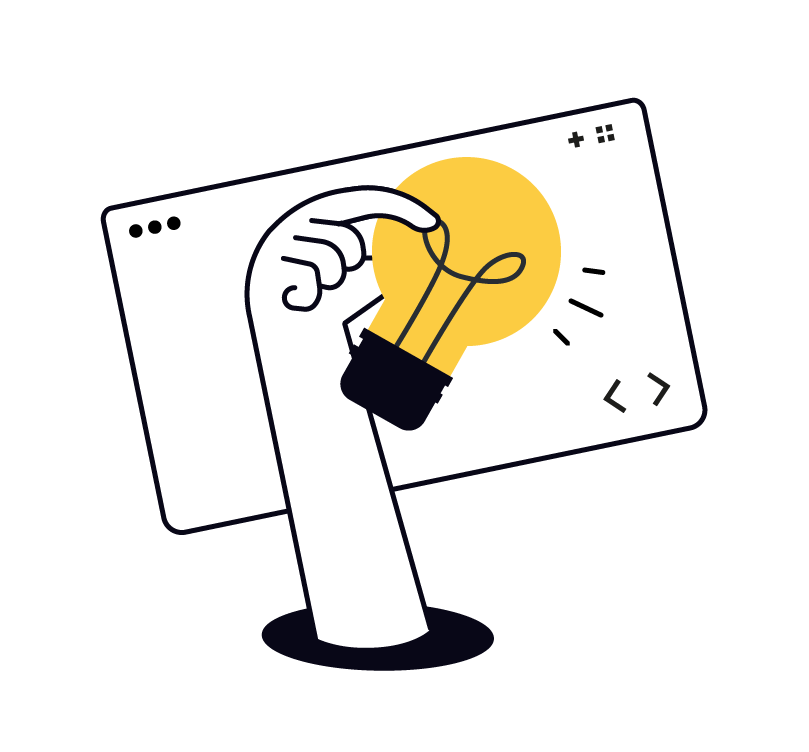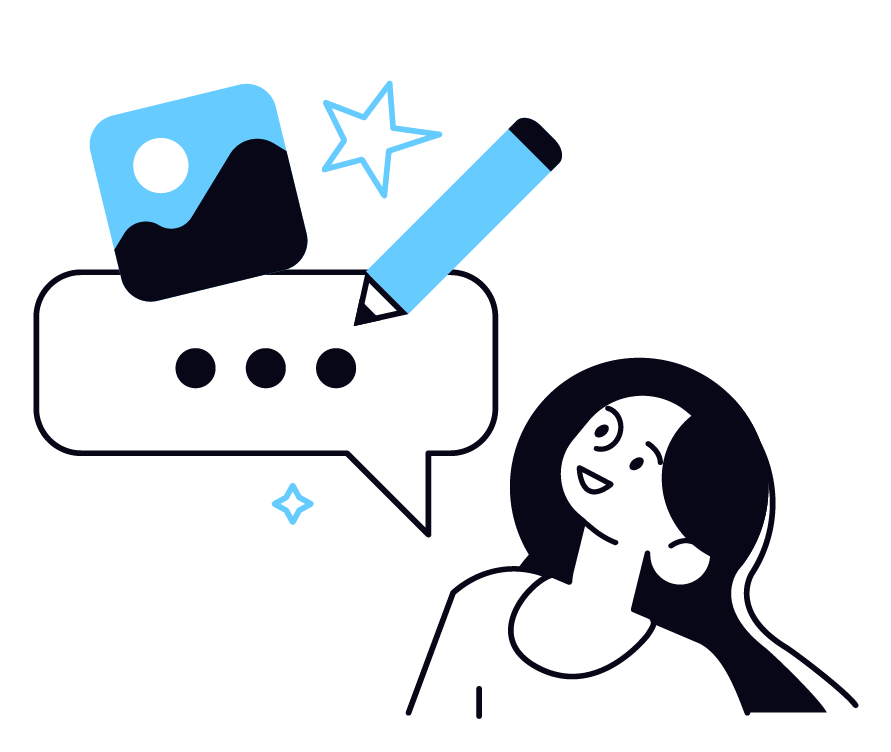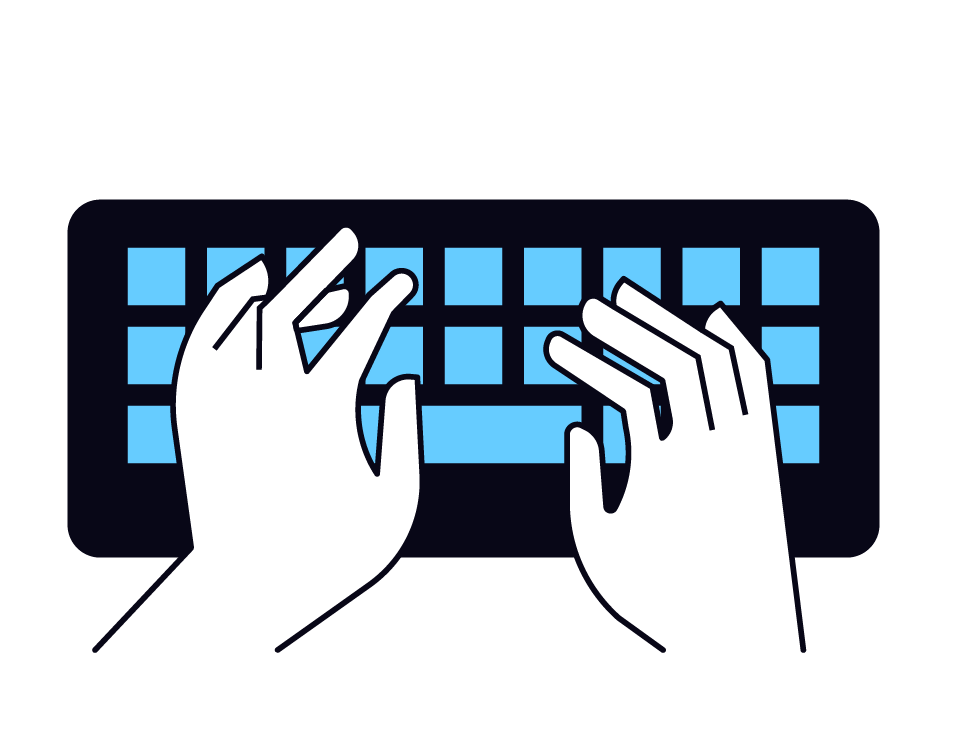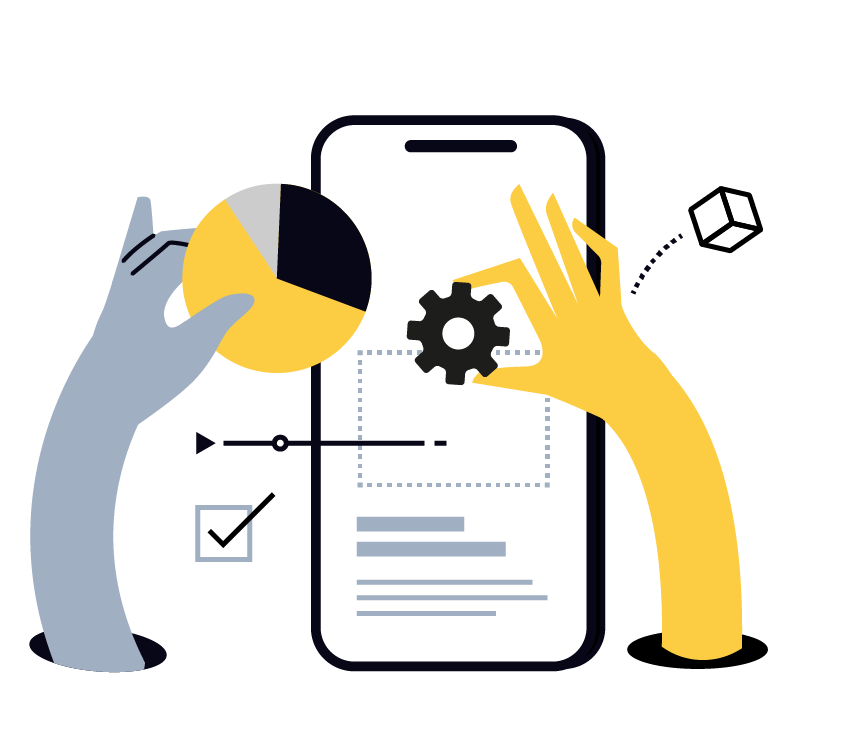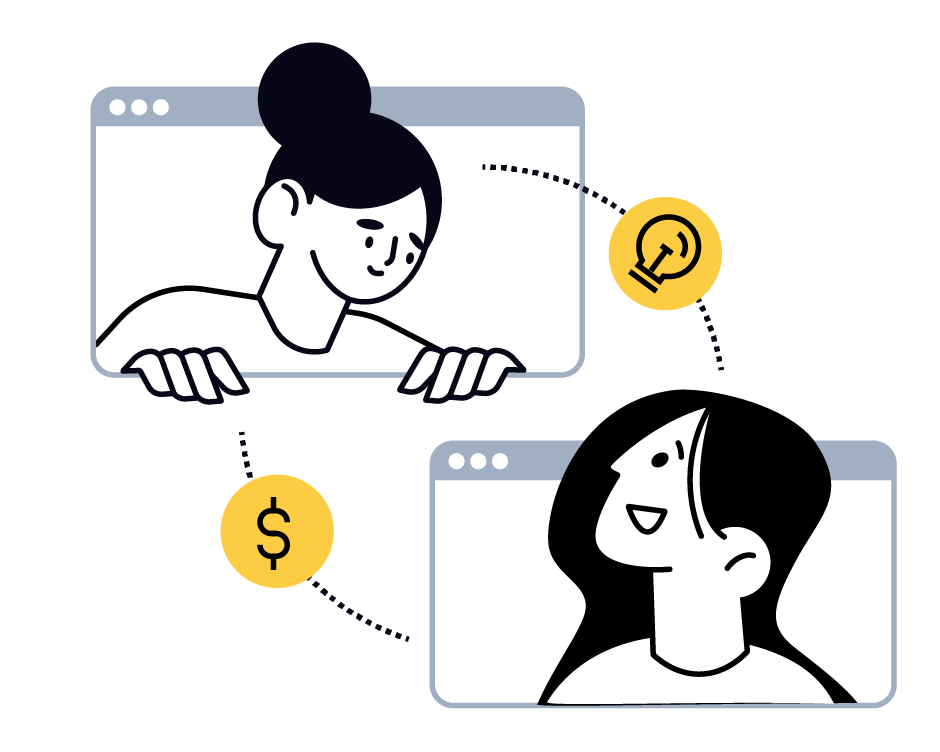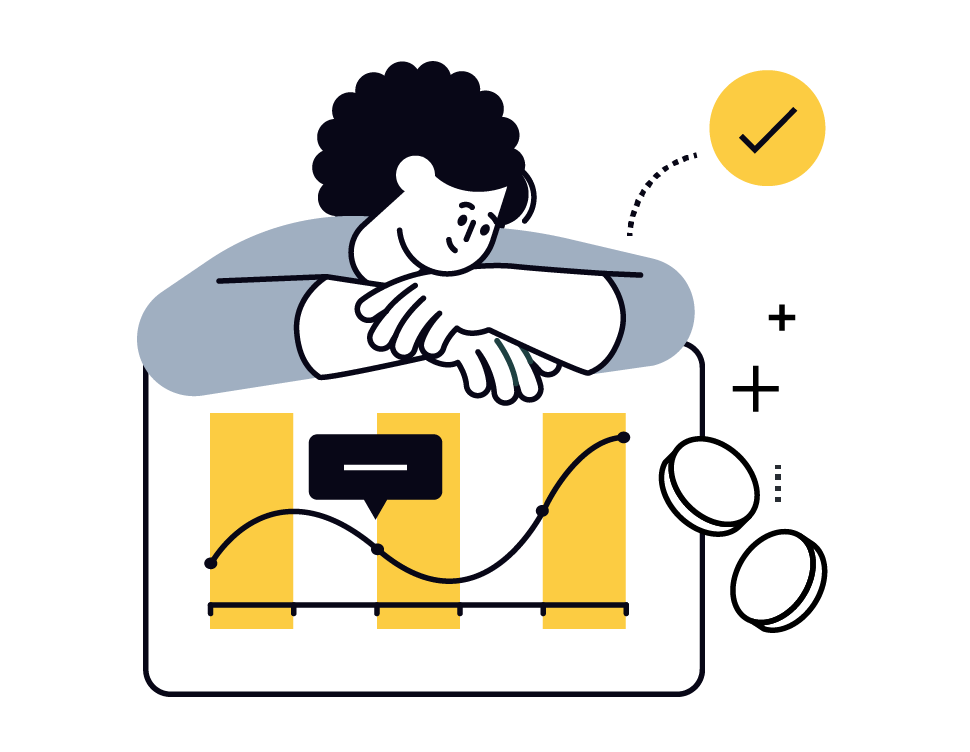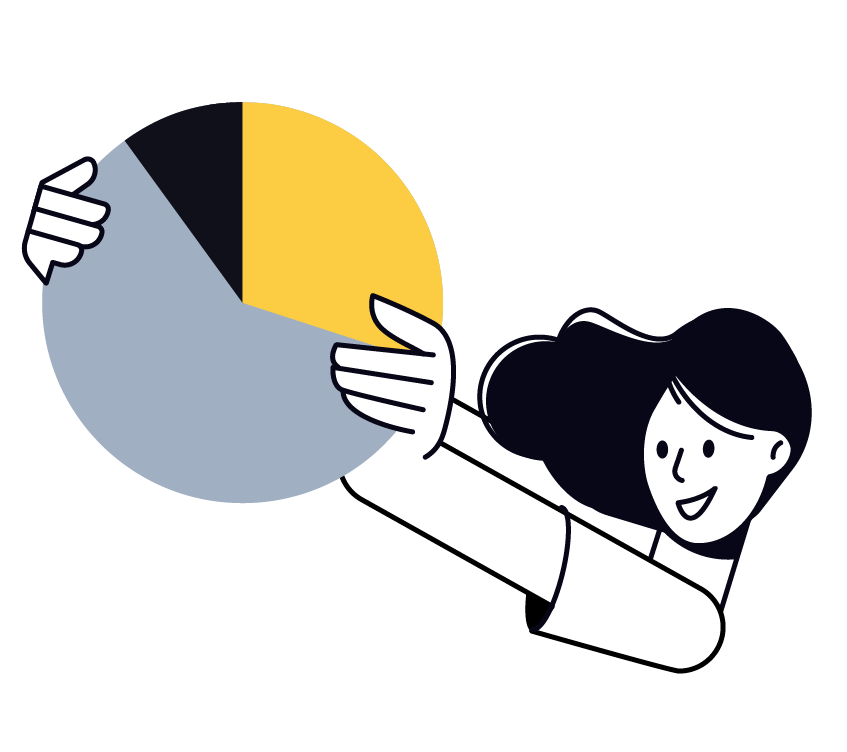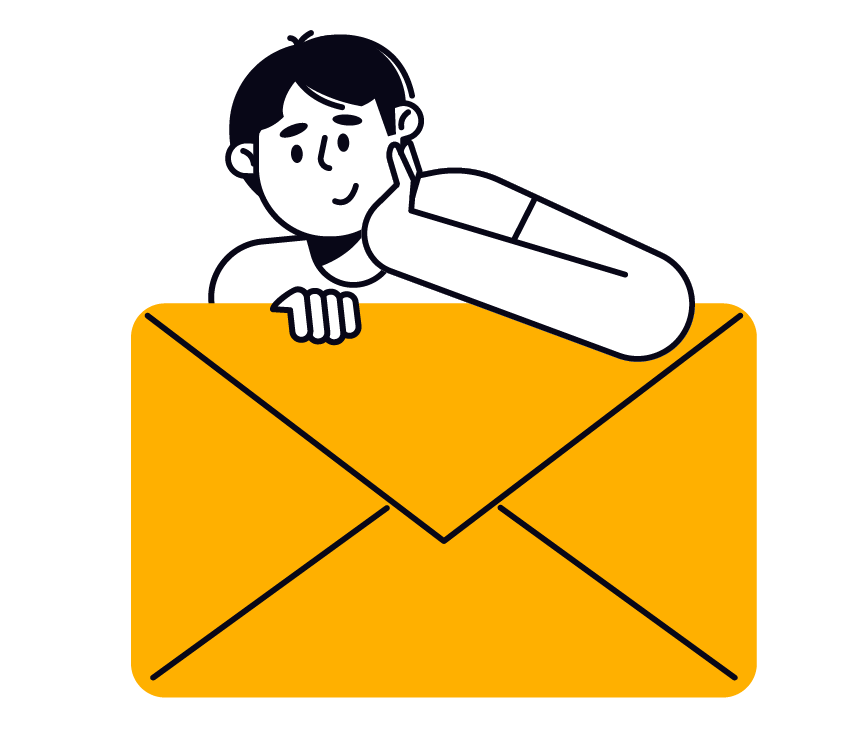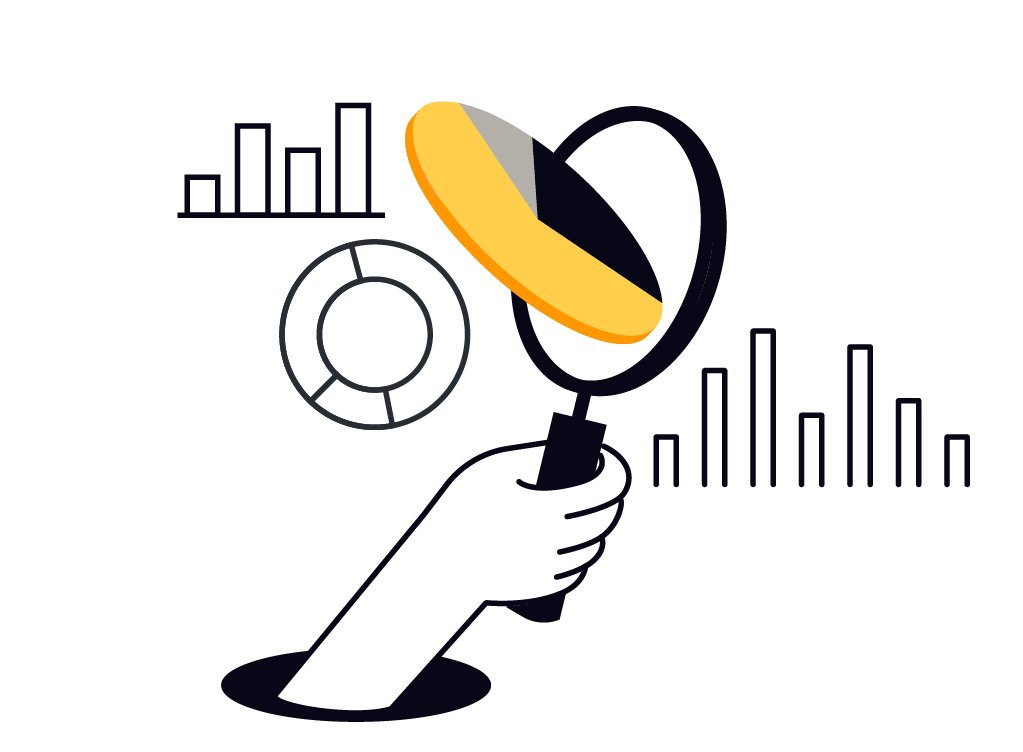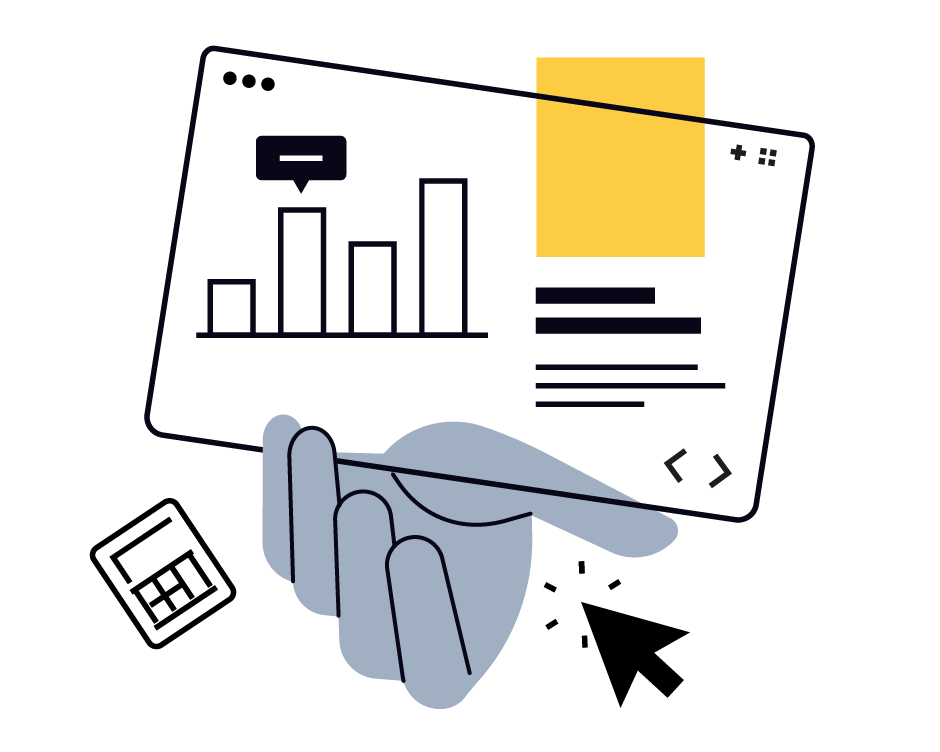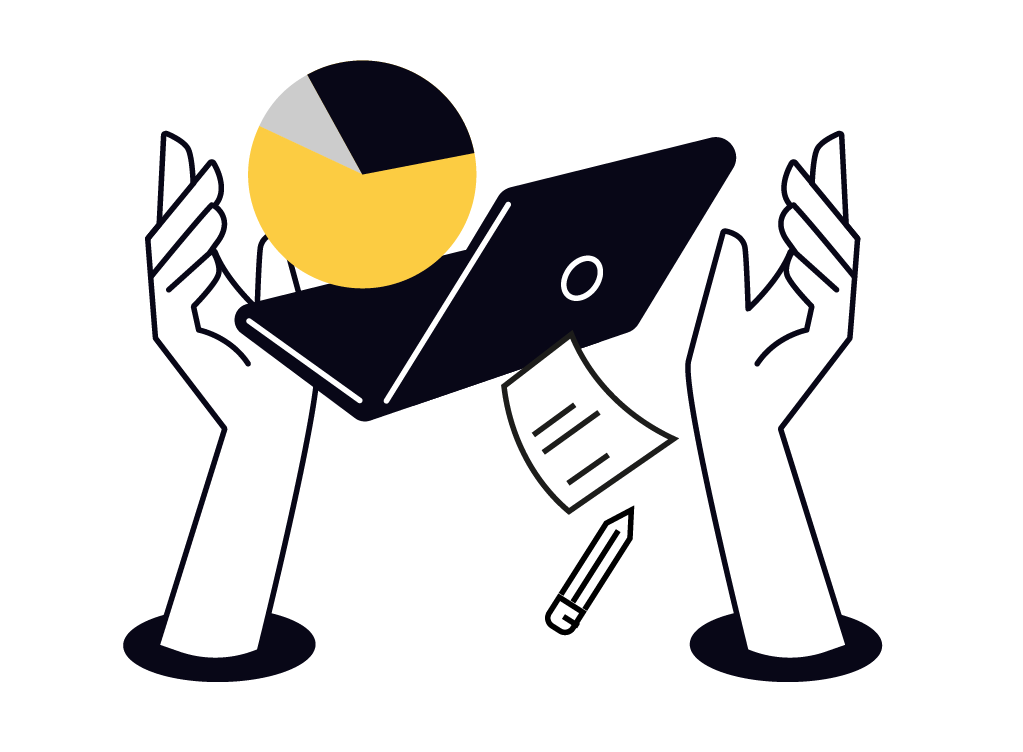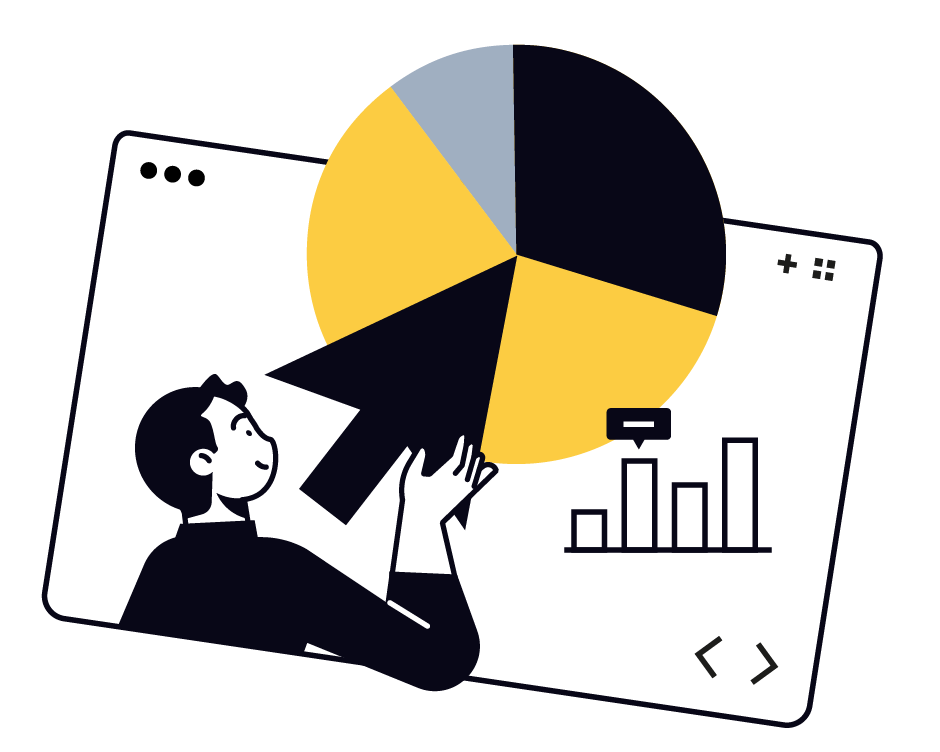1. セグメント設計は“会員活用”の出発点
BtoBの会員サイトでは、会員情報を集めるだけで終わらせてはいけません。真の成果を得るためには、集めた会員データをもとに“セグメント設計”を行い、それに応じたアプローチを展開していく必要があります。
セグメントとは単なる分類ではなく、「会員ごとのニーズや関心に応じて、最適な情報やアクションを提供する」ための戦略的な基盤です。CMSやCRM、MAと連携しながら、属性情報と行動データを組み合わせて、より実践的で効果的な活用を実現しましょう。
1-1. セグメントとは「行動を変える」ための切り口
セグメントを切る最大の目的は、“ユーザーの次のアクションを引き出すこと”です。よくある活用例としては:
- パーソナライズされたコンテンツ表示:職種・業種に合わせた事例や製品紹介を出し分ける
- セグメント別メール配信:興味のあるテーマごとにメールの文面やタイミングを調整
- 営業アプローチの優先付け:関心度の高いセグメントをHotリードとして営業に連携
- 再活性化のターゲット特定:長期非アクティブ会員への再接触施策を設計
このように、セグメントは「ターゲティング精度を高める」だけでなく、「ユーザーの行動を促進する施策」を立案する起点になります。さらに、サイト全体のUX改善や施策のROI最大化においても、セグメントによる分解・検証が鍵となります。
1-2. 属性×行動ログで多層的な分類をつくる
BtoB会員サイトでは、単一軸の分類では不十分です。「静的な属性」と「動的な行動データ」の両軸で会員を分類することで、より現実的なニーズ把握と個別対応が可能になります。
属性軸(プロファイル情報)
- 業種・業界、企業規模、所在地
- 部署・職種、役職
- 導入フェーズ(検討中/導入済/他製品利用中など)
- 会社の役割(調査/比較/意思決定/運用など)
行動軸(ログデータ)
- 閲覧ページのジャンル・頻度・時間帯
- 資料ダウンロード履歴、動画視聴履歴
- メールの開封/クリック状況
- セミナー参加、アンケート回答などの能動的アクション
- ログイン頻度や直近アクセス日
具体的なセグメント設計例:
- 「中小企業×営業部門×製品ページを複数回閲覧」→ 見込み度が高く即アプローチ対象
- 「大手企業×研究開発×セミナー視聴」→ 育成リードとしてナーチャリング対象
- 「医療従事者×地方勤務×長期間アクセスなし」→ リテンション施策を検討
- 「意思決定層×複数資料DL×メール未開封」→ アラートと再配信設定
このように、セグメント設計の精度が上がることで、コミュニケーションの質も大きく向上します。
2. スコアリングと行動連携による実践的な活用法
セグメントで分類しただけでは、具体的な施策の優先順位は見えてきません。そこで重要なのが「スコアリング」です。行動データに基づいてスコアを算出し、“今注力すべき会員”を抽出することで、営業やマーケティングのリソースを集中させることができます。
2-1. スコアリングの基本と使い方
スコアリングは、「会員の温度感を数値化する仕組み」です。以下のような行動にスコアを設定します:
- ページ閲覧:1ページ = 1pt(製品・価格ページは+3pt)
- 資料DL:10pt(ホワイトペーパーなど高価値資料は+20pt)
- メール開封:3pt、クリック:5pt
- セミナー申込:20pt、参加完了:30pt
- フォーム問い合わせ:50pt(極めて高スコア)
- 最終アクセスからの経過日数:日数が長いほど減点(-1pt/日)
活用パターン:
- Hotリード(スコア80以上):営業通知、1営業日以内にフォローアップ
- Warmリード(スコア30〜79):MA施策による継続育成(メール、動画)
- Coldリード(スコア0〜29):再活性化対象。閲覧履歴や業種別の再アプローチ施策を検討
追加活用例:
- スコア上昇をトリガーとした自動リマインドメール
- 特定セグメント+一定スコア到達で営業自動割り当て
- リードスコアの推移を時系列で可視化し、関心の高まりを予測
こうしたスコア設計をCMSやMAに実装することで、単なる「データ蓄積型サイト」から「リアルタイム施策運用型サイト」へと進化させることが可能です。
3. まとめ|セグメントがあるから戦略が立てられる
セグメント設計とスコアリングは、BtoBサイトにおける“成果の出るデータ活用”の基礎となります。CMSや会員管理機能だけでなく、MA、CRM、SFAといった外部ツールとの連携も前提にした全体設計が重要です。
定義されたセグメントがあることで:
- ターゲティング精度が上がり、不要なコストを抑えたマーケティングが可能に
- 成果の見える化と振り返りができ、PDCAが回せる
- パーソナライズされた施策が設計でき、ユーザーの体験価値が向上
多くの企業が「データはあるのに活かせていない」と感じる原因は、“設計されていない”からです。今こそ、セグメントとスコアを中心とした「会員活用設計」を見直すタイミングです。
次回は、この基盤を土台に「関係性を深める会員向けコンテンツ設計|維持・育成・再活性化の戦略」をテーマに、実際にどんなコンテンツが会員とのエンゲージメントを高めるのかを掘り下げていきます。