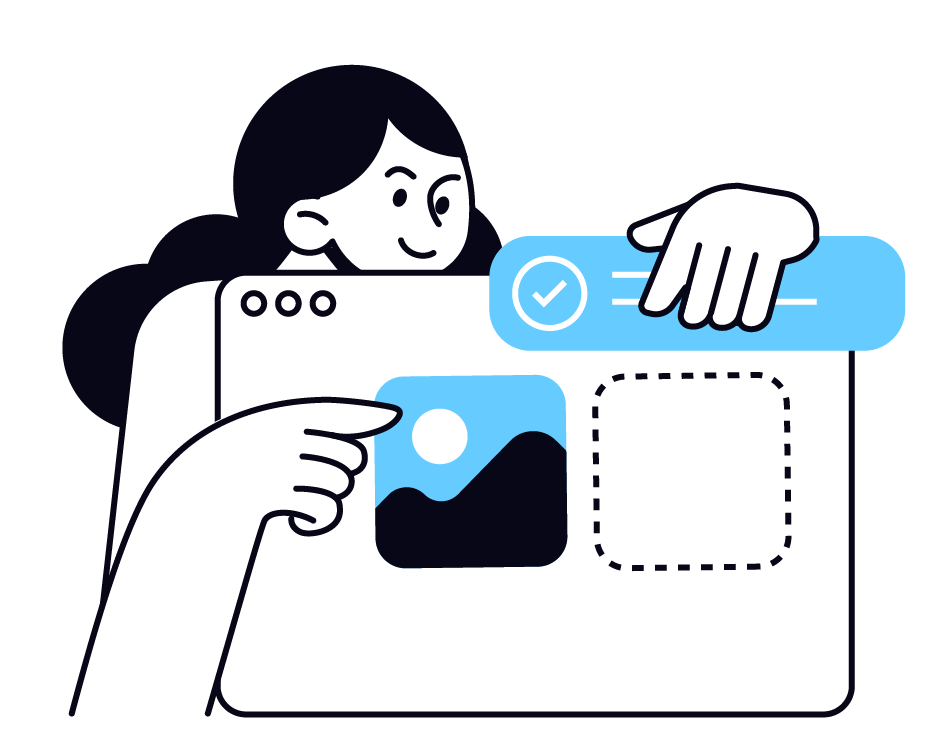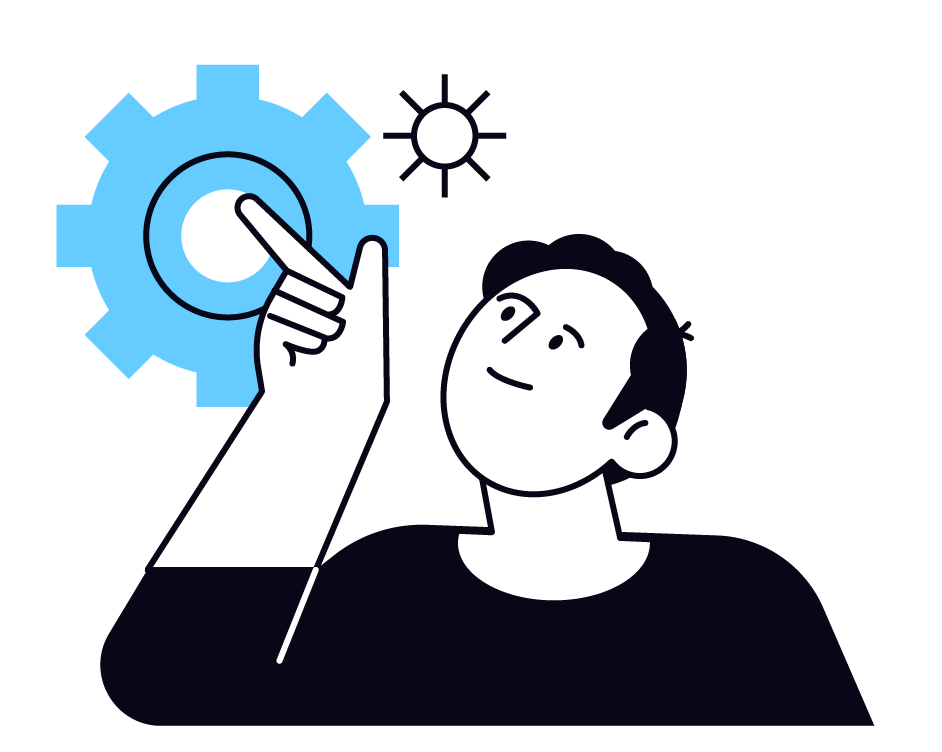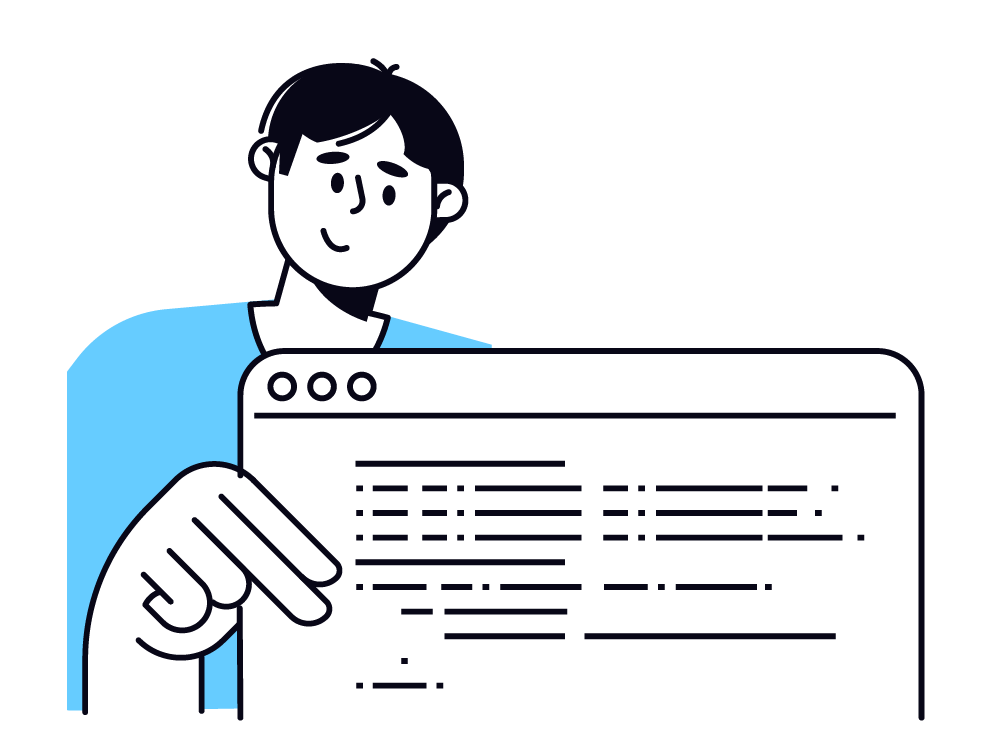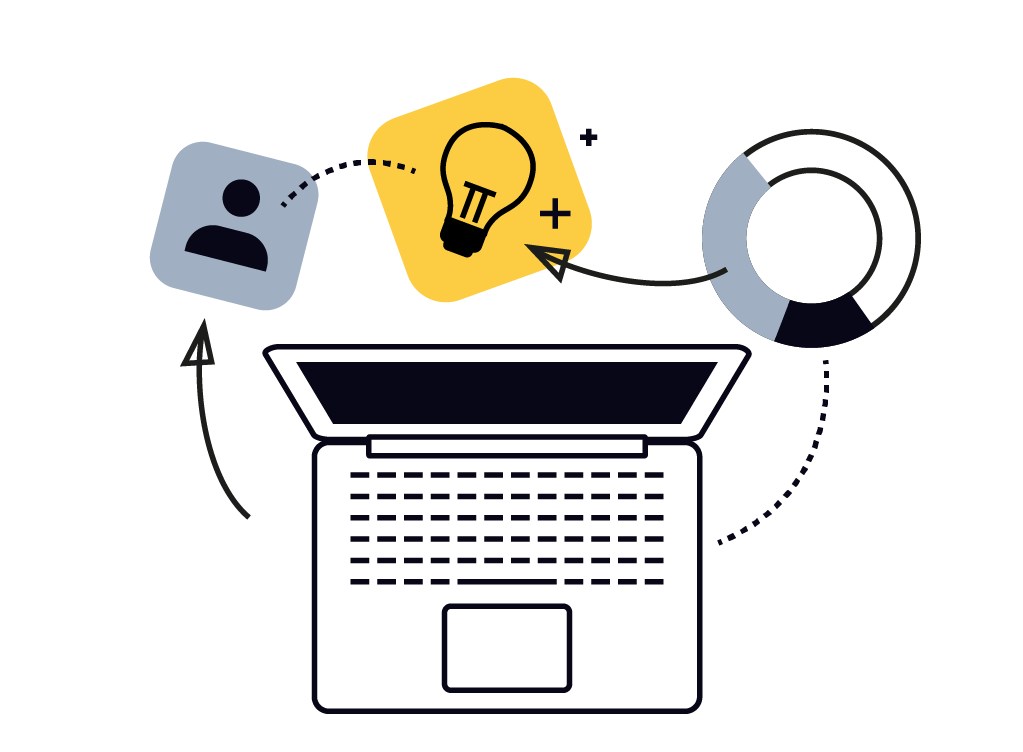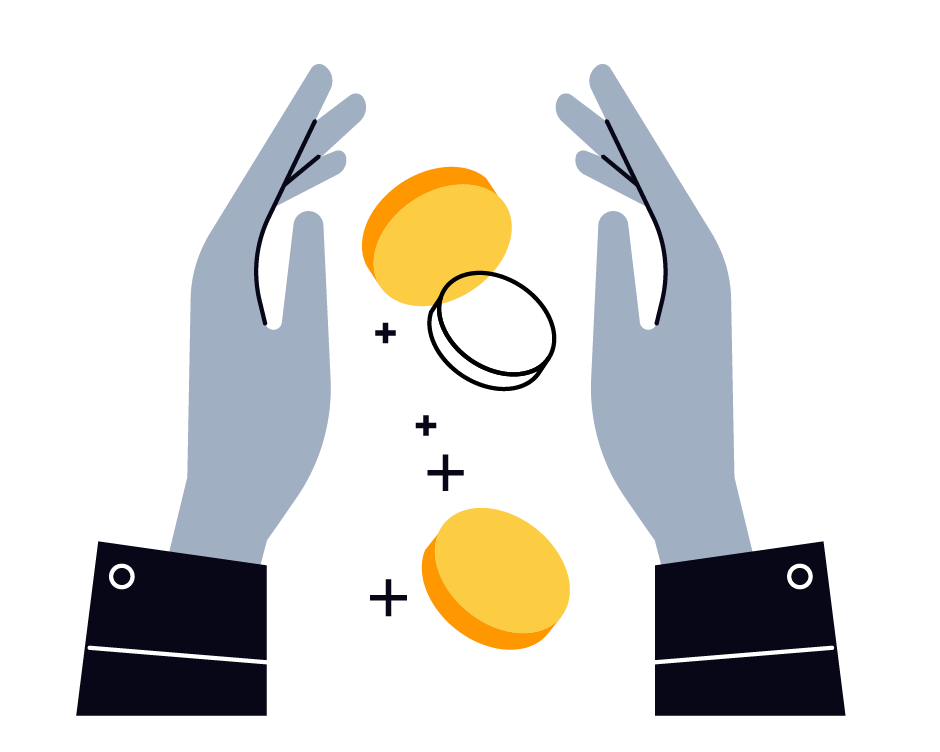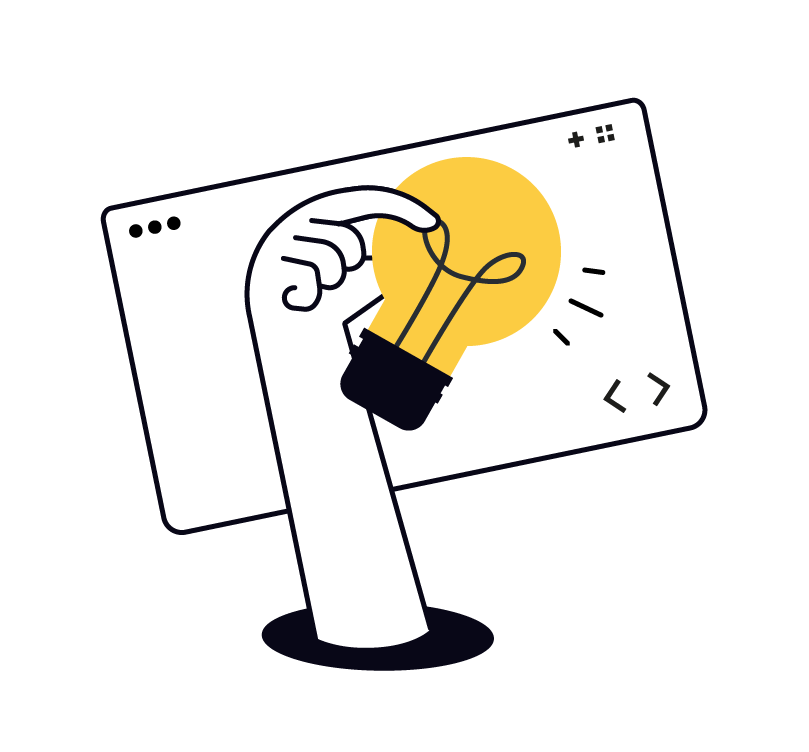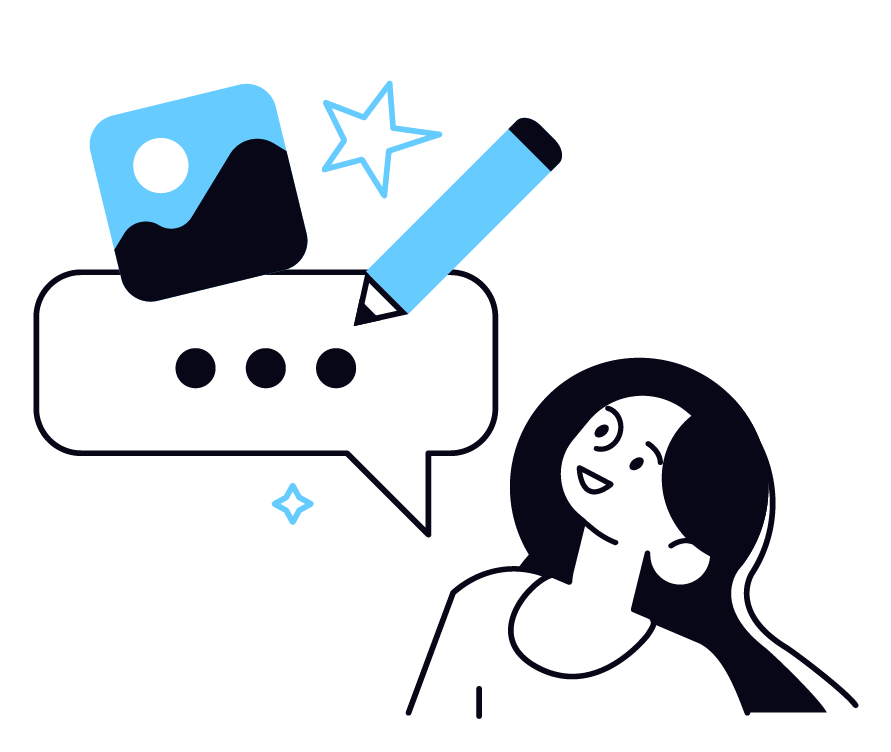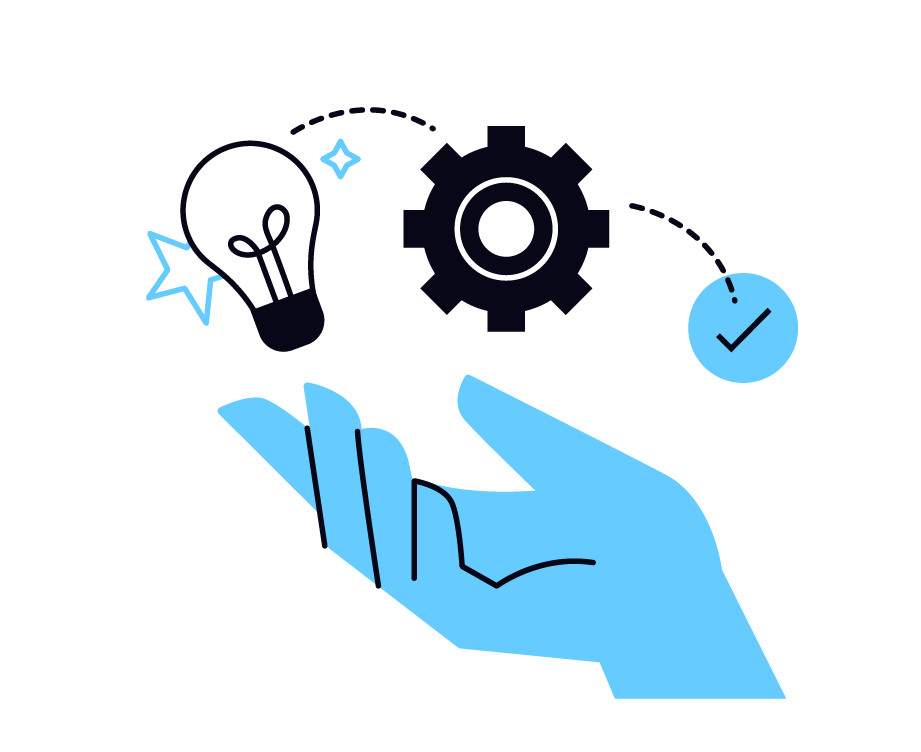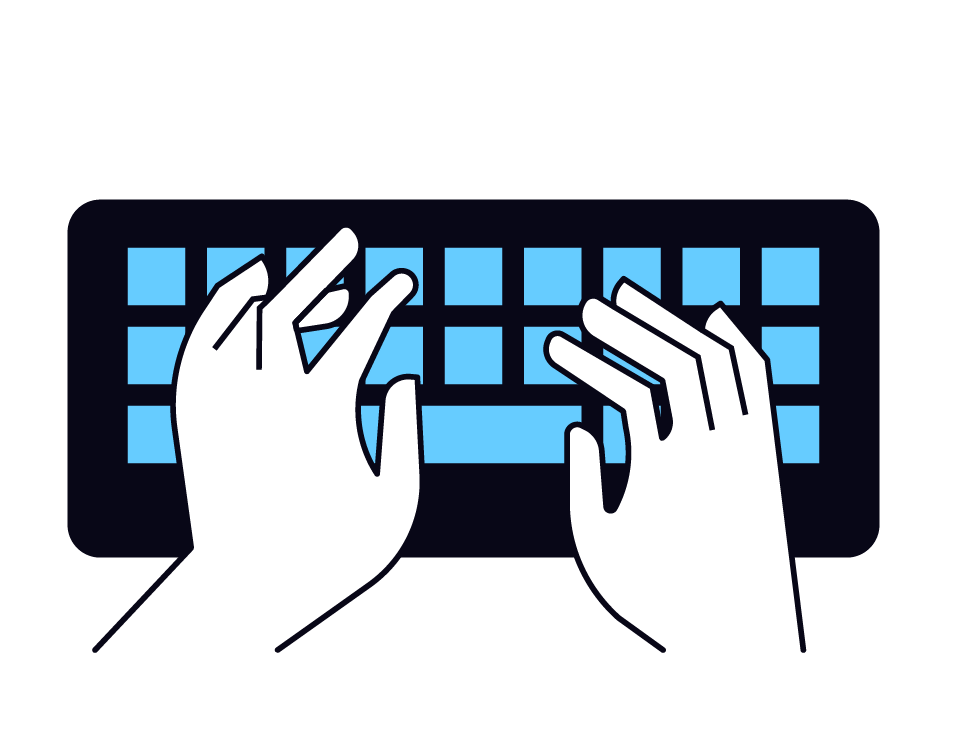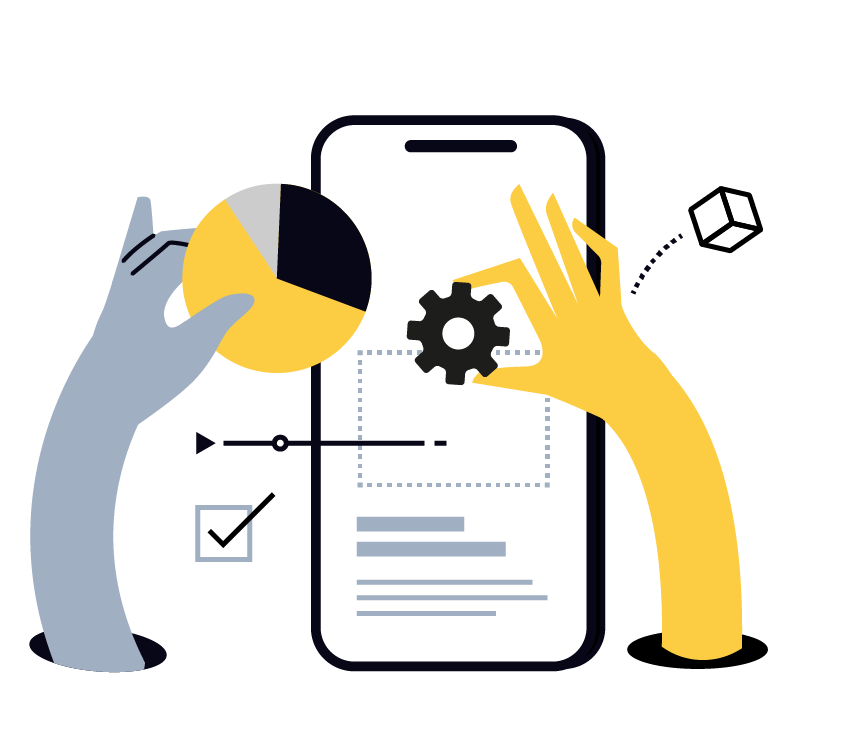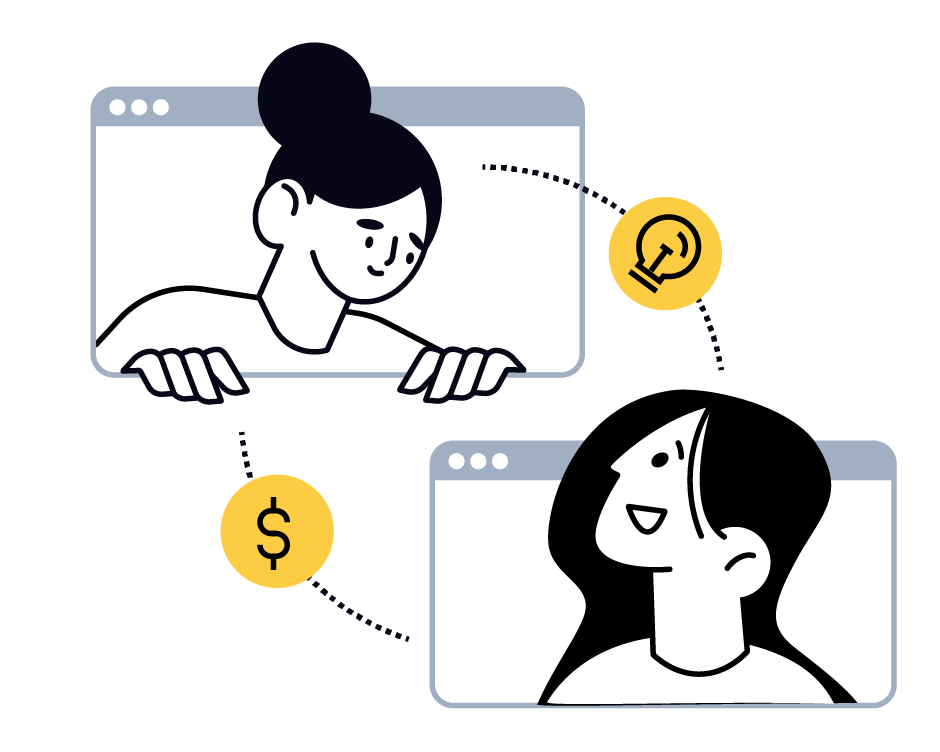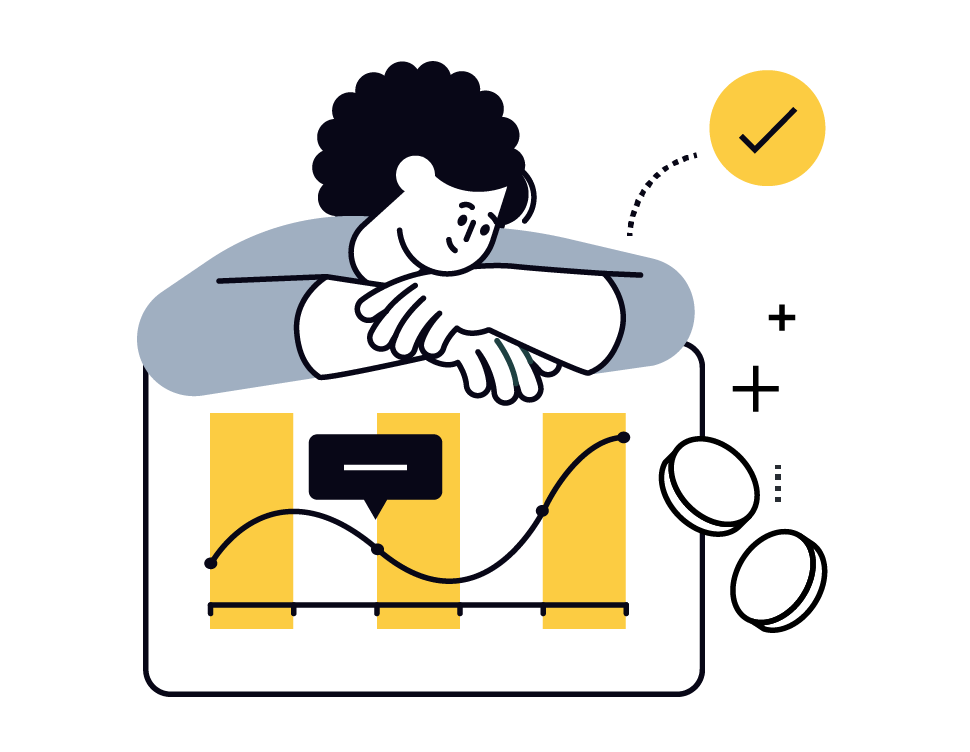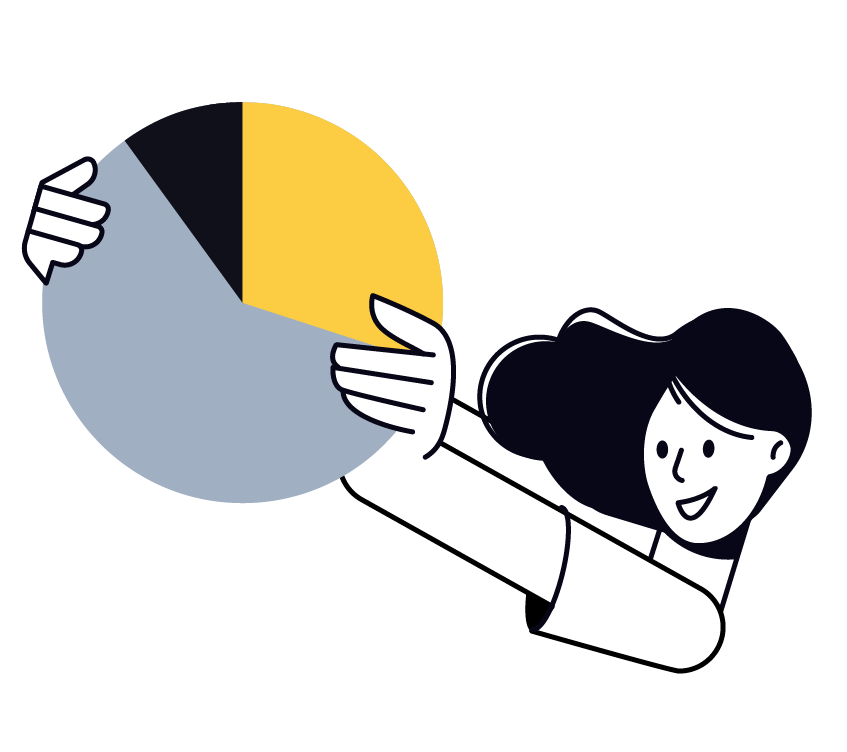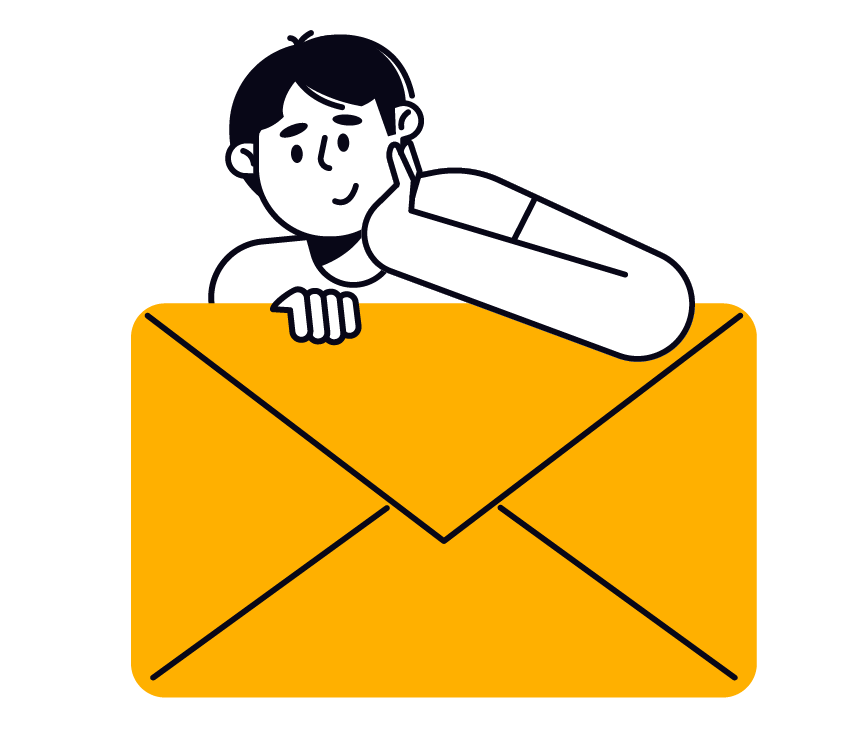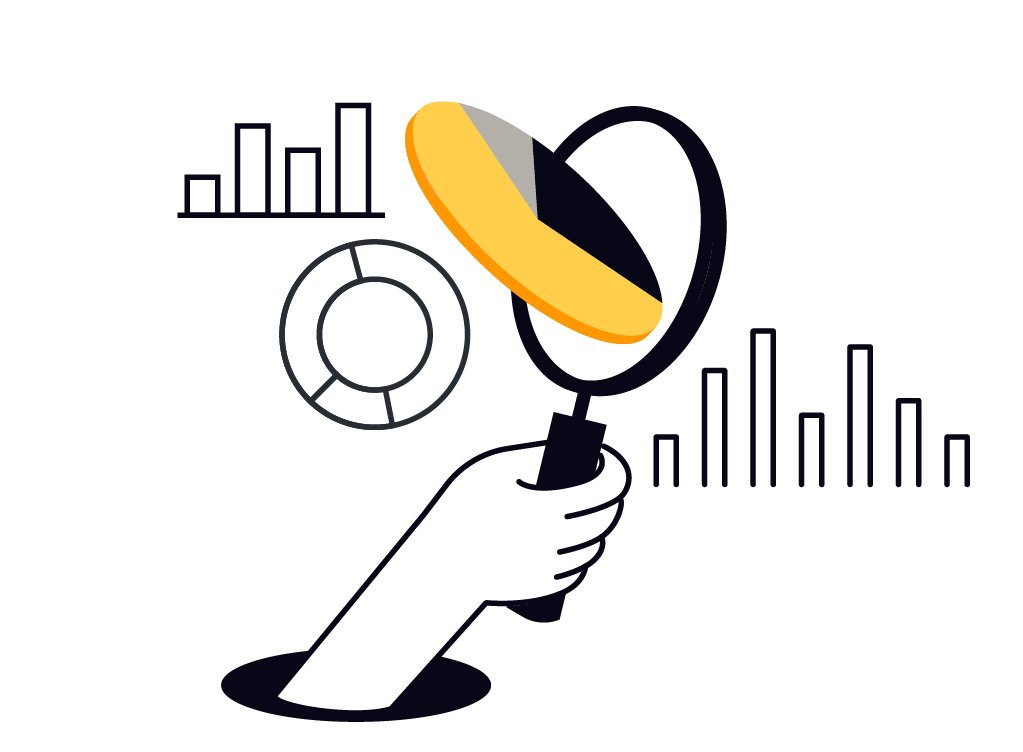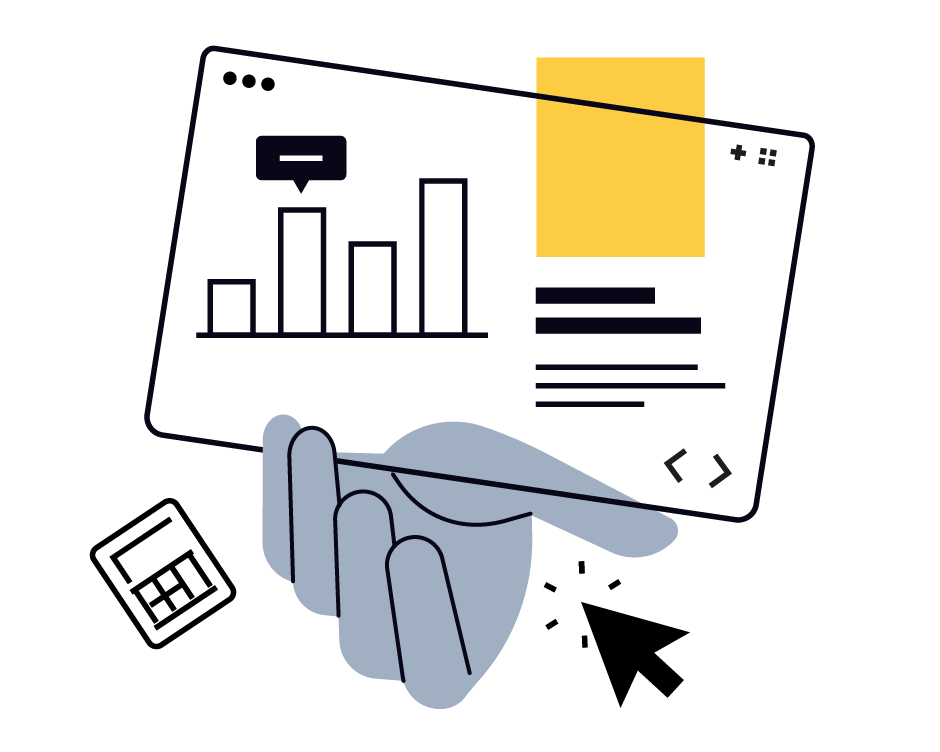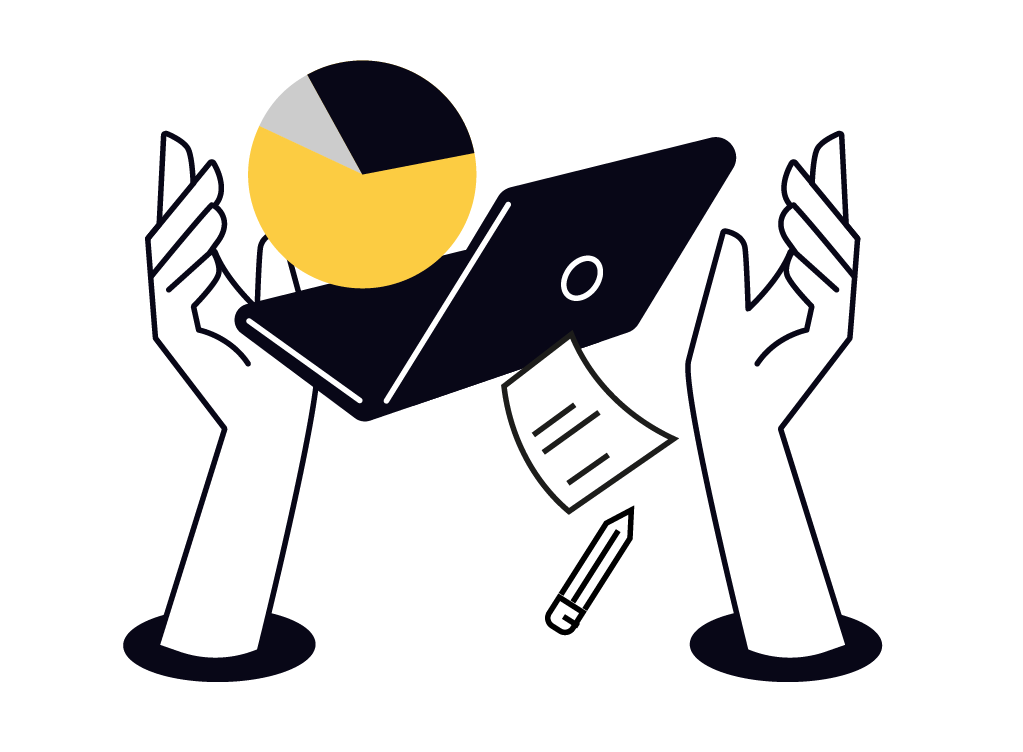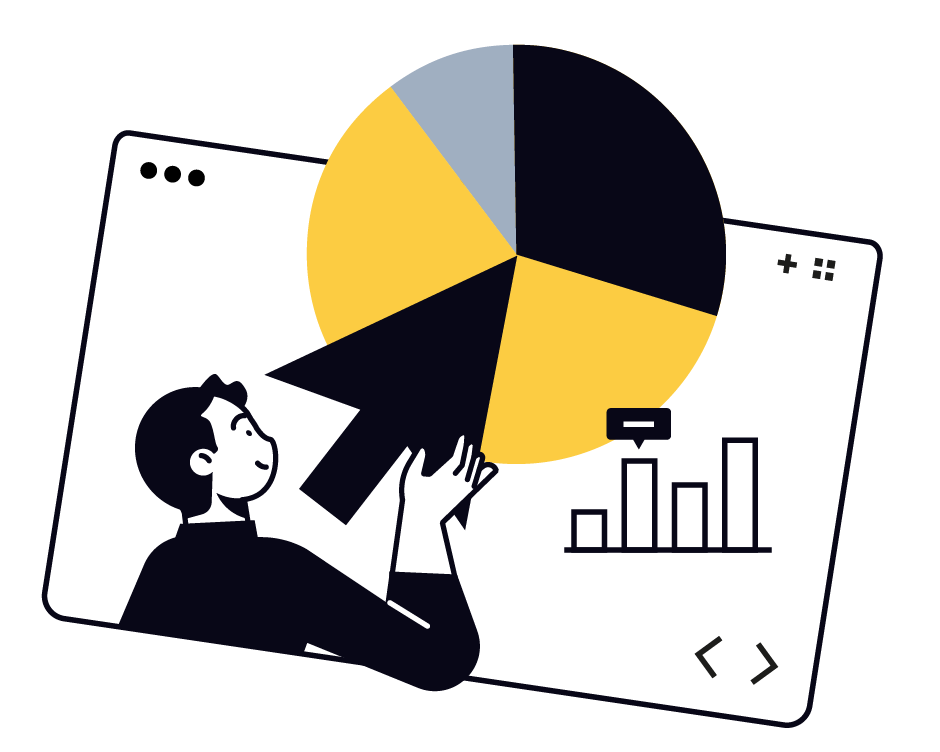成果が続くコンテンツ運用設計
会員サイトを立ち上げた直後は更新も順調に進むものの、数ヶ月後には更新が止まり、誰も触らなくなるケースは少なくありません。
多くの担当者が口にするのは次のような悩みです。
- 忙しくて更新の優先度が下がる
- 何を追加すべきか判断できない
- 更新しても成果が見えない
- 社内で協力が得られず担当者だけが疲弊する
しかし、更新が止まる最大の原因は やる気や人手不足ではありません。
根本にあるのは、成果につながる運用フローが最初から設計されていないことです。
成果が続く会員サイトは、更新ではなく運用を設計している
本記事では、BtoB企業におけるコンテンツ運用を
継続・可視化・改善 の三つの軸で整理し、
明日から実践できるステップとしてまとめます。
成果を定義しない運用は続かない
BtoBの成果は「購入」ではなく「熱量の見える化」
BtoCのように即時の購入やコンバージョンを成果と捉えると、
会員サイトの価値は正しく評価できません。
BtoBでは、次のような行動が成果のシグナルになります。
- 特定の技術資料を複数ダウンロードした
- セミナー動画を最後まで視聴した
- 製品比較ページの閲覧が増えた
- 30日以内に複数回ログインした
これらは 意思決定の温度が上がっている証拠 です。
成果の定義は四つの軸で整理できる
BtoB会員サイトでは次の指標が実務に直結します。
- 再訪率
- 閲覧の深度(ページ数や滞在時間)
- 行動の変化(資料DLや問い合わせ意向)
- セグメント別の活性度
成果とは「誰が何に興味を持っているかを把握できる状態」である
この定義が共有されていないと、更新は義務になり、必ず止まります。
コンテンツは“資産”として積み上げる
更新を続けるための最も重要な考え方は、
コンテンツを 消耗品ではなく資産として設計する ことです。
検討段階に応じたストック設計
会員の行動は段階があります。
| 段階 | 必要な情報例 | 役割 |
|---|---|---|
| 認知 | 概要、導入事例、業界別のメリット | まず興味を持つ |
| 比較検討 | 機能、よくある質問、動画解説 | 不明点を解消 |
| 社内展開 | PDF、提案資料、比較表 | 稟議を通す |
| 運用フェーズ | 活用ノウハウ、更新情報、サポートFAQ | 継続利用 |
ひとつのページで完結させるのではなく、
複数の接点が連続するストーリー を作ることで再訪が生まれます。
更新頻度より設計の再利用性を高める
成果が続く会員サイトに共通するのは、
「更新しやすい構造」を持っていることです。
たとえば次のような考え方があります。
- 固定ページはストック、更新情報は別レーンに分離
- 一度作ったパーツは複数ページに参照で配置
- FAQは追加しやすい形式に統一
- タグで検索性と出し分けを同時に成立
更新量ではなく更新しやすさが寿命を決める
運用が回るサイトほど、無理をしていません。
成果につなげる運用フローのつくり方
KPIは「集計できる状態」を先に作る
KPIを設定しても、数値が拾えなければ意味がありません。
まずは次の状態を整えることが重要です。
- ページ別閲覧データを取得できる
- 会員属性ごとに傾向が確認できる
- ダウンロード数や動画視聴完了率を記録できる
- 月次で比較できる形式になっている
KPIの例としては次が現実的です。
- 再訪率(30日以内)
- 会員1人あたりの閲覧ページ数
- コンテンツ別の閲覧比率
- 資料DLからフォローアクションにつながった件数
数字が見えると、更新は努力ではなく改善になる
更新を“業務の一部”に組み込む
更新が止まる最大の理由は、
サイト運用が日常業務と切り離されていることです。
次のように業務と結びつけると自然に回ります。
- 営業会議で出た質問を翌週FAQに追加
- 製品改訂のタイミングで比較表を更新
- イベント後に資料とフォロー記事をセットで公開
- サポートに多い問い合わせをナレッジ化
特別な作業ではなく、
業務そのものがコンテンツになる状態 が理想です。
成果の共有がモチベーションを生む
担当者が疲弊する最大の理由は、
成果が見えず、評価されないことです。
次の共有は非常に効果があります。
- 月間の成果を1枚にまとめて共有
- よく見られたコンテンツをランキング表示
- 営業に活用ケースをフィードバック
- 上層部に改善推移を報告
成果が共有されると「更新しなきゃ」ではなく「更新したい」に変わる
これは継続の大きな分岐点です。
担当者が疲弊しないための運用設計
属人化を防ぐための整理ポイント
- 更新ルールと責任範囲を明文化
- テンプレートとタグの統一
- 承認ステップを簡素化
- 役割を固定化せずチームで分担
属人化は停止の予兆です。
負担を偏らせない構造が長期運用を支えます。
自動化できる領域はツールに任せる
すべて手動で行う必要はありません。
- 更新通知メールの自動送信
- 週次のログ抽出
- アクセスの異常検知
- 新着の自動反映
「手間を減らす設計」は、運用を続ける前提条件です。
まとめ:成果が続く会員サイトは設計で決まる
会員サイトの成果は、公開直後ではなく
運用の積み重ねによって生まれます。
重要なのは次の三つです。
- 成果の定義を最初に共有する
- コンテンツを資産として設計する
- 更新が自然に回る運用フローを作る
そのうえで、数字を可視化し、社内に共有することで
会員サイトは 続ける価値がある取り組み へ変わります。
次回へのつながり
第6回となる本記事では、会員サイトの成果を維持するための
運用と改善サイクル を整理しました。
次回の第7回では、実際に多くのBtoB企業が直面する
「よくある課題とその解決策」を解説します。
更新が止まる理由や離脱の兆候を見極め、
継続利用へつなげるための具体策を掘り下げます。
あわせて、全8回の構成を一覧で見たい場合は