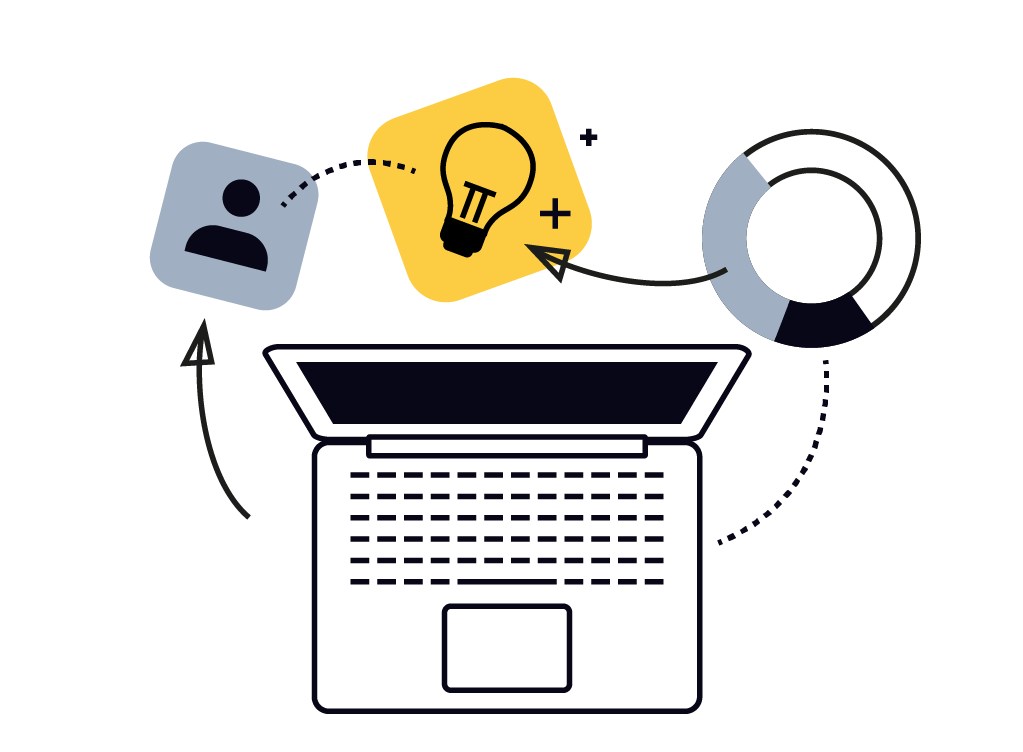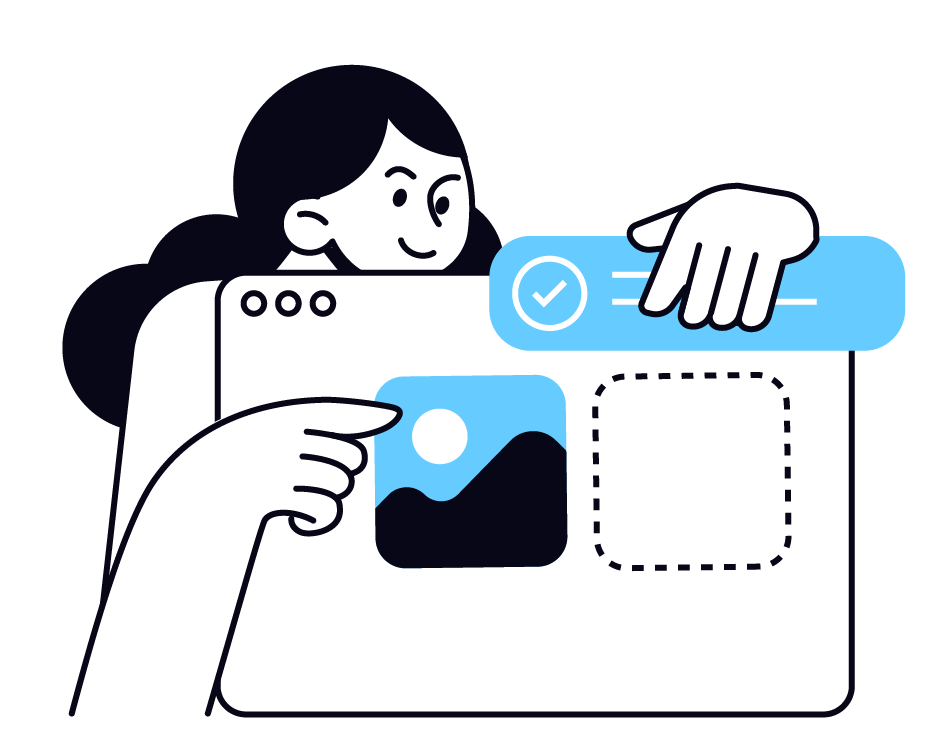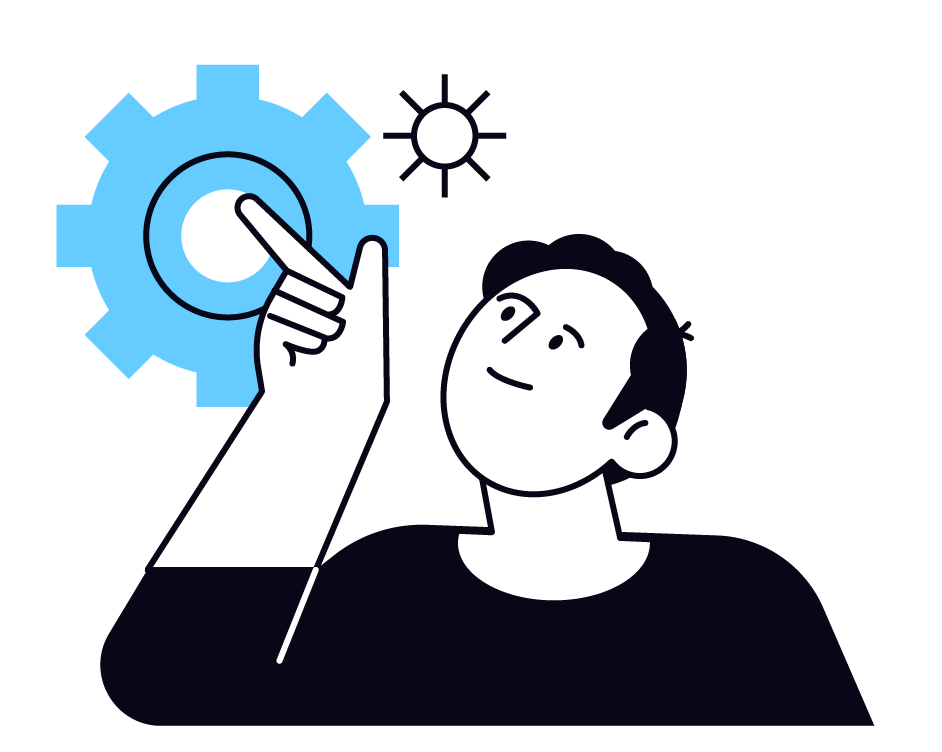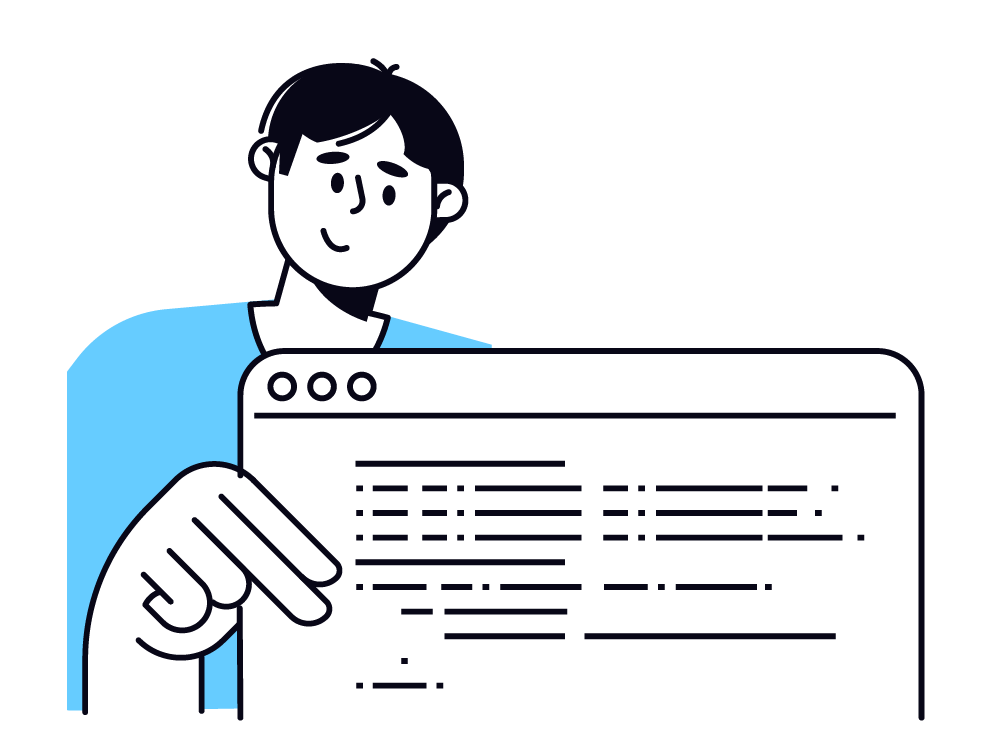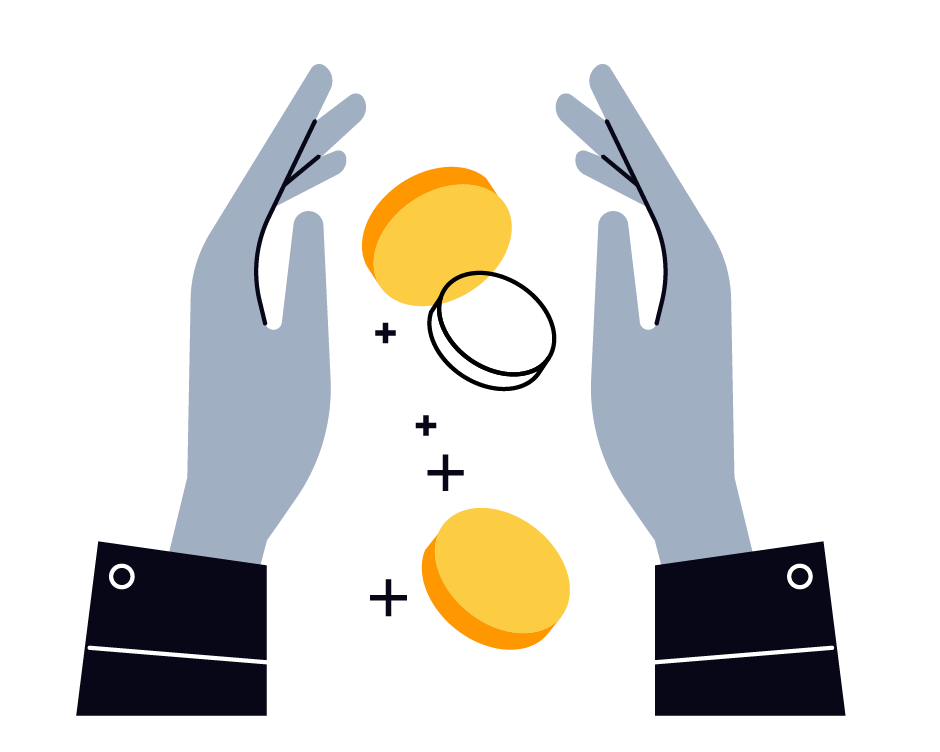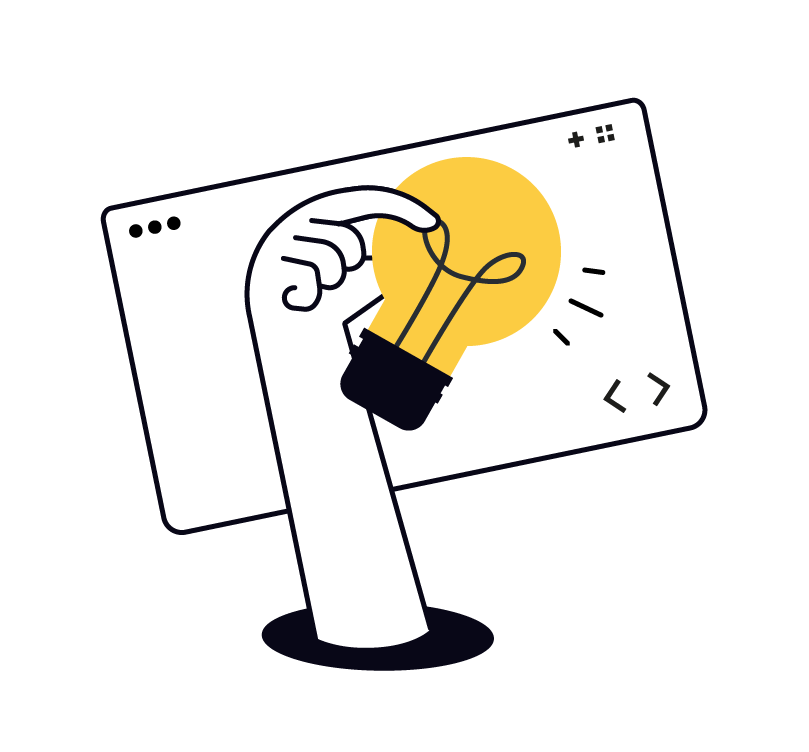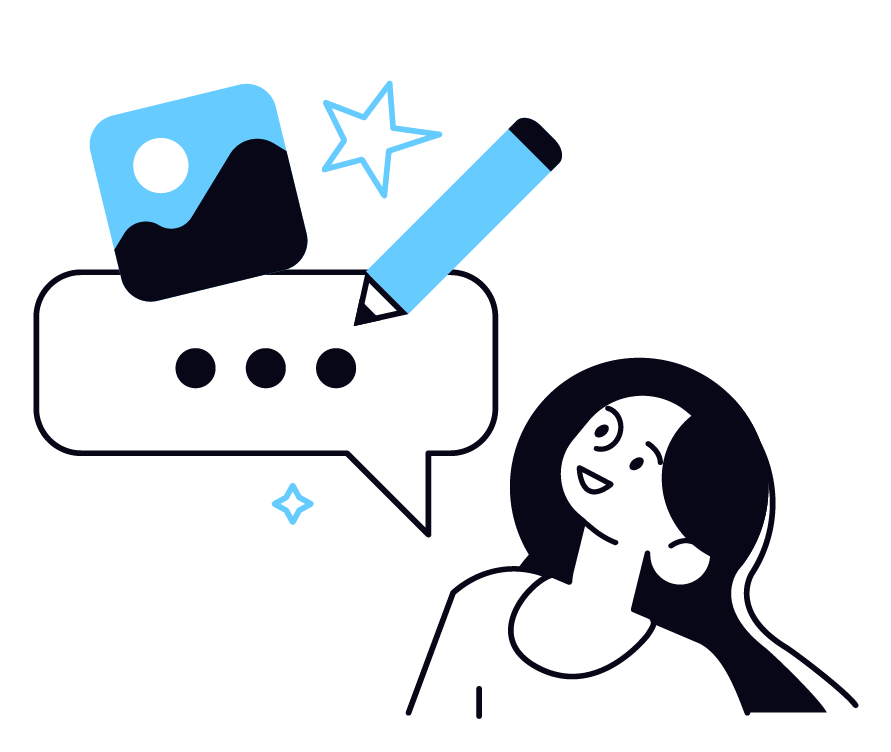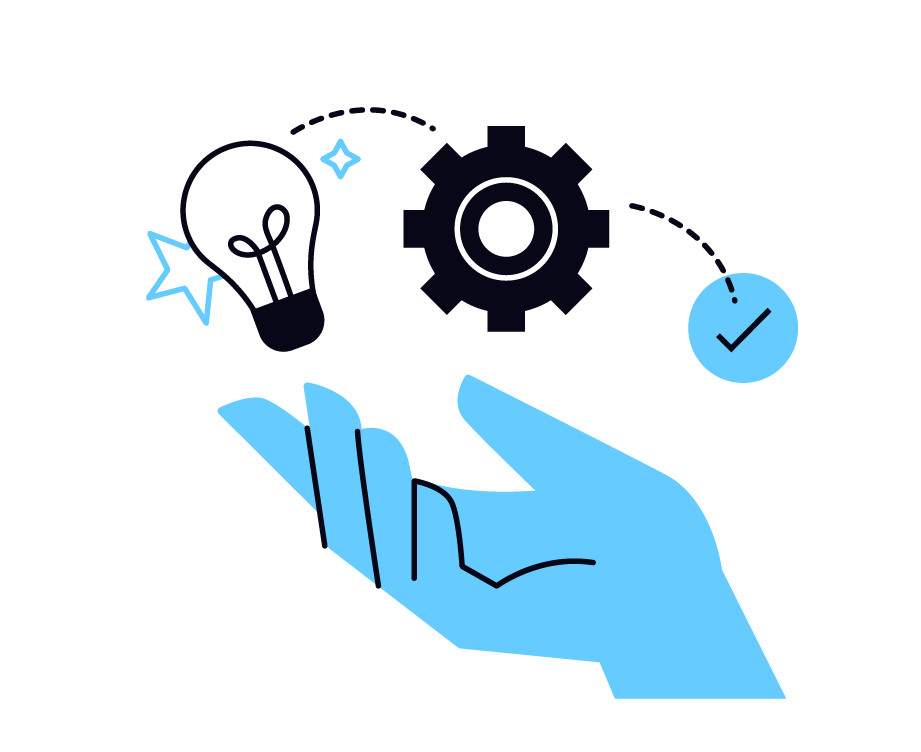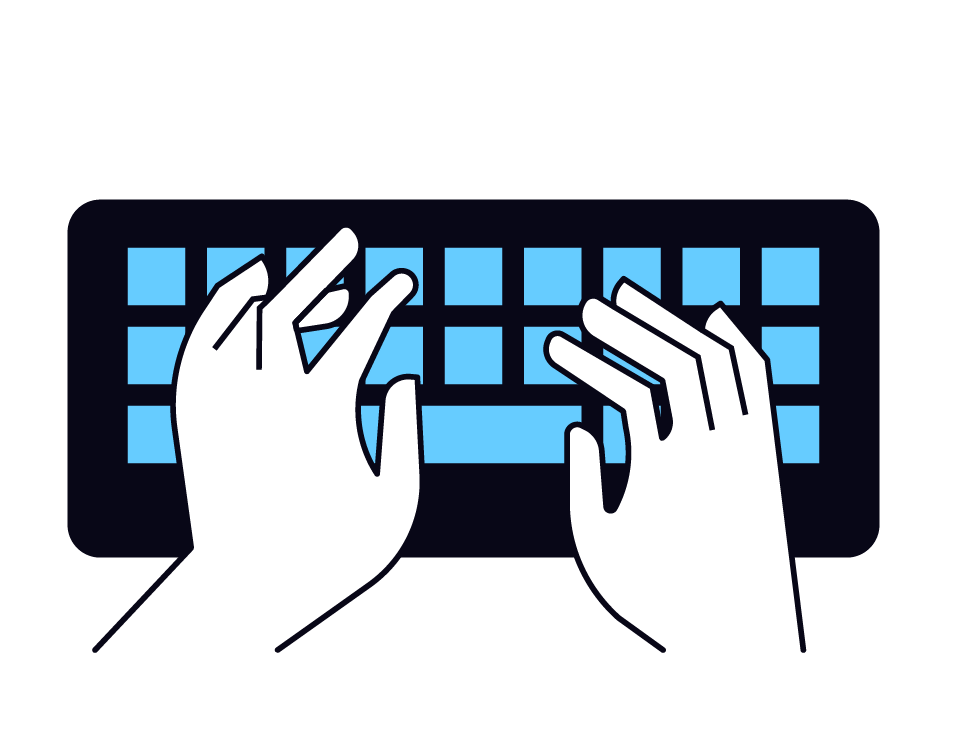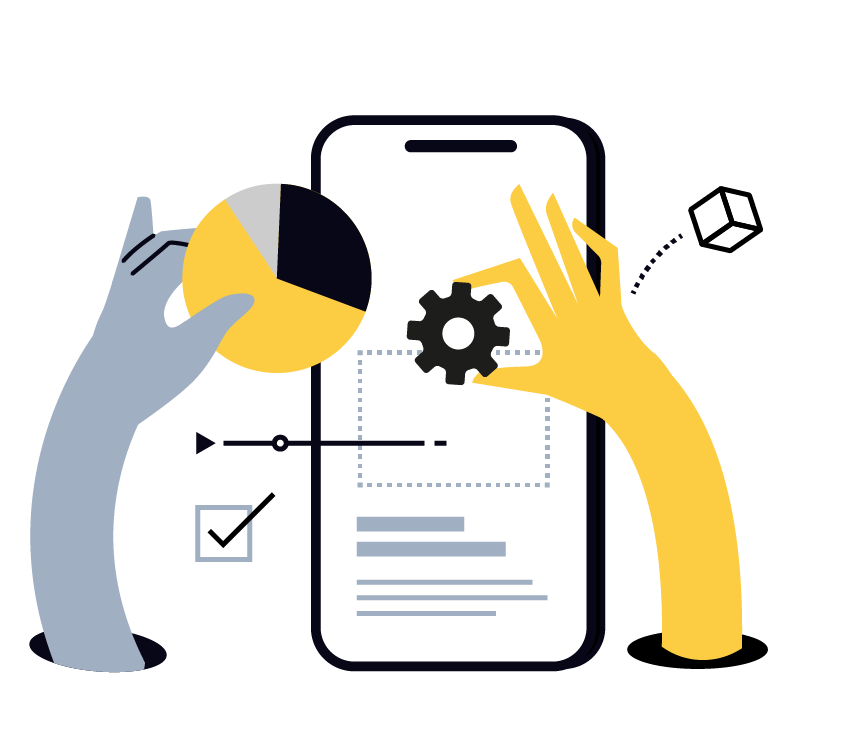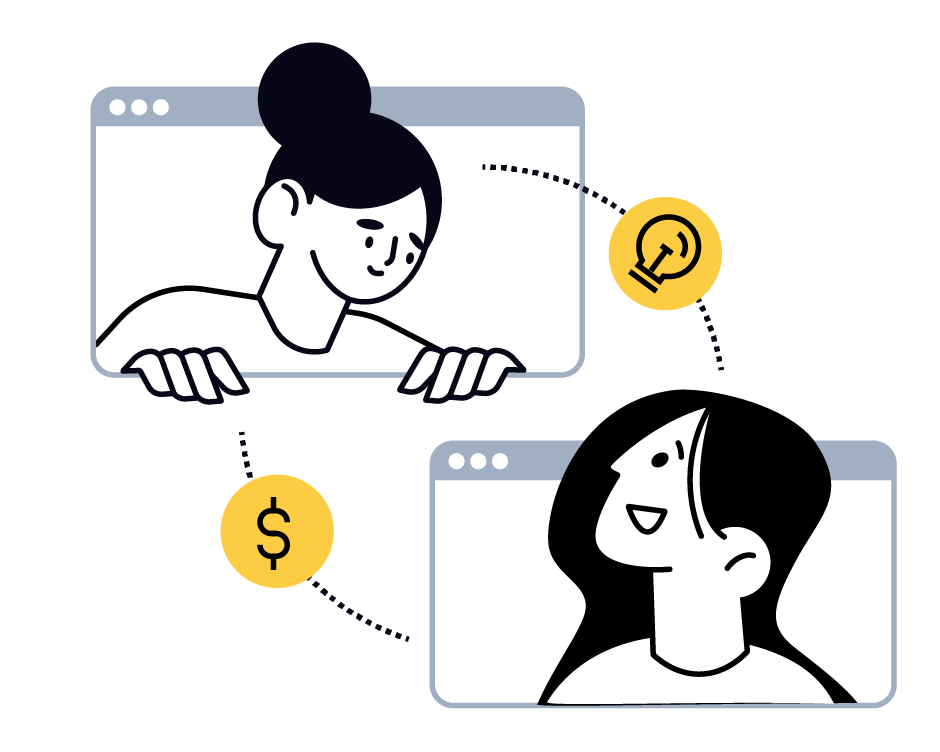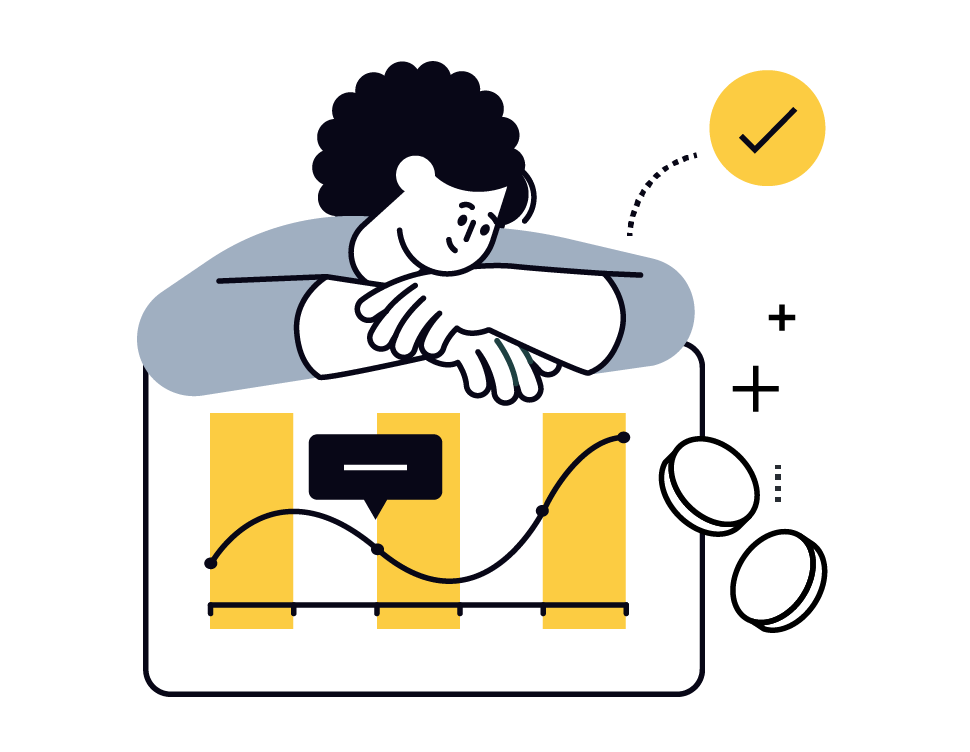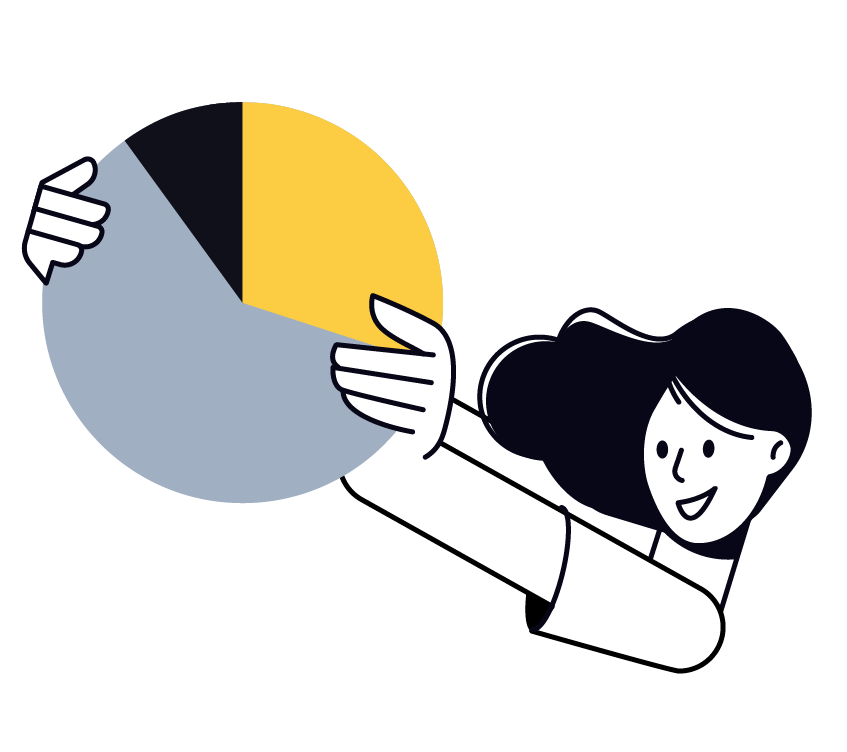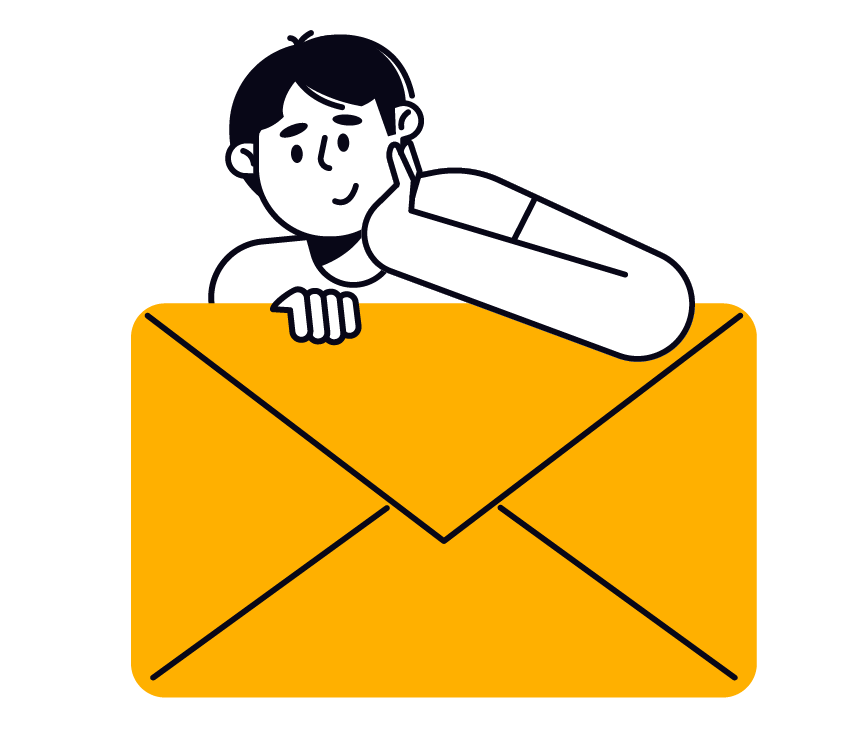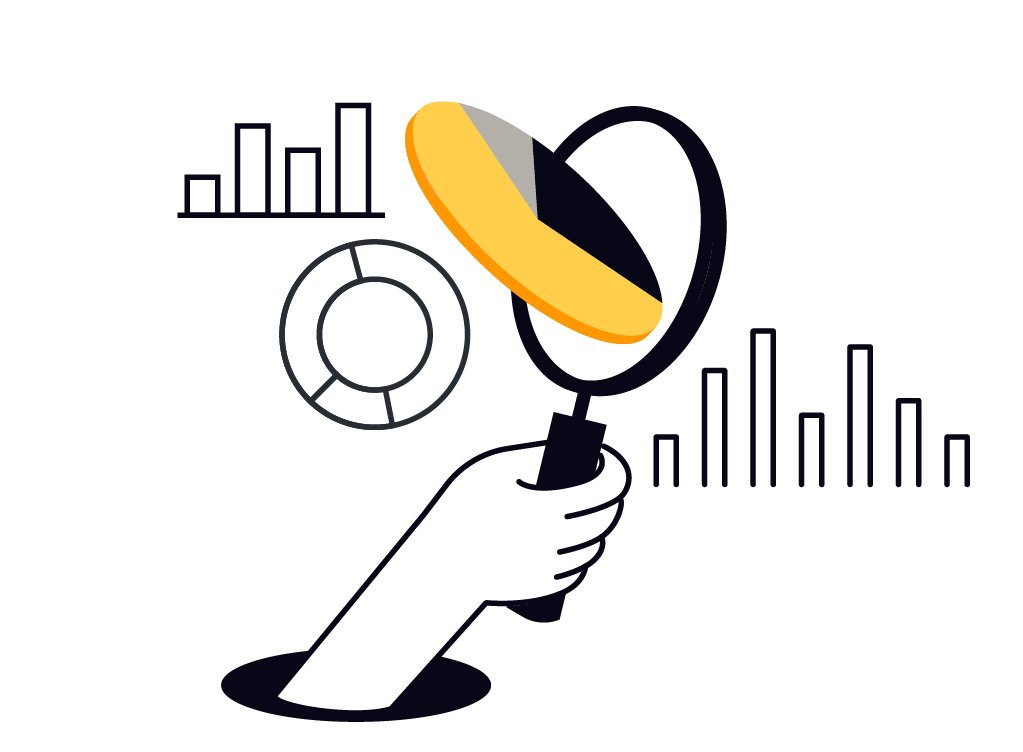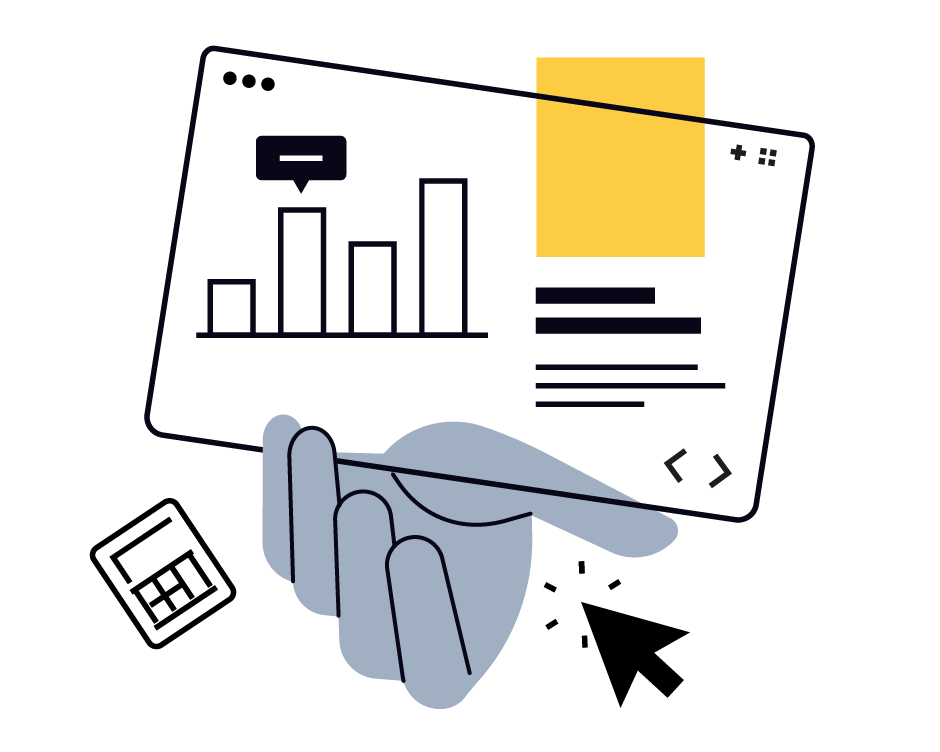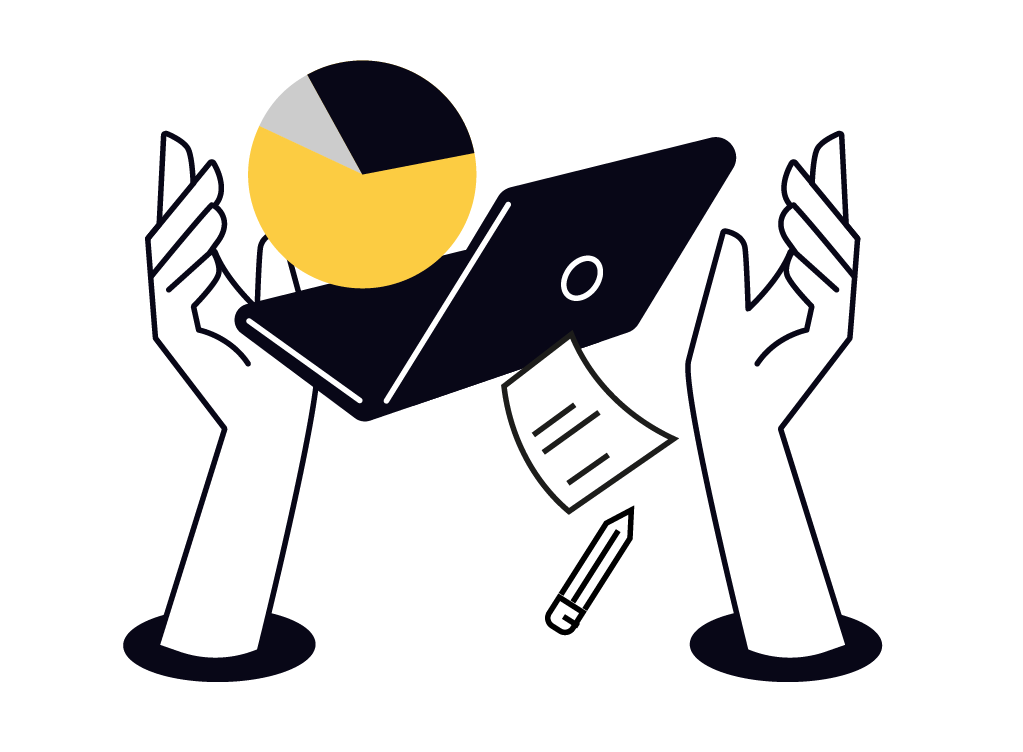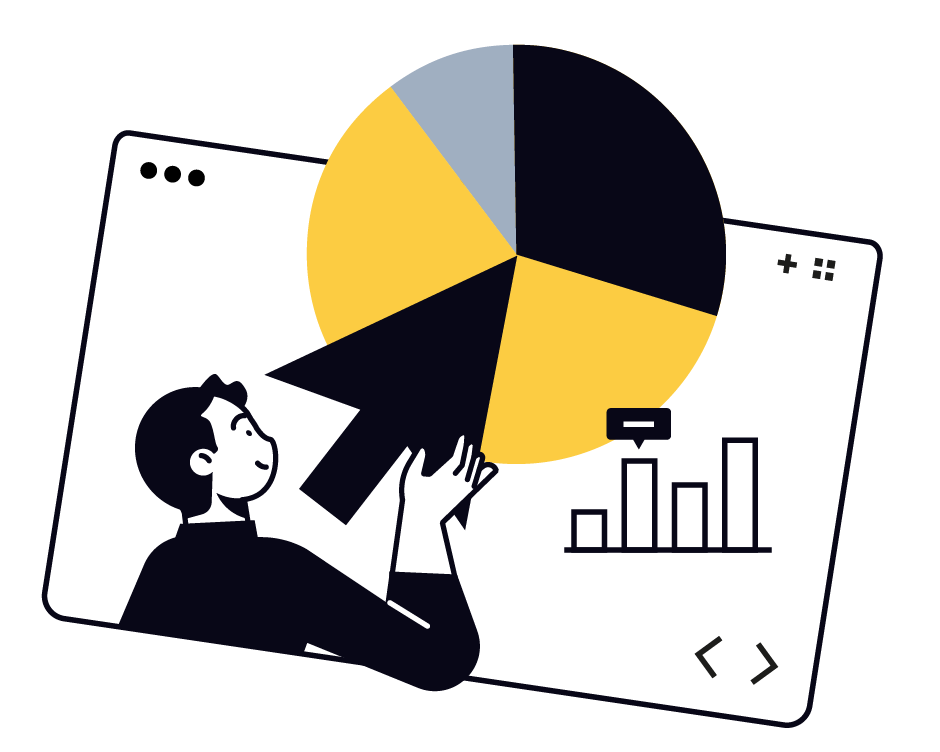BtoBサイトにおいて、フォームはCV(コンバージョン)の最終ステップであり、ユーザーの行動を成果に変える“決め手”となります。資料請求、問い合わせ、デモ申込み、メルマガ登録など、すべてのアクションの裏にはフォームが存在し、設計の良し悪しでCV率は大きく変動します。
本記事では、「CV率が思ったように伸びない」「せっかく流入しても離脱されてしまう」といった悩みを持つBtoB企業のWeb担当者・マーケ担当者に向けて、実践的かつ即効性のあるフォーム改善のポイントを詳しく解説します。
1. フォーム設計がCVを左右する理由
1-1. フォーム離脱は“ほんの些細な”ことで起きる
多くのWeb担当者は、フォームを「単なる入力欄」と捉えがちですが、実際にはユーザーの心理的なハードルが最も高まる瞬間です。項目が多すぎたり、入力に迷ったり、エラーでつまずいたり──たった一つの“違和感”が、CVの取りこぼしに直結します。
この段階での離脱は非常にもったいないもの。なぜなら、ここまで来たユーザーはすでに関心を持っており、フォームがスムーズであればCVしていたかもしれないからです。
1-2. フォーム最適化は最小コストで最大効果を得られる
広告費を増やしたり、リード獲得キャンペーンを強化したりするにはコストも手間もかかりますが、フォーム改善は少ない労力で効果が出やすい領域です。特に以下のような課題を抱えている企業には、すぐに取り組む価値があります:
- サイト流入は一定あるがCV率が低い
- フォーム到達率に対して、完了率が著しく低い
- 競合と比較される中で、少しでも差をつけたい
「改善余地の宝庫」とも言えるのがフォーム設計なのです。
2. CV率を上げるフォーム設計の実践テクニック
2-1. 項目数は“最小限”にする
BtoBにおいては営業部門やカスタマーサクセスから「この情報も入れてほしい」と要望が集まりがちですが、ユーザーにとっては負担になるだけ。特に初回接点では、“必要最小限”に絞ることが基本です。
実務上のポイント:
- 営業的に後から確認できる情報はフォームに入れない
- 本当に必要かどうか、全項目を棚卸しする
- 「削ると困る理由」ではなく「削れる理由」を探す
例:初回接点で省略可能な項目
- 電話番号 → ヒアリング時に取得できる
- 会社住所 → メール連絡で十分なケースが多い
- 従業員数 → セグメントには使えるが、初回では優先度が低い
2-2. スマホでの使いやすさを最優先に
BtoBの商談導線といえど、スマートフォン経由の訪問者は年々増加しています。特に移動中や隙間時間に情報収集するユーザーにとって、スマホでのフォーム体験が悪いと即離脱につながります。
チェックポイント:
- 入力欄の幅や文字サイズが指先に合っているか?
- 数字・メール・日付など入力形式に応じてキーボードが最適化されているか?
- ラジオボタンやプルダウンが操作しやすい配置か?
- サンクスページまでのフローがストレスなく完結できるか?
スマホファーストでフォームを作ることは、CVを取りこぼさない第一歩です。
2-3. ステップ型フォームで「心理的ハードル」を分散
ユーザーがページを開いた瞬間に10項目以上の入力欄が並んでいると、それだけで「面倒だな」と感じて離脱するリスクがあります。
ステップ型フォームのメリット:
- 見える項目数を減らし、心理的負担を軽減
- 最初のステップで離脱率を把握できる
- 入力に集中してもらえる構成になる
たとえば「1ステップ目で課題選択 → 2ステップ目で会社情報 → 3ステップ目で個人情報」といった流れにすることで、入力のハードルが格段に下がります。
2-4. エラー時のストレスを最小限に
入力エラーが原因での離脱は意外と多く、特に以下のような設計ミスが原因になります:
- エラー内容が不明確(例:「入力が間違っています」だけ)
- 入力内容が消えてしまう
- 入力制限が厳しすぎて先に進めない
改善ポイント:
- リアルタイムでのバリデーション(入力中にエラーを通知)
- 入力保持機能の実装(リロードで内容が消えない)
- わかりやすいエラーメッセージ(例:「メールアドレスが正しくありません」)
これらの工夫は、ユーザー体験の向上と離脱率の低下に直結します。
2-5. CTA文言・周辺情報も含めて最適化
「送信」や「登録」といったボタン文言は無機質になりがちですが、これを「○○をダウンロードする」「無料で相談する」など、ユーザーが得られるメリットに言い換えるだけでCV率が上がることがあります。
さらに、ボタンの上に配置される補足文(マイクロコピー)や、送信後のサンクスページにおける次アクションの案内も含めて最適化することで、ユーザーの満足度や好印象を高めることができます。
3. より高みを目指すために:ABテストと改善の習慣化
3-1. フォーム改善に「正解」はない
フォームの改善において、他社事例やベストプラクティスは参考になりますが、「自社のターゲットにとって最適かどうか」は別問題です。そのため、ABテストで実際の成果を見ながら改善を繰り返すことが必要です。
3-2. ABテストで試すべき項目例
- CTA文言の違い(例:「資料請求」vs「今すぐダウンロード」)
- フォームの構造(ステップ型 vs 一画面型)
- フォームの配置位置(ページ下部 vs サイド固定)
- 補足文の有無(安心感を与える文言)
ABテストでは、「1回で大成功」を目指すのではなく、着実にCV率を引き上げるプロセスが重要です。Google Optimizeやヒートマップツールと併用すると、改善インサイトが得やすくなります。
4. まとめ|成果を上げるフォームには“設計の理由”がある
CV率が高いフォームは、偶然ではなく明確な「設計意図」が反映されています。ユーザーの離脱理由を理解し、フォームの構成・項目・表現・デザインを細かく見直すことで、流入数が少なくても成果を出せるようになります。
フォームはただの入力欄ではなく、「ユーザーの行動を成果に変えるインターフェース」です。次回は、実際のBtoB企業でのフォーム改善事例をもとに、どのような施策が有効だったのかを掘り下げていきます。