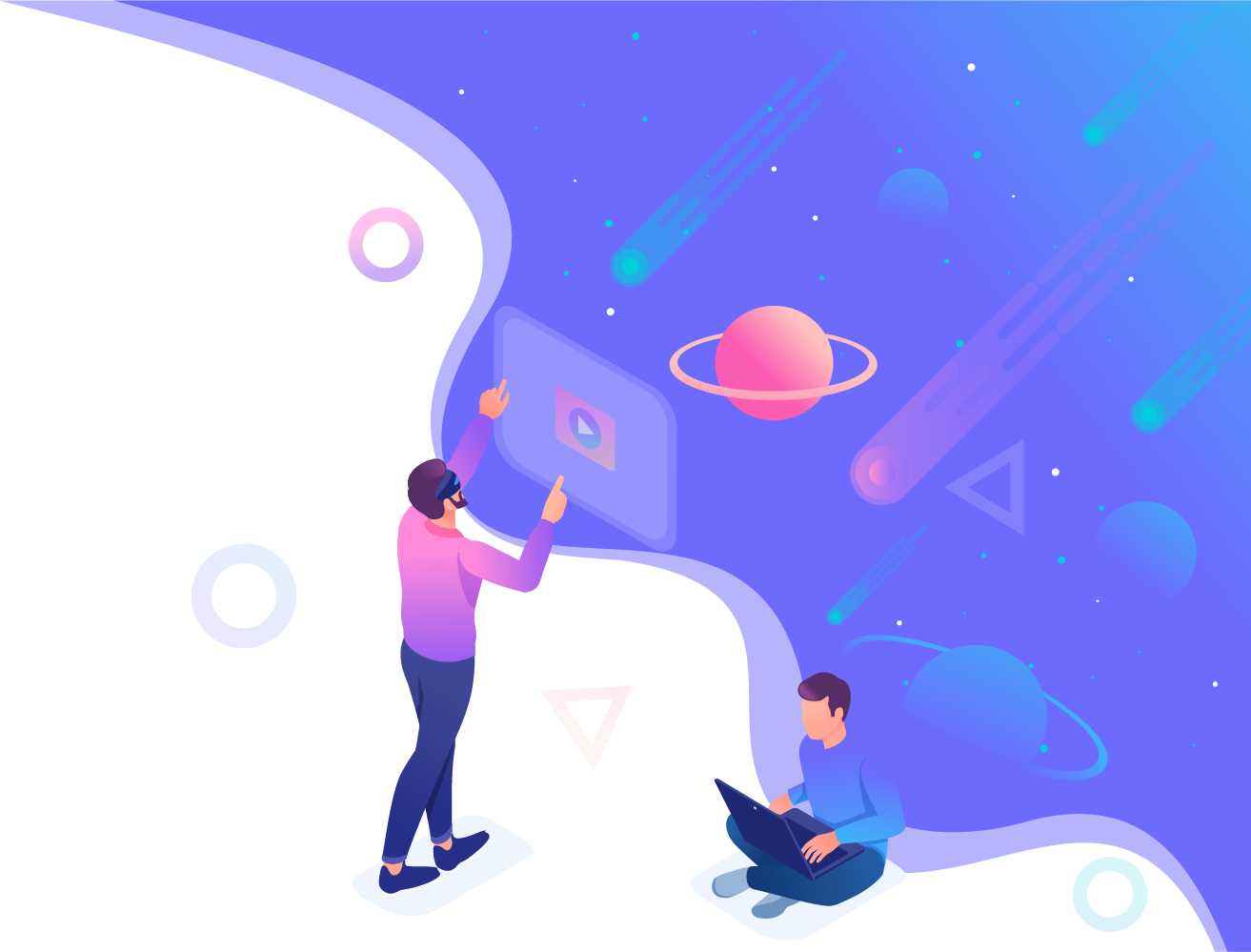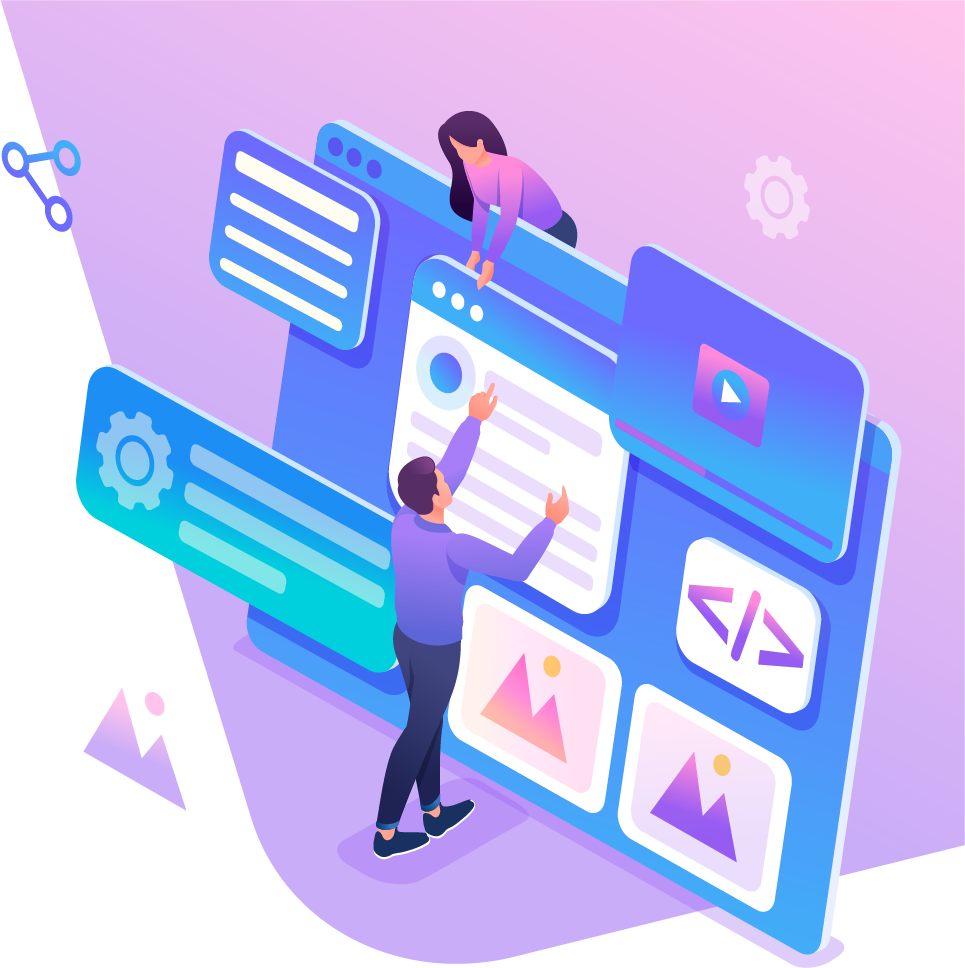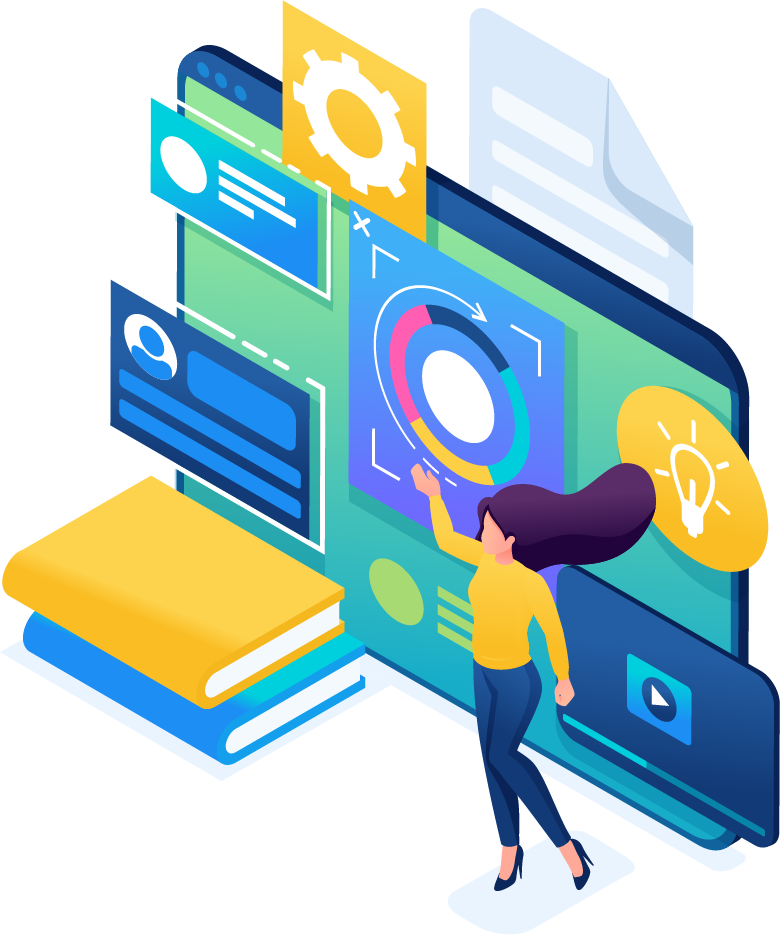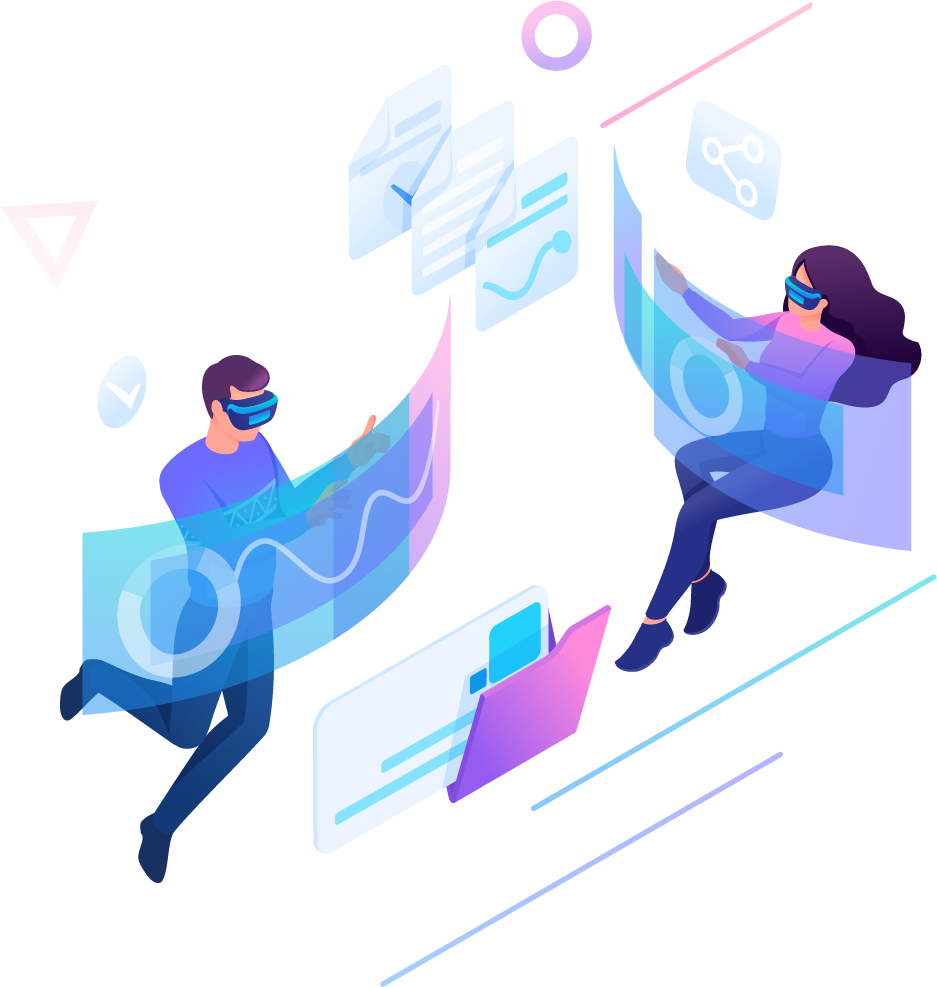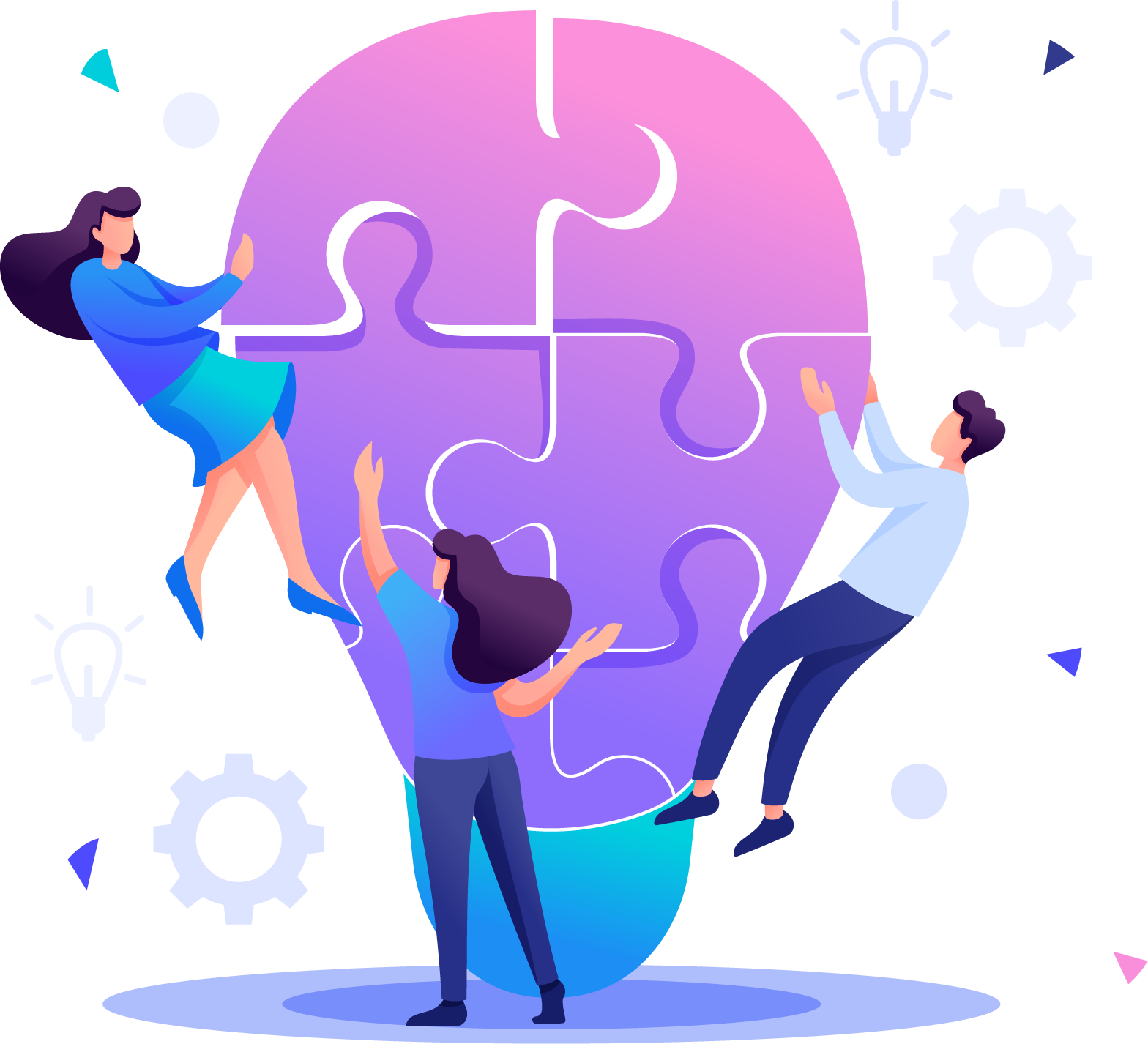ChatGPT統合によるCMS革命
ChatGPTの実践活用:私たちのSEO戦略への影響
ChatGPTがSEOに与える影響については、さまざまな意見がありますが、実際にはどうなのでしょうか。私たちはこの疑問に答えるため、実際に自社のコンテンツリライトにChatGPTを導入し、その成果を見てきました。この記事では、ChatGPTを使ったリライトが私たちのSEO戦略にどのような影響を与えたか、そしてそれがなぜ重要なのかをお伝えします。
ChatGPTとSEO効果の探求
この記事では、私の実体験に基づき、ChatGPTを利用したリライトがSEOにどのような影響を与えたか、そしてそれがなぜ重要なのかをご紹介します。自社サイトのコンテンツは私一人で書いていますが、今ではほぼすべてのコンテンツをChatGPTを使ってリライトしています。リライトする目的は何といっても、人が読んで読みやすい、わかりやすいものになるからに他なりません。
どうしても自身で書くと、特にCMS自体も自分たちで開発しているものなので、誇張する点や表現が偏りがちで、普通の人からは読みにくいものになりがちなのですが、ChatGPTを使う客観的で平易なわかりやすい読み物にしてくれます。
当然自社サイトの運用をしているからには、SEO的な成功、検索上位に表示されるという目標はあるにはありますが、本当の目的は自分たちが開発しているものの良さを多くの人に伝えたい、わかってもらいたいということです。(例えば、自分で書いたコンテンツは句読点の打ち方ですら読む方にとっては読むのが苦痛になっているのでは、と思うこともあります。)
ChatGPTによるリライトの実際
リライトになるのでベースは私、人間が考えたコンテンツをChatGPTが万人に対して読みやすくするものなので、極端に悪くなるというケースはほぼ無いように思えます。ひと昔のAIというと何をいっているのかわからない明らに機械が書いた文章になりがちでしたが、現在のAI技術だと元々のコンテンツの内容をゆがめることなく平易な文にしてくれます。(何より、自分の書いたコンテンツが人に対してわかりやすいものになるので、それだけでうれしい限りです。
ChatGPTを使ってリライトしたコンテンツに置き換えるのは、SEO的に何かペナルティになるのではないかなど、考えると正直少し勇気が必要でしたが実際に置き換えてみしてしばらくすると、SEOの順位は確実に上がったと思います。
参考ですが、コンテンツ数で言うと1000~2000文字が50ページほどで期間は2~3か月かかったと思います。
SEO成功へのChatGPTの役割
狙ったワードは英語3文字の、いわゆるビッグワードです。リライト前は別の比較的競合性の低いキーワードと合わせることで、なんとか検索結果2,3ページ目に入る状態だったのが、今では3文字のビッグワードでだけで検索結果3ページ以内に入るようになりました。1位や1ページ目ではありませんが、他の上位を占めているサイトは「とは」コンテンツなどの明らかにSEO対策の記事で、中を読んでもどれも似たり寄ったりや表面的なもので目新しい情報はありません。
その領域に詳しくない初心者の方が頻繁に検索をするので「とは」コンテンツは検索エンジンで上位にくる傾向があるようです。SEOのコンサル会社に相談すると必ずと言っていいほど、こういったコンテンツの制作を勧められます。
弊社製品の場合は、初心者向けではなく、ある程度知識、経験を持った方が対象になるので初心者向けのコンテンツで検索上位に上げてもあまり効果はないと考えていました。
理由は「とは」でサイトに訪れる方は、情報収集している段階なので、ざっとした内容を読んだ後はすぐに離脱してしまう、また、初心者向けのコンテンツでは弊社製品の強みを伝えるのは難しいと思ったからです。
「とは」コンテンツだと検索上位には上がるかも知れませんが、弊社にとっての見込み客を探す、弊社製品の良さを伝える本来の目的は達成出来ないので、費用対効果では成り立ちません。
弊社の場合は、純粋に製品サイト、トップページを検索上位に表示したかったので結果的には満足のいくものだったと思います。
ChatGPTによるコンテンツ作成の新たな地平
他にもリライトではなく、ほぼすべてChatGPTで書いた記事もあります。その場合は読み手の興味を考えて、書く内容をChatGPTに伝え、その回答を元に何度も質問を掘り下げていくことで、読み手にも満足してもらえるであろう読み物に仕上げることが出来ていると思います。
正確に言うと、ChatGPTが完全に書くのではなく、人のアイディアに沿ってChatGPTが正確に手助けをすることで、人だけ、AIだけではできないことが実現できているのではないかと思います。
「ChatGPT(AI)=SEO用の記事を書く」と言葉だけ聞くと完全に自動で著作権侵害のリスクも犯すグレーな手法に聞こえがちですが、正しい使い方をすれば間違いなく役に立つと思います。
ChatGPTの活用範囲と未来
弊社のツールではサイト上のアクセスログを個人別、ページ別に閲覧することができます。リライト後の動向をみているとコンテンツ辺りの滞在時間も増えています。これは読む人にとって、何か価値のあるものを提供できている証拠であると言えます。
どこまでChatGPT(AI)の利便性を享受できるかは完全に使う側によります。
例えば、ここで言っているChatGPTへの指示(プロンプトと呼ばれています)をどう書くかでも得る結果は全く違うものなります。プロンプトをうまく使えるかがChatGPTを使ったリライトでいい結果を出せるかの鍵となるといって過言でないでしょう。
ChatGPTの機能を利用して出来ることはもっと沢山あると思います。
弊社のツールはCMSです。「ChatGPT(AI)との連携」というとコンテンツライティング、をイメージするかと思います。
確かに他のCMSベンダーもChatGPTの連携機能というとCMSの管理画面からChatGPTに接続してアイディアをもらう程度にとどまっていますがCMSとChatGPT(AI)との連携することで広がる可能性について取り組んでいる弊社の試み、レコメンデーション、タグ付け、チャットボットの作成などを、具体的な例を踏まえて次回以降の記事で少しずつご紹介したいと思います。